

�@��ɑ�^�J�����ނɊւ��镶����I��ŏЉ�܂��B���p����ꍇ�͕K���������Q�Ƃ��Ă��������B�{�^�����N���b�N�A�܂��͉��ɃX�N���[�����Ă��������B
�@ �J���������R�J�����́A��`�w�I�ɂ͓Ɨ���B��`�w�̏����W�]�́I�H
�@�@���܂ł̌����Ώۂ�mtDNA�Ɍ����Ă������A���q�}�[�J�[�Ŋj�̈�`�q���Q�m�����C�h�ɕ��́B
�@�@���̃X�e�[�W�́A����̎��ʂ���r�I�e�Ղł���Ƃ��ꂽ�B
�@�@��r�I�q�b�g���̍����C�O�̊C���E�I�b�`���O�̃X�|�b�g���Љ�
�@�@Strix Vol.24,2004�N�łŎ������������Ƃ�⑫�������ďЉ�B
�@�@BirdingWorld�� Vol.20 No.4 �̖��͓I�ȋL�����Љ�B
�@�@�������̖��s�L�^������B���ɂ̎��ʂ͑��ւ��낤�B
�@�@mongolicus�́u������J���v��vegae�́u������J���v���r����B�O�W�N�R���Q��
�@�@���V���g���B�ƃI���S���B�ł͂V�T���̃R���j�[�Ō��G������Ƃ����B�@08�N�Q���P��
�@�@�J�����Ȃ̎�̕��ނ�i���̉ߒ��܂��čĐ��������_���ł��B08�N1���Q��
�ȉ��̃R���e���c�͂�����E�E�E
24.�����S���J����L.(c.)mongolicus�̗��̃p�^�[��
�@�@�C�G�\�_��(2001)�ɂ�����S�̃|�C���g��v�Ă݂܂����B 07�N11��28��
23�D�uGulls�@of Europe, Asia and North America�v�̏��łƉ�����
�@�@�ԈႢ�̑������Ŗ{���܂���ʂɗ��ʂ��Ă���B�����ł̃i���o�[��ISBN-07136-7087-8�ł���B07�N10��
22�D�k���`���V�A�ɂ����ĉ��F���r�̃Z�O���J�����������������R
�@�@�}���Ȍ��G�ɂ���Ă��̂悤�ȕω����N�����Ɛ��肳��Ă���B�@07�N8��16��
21. monophyletic(�P�n)�ł��邱�Ƃ��Ӗ����邱�ƁB
�@ �@�J�T�T�M�ނƃJ�����ނ̈�`�w�I�����̔�r 07�N7��13��
�Q�O�D�L�A�V�Z�O���J����Yellow legged Gull�A����michahellis�̕��ނƊ��H����
�@�@�ɐB�n�̍L����ɂ���Ċ��H�����ɍ����o�Ă����B�@07�N5��13��
19.��^�J�����ނ̃n�v���^�C�v�ɂ��ĂR�̘_�������r���[����B07�N3��12���@
�P�W�D�V���J����L.hyperboreus����barrovianus�ɂ���
�@�A���X�J�ŔɐB���A�����J���ʂʼnz�~����Ƃ���邪�A�傽��z�~�n�͓��{�������H07�N2��17��
�P�V�D�J�����̖��O�ɂȂ����l�X
�@�J�����̖��O�ɂȂ����i�`�������X�g�̃o�C�I�O���t�B�[�i�`�L�j���Љ�B07�N1��1��
16.�J�i�_�J�����̓A�C�X�����h�J�����̈���̈�ł���Ƃ�����(99�N�j
�@�J�i�_�J�����̔�������99�N�Ɏ���S�V�̊w�����Љ���R�����B�@�O�U�N�P�Q���R��
�P�T�DKelp Gull�����{�ɗ���\���Ƃ��̎���
�@�씼���̑�^���F�J�����́A�قƂ�ǂ��{��ł���B06�N11��
14.GULL���邢�̓J�����̌ꌹ�ɂ���
�@�@�I�b�N�X�t�H�[�h�p�p�����ȂǂׂĂ݂��B06�N10��
�P�R.Cris Gibbins���̒��q�̃Z�O���J�����L�^
�r�f�I����g���ăZ�O���J�����̌`�Ԃ͂��Ă���B�X���P�R��
1�Q�D�C���̎���
�@�@�쒹�̎��̂̕a���w�I�����@06'8��12��
�P�P�u����kumlieni�v�̓A�C�X�����h�J�����̈��킩�A����Ƃ����G�킩�H
�@�@�������̕������Љ�܂��B�@06'7��9��up�@2006�N12��03���X�V
�P�O�D�C�G�\����2002�N�_��
�@�@Dutch Birding���f�ځASystematics of Larus argentatus-cacchinnans-��uscus complex revisited
�X�D�������T���ăJ�����ނ�ߐH����V���`
�@�@�J�i�_�ɂ�����s���w�҂���̕B5��9������
�W�D���Y�����ʓ��v�i�_�ѐ��Y�ȁj
�@�@���v�̌�������ѐ��Y�Ə��B���Y�ƂƃJ�����ނ̊W�B�i06'Apr.18up�j
�V�D�����\�����́u�o���g�C�̃L�A�V�Z�O���J�����Ƒ��̉��F���Z�O���J�����v(98�N3��)
�@�@�t�B�������h�̐�厏�A���[���f�ځB�u���F�����v�ɂ��Ă̔M���_���ł��B�i06'Mar.10�@up�j
�U�D�e�B���o�[�Q�����́u�Z�O���J�����̐��E�v(1953�N)
�@�@�u�ÓT�v�ł����A���ǂ�ł��������ʔ������Ƃɋ����܂����iFeb.20 2006up)
�T�D�j�[������[�Y����05'�R�����u�؍��ɂ����鈟��barabensis�A���ʂւ̽ï�߁H�v
�@http://www.birdskorea.org/barabensis.asp�ɂ���Feb.1.2006up�@
�S�D�n���u�T���Z�O���J�����̐�����ĂĂ����b�iBirding World��2001.14-6�̃R�����v��j
�@�@�Z�O���J����������I�H�B���̐^���ƈӊO�Ȍ����B�@Jan.6 2006up
�R�D�Z�O���J��������mongolicus�̋�B�ɂ�����z�~�i�Q�O�O�R�j
�@�@�����r�����������u�����D�Q�Q�ɏ��������e�̃T�}���[�B���̌�̘b�B Dec.24 2005up
�Q�DCrochet���m�̘_���iThe Auk��2002�N�V���f�ځj�̏Љ�
�@���̏d�v�Ș_���̓l�b�g�œǂ߂܂��BC���������������ɂ���^�J�����ނ�mt-DNA���́BDec.24 2005up
�P�D�Z�O���J�����͂��͂�u���̉��i���[�h�I�u�U�����O�j�v�ł͂Ȃ��B
�@ �����w�j��A�L���Ȑ��������ꂽ�BBirdingWorld�̃R�����̏Љ��їv��B Dec.24 2005up
�Q�T�D�q���N�r���J�����A�S�r�Y�L���J�����A�����J�����Ȃǂ̑������ς��Ƃ����_��
Phylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markers
J-M.Pons, A.Hassanin, P-A Crochet�A2005, Molecular Phylogenetics and Evolution, France
�@�i���̃v���Z�X�܂����q�ϓI�Ȍn�������\�z���邽�߁A�T�R��̃J�����ނ�mt-DNA�ɂ��Ĉ�`�q�z��̒������s�������̂ł���B���̌��ʁA������J�����ނ͂P�O���ɐ������ꂽ�B
�@�傫�ȂS�̃O���[�v�Ƃ��ẮA�ȉ��̂��̂�����B
�@��^�Ŕ������̃J�����i�F�Z�O���J����complex�j�A
�A�������̃J�����i�F�I�I�Y�O���J�������܂ޒ����A�W�A�O���[�v�j�A
�B�t�[�h�����Ԃ����J�����i�F�k��Ă̒��^�J�����O���[�v�j�A
�C�}�X�N�����Ԃ����J�����i�F�����J�����ɋ߉��̖k�����̃O���[�v�j
�@�O�R�̃����N�̎d���́A��`�w�A�`�Ԋw�A�s���w�̂R�ɂ���Ďx������邱�ƂɂȂ������A���̑��̂��͉̂~���ȉ��������Ă��Ȃ��B
�@�܂��A�~�c���r�J�����A�]�E�Q�J�����ȂǏ\���킪���̂S�̃O���[�v�Ɋ܂܂ꂸ�A�U�����`�����Ă���B�܂��ו��ł͌����̗]�n���c���Ă���Ƃ̂��ƁB���ɖ�肪�w�E����Ȃ���A����̕����ɍL����������Ă������낤�B���{�ŋL�^������J�����ނɂ��Ă͈ȉ��̂Ƃ���B
�@������Z�O���J����complex�ƃE�~�l�R�E�J�������́ALarus���Ɏc���Ă���B
�@�����J�����A�{�i�p���g�J�����A�n�V�{�\�J�����ɂ��ẮA�V����Chroicocephalus�ƂȂ���Larus������Ɨ��B
�@�q���J����Rhodostethia rosea�E�E�E�E�E�q���N�r���J�����Ƃ�������ɂȂ����B�P���Q��B�V����Hydrocoleus
�@�S�r�Y�L���J����Larus relictus�E�E�E�E�I�I�Y�O���J�������ƈꏏ�ɂ���āA�V����Ichthyaetus
�@�Y�O���J����Larus saundersi�E�E�E�E�E�Ɨ������V����Saundersilarus�ƂȂ�B�P���P��B
�@�A�����J�Y�O���J����Larus pipixcan�E�E�k��ā`�K���p�S�X�̃J��������ƈꏏ�ɐV����Leucophaeus
�@�����C�J����Larus atricilla�E�E�E�E�E�V����Leucophaeus(����j
�@�]�E�Q�J����Pagphila eburnea�A�N�r���J����Xema sabini�A�A�J�A�V�~�c���r�J����Rissa brevirotris�A�~�c���r�J����R. tridactyla�ɂ��ẮA�����͂��̂܂܂ł���B
�@�܂��A���̘_���̋����[�����������p����Ă���A�ʔ����B
�@�J�����Ȃ̒��Ƃ̋߉��W�ɂ��ẮA�A�W�T�V�ȁA�g�E�]�N�J�����ȁA�n�T�~�A�W�T�V�Ȃ������Ƃ��߉��Ƃ���Ă������A�Ȃ�ƃE�~�X�Y���Ȃ����Ȃ�߉��ł��邱�ƁI���L����Ă���B
�@Crochet(2002)�́A��^���F�J�����ނɂ�����X�̎퓯�m�́u���ʑc��������Ȃ��v�A���Ȃ킿���G�������̉ߒ��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���Ƃ������Ƃ����������A�������ɃJ�����ȑS�̂̑傫�Ȍn�����Ƃ��Ắu���ʑc��������Ȃ��v�Ƃ܂ł͂Ȃ�Ȃ������B
�@�I�I�Z�O���J�����Ɉ�ԋ߉��Ȃ̂́A�A�C�X�����h�J�����I�H�iFig�P�j�A�n�����ł͂����ǂ߂�A�Ƃ�������������B�Ȃ��������S���J�����ɂ��Ă̏��͑S���Ȃ��B���{�ł͌����Ȃ���ނɂ��Ă�����I�ȐV�m��������B
�@�����ޗ��͉H�тƋؓ��̗����ŁA�̎�n�̃��X�g������B�E�~�l�R�̍̎�n�͓V�����ƂȂ��Ă���B
�@���̘_���̗v��ɂ��ẮA�Ⴆ�Ή��L�̃T�C�g���猟�����Ė����ŃA�N�Z�X�ł���B�S���_�E�����[�h�͗L���Bhttp://www.sciencedirect.com�@���邢�̓G���[�r�A�W���p���̘_�������ł��o��Bhttp://japan.elsevier.com
�o�r�D���҂̈�lCrochet���m�́A2002�N�Ƀ��[���b�p�嗤�A2005�N�ɃA�����J�嗤�̃J�����ނɂ��Ă̘_�����o���Ă���B2008�N�ɂ̓A�W�A�̃J�����ނɂ��Ę_���\����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͊��҂��Ă���B
26.���V�J�����ƃA�����J�I�I�Z�O���J�����̐���Ȍ��G(�k��)
 �ʐ^�P�F���V�J�����ƃI�I�Z�O���J�����̌��G��
�ʐ^�P�F���V�J�����ƃI�I�Z�O���J�����̌��G���uPetersons reference guides, Gulls of the Americas �v,2007 Howell, Steve N.G.,Houghton Mifflin Company,ISBN-13;978-0-618-72641-7, P478-480
�@���̖{�ɂ́A�k�A�����J�嗤�̃J�����ތ��G��ɂ��Ă̏ڂ�������������B�J�����ނ̌��G����A��╁�ʂ̂��̂ƁA���������̂̓�ɕ����ďЉ�Ă���Bamazon.com�ōw�������B
�@�A�����J�Z�O��smithonious�~�V���J����hyperboreus�A�V���~���Vglaucescens�A�Z�O���J����vegae�~�I�I�Z�O��schistisagus�A���邢�̓I�I�Z�O���~���V�ɂ��āA���ꂼ��̌��G������Ă���X�|�b�g���x�[�����O�C�����ӂɂ���Ƃ����B�����́A�n�}�Ō������A��S�����ȉ��͈͓̔������A�A�����J�I�I�Z�O���~���V�J�����ɂ��ẮA���O���̏B�P�ʂ̍L���ł̌��G���i��ł���B�ʂ����āA�ʎ�ƌ�����̂��Ƃ������Ƃ�����B
�@���V�J�����FGlaucous-winged Gull, Larus glaucescens
�@�A�����J�I�I�Z�O���J�����FWestern Gull, Larus occidentalis
�@�u���V���g���B�ƃI���S���B�ɂ����Ă͗���̃R���j�[�̂V�T���܂ł����G�̂ō\������Ă���B�J���t�H���j�A�B�������݂ɂ����ẮA�A�����J�I�I�Z�O���J�����ƃ��V�J�����̉z�~�̂̂P�T�|�Q�T�������G��̓����������Ă���A�ꏊ�ɂ���Ă͂T�O���ɒB����B�J���t�H���j�A�B��쉺����ƌ��G��͑Q���I�Ɍ����Ă����B�v�i�O�q��P479�j
�@�A�����J�I�I�Z�O���J���������{�ɗ���\��������̂ŁA���G��̓����ɂ��Ă��v�`�F�b�N��������Ȃ��B
<���G��̌`��>�F�v��A�I�I�Z�O���J�����Ƃ̔�r
�@���G��́A���ϓI��痂����̂��A���L�����ŁA��[���c��{�A�W�F�Ȕw�̐F�iKodak6-8VS9.5-11.5�j�������Ă���B�E�B���O�`�b�v�̏�ʂ͔����F���ۂ����A�܂��͔������ɂȂ�X��������B�E�B���O�`�b�v���ł��ÐF�Ȍ��G�͈̂�ʓI�ɁA�^���O�̐�[�������ۂ��B������P9�̃~���[���Ȃ��Ƃ����Ⴂ�������āA�E�B���O�`�b�v�̃p�^�[���̓I�I�Z�O���ɂ悭���Ă���i���V�J�����̃p�^�[���ƃA�����J�I�I�Z�O���̍��������킹���悤�Ȃ��́j�B
�@���̔����A������G�b�W�͕��ϓI�ɃI�I�Z�O���J���������L���B�܂��A�I�I�Z�O���̓A�C�����O���Ԃ݂�тт邱�ƁA�{�̑��������s���Ă��邱�ƁA�����đ����Ԃ݂��������ƂȂǂɒ��ڂ��ׂ��ł���B
�@�ʐ^�̐����F�@�{����[�������ă��V�J�����I�������i���q 2008�N3���j�B�I�I�Z�O���J�����͂��̎ʐ^�̂悤��P6,P7�̃^���O��[�̔���������Western���L���B�����Ԗ��������B�A�C�����O���s���N����Z�ԐF�ł���_���Ⴄ�B�o�P�O���ł����F�ł���B���̎ʐ^�̓��V�J�����ƃI�I�Z�O���J�����Ƃ̌��G��Ǝv��ꂽ�B
27�D�����S���J����L.(c.)�@mongolicus�̉�����J���̐F�́H
Yesou,P. 2001 Phenotype variation and systematics of Mongolian Gull. Dutch Birding 23:65-82
 �ʐ^�F�Z�O���J����L.vegae�i�s���ɂ�08'�N2���j
�ʐ^�F�Z�O���J����L.vegae�i�s���ɂ�08'�N2���j�@�C�G�\(2001)�_�����ɂ́A�����S���J�����̓����Ƃ��āu�W�D�F�̉�����J���v�Ƃ����L�ڂ�����B���̌��_�����̐��Ȃǂ�������Ă��炸�A����vegae�Ƃ̔�r���ڂ��Ă��Ȃ����A�l�@�����ŁAL.cacchinnans�̉�����J�������F�ŁA�����S���J�������W�D�F�ł���_�����ʓ_�Ƃ��ċ������Ă��邽�߁A�����̃����S���J�����́A�u�W���D�F�̉�����J���v�����Ɛ��������B
���C�G�\�_���̕����v�V�T�y�[�W�̎ʐ^�m�O�D�P�O�O�̐���
�@L.c.mongolicus�A�����A�����ʁA�o�C�J���A���V�A1992�N�T���i�s�G�[���C�G�\�j�Amid-grey�̕��؉H�ƁA������W�F�̉�����J������ђ��J���A�����Ĕ��F�̏��J���B���ւ͕����I�ɉA�ɂ��W���D�F���������Ă���A�����͔��ł���̂������猩��Ɣ��������ʂ��Č�����B
���j�����Ŏg���Ă���'remige'�ƌ����P��͉p��̎����ɂ͂Ȃ��A�p���'feather'���Ӗ�����t�����X��̃��~�[�W���H�Ǝv����B
�@���_���f�ڎʐ^�ł̓����S���J�����́A�u�W���D�F�̉�����J���v�����J���Ə��J���ƂłR�i�K�̃O���f�[�V����������Ă���B����ɑ��āA���{�̃Z�O���J�����A�����鈟��vegae���ώ@�������A������J���́A�قڔ��F�Ɍ�����B�d�v�Ȏ��ʓ_�ɂȂ邩������Ȃ��B���ۂɎ�Ɏ���Ă݂�Ƃǂ�ȐF���Ȃ̂��낤�Ǝv���A���炳��Ă���vegae����ɂƂ��Ē������Ă݂��Ƃ���A���S�Ȕ��F�ł͂Ȃ��A��[�����ɂ��������ȊD�F���ۂ��F���������Ă����B�F���C���f�b�N�X�������čs���ׂ��ł������B���{�����͔����A�������J���Ƃ̐F�����͂Ȃ������B��O�ʐ^�ł������̓������x������P�[�X���������A�I�o�I�[�o�[�ɋ߂������ȏ����`���D���F�̍��ق�\������̂�2008�N���_�ł̗����ł̃f�W�^�����J�����ł́A�܂����Ƃ���Ƃ���ł�����B
�@��O�ł��̕������͂����蕪����ʐ^��͓̂�����A����A���w�@��ƋZ�p�̌���ɂ��A��葽���̒m�����W�܂邱�Ƃ����҂������B�n�捷��̍������邩������Ȃ��B�����Ȃ�A���Ȃ�N���ȉ摜�������A�����A�ʂŎ�Ԃ���~�܂�B
�@�ŋ߁A��s���̃����S���J�������B�e����@��������B���N�̔O��ǂ���W�D�F�̉�����J�����m�F�ł������A�R���̘A�ʎʐ^�̓��A�Q���͔���т��Ă��āA�m�F�ł��Ȃ������B�����ȍ��قȂ̂ł���B�܂��A���ʂ̃Z�O���J�����ł��B�e�����ł́A�A�ŁA�����D�F��тт邱�Ƃ�����B
�Q�W�D�q���J�����ɏo����߂ɂ́E�E�E
�@
�@���{�ŋL�^������J�����Ȃ̒��ŁA�ώ@�����Ȃ����q���J�����B�C�O�Ŋm���Ɍ�����ꏊ�͂Ȃ����l���Ă݂��B�q���J����Little Gull�Ƃ����p���̂Ƃ���A�S��25cm�Ə������A�N���n���A�W�T�V�ނ̂悤�Ȉ�ۂ�����Ƃ����B�c���Ɠ~�H�̓{�i�p���g�J�����Ɏ���B�A�����J�ł̓{�i�p���g�J�����ƈꏏ�ɍs�����Ă��邱�Ƃ������Ƃ����B�܂��A�A�W�T�V�̂悤�ȓ�����A�E�~�c�o���̂悤�ɑ��𐂂炵�Đ��ʂ������߂铮��������Ƃ����B
�@�k�C���ł̋L�^�����邽�߁A�ɖk�̃]�E�Q�J��������уq���N�r���J�����A�܂��͊O�m�̃X�y�V�����X�g�F�N�r���J�����A�Ƃ��������Ԃ�A�z���Ă������A���ׂĂ݂�ƁA�����ł͂Ȃ������B
�@�ɐB�n�͐��E�I�ɂ́A�J�i�_�A���V�A�k���A�V�x���A�i�o�C�J���̓������ʁj�́A�R�ɕ�����Ă���B�A�����J�嗤�֍L�������̂͂��ŋ߂̂��ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������B�ŏ��̃A�����J�嗤�ł̋L�^��1919�N�ł���B���[���b�p�A�n���C�A�A�����J���C�ݒ����A�ܑ�A�����嗤�A�Ȃǂʼnz�~����Ƃ����B
�@�k�A�����J�ł͂P�P���ƂP���ɓn��̃s�[�N������Ƃ����B�X���㒆�{�A�k�h�C�c�̌Ώ��ł́A�n��̑O�Ɋ��H���I���̂�҂��߁A����H���Q��ɂȂ��ĉ߂����Ƃ����B�x���M�[�I�����_�ł́A�W������P�O���ɁA�������ς����đ��v�P���H���C�ݐ���ʉ߂���Ɛ��肳���B
�@�t�����X�k�����p�h�J���i�h�[�o�[�C���̃t�����X������̖��́j�̃O���l���i�D�F�̕@���F�ًI�s������j�ł́A�P�P���n�߂ɒʉ߂̃s�[�N������Ƃ����B�R�O�|�U�O�{�̖]�����Ő�ǂ̏ォ��C�����Ă���A����m���͍��������B�C�͏������������B�S�A�T���̓n��̎����́A�C�����z���鏬���ɖ����Ă���B��������Ȃ���A�u�q���l�v��҂̂��悢��������Ȃ��B�����s�����Ƃ��́A���Ԃ����Ȃ��A�p���[�̂���@�ނ������������猩�邱�Ƃ͖����������A�q���J�����ȂǍl���Ă����Ȃ������B
�@���̒����A�����āA�������z�~���Ă���ꏊ���t�����X�̃{���h�[�n���ɂ���B���C���ŗL���ȃ{���h�[�n���̋�`����V�O�����قǓ�쐼�ɉ������ꏊ�ɂ��鏬���Șp�A�A���J�[�V�����p�̃e�V�����R�����ł���B�����̂g�o�͎��ɔ������A�֗����B�������p�ꂾ�i�j�B
�@�~�Ƀ{���h�[�w���烌���^�J�[�ł��̎��ӂ����̂��ʔ��������m��Ȃ��B�����������C�������߂������B���[���b�p�`���E�q��A�n�V�O���N���n���A�W�T�V�Ȃǂ����҂ł���B�܂��A�ᒹ���W�c�ʼnz�Ă���ꏊ���A���[���b�p�̌Ώ��ɂ���Ƃ����B�I�����_�����]�ԗ��s�����Ƃ��ɁA����炵�����̂������ƌ����悤�ȋC������i�����J�����̂悤�ŁA�l���^�̖͗l���������j���E�E�E�E�͂āH�B
�@���n���C�̉z�~�̂����Ȃ葽���A�G�W�v�g�̃i�C���f���^�ł͖��P�ʂ̋L�^������B�J�X�s�C�ɂ������Ƃ����B
�@�A�W�A�ɓ��ł̉z�~�͂悭�킩���Ă��Ȃ��B�ɓ����̎�ȉz�~�n�̓I�z�[�c�N�ł���Ɛ��肵���L�q���������B���݂ł́A�����̖k�����A�k�����A�����̂R�ɕ��U���ĉz�~����Ƃ���邪�A�ڍׂ͕s�����B2000�N�ɂ́A���������̒��쌧�ŁA�P�̂��B�e���ꂽ�B�ӊO�ƌ��߂�����Ă���̂����m��Ȃ��B
�Q�l�����FOlsen K. et. al 2003 Gulls of Europe, Asia and North America, Helm
http://www.parc-ornithologique-du-teich.com/english/accueil.htm
http://www.surfbirds.com/trip_report.php?id=1197
�Q�X�D�J�����ނ̃e�����A��D-���[�v
�@
�@��ʓI�ɁA�����̐��F�̍\���̗��[�ɂ̓e�����A�Ƃ����c�m�`�̒[�����тĂ���A��������邽�тɒZ���Ȃ�B�c�m�`�̕����̎d�g�ݏ�A�d�����Ȃ��炵���i���P�j�B
�@���ꂪ�Z���Ȃ��Ė����Ȃ������A�זE����������N����B�܂��A������������邽�߂̃e�������[�[�Ƃ����V�X�e��������B�e�������[�[�́A�c�m�`�ƃ^���p�N���̕����̂ŁA�Z���Ȃ����e�����A����������B���ΐ����p�������āA���e���������Ȃ��悤�ɂ���悤�Ȃ��̂��낤���B
�@���̃e�������[�[���������߂ɁA�C���́A���ނƂ��Ă͎����������Ƃ����B�Ⴆ�A�E�~�l�R�͔N��ɂ���āA�e�����A�[�[�̗ʂ��Ⴄ�̂ł́H�A�Ƃ�������������i2007���{���w��|�X�^�[���\�j�B
�@�e�����A�́AT-���[�v�Ƃ����w�A�s����ɐ܂�Ȃ����������ƁAD-���[�v�ƌĂ�镔���������Ă���B�c�|���[�v�́A�Ђ����قǂ��Ȃ��悤�ɁA��[��2�d���ɐH������łR�d�ɂȂ����悤�Ȍ`��ł���B ���̍\����wikipedia�̃e�����A�̐����}������Ƃ킩��₷���B
�@2000�N��Crochet�̘_���i�O���P�X�j�ɂ����Ă��A�e�����A��D-���[�v�ɂ��Ę_�����Ă���B
�@�e�����A�̌`������D-���[�v�ƌĂ�镔���́A��ʓI�ɕψِ��������A�C���Ƃ��Ă̑�^�J�����ނ́A���̕������A�\���I�ɓ��ٓI�Ȍ`��ł��邽�߂ɁA��^�J�����ނ́u���^���v�������炳���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������ɂ��ẮA�����Ŕے肳�ꂽ�BD-���[�v�ɓ��ʂȍ\���͔F�߂��Ȃ������̂ł���B�����āA�J�����ނ̔����ŕ��G�ȍ��فi���^���j�́A���G�ɂ���āA���̂قƂ�ǂ����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�@���ŏI�I�ɓ����ꂽ�B
�@
���P�F�v���C�}�[���ڍ�������������DNA�̕������X�^�[�g���邪�A�v���C�}�[�����̒��������A���Α��̂c�m�`���̕������Ȃ���Ȃ��Ƃ������R�ɂ��B
30.�I�[�X�g�����A�ŗL��n�V�u�g�J�����́A�E�~�l�R�̋߉��킾�I
�@�n�V�u�g�J����Pacific Gull�ALarus pacificus�́A�Z�O���J������菭���傫���A����Ƃ����̌^�ɉ����A�O���e�X�N�ȂقNj���Ț{�����B�I�[�X�g�����A��������^�X�}�j�A�ɂ����Đ�������B�C���^�[�l�b�g�ʼnp����������ƌ��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�������������A�k�����ɗ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv����B�~�i�~�I�I�Z�O���J����Kelp Gull�Ɉ�������āA��⌸���X���ɂ���B�����ɍ��l���̂��̂������ăJ�j�Ȃǂ�H�ׂ�炵���B
�@BirdingWorld��2007�N��Vol.20 No.8�̃R�����@�ł́A�ɓ��̃E�~�l�R�y�ѓ�ČŗL��Q��i�y���[�J����Belcher's Gull�A����сA�A���[���`���J����Olrog's Gull �j�ƌ`�ԓI�ɋ��ʓ_�������Ƃ̎w�E���������B�ؚ��ȃE�~�l�R���A����ȗY���̂悤�Ȃ����J�����ɋ߉��W������Ƃ͎v�����Ȃ��������A�c���̚{��[�������A�����̔w�������ۂ��A�����̔��ɍ����т�����A�������F���ȂǁA�m���Ɏ��Ă��镔���������B
�@�ٍe�Q�T�ŏЉ��2005�N�̃t�����X�̕����A�ɂ�����n�����i��Q�T���j�ł��A�u���̍����J�����ށv�Ƃ��āA��L�S��̋߉��W���L�ڂ���Ă����B�S���u�₵���嗤�̃J�����ނɗމ��W�����邱�Ƃ��ʔ����B
�Q�l�����F
�@Birding World Vol.20�@No.8
�APhylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markersJ-M.Pons, A.Hassanin, P-A Crochet�A2005, Molecular Phylogenetics and Evolution, France
31.�j�V�Z�O���J����3����i���[���b�p�j�ɂ���NOV.15 2008

 9��30��
9��30���j�V�Z�O���J����L.fuscus�́A���B�̃t�����X�Ȗk�ŔɐB�����^���F�J�����̈�ł���B
�@ ���{�n���̉\���͏��Ȃ����A�S���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���ɖk���ŔɐB������fuscus�́A���̂Q����Ɣ�ׂăA�t���J�Ȃǂւ̒������̓n������邱�Ƃɉ����A��O�I�Ȗ��s����Ƃ��ē�A�t���J�A�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̋L�^������A�������̕��Q�Ԃ肪�ۗ����Ă���B
�@�k�����烍�V�A�ɂ����ĔɐB���邱�̊��fuscus�͋}���Ɍ������Ă��邱�Ƃ�����A�t�B�������h�������R�j�����ق��A�����̂��߁A�ɐB�n�ɂ����đ�K�͂ȑ��֒������s���Ă���B���ɓI�Ȏ��ʕ��@�Ƃ��ẮA���ւƂ������ƂɂȂ邾�낤�B
�@���ފw�I�ɂ́A�z�C�O�����J����L.heuglini������Ƃ��Ċ܂ނƂ��������������B�������A2002�N�̃C�G�\�_���A2003�N��Olsen��̐����ɂ��ƕʎ�Ƃ���A���̌�̔��_�͓��ɖ����悤���B
�@��ʓI�ɂ̓j�V�Z�O���J����L.fuscus�̈���Ƃ��ẮA���fuscus�Aintermedius�Agraellsii�̂R������Ƃ����B�C�M���X�E�t�����X�Ō�����̂́A��҂Q����̕����B��킪���p���Ă��邩�ǂ����ABirdingWorld���������L���������Ă���B�������A�ŏI�I�ɂ́A�ɐB�n�ő��������ꂽ���ւ����ߎ肾�ƂȂ��Ă���̂ŁA����Ԃ̖�O���ʂ͓���ƌ������ƂȂ̂��낤�B�Ƃ�����苫�ڂ�����Ƃ������Ƃ��B
�@���́A�t�����X�A�u���^�[�j���n���ɂ����Ĉ���graellsii�܂���intermedius���ώ@����@����i�ʐ^�j�B�X���R�O���̏��́AP8/9/10�����H���Ƃ��Ȃ葁���B�����炭�t�����X�k���ȂǁA���̈���Ƃ��Ă͂��Ȃ��ŔɐB�����̂ł��낤�B�����~�H�Ɋ��H���ăS�}���炯�ŁA�S�}�͓��{�Ō���u�z�C�O�����n�i'taimyrensis')�v�����ׂ����B�̌^�I�ɂ͊p�����Ă���A�ʐ^�Ō������Afuscus��heuglini�Ƃ͈���Ă���悤�ȋC������B���ʂ͔����B�w���̐F�̓I�I�Z�O���Ɠ������炢�����Z���B�傫���́A�Z�O���J��������argentatus�Ɠ������炢�ŁA�a�̑��D��ł������Ă��Ȃ������B
�@�j�V�Z�O���J�����R����̂����A���fuscus�݂̂����������闝�R�́Afuscus�����^�ł��邽�߂ɁA�Z�O���J�����A�I�I�J�����A�y�уj�V�Z�O���J�������Q����Ƃ̍R���ɔs����邩��ł���B�P�X�R�O�N��ȑO�́A�k����fuscus�A�I�����_��intermedius�A�C�M���X��graellsii�̂R���킪���ǂ��ĔɐB���Ă������A��҂Q���킪�������A���ł́Agraellsii��intermedius���������ĕ��z���L���A�t�����X�k���܂ŔɐB���Ă���Bintermedius�́Afuscus�̗̈���������Ă���B
�@�̐��Ɛ����悪�g�債�����ʁA��Ԍ��G������ɂȂ�ƌ�������́A��^�J�����ނł������݂邱�Ƃ��ł���i�F�ٍe11,16,26�j�B�j�V�Z�O���J���������탌�x���ł͂����������̂��B
�@�܂��A���H�����͔ɐB�n���ɂ��Ȃ����Ă���Ƃ������Ƃ��ŋ߂킩���Ă��Ă���B
<�z�C�O�����J�����Ƃ̔�r>
�@�z�C�O�����J����L.heuglini�i���j�́A�~���[���P�����Ȃ��̂������B�r�͉��F�ł��邪�A�s���N�F�������Ă�����̂������B�j�V�Z�O���J����fuscus�ƃz�C�O�����̊��H�����͂قړ����ł��邪�A�j�V�Z�O���̕������x���i3���O������4����P10�������j�B�j�V�Z�O���Q�����11������12����P10�������Ƃ����̂��W���I�̂悤���B
�@�j�V�Z�O���̊��ȊO�Q����̓����͂��p�����Ă���X��������B�z�C�O�����ƃj�V�Z�O���R����̒��ŁA�����Ƃ��w���������̂͊��fuscus�ł���B
�@�z�C�O�������heuglini�ƁA�j�V�Z�O���J�������fuscus�͐����悪�ד��m�ł��邽�߁A���G���Ă���\�������邪�A�S�̂Ƃ��Ă͂悭�������Ă��Ȃ��B
<�Q�l����>
�EBirdingWorld Vol.20 No.4
�EBirdingWorld Vo.19. No.9
�@Olsen K. et. al 2003 Gulls of Europe, Asia and North America, Helm
�R�Q�D��X��u�J�������ۃ~�[�e�B���O�v
�@��X��u�J�������ۃ~�[�e�B���O�v���A�Q���Q�U������R���P���i���n���ԁj�܂ŁA�X�R�b�g�����h�ŊJ�����B�s�[�^�[�w�b�h�Ƃ����X�R�b�g�����h�̋��`�ŁA�J�����ނ���������W�܂�ꏊ�ł���B�J�Ó��͊ώ@�œK���Ԃɐݒ肳��Ă���A���Ԃ́A���n�ł̊ώ@�A��̓z�e���ASwallow Waterside Inn��,���\��italk�j������B
�@���R�W���A���R���U�B���Ƀz�e���̗\�̕�W�����͂��Ă��Ȃ��悤���B��Î҂�CrisGibbins����́A�O���ŏЉ���Ƃ���A���q�ɂ��������Ƃ�����悤���B�}�j�A�b�N��HP���ƂĂ��i�D�����B
http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com/
�@Aberdeen Airport���Ŋ��̍��ۋ�`���B��������A���낢��Ȍo�H���l�����邾�낤�B�����h���A�p���o�R���l������BHIS���ɑ��k����Ɨǂ��ł��낤�Beasyjet.com�Ƃ����ቿ�i�H���̃G�A���C�����A�����h����Luton��`�i�q�[�X���[�ł͂Ȃ��j����o�Ă���B��������̓����^�J�[�E�E�E���ȁH���͎d�������邩��s���܂��A�s�����l�͂����肢�������̂ł��B
�@�g�[�N�i���\��j�Ŕ����������l�͎��O�Ɏ�Î�CrisGibbins����ɘA������ƌ������Ƃ����A�g�[�N�̃e�[�}���ނ�HP�ɏo�n�߂Ă���B�ȉ��̂Ƃ���A�l�b�g�Ō������Ƃ��閼�O������ق�B�M�C���`����Ă���ł͂���܂��B
Martin Reid: �Z�O���J����complex�̎��ʂ̃~�X�e���[����ǂ���B�A�����J�嗤����̎��_�B
Martin Garner: ��^�J�����̎��ʂɂ�����V��������͉����H
Martin Collinson:��^�J�����̕��ފw�ɂ����関�������
Morten Helberg: �k�m���E�F�[�̃j�V�Z�O���J�����̓n��Ə�
Mars and Theo Muusse: �j�V�Z�O���J�����̗c�H�̕����I�Ȋ��H
Risto Juvaste: �@�ߊl�����ɂ������^�J�����̐��ʔ��f
Peter Rock: �s��̃j�V�Z�O���J�����͓n������Ȃ��X��������
Albert Cama: �̐H�̐�p�Ƃ��č����đ҂F�\���ɓq����J������
Michalis Dretakis: Heraklion�`�̑�^�J����
Annika Forsten: �j�V�Z�O���J�������fuscus�̊O���ɂ�����N��Ɋւ���o���G�[�V����
Paul Veron: ���̂P�O�N�Ԃ̃`�����l�������ɂ�����J�����ނ́u�K�^�v�̕ω�
Kalev Rattiste & Lauri Saks: �����H�ɂ����鐬�n���̔���́A�J�����̔N����ǂꂭ�炢���f���Ă��邩
�R�R�D�J�i�_�A�j���[�t�@���h�����h���Z���g�W�����̃J������
 �i�A�C�X�����h�J��������kumlieni�A���q�A��莁�B�e�j
�i�A�C�X�����h�J��������kumlieni�A���q�A��莁�B�e�j�@�J�i�_�̃j���[�t�@���h�����h���̋��`�A�Z���g�W�����iSt.John�j�ł́A�P�N���A����H��Kumlien's Gull�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�J�i�_���C�݂̃g�����g�����s�@�Ŗk�ɂS���ԁB���{����͂���ς艓���B
�@�G�A�J�i�_�̓g�����g�������R�ւ��炢����悤���B�J�i�_�ł����Ƃ��~���m�����������A��r�I���g�Ƃ���A�Y�o����Ζ��K�X�̉��b�Ōo�ϓI�ɖL���ȓs�s�ł���Ƃ����B
�@BirdingWorld�� Vol.20 No.4 �̖��͓I�ȋL���𒆐S�ɏЉ�����B
�P�j�J�i�_�J�����Ɍ���Ȃ��߂��J�����A��
�@�@���{�ł́A�A�C�X�����h�J����L.glaucoides�̈���Ƃ���邱�Ƃ������A����Kumlieni�B
�@�@���̒��҂́A����kumlieni�A���Ȃ킿Kumlien's Gull���A�A�C�X�����h�J�����ƃJ�i�_�J�����̌��G��Ƃ��Ă���B���̂悤�Ȍ��������Ă���l�̓A�����J�嗤�ɂ͂��Ȃ葽���悤���B�����������_���璭�߂�ƁA����Ȃ��J�i�_�J�����ɋ߂�Kumlien's���܂����݂��Ă��邱�ƂɂȂ�A�m���ɂ����ł͂����������o���G�[�V����������Ă���iPlate1�`8)�B
�@�@��������Q��~�H�̂��u�_�[�N�J�����A���v�Ƃ��Ď�����Ă���iPlate11�j�͈̂ӌ����������Ƃ��낾�낤�B��P��~�H�̏���̐F�ɂ��ẮA�f�ڂ��ꂽ�ʐ^����������L���v�V�����ɂ��ƂQ���̒i�K�ŁA�������ɋ߂��̂����ŁA���Ȃ�D���F�Ƃ��������̂�����������A�Ə�����Ă���B�܂��A�~�̏I���ł́A���Ȃ�̒E�F���Ղɂ��ސF�����蓾��Ƃ��Ă���B
�Q�j�A�C�X�����h�J�������glacoides�́ASt John�ɍs���Ό����邩�H
�@�@���̖₢�����́A�������炱���ɗ���o�[�_�[�ɂƂ��ăz�b�g�|�e�g(:�F��������Ȃ���)�ł���A�Ƃ��Ă���B�u�Β��̌I�v�݂����ȃj���A���X������̂��낤���H�@kumlieni�����̂U���́A���������Ƃ�������������Ƃ̂��ƂŁA�f��͂��Ă��Ȃ������������̂𐔌̌����A�Ə�����Ă���B����H�̒��̐��H�ł��邪�A�O�O�ɒT���Aglaucoides�܂��́A���Ȃ肻��ɋ߂��̂����邱�Ƃ��ł��������B������ɂ��Ă��A���̒��҂́A����Ȃ�glacoides�ɋ߂�Kumlien's Gull�����āA����͐^�̃A�C�X�����h�J�����ł͂Ȃ��Ƃ�������ł���iPlate8.9�j�B
�@�@���āA���̈ӌ����E���Ă݂悤�BGrant(1986)�́Aglaucoides��kumlieni�͑o���Ƃ��A�o���G�[�V�������L���āA���ʂ͕s�\�Ƃ��Ă���BMartin Garner,Yann Kolbeinsson,Bruce Mactavish��́A�u�p���ɖ��s����A���ʉ\��Kumlien's�̑�P��~�H�ƐM������̂̊O�����́A�H���𒆐S�Ƃ��ė��قɍL�����[�ɓ��B����l�X�Ȓ��F�i�ŐV���ł́j�̂��̂ł���B���W�ŁA�����ۂ�������H�A���������肵�Ȃ����A�����͐�[���班�������ɏ����ȃ}�[�N�������Ă���B�Q��������S���ɂ����āA���F�̕�����}�[�N�͔��ꂽ��A�������肷��̂������A���̊O������̓N���[�~�[�Ȓ��F���A���ɋ߂��F�ɗ��܂��Ă���B�v�Əq�ׂĂ���iBW���AVol.13 No.3�A2000�N�j�B�������A�p���ɂ̓J�i�_�J�����͓��{�Ɣ�ׂĔ�r�I���Ȃ����߁A�J�i�_�J�����Ƃ̔�r�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�R�j�V���J������S�̈���H
�@�@�O���[�������h�Ƃ��̎��ӂɏZ�ރV���J�����́A���̒n��̂��̂Ɣ�ׂĐ����̔w���̐F�A�c���̐F���A���Ȃ蔖�����߁A������S�Ԗڂ̈���'leucerectes'�Ƃ���������邪�A����ɂ��Ă͔ے�I�Ȉӌ��������BSt John�ł́A���̋c�_�̑ΏۂƂȂ锒���ۂ��V���J���������邱�Ƃ��ł���Ƃ���(Plate12)�B
�S�j'Nelson's Gull'
�@�@�A�����J�Z�O���J����L.smithonianus�ƃV���J�����̌��G��̂��Ƃ��ANelson's Gull�Ƃ����炵���iplate13.14)�B�Ȃ��A���argentatous�ƃV���J�����̌��G��́A���[���b�p�ł�VikingGull�ƌĂ�Ă���炵���B�x�K�V���ɂ��i�D�ǂ��������͖����̂��낤���H
 �V���J�������G��A�O�d���i�Q���j
�V���J�������G��A�O�d���i�Q���j�T�j�I�I�J����L.marinus�Ƃ��̌��G��
�@�@���B�Ɏ�ȔɐB�n������I�I�J�����������ł͏��������邪�A���̑����́A���V�J�����Ƃ̌��G��ł������Ƃ����B�A�����J�嗤���̃��V�J�����̔ɐB�n�ɁA�I�I�J�������Z�ݒ����Ă���\��������̂ł͂Ȃ����H�������������G�͓̂��{�ɂ�����邩������Ȃ�(Plate15.16)�B
�U�j�]�E�Q�J����Pagophila ebrunia�͌��邱�Ƃ��ł��邩�H
�@�@2007�N�ɂ͂Q�T�Ԃ��؍݂��āA�����̃o�[�_�[�����̉��b�ɂ����������Ƃ̂��ƁB���̒��̏Z���̉��l���M�S�Ȃf�t�k�k�d�q�r�������ŁA�a�t���ɐ����������ʂ��Ƃ����B���܂߂ɉp��Ńl�b�g�������Ă���Ƃ��������K�^�Ɉ��������邩������Ȃ��B(Plate25)
�V�j����smithonianus�ƈ���argentatus�̈Ⴂ
�@�@���̋L���̂�����̖ڋʂ��A���̂Q�̈���̑�P��~�H�ō����ۂ��^�C�v���m�̔�r�ł���A
�ׂ����L�q���Ȃ���Ă���B���{�ŁA���̂��Ƃ����ɂȂ邱�Ƃ͖����Ǝv���邪�A���ׂ̍������͓͂��{�ł̊ώ@�ɒʂ�����̂����邩������Ȃ�(plate17-23)�B
�W�j���̑��̏��
�@�@����������̐����ɂ��A�A�C�X�����h�J��������kumlieni�����W����A�m��l���m��r�����̗L���X�|�b�g�������Ȃ��Ă��܂����B
�@�@�l�b�g�ŏh��T���Ă݂�ƁAGULL HOTEL�Ƃ������̃z�e�������������A�J�����E�I�b�`���[��p�B�̏h���ǂ����͕s���B�@�n���̏��͈ȉ��̃T�C�g�Ō��邱�Ƃ��ł���B
�@�@http://www.web-nat.com/bic/newfound.html
�@�A�C�X�����h�J�����ɂ��Ă̎Q�l�����Ƃ��ẮABirdingWorld Vol.13 No.3�iIndentification of first-winter Kumlien's Gull)������B
�R�S�D�X��H�ׂ��J�����ނ̊ώ@
�@���͒��茧�̐V���苙�`�ɂ����Ċώ@�����s����Strix Vol.24,2004�N�łŕ����B���̌�̊ώ@�E�l�@�������ďЉ��B
�@

��Strix�ŕ����ώ@�̊T�v��
�@2005�N1������2���ɂ����Ē��茧����s�O�d�̒���V���`�i32��49�f,129��39�fE�j�̒��ԏ�ɂ����āA�I�I�Z�O���J����Larus schistisagus�A�Z�O���J����L.argentatus����ʂ̕X��ێ悷��s�����ώ@���ꂽ�B�@����V���`�͐��g���ʂőS���P�T�ʂ��ւ鋙�`�i�_�ѐ��Y�ȁA2005�j�ł���A�s�ꂩ��p�����ꂽ���⋙�D����̐��g����Ƃł��ڂꗎ�������Ȃǂ��̉a����g�rMilvus migrans�A�n�V�u�g�K���XCorvus macrorhynchos�A�A�I�T�MArdea cinerea�̏W�Q��1�N��ʂ��Ċώ@����A�~�G�ɂ̓I�I�Z�O���J�����A�Z�O���J�����A�E�~�l�RL.crassirostris�������ɉ����B
�@�����̒��ނ̊ώ@��2004�N11������2005�N4���܂ł̊ԂɌ��Q�`�R��A�v14��s�����B���g����Ƃ͖�������n�܂�x���Ƃ����O�ɏI���B�ז��ɂȂ�Ȃ��悤�z�����A�ώ@�͌ߑO�P�O���ȍ~���v�܂ł̊ԂɂQ�`�R���ԍs�����B���g����Ƃ��s���ݕǂɐݒu���ꂽ�Q�̖h�g��ł́A�I�I�Z�O���J�����y�уZ�O���J�����������ώ@����A���̐���12����{���瑝��300-1000�H�ɋy�Ԃ��Ƃ��������B�g�����̑N�����₷���߂ɍ`�ɗאڂ��鐻�X������_���v�J�[�ʼn^�э��܂ꂽ�N���b�V���A�C�X�́A�o��Ƃ��I���ƁA�s�v�ɂȂ������̂����ԏꂩ�~�n���̘H��Ɏ̂Ă���B�X��͑傫�Ȃ��̂Œ��a�P�O�����قǂł���A�����͂R���������ł������B
�@�X�̎��͂ɂ͕X��H�I������A���邢�͂��ꂩ��H�ׂ邽�߂̏��ԑ҂��Ǝv����̂������W�Q���`�����Ă����B�X��H�ב����鎞�Ԃ͂P�̓����菭�Ȃ��Ƃ��P���Ԉȏ�ł������B���̒��ŗn�����悤�ȍs���͌���ꂸ�A�f�����ۓۂ݂��Ă����B
�X�m���t�����Ă��鎞�ɂ͚{�Ōy���˂��������Ƃ�����ꂽ�B���ɂ͕����̂����݂��Ɍ���������Ă����B�H�ׂ�ʂ͌̂ɂ���Ă��Ȃ�Ⴄ�悤�Ɍ������B
���E�~�l�R�͉��̕X��H�ׂȂ����H��
�@���̓E�~�l�R���X��H�ׂĂ���Ƃ�����������Ƃ��Ȃ��B�{�ŕX������Ă�����ł���Ƃ������Ɍ������A���ݍ��ނƂ���͊m�F�ł��Ȃ������B��^�J�����́A��������H�ׂ邪�Ȃ��Ȃ̂��낤�B
�@�E�~�l�R�ɑ��čs��ꂽ�����ɂ��ƁA�C�������Ŏ��炵���͉̂��B����債�A�^�������Ŏ��炵���̂͏k�����F�߂�ꂽ�B����ɑ��쐶�̂̉��B�̑傫���́A���̒��Ԃɂ��邽�߁A�����̌̂͂�����x�A�͐쓙�Ő�����⋋���Ă���Ɛ�������Ă���B�ώ@��Ƃ��Ă��͐�ł̐����ێ�s��������������Ƃ̂��Ƃł���iBirder 2005�N4�����j�B
���ǂ̂悤�ȕX���D�ނ���
�@���D�̑D�q����ݕǂɎ̂Ă�ꂽ�X�́A���ԏ�Ɏ̂Ă�ꂽ�X�Ɣ�r���āA�J�����ނ����܂�Q����Ȃ������B���������邽�߂ł���悤�Ɏ��ɂ͎v��ꂽ�B

���ǂꂭ�炢�X��H�ׂ邩�H��
�@�ނ�͑����̏ꍇ�A�X���P�O�O�`�Q�O�O�b�b�͐H�ׂĂ���Ǝv��ꂽ�B�����P���ɐl�ԁi�̏d�U�T�����j�Ɋ��Z���Ă݂�ƁA�P�R�O�O�|�Q�U�O�O�����ɑ�������B�P�Ȃ�n�D�Ƃ������A�؎��Ȑ����I�~��������̂ł͂Ȃ����낤���B
���c���͕X���D�ށH��
�@�X��H�ׂɗ���Q�������ƁA���̗c���̔䗦�́A���`�S�̗̂c����Ɣ�r���Ė��炩�ɍ����Ǝv��ꂽ�B�@�@�c���͉��B��t���̋@�\�����n�ł��邽�߁A�C�����琅����ێ悷��@�\���キ�A�X�ɑ���~���������̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l����B���邢�́A�����Ƃ͈Ⴂ�A�a�Ƌ��ɊC�������ݍ��܂Ȃ��悤�ȁu�Z�p�v���擾���Ă��Ȃ����߂�������Ȃ��B
�@�X��H�ׂ�Q�̗c����Ƌ��`�S�̗̂c����ɗL�Ӎ������邩�ǂ������A���v�w�Ɋ�Â��J�C�Q�挟��Ŋm���߂悤�Ƃ������A���z�Ńf�[�^�����Ă��܂��A�v�Z�ł��Ȃ������B�����A����̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z����B�N������Ă݂܂��H�B���ɑ����Ē����Ă����܂��܂���B
�����`�̏�
�@���茧����V���`�A���茧���Y�s���싙�`(�F���̂���Ɠǂ݂܂��j�A��t�����q�`�ł������B���R�����È�`�A���挧���`�Ȃǂł͕X���Ȃ������B���q�`�ł́A���V�J��������сA�V���J�����̗c�����X������ł���̂����邱�Ƃ��ł����B
���֑�������Strix���̋x���͓ǎ҂Ƃ��Ă��A���e�҂Ƃ��Ă��A���Ɏc�O�ł������B��厏�̏����o���u�����v�Ƃ������̂́A�����̓ǎ҂Ƃ̊W���Œ����N���ō������̂ł���A���{�쒹�̉�̑傫�ȋ��S�͂ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���H
�R�T�D�N�r���J����(�T�o�C���Y�K��)������ɂ́E�E�E�E�E
�@���{�ł̋L�^�͏��Ȃ��B�O�m���������A�嗤�̐����ł̏o�����������B���̃J����������m���������C���E�I�b�`���O�̃X�|�b�g���R�I��ł݂��B���̊O�m���C�������҂ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�Â���܂܂�Ă��邩���m��Ȃ��̂Œ��ӂ��ꂽ���B
�P�D�p���X�y�C���Ԃ̃t�F���[
���̃t�F���[�̍ő�̃|�C���g�́A��^�D�Ȃ̂ŗh�ꂪ���Ȃ����Ƃ��B�C���ώ@���̏��^�D�́A�h��邵,�`����(�T���a�j���L���D�����邵�A�O�r�͎g���Ȃ��B1999�N��8����{����10�����{�܂ł̐���30-40�q�C�̂����A�ڗ����̃o�[�_�[��������̂͊���s�������A�N�r���J������13��ƋL�ڂ���Ă���B�i�K�X�N�W���Ȃǂ̊C�b�ނ�������Ƃ̂��ƁB�r�X�P�C�p�̑嗤�I�̉��ɓ�����|�C���g�������Ƃ��o���m���������Ƃ����B������3���ŁAPlymouth-Santander(Brittany Ferries)�APortsmouth-Bilbao(P&O ferries)���T�Q�։^�s�B�����h������͂��ꂼ��A�R�O�Okm�܂��͂P�O�O�����قǗ���Ă���B
�Q�l�����FBirding World Vol.13-No.4�@
�Q�D�A�����J�J���t�H���j�A�B�����g���[�p�̊C���E�I�b�`���O�{�[�g
�@8�����{-9������̋L�^�������B�T���t�����V�X�R����o�X�Ń����g���[�܂Ŗ�R���ԁA�A�����J���w�̋����X�^�C���x�b�N�́u�ʋl�����v��K�˂���A�����قŋ���ȃP���v��������A�C�݂Ń��b�R�A���`�ŃJ�����ނ��ώ@�����肵�Ȃ���D��҂̂��y������������Ȃ��B�T1����x�̏A�q���H�����ɂ��Ă̏��ɗ��ӂ��ׂ����B�V���i�K�X�N�W����V���`�Ȃǂ�������\��������B
http://www.montereyseabirds.com/index.htm
�R�D�A�����J���V���g���B��Westport
�@8���`9���ɋL�^������BWestport�́A�V�A�g������P�Q�O�������炢���ꂽGray's harbour�n��ɂ���BPhil Anderson�Ƃ����l�����C���c�A�[����悵�A���U��������v�܂ŏ����ȃ{�[�g�ʼna�i�`�����j���T���Ȃ���s������B�W���͍����̃V�[�Y���ŁA�閾���O���烌�X�g�������J���Ă���B�W���P���ƂQ���ɎQ�������l�́A�N�r���J�������܂ނR�O��ނ����Ă���B�f�[�^���������A�����g���[���n�������͏��������A�W�����s�[�N�Ǝv���A�q�b�g���͂��Ȃ荂���B�܂��A�`�̓J�����ނł����ς��Ƃ����̂��������B
�@�ʋt�F���[��N�W���E�I�b�`���O�{�[�g�ł��C�����݂邱�Ƃ��ł���A�Ƃ��邪�A�N�r���J�����͂ǂ����낤���H�B�E�~�X�Y���ށA�C�K���ނȂǂ����͓I���B
�Q�l�����FBirding World Vol.16 No.2
http://www.westportseabirds.com/about.html
�R�U�D�z�C�O�����J����L.heuglini�ƃj�V�Z�O���J����L.fuscus�̂Q�N�ڈ������̎��ʂɂ���
 �s����iβ�����G��Ǝv����j2004�N3/26���茧���]��
�s����iβ�����G��Ǝv����j2004�N3/26���茧���]���@�z�C�O�����J����L.heuglini�ƃj�V�Z�O���J����L.fuscus�́A���ʂ��]��ɂ������ł��邽�߁A�쒹�ώ@�l���̑����p���ɂ����Ă��A�z�C�O�����̓n���ɂ��Ă͌��y����������X���ɂ���B
�@���LHP�ł́A�k���[���b�p�ɂ����āA��r�I�킩��₷�����ʕ��@�Ƃ��āA�t�̓n�莞���̑�1��~�H��������1��ĉH�ւ̈ڍs�����ɒ��ڂ��Ă���BHP�̊e�̂̓������������A���m�ȍ�������Ǝv��ꂽ�B
�@������'taimyrensis'�ƃz�C�O�����J���������ʂ���Ƃ����ɓ��ݏZ�̃J�������D�ғI�ȋ����ɂ��Q�l�ɂȂ邩������Ȃ��B
�@�Ȃ������Ńz�C�O�������邢��heuglini�Ƃ̓z�C�O�����J�������heuglini�������Bcacchinnans�̓J�X�s�L�A�V�Z�O���J�������Afuscus�̓j�V�Z�O���J���������w���B�i�h�y�y�Ƃ́A����ۂŔc�������ׂ������ł���B
�@����̘a��́A�킩��₷���ɏd�_��u���A�u�Ӗ�v�����߂Ȃ̂ŁA���e�̌������ɂ��Ă͒��ӂ��ꂽ���B
��BirdingWorld��Vol.19 No.2 2007�̏Љ�L�����灄
�@�z�C�O�����J�����̎��ʂ́A�J�X�s�A���L�A�V�J����cacchinnans�Ɣ�ׂ�ƕs�����ȕ���������B
�@�������A2�N�ځi��2��calendar year�F���L�Q�Ɓj�́A���B����k�������́A3������6���܂ł́A��r�I���ʂ��₷���B���L��website�́A�j�V�Z�O���J��������graellsii,fuscus,intermedicus�A����уz�C�O�����̊��H�̃o���G�[�V�����ɂ��Ă̍l���������Ă���B2009�N7���Ɏʐ^���lj����ꂽ�B
�@http://www.gull-research.org/heuglini-id/conclusion.html
��HP��蔲���a��
�@�ȑO��HP�ł́A�����Ńj�V�Z�O���J����fuscus�Aintermedius�y��graellsii�ɍ�����heuglini�̗l�X�ȃo���G�[�V�����ɂ��ċL�q���Ă����B���̎��ʎ��̂́A���ٓI�ŁA�L�q�I�Ȏd���ł���B���s���Ă���heuglini���^���̂�\�ɂ��邢�����̓����ɌX�����邽�߁A�������邱�Ƃ́A���Ȃ荢��ł������B�����ƂȂ�L�[�|�C���g����̑I�����A��O�I��heuglini�̂������ʂ��邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��낤���H
�@���V�A��Syktyvkar�Ŋώ@�����z�C�O�����ɂ��ẮA�O���I�ȓ������������A���̒n�ɂ����ẮA�u����2�N�ڂ̌́v�A���u������̂Q�N�ڂ̌́v�́A�z�C�O�����ł���Ǝ��M�������Č�����B�������������́A���Ԃ�A���̑�^�J�����Ɠ����悤�ɔ������A�����̓T�^�I�ȃj�V�Z�O���J���������Ƃ���ׂđ傫�ȈႢ������B�����̌̂́A�z�C�O�����̗�O�I�Ȍ̂̎��ʂɃA�v���[�`���邽�߂̘_���I��ՂƂȂ邾�낤�B������Syktyvkar�ɂ����Ă͓T�^�I�ȃz�C�O�����ɉ����āA�������u����Ȍ́v������B�����́A�命���̓����I�Ȍ̂Ƃ́A�H�F�E���H�Ejizz�̂ǂꂩ�A�܂��͕����̓����ɂ����āA�قȂ��Ă���B���̌̂₱�͓̌̂T�^�I��graellsii���邢�́Aintermedius�ƃI�[�o�[���b�v����B�������Agraellsii��intermedius�ɂ��Ă������I�Ƃ͌������A�����̃o���G�[�V�����ɂ��Ă͑��֒����ɂ���ċL�q���邱�Ƃ����݂Ă���B
�����ʊ��
�@��r�I���ʂ͗e�Ղł͂��邪�A��O�I�Ȍ̂��������āA�j�V�Z�O���J�����ƃI�[�o�[���b�v����B�����ł͂��̃o���G�[�V�����ɂ��Ă����y����B���ʂ̊�Ƃ��āA���V�A��Syktyvkar�ɂ����Č���ꂽ�T�^�I�Ȃ��̂������āA�����I�ȃz�C�O�����J�����Ƃ���B
�P�D���H
�@�j�V�Z�O���J�����̑�P��~�H�����S�ɉH�F�̍X�V���������鎞���́A���܂�킩���Ă��Ȃ����A���fuscus�ɂ��Ă͊��m�ł���i���̈���graellsii��intermedicus�́A���z���L�������A�ɐB�����������ɂ���邽�߂Ǝv����B�����������j�B
�@�z�C�O�����̓j�V�Z�O���̋��e�͈͓��ɂ͂��邪�A�ǂ��炩�Ƃ����Ί��fuscus�ɋ߂��B�Ẵ��V�A�Ō�����z�C�O�����́A�J���ƎO��̂��ׂĂ��z�~�n�ɂ����Ċ��H���A����Ɣ��H�̈ꕔ�������͑S�����������Ă�����̂�����B�j�V�Z�O������intermedius�͂P��ڂ̓~���z�������_�Ŏ�������H���Ă����̂͂P�Ⴕ���Ȃ��iRik Winter)�B
�@�����̃z�C�O�����i�P�O�������j�͂P��߂̓~���I���Ă���������H����B��P��ڂ̓~�̊Ԃɂ��ׂĂ̏�������H������i�T�ᖢ���j������B�H�ł����Ă��A�T�^�I��fuscus�Ɠ����̊��H�헪�������̂����邩������Ȃ����A���̂��Ƃ́A����graellsii��intermedius�ł́A�r�ւȂǂɂ���ďؖ�����Ă��Ȃ��B�z�C�O�����͂P��ڂ̓~�̌�ŏ����̏���݂̂����H����B�����Ėk�A��O�Ɋ��H���ꎞ��~����̂�������Ȃ��B�����Ŏ����Q�́i�����N�j�̂悤�ɕ����ʂ�̘A���ł���K�R���͂Ȃ��B
�@����ɂ��Ă��������Ƃ�������B���Ⴊ���Ȃ��̂ŁA���Ƃ������Ȃ����A�P��ڂ̓~���I���Ă���c��̏����̏���Ǝ�������H���邱�Ƃ�����B
�@�d�v�Ȃ̂́A�����̊ώ@���s��ꂽ�̂́A�āA���Ȃ킿�Q�N�ځicalender year�j���ƌ������Ƃł���B�~��ʂ��Ă̊��H�̉ߒ��ɂ��Ă͊m�F�������ɐ��肵�Ă���B
�Q�D���
�@�����Ƃ��z�C�O�����炵�������I�Ƃ́A�Q�N�ځi�����j�̏t���珉�Ăɂ����ĒW���u�p�E�_�[�u���[�v�̌��H����щJ���ł���B�����̉H�F�́A�����ƂĂ��V���v���ȃp�^�[���i�F�ÐF���͉H���̃V�}�݂̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������j���������߁A�����Ɏ���B������heuglini�̔N��𐄒肷��͓̂�����Ƃł��邪�A�قƂ�ǂ̂Q�����̂͂Q�Ԗڂ̉H�т̒��ɂR�Ԗڂ̉H�т�����B�����Ƃ����H�̐i�s�����̂́A�R������graellsii�Ɏ���B
�R�D�����Ƒ̊�
�@�z�C�O�����̓����Ƒ̊��́A�����قƂ�ǔ��F�ɋ߂��A���_�ׂ͍��l�b�N���X�̂悤����̉����A����Ɍ��肳���B
�S�DJizz�i�����ڂ̑���ہj
�@�j�V�Z�O������graellsii��intermedius�Ɣ�ׂāA�قƂ�ǂ̃z�C�O�����͂��Ȃ�G���K���g�Ɍ�����B�����ȓ��A�����X�����Ƃ����������A������ƒ������ɂ����̂ł���B�H�F�ƍ��킹�čl�����cacchinanns�ƊԈႦ�Ă��܂������ł���B�������Ƒ̊��A�̂ɂ���Ă͌��H�ƉJ���̃p�^�[�������Ă��Ă��A�ގ����͍����B
�@�����p���A�ÐF�̏�������A�~�G�̊��H�����A�ċG�̊��H���������鎞�����m�F���邱�Ƃɂ���āAcacchinnans�Ƃ̌�F��h�����Ƃ��ł��邾�낤�B���ׂẴJ�����ނƓ����悤�ɁA�z�C�O�����̑̌^�͕ω��ɕx�ނ��߁Acacchinanns�ɂ悭����jizz�͔̌̂r������ׂ��ł͂Ȃ��B
�@
�T�D���̗���
�@�z�C�O�����̗��̗����́A�Ȃ��Č����ɔ������̂������B���̗����ɈÐF�������̂ɂ́A�ׂ������Ȃ̓������e�H������B
�@�@���ȉ��A����
�⒍�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��Gulls�@of Europe, Asia, North America P392��蔲����
3.First-spring/summer heuglini(3-10��) �t�܂łɁA�w�A���H�A�����ĉJ���̈ꕔ�������Ɠ����悤�ȊD�F�ɂȂ邪�A���ܒW�F�݂̉H�F������A�����Ēʏ�͒W�F�̒W�F�Ӊ����Ă���B�܂��A���i���ɏ�������j�Ɣ��H�A�������������H�͑���~�H�����������Ƃ̃R���g���X�g�������ł���B
���̔��������͌����B�{�͓��F�Ő�[�ɍ����`�b�v������B���ƕ����͔��F�ŁA�㓪���ɍׂ����S�}�͗l�������Ă���B
�⒍�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����p���F
�@�f�B�X�v���C�̂P��ŁA�s���w�I�ȃe�L�X�g�ɏڂ����Bcacchinnans�ł͓����I�ȁu�A�z�E�h���l�p���v�Ƃ����������L�������L�����삪������Ƃ����B
�R�V�D�~�g�R���h���A����ъj�̂c�m�`�����炩�ɂ����Z�O���J���������̂̐i��
�uIntrogressive hybridization and the evolutionary history of the herring gull complex revealed by mitochondrial and nuclear DNA�v
�@90�N��㔼���瑱�����J�����ނɊւ����A�̏d�v�Ȉ�`�w�I�����_���ɂ����ẮA��Ƀ~�g�R���h���A��DNA�ɂ��Ă̐��ʂ��_�����Ă����B�������Amt-DNA�͕�n��`�q�����p�����Ă��Ȃ��̂����ł������B���̘_�������ł́A�j��DNA�ɑ���AFLP�Ƃ�����`�q�}�[�J�[���g�p���邱�Ƃɂ��A�Q�m�����C�h�Ȑ��x�̍�����`�����ꂽ�BAFLP�́A1995�N�ɔ������ꂽ��`�q�}�[�J�[�ł���A��x�ɐ��S�̈�`�q���ɂ��Ă̏�����邽�߁A��I�Ȉ�`����m��Ƃ����ړI�ɍ��v���Ă���B���̘_���̏ꍇ�A230���̈�`�q���ɂ��Ă̏����ꂽ�Bmt-DNA�ɂ�鍡�܂ł̌������ʂɂ͑傫�ȊԈႢ�͂Ȃ������Ƃ������_���̂ɂ͋����͂Ȃ����A�d�v�Ș_���Ǝv����B
�@�@�@�@�@�@http://www.biomedcentral.com/1471-2148/10/348
���_���̑�Ӊ���
�~�g�R���h���A����ъj�̂c�m�`�����炩�ɂ����Z�O���J���������̂̐i���ƃC���g���O���b�V�����I�Ȍ��G
���̘_���̈Ӌ`�F
�@mtDNA�i�~�g�R���h���A�̂c�m�`�j�̕��͂ɂ���āA�M�҂�́A�O�̘_���Łi2003�j�̃Z�O���J���������̂̎�̎핪���̃��f���̓����O�����ł͂Ȃ��A�����ƓK�������f��������Ƃ������Ƃ��������B�������A�Z�O���J�����ƃV���J�����ɂ��ẮAmtDNA�̃n�v���^�C�v�ɋ��ʑc�悪�Q����悤�Ȃ��������A�Ƃ����\�z�O�̌��ʂ������ꂽ�B�܂�mtDNA�����ł́A�Z�O���J���������̂̎핪���ɌW��̐��ϓ��ɑ��鐳�m�ŏڍׂȓ��@�͓�����Ƃ����������B�܂�A�~�g�R���h���A�����łȂ��A����F�̂ɂ��Ă���`�w�I���͂��ׂ��������̂ł���B
���ʁF
�@�ȏ�̗��R�ɂ��A�����̎�ɂ��āA�i���j���č\�z���邱�Ƃɂ����B����́AmtDNA�̃V�[�P���X�y�сA230�̏���F�̂̑������ꂽ�t���O�����g���̑��^�I��`�q���iAFLP)�ɂ����̂ł���B��̃��x���ł́AmtDNA��AFLP�̈�`�q���͑�܂��Ɍ����Ē��a���Ă����Bargentatus��hyperboreus�����łȂ��A�I�I�J����L.marinus�ɂ����Ă��A�Q�ɋ�ʂł���mtDNA�̃n�v���^�C�v�̃O���[�v�����邱�Ƃ��킩�����BAFLP�f�[�^�ɂ��Ă��A������argentatus�Ahyperboreus�����mariunus�̌̌Q�ɂ�����Q�̃T�u�O���[�v�����邱�Ƃ��킩�����B����́A�Z�O���J���������̂̌̐��ϓ��̃V�i���I���핪���ɉe�����Ă���Ƃ����ŏ��̉������x��������̂ł���B
���_�F
�@�����̂Q�̋��ʑc������R��̃J�����̂��ꂼ��ɂ��āAmtDNA�̃C���g���O���b�V�������A�l�X�ȔN�㖈�Ɍ̌Q�ԁA���邢�͎�̌Q�Ԃł������s��ꂽ�B����ɁA�����̏���F�̂�AFLP��`�q���Ɋ�Â��A�R��̃J�������ꂼ��ɂ��āA��ʉ\�����t�s�����̐����v�I�V�i���I�̏؋����������B�Z�O���J���������̂̐��m�Ȉ�`�w�I�����j�ɂ��ẮA����ɐ����ȓ��@�͂܂��s�\�ł���A����̉ۑ�Ƃ��ẮA��葽���̏���F�̂̃V�[�P���X��K�v�ł���B
�R�W�D�n�����̍��قɂ��ẴJ�����ނ̈�`�w�I�����i�h�C�c��j
�@�J��������R�J����brachyrhynchus�͕ʎ�ł���Ƃ������A�����W�]�ȂǁB
Molekulargenetische Untersuchng in der Gruppe der Moewen(Laridae)�@zur Erforschung der
Verwandtschaftsbeziehungen und phylogeographischer Differenzierung
http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/980/
Sternkopf, VIviane
�@���̘_���́A�O���Ŏ��������q�}�[�J�[�AAFLP���g�p������`�q���͂̎��̌����i�K�̓W�]�������Ă���B�~�i�~�I�I�Z�O���J����(kelpGull)�ƃJ�����iL.canus�j�ɂ��ẮA�A�t���J�����Ăɑ��g���n������A�P���Q���������ɓn�����̂����Ȃ葁������ł��������Ƃ������ꂽ�B�����ٓI�Ȍ`��������Ă���̂ŁA��͂肻�����Ƃ������z���������B�J�����S����ɂ��ẮA����R�J����brachyrhynchus���A���̂R����Ƃ͈���āA���S�ȕʎ�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B���{�̓~�̒��q�⓹���Ō��邱�Ƃ�����̂ŁA�v���ӂ��낤�B�v��͉p��ł��邪�A�{�����h�C�c��ł��邽�߁A���_�ɂ�����v���Z�X���悭�킩��Ȃ������̂��c�O�B
�v��̉���
�P�D�J�����ނ̌n��
�@��{�I�ȑ��i�V���j�ƁALarus���i�U�̈�`�I�ɕ��������U�̃O���[�v�j�ɂ��Ă̖��m�Ȍn�������������B���܂ł̂U�̃T�u�O���[�v�͂��̂܂x�����ꂽ�B�u�����������V������^�J�����ށv�̊֘A�����A���̘_���Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B�d�v�Ȃ��Ƃ́A��{�I�ȃJ�����ނ�taxa���Ȃ��ł���Signal�i�Ӗ��H��H���j���������Ă��邱�ƁA����LDH�i���F���_�E���f�y�f�j�̃V�[�N�G���X�ɂ����錇����`�q�ł���B���̂��Ƃ́A������{�ł��Ȃ������A����Ȃ�^��ɂ��Ē�������̂ɖ𗧂��낤�B
�Q�DAFLP
�@1995�N�AVos��ɂ���āA����܂ł̑��Q�m���̒m����K�v�Ƃ��Ȃ�AFLP�̎�@���J�����ꂽ�B�����A���[���b�p�Z�O���J����argentatus�A�V���J�����A�I�I�J�����̂R����܂ނV��taxa�������B����̓~�g�R���h���A�Ə���F�̂̃p�^�[�����r���邽�߂̂��̂ł���B�~�g�R���h���A�ɂ����ẮA�����R��̃C���g���O���b�V�����i��`�q�Z���j���m�F���ꂽ�B�V���J�����́A�N���C�h�P�̃n�v���^�C�v���l�����Ă����B����̓��[���b�p��argentatus�̂Ɠ������̂ł���B�I�I�J�����̓A�����J�嗤�ɋ���Ƃ��ɁA�A�����J�Z�O���J�����ɑ��ăN���C�h�Q�̃n�v���^�C�v���������Ă����Bargentatus�͒��������ɐB�R���j�[���ׂĂɂ����āA�N���C�h�P�ƂQ�������Ă���A�Q�̋��ʑc������p�^�[���ł������B�n���w�I�ȃO���f�[�V�����ɂ���āA��̒n���ŃN���C�h�Q����葽��������̂ɑ��A�k�̒n���ł̓N���C�h�P������������B�Â�����̃j�V�Z�O���J�������N���C�h�Q�̃~�g�R���h���A�Q�m����argentatus�̌Q�Ɉړ����A��������̑S�Ă̕��z��ւ̊g�U���A�Q��ڂ̕��z�g��̒��ŋN�����B����F�̂̂S�̈�`�q���C���ɂ���āA���Ȃ��p������geneflow���L������邱�Ƃ������ꂽ�B
�R�D�~�i�~�I�I�Z�O���J�����iKelp Gull�j
�@�S�̈���ɕ��ނ����iJiquet 2002)�B���̌̌Q�̒����́A�R���g���[���̈�iHVR I�j�Ɠ����悤�Ƀ~�g�R���h���A�̃`�g�N���[������ND2�Ɋ�Â��čs��ꂽ�B���������R���j�[�Ԃ̖��m�ȕ������F�߂�ꂽ�B�P���v�J�����̋N���̓A�t���J�암�ł���B�ŏ��̕��z�g��ŁA�A���[���`���ɐN�����A�����ăP���Q���������i��C���h�m�̌Ǔ��ŁA���Ȃ���ٓI�Ȍ`���������Ă���B��Ғ��j�A��ɂƑ������B�Q��ڂ̕��z�g��ŁA�`���ɐN�����ē�Ă𐪕������B�`���ƃA�t���J�암�̌̌Q�͍��ł��~�g�R���h���A�̃n�v���^�C�v�����L���Ă���B�j���[�W�[�����h�ƃ`���^�������̌̌Q�͐V�������Ƃ��m�F���ꂽ�B�I�[�X�g�����A�̌̌Q�́A�������ł��邪�A�Ō�̕��z�g��ɂ����̂Ǝv��ꂽ�B
�S�J����L.canus
�@�P���v�J�����Ƃ͔��ɁA�J����L.canus�ɂ͓�����`�q�V�[�P���X��ɁA�S���قȂ��`�q�I�ȕ������F�߂�ꂽ�B�J����L.canus�͕\���^�ɂ��A�S�̈���ɕ��ނ���Ă���B���тR����canus,heinei,������kamtschatschensis�̂R����́A�C�ӌ�z����̌Q���`�����A���̔��ʁA�����ЂƂ̈���brachyrhynchus�͑��̂R�̈���Ɩ��m�ɋ�ʂ���邱�Ƃ��n�����ɂ��킩�����B�]���āA����brachyrhynchus�͊��S�ȓƗ���Ƃ��Ĉ������Ƃ����B
�T�D�r�m�o�̕��͂ƁA�U�D�����̓W�]
�@���낢��ȃk�N���I�`�h�̃|�W�V�����iSNPs�FSingle Nucleotide Polymorphism:�ꉖ��^��)�́A���q�i���̐����ɕK�v�Ȋ�{�I�Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�R�Q�O�O�O�̒f�Ђ�CROPS�i���F���q�}�[�J�[���g���Č̖��̍��ׂ镪�͕��@�ŁAKeygene�Ђ�HP�ɏڂ����}����ŁA���Ђ̎�@�������Ă���B�j���g���čs��ꂽ�B���ǁA�P����SNP�����܂V�S�O�O�̂��낢��Ȓf�Ђ����o����A�Q�S�O�O�O�̒f�Ђ͈�`�I�ȃo���G�[�V�����������Ă��Ȃ������B�]���āASNP�̔䗦�́A�T�O�O�k�N���I�`�h�ɑ��Ĉ�ȏ゠��B����́A�q�g�̂悤�ɂٓ��ނł�������̂Ɠ��l�ł���B
�@�����I�ȓW�]�Ƃ��āA���낢��Ȉ�`�q���ɂ��Ă̐V�m�����������ꂽSNP�̃^�C�v�������s���A����F�̂ƃ~�g�R���h���A���r�����悤�ɁA����F�̂Ɛ����F�̂�SNP���̔�r�����邽�߂Ɏg����悤�ɂȂ��Ă������낤�B
�p�^�S�j�A�̐������N�W����H�ׂ�~�i�~�I�I�Z�O���J����
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8438249.stm
�R�X�D�N�W�����P���p�^�S�j�A�̃~�i�~�I�I�Z�O���J����
�@BBC�̃j���[�X�ԑg�B
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8438249.stm
�@���H�̃~�i�~�I�I�Z�O���J���� Kelp Gull, Larus dominicanus���A�R�N�N�W��gray (or grey) whale, Eschrichtius robustus�ɌQ�����Ă���B���サ���N�W���̓��ɚ{�������ȏ�˂��h�����Ă���B�R���[�Q�������Ղ�̔�ƍ��J�����[�̎��b�w��H�ׂĂ���B�p�^�S�j�A�i�A���[���`���j�̃J���������́A�������N�W����H�ׂ邱�Ƃ��w�K�����̂��B
�@���Ɏq���̃R�N�N�W�����_���A���̃X�g���X�ɂ�鎀�S�����}�㏸���Ă���B�I�̑���̒��a��T�O�����̍E���J����ꂽ��A�C�������ċ����ɂȂ��Ă���Ԃ����N�W���̉f���͒ɁX�����B��N�W���́A���т��U��グ�ĈЊd�����邪�AKelp Gull�����͋C�ɂ��Ȃ��B�@
�@�������N�Ɏn�܂�������ł���A���N����}�����Ă���B���̒n��ł͊m�F����Ă��Ȃ��B�l�Ԃ̃S�~�̂ď���a��Ƃ��ăJ�����ނ̌̐����}���������A�S�~�̂Ȃ����Ԃɉ쎀����̂�����B�����c�邽�߂ɁA�Ȃ�Ƃ��V�����a���J�����悤�Ƃ������ʂ����ꂾ�Ƃ̂��ƁE�E�E�E�E�E�B
�S�O�D�A�����J�I�I�Z�O���J�����ƃI�I�Z�O���J�����̎��ۂ̎���


�@
�@�A�����J�I�I�Z�O���J����L.occidentalis�̓A�����J�嗤���C�݂̑�^���F�J�����ł���B
�@���{�ł܂��L�^���Ȃ��i���Ԃ�j���A�n���̉\���������͂Ȃ��B
�@���{�̃I�I�Z�O���J�����ƋɎ����Ă��邽�ߎ��ʓ���ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B�I�I�Z�O���J������
�k�ĂŋL�^������������A�������̕����ł��̎��ʓ_���_�c����Ă���B
�@���́A2010�N9���A�k�ăJ���t�H���j�A�B�����g���[�ɂ����Đ������̃A�����J�I�I�Z�O���J�������ώ@���A���ۂɖ{�퐬�������������Ƃ��Ɏ��ʂł��邩�ǂ��������Ȃ�̎��_�ŃV�~�����[�V���������B
�P�D��t���Ƒ����
�@�{�����������A�ڂ�������������B����A�{�̐F�A���̐F���ŏ��ɁA������Ǝv���_��������Ȃ��B
�Q�D�{�̐F�A
�@�N�₩�ȉ��F�̌̂������B�����ł��Ȃ��̂������������A���V�J�����Ƃ̌��G�̂��낤�B�܂��ڂɓ��镔���Ȃ̂ŁA�ŏ��ɋC�Â��_�Ƃ��ĈӊO�Əd�v�Ǝv����B�{�͑N���F�ŁA���{�̓ˊp���傫���A��[�������B�I�I�Z�O���Ɣ�ׂăA���o�����X�ɑ傫����ۂ�����B
�R�D�A�C�����O�ƌ���
 �@�����ł́A�A�C�����O�̓N���[���C�G���[�ƂȂ��Ă���B���������s���N�F�����������F�����������B���V�J�����Ƃ̌��G�̂��߂����m��Ȃ��B���F�̃A�C�����O�͓��{�̑�^���F�J�����ł͌��邱�Ƃ��Ȃ����߈�ۂɎc�����B���ʂ͂�▾��߂̑N���F���������Ǝv�����B
�@�����ł́A�A�C�����O�̓N���[���C�G���[�ƂȂ��Ă���B���������s���N�F�����������F�����������B���V�J�����Ƃ̌��G�̂��߂����m��Ȃ��B���F�̃A�C�����O�͓��{�̑�^���F�J�����ł͌��邱�Ƃ��Ȃ����߈�ۂɎc�����B���ʂ͂�▾��߂̑N���F���������Ǝv�����B�S�D�w���̐F
�w���̐F�̓I�I�Z�O���J�����Ɠ������炢�̔Z���ł��邪�A���V�J�����Ƃ̌��G���������߁A
���Ȃ蔖�������̌̂������B��ʓI�Ɍ��̋�ŕω�����̂Ŕw���̐F��
���Ȃ芄������Ĕ��f���ׂ����낤�B
�T�D����
�@������Ƃ��ɎO��ɑ����Ď��̐�[�̔�����[�������̂悤�ɏo�Ă���X��������B�I�I�Z�O���J�����ł����X�݂�B���̂����ݕ��ŕω���������̂��낤�B
�U�D���̐F
�@�I�I�Z�O���J�����͐Ԃ��ۂ��F�̌̂������A�A�����J�I�I�Z�O���J�����́A���߂̃s���N�F��
�����B�A�����J�I�I�Z�O���J���������ɂ������Ƃ��ȂǐԖ��������Ă��邱�Ƃ�����B�܂�
�ʔ������Ƃɏt��ɂ͑������F�݂������Ă���̂�����Ƃ̂��Ƃŋ����[���B
�V�D����P8�`P6�ɂ����Đ�[���̃T�u�^�[�~�i���o���h���F�������̔��F���imoon)�������B
�@�����ŋ�������Ă���d�v�|�C���g�ł���B���F�������[���̓I�I�Z�O���̕����傫���A�����Ă�
�邾���ł͂Ȃ��A�R���g���X�g���ĂŌ`���ۂ��O�����^�Ŋۂ����̂������B�ȉ��ʐ^����ɂ��L�^�B
���H�����ł��邽�߁A���킩��ɂ����B������A�~�ɓn�Ă��Ďʐ^���X�V���������̂ł���B





�~��2989�FP9�����AP8�P7,P6�Ƀ��[��������B
����3287�FP9�����AP8P7P6�Ƀ��[��������BP8P7�̂͋����B
�@�@��P9�����AP7P6�݂̂ɋ������[��������B
�~��3063�FP9�����AP8,P7�Ƀ��[��������B
����3022�FP10P9�����AP6,P5�ɋ������[��������B
����3024�FP9�����AP7P6�Ƀ��[��������AP6�͋����B
����3456�FP8�L�W���AP6�݂̂ɋ������[��������B
�@��ϓI�ȕ\���ł����Ȃ����A�U�̒��A�R�͓̂���ł��Ⴂ�����Ăł������B�ʐ^�ł́A���炩�Ɏ��ʉ\�Ǝv����̂͂U�̒��S�̂ł������B
�@��r�ΏƂ̂��߂ɒ��q�`�Q�����{�̃I�I�Z�O���J�����̓T�^�I�ȑ傫�����[���������B


�S�P�D��^���F�J�������ފw�̐��E�I�����ɂ���
�@2012�N�ɏo�����{���ޖژ^��V�ł̑O�����ɂ́A�ŐV�̌������ʂ��������|�A������Ă���B�ł́A�e���̑�^���F�J�����ނɂ��Ă̌����I�Ȏ핪�ނ́A�����_�ł͂ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤���B
http://www.aerc.eu/tac.html
�@����AERC TAC�́A���B�T�J���̒��ވψ���iUK,France,Netherland,Sweden,Germany�j�̎�ƈ���̕��ނ̕ύX�����ă��R�����f�[�V�������o���Ă��� �B�ߔN�̑�^���F�J�������ނ̕ύX��AERC TAC���R�����f�[�V����(2010�j�ɂ��ƁA�ȉ��̂Ƃ���i���̕��ނ͏ȗ��j�B
�i�P�j�@�T�J���̈ψ����v�������ށF
European Herring Gull Larus argentatus(spp argentatus, argenteus)
Caspian Gull Larus cachinnans(spp.cachinnans)
Yellow-legged Gull Larus michahellis(spp. michahellis, atlantis)
Armenian Gull Larus armenicus(spp. armenicus)
Lesser Black-backed Gull Larus fuscus (spp.fuscus, intermedius, graellsii, heuglini,barabensis)
�i�Q�j�@�S�J���̈ψ����v�������ށF
American Herring Gull Larus smithsonianus (spp.smithsonianus)
�i�R�j�@�R�J���̈ψ����v�������ށF
L.vagae�ispp. vegae, mongolicus)
�@�z�C�O�����J����L.heuglini�͂T�J���̈ψ���̂��ׂĂŁA�j�V�Z�O���J����fuscus�̈ꈟ��Ƃ��Ĉ����Ă���B���ޖژ^��V�łɂ����Ă� �A�z�C�O�����J�������A�j�V�Z�O���J�����̂P����Ƃ��Ĉ����Ă���̂́A���E�I�Ȋw�p�I�����ɍ��v���Ă���ƌ����������B
�@�L���Ȉ�ʓI�����uGULLS OF EUROPE, ASIA AND NORTH AMERICA�v�ȂǑ����̐}�ӂɂ����ăz�C�O�����͓Ɨ���Ƃ��Ĉ����Ă��邪�A����GULLS�ł́Aheuglini��fuscus�Ƃ̌��G�͂悭�킩���Ă��Ȃ��A�Ƃ�������Ă��Ď�C��������j���A���X������B���E�̈�ʃo�[�_�[ ���x���ł��_�c�������ł���i���L�����j�B
�@�܂��A��HP,�J��������������No.36�ɂ���A�u�j�V�Z�O���J�����ƃz�C�O�����̎��ʁA�Q�N�ڈ��������ł����ʂ��₷���v�́A����̎��ʂ��ɂ߂ē�����Ƃ������Ă���B����̌`�ԏ�̃I�[�o�[���b�v���傫�����Ƃ��A���̂Q������Ƃ��ꂽ�w�i�̂ЂƂ�������Ȃ��B
�@����mongolicus���R�J���i��ݽ�A����ށA�j��L.vegae�̈���ɓ����Ă���B
���{���ޖژ^��V�łł́A����mongolicus��L.cachinnans�ɓ����Ă���B����̓���������肽�� �B
�@L.cacchinnans�́A5�J����v��L.michahellis�ƕʎ�ɕ������Ă���A��`�w�I���삩��Crochet�_��2005�i��HP�Q�T�ŏЉ�j���A������x������B�������n�����{���ޖژ^��V�łł́A����ƂȂ��Ă���B�g���R��M���V���ł́A����̒��ԓI�ȓ����̌̂������Ƃ����iGramp&Simmons1983�j������A����ɕ�����T���Ă݂����B
�@American Herring Gull Larus smithsonianus�̓X�E�F�[�f���ȊO�̂S�J���łP��Ƃ��ĔF�߂��Ă���B��`�w������Crochet��̘_����������x������ł��낤�i2005��HP19�j�B�������A�A�����J��AOU�́A�����_�ł͂����argentatus�Ɋ܂߂Ă���悤���iwikipedia�j�B
�����̑��Q�l������
�i�P�j���E�̈�ʃo�[�_�[�ɂ���ʓI�c�_
http://www.birdforum.net/showthread.php?t=10805
�i�Q�j�o�[�h���C�t�C���^�[�i�V���i���i���R�ی슈���ɉe������Ƃ������R�ŕێ�I�ȌX���j
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3231
�S�Q�D���q���̕��͔��d���݂ŗ\�z�����J�����ނ̃o�[�h�X�g���C�N�@Feb.2013
�@�J�����}�j�A�ɂƂ��Đ��E�I�ɗL���Ȓ��q���`�i��t���j�����A���q���ɑ�K�͂ȕ��͔��d���̌��v�悪����i�����@�A�j�B����25�N�ɂ͒��q��3km�ɗm�㕗�͔��d�̍ŏ��̈��ғ�����\��B���܂������A����ɑ��₵�Ă������Ƃ�������������B
�@�C���̂�������W�܂�Ƃ���ɑ�^���͔��d��ƁA���R�̂��ƂȂ���A�C���̃o�[�h�X�g���C�N���N����B
�@�C�M���X�̊C�㕗�͔��d�̎����B�ɂ��ƁA�x���M�[�̊C���̃\�[���g���o���N�̂U��̗m�㕗�����ł����Ƃ��J�����ނ͏t��1720.5�H�i���ʖ�W�O���j�A�H���P�S�W�W�H�i���ʖ�V�O���H�j�Ɛ��肳��Ă���B����͔�s���[�g�Ɣ�s���x����\�������v�Z�ɂ��B�J�����ނ̔�s���x�����Ԃ̉��͈͂ƈ�v���邽�߁A�Փˊ댯���͂T�O�O���̂P�ɂ����ƌ����B�P�Ȃ鐄��l�ł͂��邪�]��ɂ������B
�@���āA���q���͊C���̓n��̏d�v�n�_�ł���A���q���`�ɂ͖��P�ʂ̃J�����ނ��z�~����B���ʂ͓��Y�����n�̂�����z���邾�낤�B�����U��ŔN�ԂR�O�O�O�H�ȏ�Ƃ����̂́A�P���Ɍv�Z����ƂU�O��̕������ł����ꍇ�R���H�ȏ�ł���B
�@�������J�����ނ͓����悢�̂ŁA�Փ˂��������\���͍����B����̂��鋙�`�ŗe�ɂ�钹�ނ̋쏜���������Ƃ����邪�A�J�����ނƃJ���X�͏e��������ƒ����ɓ����o���Ă��܂��A�g�r�������]���ɂȂ��Ă����B���̋��`�ł͕ʂ̓��ɋ�������S���o�P�b�g��@���āi���������т�����𗎂Ƃ����߁j�A�e����������̉������Ă������A�J�����ނ͑S���������Ȃ������B�e���Ƃ��̉��������A�w�K���Ă����̂ł���B�����̕��艹�͑傫���������B����������w�K���ĉ���s�����Ƃ�\���͍����Ǝv���B
�@�O�q�̉p�������ł��J�����ނ̑�ʃo�[�h�X�g���C�N�̎���͎��ۂɂ͊m�F����Ă��Ȃ��Ə�����Ă���B������ɂ��Ă��A����̓����ɒ��ڂ��Ă��������B�܂����̊C���A�A�W�T�V�ށA�J���ނ̃o�[�h�X�g���C�N�ɂ����ڂ���K�v������B
���Q�l������
�@NEDO��HP
�@�@�@�@http://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_100148.html
�A���q�s��HP
�@�@�@�@http://www.city.choshi.chiba.jp/osirase/2012/youjou-fuuryoku.html
�B�쒹�Ɨm�㕗�͔��d�|���̉e���ƕ]���A���{�쒹�̉�A2011�N3��
�S�R�D�C�X���G���̑�^���F�J�����͂ǂ���H
http://ja.scribd.com/doc/35474073/israel-large-gulls-fast-identification-guide
�@���{�ł͋H�ȃJ�����������钆���B���̂g�o������ƃC�X���G�����C�C�������B������邽�߂ɂ͓o�^���K�v�B��ȃJ�����́A�A�����j�Aarmenicus�A�X�e�b�vbarabensis�A�J�X�scacchinnans�A�z�C�O����heuglini�A�j�V�Z�O���J����fuscus�A�L�A�Vmichaheris�̂U��ށB
�@
�i�P�j���S���ǂ����H
�@�@��ɂ����ƃK�U�̃n�}�X�A�k�ɋ߂Â��ƃ��o�m���̃q�Y�{���A�Ƃ����킯�ň��S���S�Ƃ����_�ł́H�����A�e���A�r�u�ɂ��Ă͉��B�l�����N�勓���ē������ɗ�����x�̈��S�͂���B�s���Ȃ�O���Ȃ̂g�o�ɒ��ӂ���ׂ����B�x�O�Ɉ�l�œd�ԂƓk���ŌJ��o���͎̂��M���Ȃ��B�^�N�V�[�̈���`���[�^�[�͈����炵���B
�@�����������������n���C���̃|�C���g�͂Q�ӏ��B
�@�e���A�r�u����V�Okm�k�ɂ���Ma'agan Michael�͗{���ꂪ�U�݂��Ă���google�}�b�v�Ō��Ă��C�C�������B�n���S�łP���Ԃ��炢�B�܂��AAshdod�Ƃ����ꏊ���ǂ����������A�K�U�n�悩��P�O������������Ă��Ȃ��B�q��ʐ^���̈ē��}�͂킩��₷���B
�@�Ȃ��A�C�X���G���̓n�q�����L�ڂ��ꂽ�p�X�|�[�g���Ƒ��̃A���u�����ɓ����ł��Ȃ����Ƃ�����B���_�����̍���������j�����x���Œn���S���قƂ�Ǔ����Ȃ��B
�i�Q�j�n���ƃx�X�g�V�[�Y��
�@��ʓI�ɂP�����{����R�����܂łƂU�����{����X�����{�܂ł͊��H�r���Ȃ̂Ŏ��ʂ�����Ƃ̂��ƁB
�o���x���V�Xbarabensis,�ʖ�Steppe Gull
�H�̓n��11���ɑ����B�R���܂ł͎��X���邱�Ƃ��ł���B�i�h�o�C�ł͉z�~�̂����Ȃ葽���j�B
�z�C�O����heuglini
��ȃ��[�W�z���C�g�w�b�h�̃J�����ł���B�ώ@����11���`�R�����܂ŁB'taimyrensis'�͂��Ȃ��Ǝv����B�z�C�O�����J�����͍ł��傫���J�����̈�ł���Ə�����Ă���B
�L�A�V�Z�O���J����michaheris(�n���C�̉��F�����̃J�����j
��״قł͉Ē��A�ɐB���Ă���B�~�͂��܂肢�Ȃ��B
�J�X�s�L�A�V�Z�O���J����cacchinnanns
�~�ɂ͌��\�����B����Acre�i�A�b�R�FHaifa�̂�����Ɩk,�i�|���I���������ނ�����Ǔs�s�j���ӂɏW���BAshdod�ɂ������i�e���A�r�u�̓�j
�@���̌̌Q�i�ʖ�Pontic Gull�j�͏���̗����������ۂ��Ɠǂ��Ƃ����邪,���̂g�o�Ɍf�ڂ��ꂽ�̂͊F�����ۂ��B�J�X�s�C���ʂ��痈��̂��H�ʐ^�̉f��̖��Ȃ̂��낤���H
�A�����j�A�J����armenicus
�N��ʂ��Ă����Ƃ������J�����B�����Γ����ɂ���B�c����michaheris�Ǝ��ʍ���B�h�o�C���炢���ɍs���ƁA���̃J�����͌����Ȃ��炵���B
�j�V�Z�O���J�������fuscus
��������graellgii�͂قƂ�ǂ��Ȃ��BBaltic Gull�Ƃ��Ă����fuscus�A�N��ʂ��Č����ƃA�����j�A�J�����̎��ɑ����������B�w�����z�C�O��������graellgii���������B�̌^���אg�B�H���瑽���Ȃ�B��ȉz�~�n��ashdod�Ƃ̂��ƁB
�S�S�D�T�E�W�A���r�A�̃J�����ނƃ����S���J����sep.2013
�@�T�E�W�A���r�A�i�y���V���p�A�_���}�[��Dammam���Ӂj�F
�@�@���̃J�����}�j�A�̂g�o�T�C�g�ɂ̓A���r�A�p�i�y���V���p�j�̃J�����̎��ʃ|�C���g���܂�
�߂��\������B����͒����݂̂Ȃ炸�A�ꍇ�ɂ���Ă͒��q�ł����ɗ���������Ȃ��B
�@�_���}�[���̓o�[���[���Ƌ��łȂ����Ă��ē��{����s���Ȃ�o�[���[���o�R�ɂȂ邾�낤�B
�@�x���V���p�����Ō�����~���̎�ȃJ�����́A�j�V�Z�O���J�����ifuscus�Abarabensis�Aheuglini�j�A�����j�A�J�����A�J�X�s�Ƃ̂��ƁB�J�����ȊO�̓n�蒹�������A�T���n�ē�LocalPatch�́A���̒n�����g���i�N�����������j���������C��ł��邱�ƂƁA���̂��ߓs�s�̐���ɓn�蒹���W������L�l�������Ă���B
�i�P�j�A�����j�A�J����
�@�h�o�C��I�}�[���ɂ́A�قƂ�ǂ��Ȃ��Ə�����Ă���B�C�O�̒T���L�̃u���O�ł̓h�o�C�ɂ����I�Ə�����Ă�����̂����邪�A�^���悷����Ƃ�����B���āA���̃T�C�g�̎�Î҂̂���y���V���p�̉��̕��A�o�[���[���̏�����along the coastline of Tarut Bay between Dammam and Al Khoba�̂��̏ꏊ�ł́A����������Ƃ����B
�i�Q�j�����S���J�������
�@�����S���J�����̉z�~�͈͂ɂ��čŋ߂̘_�����_�C�W�F�X�g���A�y���V���p�ł́A
�����S���J�����͌����Ȃ����낤�Ƃ��Ă���B�ȉ��A����B
�@�u���V�A�����Ń����O�����������S���J�X��Sergey Pyzhyanov��ɂ���ăo�C�J���ōs��ꂽ�����ł���B������ꂽ�̂͏ꏊ�͉��C���݂������A�T�̂��I�z�[�c�N�ł���A�I�z�[�c�N�����ʼn�����ꂽ���̂�����B�k�������S���̔ɐB�n�ŃE�B���O�^�O�W�����ꂽ�X�̂̃����S���J�X�́A�؍��Ō��������B���̂��Ƃɂ�蒆���C�ݕ��Ɗ؍��̔�ɐB���ɂ����Ă͒ʏ��ł��邱�Ƃ������ꂽ(contra Collinson et al (2008), but in support of Moores (2003) and Moores et al (2009)).
�@���`�Ƃ��̎��ӂł̓����O�t�������S���J�X�͉������Ă��Ȃ��B�����č��`�ɍł��߂��ꏊ�Ƃ��Ă�350km���ꂽ�Ƃ���Ō������Ă���B�����암�ʼn�����Ȃ����Ƃ�Kennerley�炪�����S���J�X�͍��`�ł͋H�Ƃ��Ă��邱�Ƃƈ�v���Ă���B�^�C�~�����V�X��́A�Q�O�F�P�ȏ�ł���B���A�W�A�ł̉z�~�L�^�͖��L�^�ɗ��܂�B�v
�i�R�j�z�C�O�����J����
�@���̒n��ł͂k�������������Ə�����Ă���̂��ʔ����B
�S�T�D�u���v���D�ރJ�����ށH

�@���q���`�̒ʏ́u�����v�i�F���q�s������Q���ځj�B
�@�Q�O�P�P�N�Q���A���۶�ҁA�����۶�ҁA��ҁA��Ⱥ�����A�����̎��ӂ̊ݕǂ��̔g�ł��ۂɑя�ɕt�������u���ȕ��F�̕����v��ێ悵�Ă���̂��ώ@�����B���Y�H�ꂩ��̔r�������ꍞ�݁A�������������Ȋ������`�����Ă���B�ݕǂ̊���ڂ���͔����������͏o���Ă���B���������ꍞ�݁A�������f�̏L���������ɂ����B
�@�������f�ō����Ȃ�A�_������ƐԁH�A�Ƃ������Ƃʼn�Pb�Ƃ������t�������B
�@���͂��Ă݂�Ɓu���ȕ��F�̕����v����6.7mg/kg�A���ӂ̍�����D�����5.3mg/Kg�̉������o���ꂽ�B�u���ȕ��F�̕����v�́A�̎悷��Ƃ��ɂ��Ȃ�R���N���[�g�Ђ������Ă��܂����̂Ŏ��ۂ̔Z�x�͂���ɍ����Ɛ��肳���B�u���ȕ��F�̕����v�́A�_�����iPb3O4�܂���PbO�j�ł���Ǝv����B
�@���ނ��ދ�̉���e�e�̉����D��Őێ悵����̓I�E����J���ނȂǂŎ��Ⴊ����A�}�����łŎ��S����̂������B�A�q����8mg/kg(�̏d)�Ŏ��S����Ƃ�����������B
�@�u���ȕ��F�̕����v�̕t��������ꂽ�̂͒��q�`���ӂł͂��̏ꏊ�����ł���B�@
�@���ē��{�ł͏ċp�D�ڊC���ɓ������閄�ߗ��čH�����s���Ă���A���̕��@�ł͉����C�I�������ėn���o�����Ƃ��w�E����Ă���B
�@����������ێ悵�Ă���J�����ނւ̉e���͕s���ł��邪�A�S�N�A���ł����ɓn������̂����邱�Ƃ͎����ł���B�܂��A���́u���ȕ��v�����͔N�X�������Ă���悤�Ɏv����B
�S�U�D�A�C�����O�̃R���N�V����
�@�J�����ނ̔ɐB�s���ɂ����ăA�C�����O�̐F���قȂ�ƃy�A�ɐ����A�Ƃ�������������B
�@�������A������x�y�A���ł��邽�߁A�J�����ނ͔����Ɂu��Ԍ��G�v����B
�@���ʓ_�ɂ��Ȃ�A�����w�I�ɏd�v�ȃ|�C���g�ł��邪�A�e�Ō�F���邱�Ƃ������B
�@�ɐB���ɂ͐F���Z���Ȃ邱�Ƃ�����B
 |
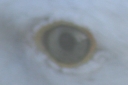 |
 |
 |
 |
�i�P�j�X���̃I�I�J�����A�A�����JDC�X���B�e�B
�@�@�@�N�����]�����b�h�A�o�[�~���I�����b�h�Ƃ����\�����낤���B�E�~�l�R���ۂ������B
�i�Q�j�X���J���t�H���j�A�̃A�����J�I�I�Z�O���A
�@�@�@�N���[���C�G���[�A�˂��Ƃ肵���Z�����F�B���V�J�����Ƃ̌��G�͐Ԍn�������Ă���B
�@�@�@���V�J������Gulls�ɐԁE���E�s���N�Ə�����Ă���B
�i�R�j�Q�����q�̃x�K
�@Gulls�ł͒P���ɐԂƏ�����Ă��邪�A��ɐB��������Ȃ̂��s���N�Ɍ�����B
�i�S�j�Q�����q�̃I�I�Z�O���J����
�@Gulls�ɂ́A�Ԃ��率���������s���N�A�Ə�����Ă��邪�A�~�̒��q�̃I�I�Z�O���́A���s���N����Ԃ̌̂������悤�Ɏv���B
�i�T�j2�����q�̃A�C�X�����h�J����
Gulls�ł�pinkish brown to red�Ə�����Ă���B
�S�V�D�����҂̉z�~�n�͂ǂ���
�@�k�����Ō���̂������Ƃ�����J�����Ȓ��ނ̓]�E�Q�J������������Ȃ��B
�@�]�E�Q�J�����̉z�~�n�͂���܂ł悭�킩���Ă��Ȃ������B���R�̈�͉q���T�����u�̏��^�[�������čs���������A�^�~�̋ɖk�n�̓��Ǝ��Ԃ̏��Ȃ��̂��ߑ��z�d�r���@�\�����ڍ����Ă��܂����炾�B�J�i�_�̔ɐB�n�ő������ꂽ���u�ɂ���ĉ𖾂��ꂽ�̂̓O���[�������h�ƃo�t�B�����̊Ԃ̃f�C�r�X�C���̐����ɉz�~�n������Ƃ������Ƃ��B�C�X�E���X���D�ނ��ߊJ�����C�ɂ͏o�ɂ����Ƃ����B
�@�f�C�r�X�C���͖k�܂U�O�x�Ȗk�ŁA�����m���ł���A�A�����[�V�����̂͂邩�k�A�x�[�����O�C�������肾�B�C�X�͂��̂����肩�痬��o���ăJ���`���b�J�����܂ł͏��ʂ����ꒅ���悤���B�I�z�[�c�N�C�̓A���[����R���̒W������ł������X�ł����ς������A�x�[�����O�C���痬��o�Ă��闬�X���͂����E���狗��������B������Ɨ���o�����C�X�ɏ���ċH�ɗ��邭�炢���낤�B
�@���ꂾ���X�Ɉˑ����Ă���̂ł���A���g���Ō̐����R�O�N�ԂłV�O�����������Ƃ����̂�
�Ó��Ȑ�����������Ȃ��B
�@�H���̓A�U���V���̎��̂�V���N�}�̐H�c���ƕ�!!�ɂ��Ȃ�ˑ����Ă���炵���B�X�R�b�g�����h�ł͐��N�Ԗ��~�C�݂̃A�U���V�̎��̂����A�ώ@�ɐ��������l������(BirdingWorld Vol.21-12)�B
�@�A���X�J�Ŗk�[�̑��A�o���[�Ɍ��ɍs���Ă�������Ƃ͌���Ȃ��H�R��s���ĂR��Ƃ��������ǁA���X�P���ł������Ƃ����o�[�_�[������i�u���O���,nabirding.com�j�B�����ɒP�ƍs������Ǝ����̃��o�T�V���V���N�}�ɒ��邱�ƂɂȂ�댯�ȏꏊ�����A�ό��ړI�ōs���Ȃ����Ƃ��Ȃ��悤���B
http://www.birdguides.com/webzine/article.asp?a=4795
�S�W�D�e�L�T�X�̃����C�J�����̉�����

�@�e�L�T�X��Galveston�p�̎��n�тɂ͊e��L�Q��������ʂɗ��ꍞ��ł���B���D�ƁA�s�X�n����̔r�o���ɂ����̂��낤���B���̎��ӂ̊����ɐ������郏���C�J�����͍����ߐH�҂ł��邱�Ƃ���A�����w�I�Z�k���₷���Ƃ���Ă���A�������̒������s��ꂽ�i�P�j�B
�@���̌��ʁA�����C�J�����̑���ɂ͍��Z�x�̉����~�ς���Ă��邱�Ƃ����������B
�@�H�тւ̒~�ς����Ȃ�����ւ̒~�ς��������Ƃ͋}���I�ɒ~�ς��i�؋��ł���A���̒n�ɓn����ɒ~�ς������Ƃ������B
�@���̊̑��̉��Z�x�́A1.9-16.0�ʂ�/���imale,n=11�j�ŁA���̏e�e��H�ׂ����Ƃɂ�钆�Ŏ���̃K���J���ނ̐��l3-6�������Ă����B���݂ɓ��{�̖k�C���{�����ł̃I�I�n�N�`���E�̝ˎ��̂̊̑������5.5-44.3�ʂ�/��(n=14�Cmean16.7�j�̉������o����Ă���i�Q�j�B
�@�������s�v�c�Ȃ��ƂɁA�e�L�T�X�̖{����ɂ����ă����C�J�����̒��ŏǏ�E�ˎ��͑S���m�F����Ȃ������j�B
�@�d�������ł̏Ǐ�́A�Z�����Ȃǝh�R�����̑��݁A�ێ�o�H���ŁA�傫���������邱�Ƃ͐����a�Ȃǂ̎��Ⴉ����m���Ă��āA���̃P�[�X�ł̗��R���s���ł���B
�@�ʐ^�̓��V���g���c�b9���̎ʐ^�̗c���B
�����F
�i�P�jRaul V.Munoz,Jr et.al. Enviromentally acquired lead in the Laughing Gull, Joul. Wildlife Vol.12,April, 1976
�i�Q�j�_�a�v�A��R�O�A�����F�L�A��t�P���A�s�z�r���A���q�������39�W(1989)
�S�X�D���l�������Y�[���V�A�W���̃Z�O���J�����͑������F��

�@���{�ɓn������Z�O���J��������vegae�ƈ���heuglini�̒��Ԍ͉̂��F���r�������Ƃ�
�����Ƃ���Ă���(Gulls)�B�֓�������B�ł�⑽���Ƃ������Ă���B�؍����C�݂ł�
����ɑ����ƌ����Ă���B
�@�t��ɑ����Ȃ邽�߁A������n�̗v��������Ƃ����Ă���B���v���I�v�f�Ƃ��ẮA
�o���g�C���݂ł́A�������n�тɔɐB����Z�O���J�����͋r�����F���Ƃ���������B
�@�h�{�w�I�Ȍ������l�����Ă���BGotland���̃Z�O���J�����͖�40���̌̂����F���r
�������Ă���A���Ƀ~�~�Y���ʂɐH�ׂ�̂͑������F���A����͂R�|�S���Ɍ����Ă���
�Ƃ���(Hario 1997)�B
�@���l�Y�[���V�A�Ŏ��炳��Ă���Z�O���J�����͑������Ȃ艩�F���B�a�͕��ʂ̃A�W�Ƃ̂�
�Ƃ������B���̓������ł͋r�̉��F�����۶�҂��������Ƃ��Ȃ��̂ŋ����[���B
�T�O�DIceland Gull spp.kumlieni�~Thayer's Gull Hybrid?�@Feb.2017



�@�uGulls of the Americas�v(Howell 2007)��252�ł̐}�\�ɂ��ƁA�{�̂̏����
�A�C�X�����h�J����kumlieni�̔��e�ɂ͂���BP10�Ƀo���h���Ȃ��AP9-6�ɂ͂���BP5
�ɂ͊D�F��������B
�@�������AGulls(Olsen et.al.2003)�̐}�\�ɂ��ƃA�C�X�����h�J����kumlieni��P5�ɂ�
�����Ȃ����ƂɂȂ��Ă���̂ŁA������̒�`����͂͂����B�A�C�����O�͈Î��F�B
I saw this gull at Choshi Fishing Port, Chiba Japan on Feb.24-26.
Maybe it would stay more longer.
As long as primary patern, blackish area was narrower and paller than Thayer's.
But P5 has a small dark spot, may out of the difinition of Iceland.
Hind neck was mottled like Thayer's rather than Iceland. Eyering was purplish pink.
�T�P�D�u�^�C�~�������ŔɐB���鉩�F���r�̃Z�O���J�����v�͓Ɨ���Ȃ̂��H
�@���{�Ŏ��X����r�̉��F���Z�O���J�����͉��҂��Ƃ����^��́A���{�̃J�������D�Ƃ̒��N�̑f�p�ȓ�ł������B����ȂƂ����`��Kennerley��(1994)�ɂ����ꂽ�A�r�̉��F���Z�O���J�����̓z�C�O�����J��������taimyrensis���A�Ƃ������͔��ɖ��͓I�������B
�@�������A�~�g�R���h���A�c�m�`�̌����ɂ��A��^���F�J�����́u���ʑc��������Ȃ��v�Ɣ������A����^�C�~�����V�X�́A�̌Q�Ԃ̌��G�ɂ��o���オ�����O���[�v�ł���Ƃ���A�L���Ȑ����AOlsen&Larsson(2004)�A�ʏ�'Gulls'�ɂ́A'taimyrensis'�͗L����taxa�i���ތQ�j�ł͂Ȃ��ƋL�q���ꂽ�B
�@�m���Ɉ�ʓI�ɓ��{�Ō���u���̉��F���J�����v�͌`���ɂ��������A�N���C���I�Ȉ�ۂ�����B���G�������Ƃ����̂��[��������Ȃ��悤�Ɏv�����B
�@�������A�؍����C�ɂ����āi�j�[�����[�Y����HP���j�ŁA�r�̉��F���w���̔Z���ψ�ȕ\���^�̑�^���F�J�����������������Ă���u�N���C���I��ہv���������Ƃ�������Ă���B����O�̒��茧�|���p�⍲�ꌧ�L���C�̊����ł��u�r�̉��F���J�����v�̑�Q�����邱�Ƃ��������B�����A�u��ہv�̘b�����Ă����ފw�I�ɂ͂��傤���Ȃ��̂ł���A����Ȃ錤�����ʂ��҂��ꂽ�B
�@2010�N��ɓ���ƁA�j�̂c�m�`�̌��������{����Ĉ��탌�x����菬���Ȍ̌Q�̌��G�iintrogression�j�����������悤�ɂȂ����B���̒��ɂ́A�K��������ʂɎ�����Ă���l�����ł͂Ȃ����̂́A�^�C�~�������̌̌Q��Ɨ���Ƃ��Ă���_��������A���̏������I�ɉ������̂��ȉ��Ɏ����B�����ɓ����邱�Ƃ𐄏�����B
�@�Ȃ��A���̐����������Ƃ���Ȃ�A���̎��ɂ͓��{�ɗ���u�i�V�������߂́j�^�C�~�����V�X�v�Ɓu�^�C�~�����V�X�ȊO�̉��F���r�̃Z�O���J�����v�Ƃ̎��ʓ_�����ɂȂ邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@Taimyr Gulls: evidence for Pacific winter range, with notes on morphology and breeding.
Klaas van Dijk, Sergei Kharitonov, Holmer Vonk & Bart Ebbinge: Dutch Birding 33: 9-21,2011
�u�����V�x���A�k���̃^�C�~�������́A��^���F�J�����ɑ�����J�������̏d�v�ȔɐB�n�ł���B�ނ�̉z�~�n�͂��܂��ڍוs���ł���B�܂����ފw�I�ȃX�e�[�^�X�ɂ��Ă����ӂ��Ȃ���Ă��Ȃ��B��`�w�I���͂ɂ��ƃ^�C�~�������̃J�����́A�ŗL�̌̌Q�ł��邱�ƁA���Ȃ킿��`�w�I�ȕ����x������\�ł���A���m�Ȉ�`�q�Z����Ȃ��ƌ������Ƃ������Ă���(Liebers 2000, Liebers et al. 2001&2004, Liebers& Helbig 2002)�B
��L�����̈��p����
Kennerley,P.R., Hoogendoorn, W.& Charlmer, M.L. 1994 Identification and systematics of large-white-headed gulls in Hong Kong. Hong Kong Bird Report 1994: 127-154
Liebers, D. 2000 Phylogeographische fifferenzirung und verwandtschaftsbeziehungen
von Grossmowen. PhD-thesis, Greifswald �@
Liebers, D, Helbig,A & de Kniff, P 2001. Genetic differentiation and phylogeography of gulls in the Larus cacchinans-fuscus group. Mol Ecol 10:2447-2462
Liebers, D, & Helbig,A, 2002. Phylogeography and colonization history of
Lesser Blacked Gulls as revealed by mtDNA sequences.�@J Evol 15: 1021-1033
Liebers, D, de Kniff, P & Helbig, A 2004. The Herring gull complex is not a ring species. Proc R Soc Lond B 271:893-901
�T�Q�D��C�̃����S���J��������
�@��C�̒��S�n�C���X�^�X�|�b�g�A�������쓃�̑Ί݂̐l���p�Y�I�O���̑O�B
�@�J�������������͂Q�O�O�H�ȏア��炵�����A�S�����Ȃ��Ƃ������邻�����B�n���S��
�싞���H�w���������15���B
�@����12��31��14������16���Ɋώ@�B���F��^�J�������ő�łR�O�H�B�얔�ɂȂ��Ă���
���������悤���B
�@���̋K���Ń����S���Ɣ��f�����̂͂P�T�H�{�A�x�K�͂R�H�{�B���̑��̃J������̓[���I
�@�藠���̂悤�ɂ���ׂ������ĉa�t�������݂����A�s���̎����𗁂т������������B
�@���̌Q�ꂪ���Ėڂ̑O�������S���������ԏɂȂ����B���炭�B�e�����Ă����
�h���[���������юn�߂��B�x��?�B�e?�P�Ȃ�}�j�A�H�N�����̂��߂ɂ��Ă���̂��킩��
�Ȃ����A�J�����͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�����S�������̂قƂ�ǂ͒W�����ʂł���A�Â����ʂ̌̂������k��B(�l�ώ@)�̂Ƃ�
����Ă����B�܂��A�����S���ł��S�}�̑����̂�A���H��������Ƃ����x���̂Ȃǂ�����ꂽ�B
�@I would like to say thanks to Craig's HP.
53.�V���̃S�r�Y�L���J����
�@�S�r�Y�L���J�����́A�n�����1���H���x�������Ȃ��Ƃ������Ă��邪�A�݊C�p��3000�H�ȏ�
�̌Q�����Ă���A�d�v�ȉz�~�n�Ǝv���Ă���i���L�_���j�BHP���ł͂P���H�ȏ�̋L�^
����Ƃ������B
�@�V�Îs�͊ό��ƌ[�ւ̂��߂ɃS�r�Y�L���J�������ώ@���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����ώ@���������݂���
����Ƃ���HP�����������B���N�O�A�V�ẪR���e�i���[�h�Ŕ����������w�����̑唚������
�̐Ւn�ɑ����Ă���Ƃ������m�F�������邪�A�����͑��v�H�E�E�E�E�B
Distribution, Numbers and Age Structure of Relict Gull Larus relictus in Bohai Bay, China
Yang Liu, Paul I. Holt, Jin-Yu Lei, Yu Zhang and Zheng-Wang Zhang
Waterbirds: The International Journal of Waterbird Biology
Vol. 29, No. 3 (Sep., 2006), pp. 375-380
https://birdingbeijing.com/2015/03/28/10000-relict-gulls/