�W�D��Ð푈(��C�푈)�̓�������
�A���f���k�d����i�P�X�S�O�j���[�g
�i�`�X�h�C�c�����ɏh�G�t�����X�œ|�ɗ����オ�����B���̔��̓A���f���k�����Ƃ�������ȃ��[�g��˔j���邱�Ƃ������Ƃ���Ă��邪�E�E�B���̃��[�g�����]�Ԃő��j�������̃��|�[�g�I
�V���K�|�[���N�U��i�P�X�S�O�j
���{�R�̓}���[�����P�T�O�O���������]�Ԃ𒆐S�Ƃ��镔���œ쉺���V���K�|�[�����ח��������B���̃��[�g�����]�Ԃŗ����Ă݂܂����B
�U�D�`�o�̉����d����탋�[�g�������i�������ҁj
���`�o�͑�ォ�瓿�����������ɏ㗤�A�����ւ̓d���������s�����B���̃��[�g�̑O�������]�Ԃő��j�����B
�C�U�x���o�[�h�̖���i�H�c���j�����]�Ԃʼnz����I
��{���n�̒E�ˁi�P�W�U�Q�j�̓�
���n���y���˂�E�˂������A���̐��ƐՂ��爤�Q���܂ł����]�Ԃő��j�������̃��|�[�g�ł��B
2003�N7���B
�g�p���]�ԁF�r�A���L�A�@�{���y�V�O�O�b�ƃI�X�v���C
��p�@�F��Q�O���~�^�l
�@�d��������悤!!�Ƃ����F�l�̒�ĂɁA���͚X�����B����͎��]�ԂŃx���M�[���Ӎ��ɍL����u�A���f���k�̐X�v�̂S�J���𑖔j����Ƃ����v�悾�����B
�@�P�X�S�O�N�T���A�i�`�X�h�C�c�͏h�G�t�����X�œ|��ڎw�����B�铽��햼�u���F�v�A���Ɍ����u�d����v�ł���B���̂Ƃ��ɂ����Ƃ������̂̓A���f���k�����Ƃ�������ȃ��[�g���T���Ԃœ˔j�����O�f�[���A�����R�������P�X�@�b�R�c�������B
�@�u�d����v�̐��ʂ͂P�疜�l���̐l��������ꂽ��P�����E����̉}��C������C�ɐ�������A�G������C�ɓ|����Ƃ����R�l�ɂƂ��ċ��ɂ̖����������B���̃A���f���k������˔j����T���Ԃ̗��������]�Ԃł��Ƃ����̂���|�ł���B
�p�����t�[�Ō������Ă݂�ƁA�I�����_�l����Ղ߂���Ō��n���h���C�u�����p��̋I�s�����������B�h�����{����\��ł���B�n�}���~�V�������łȂ�Ƃ��Ȃ肻�����B�����ق�j�Ղ���������B1�T�Ԍ�A���͍s����I�Ɣ��f�����B�����됦������ɂȂ������̂��B��M�ƃC���^�[�l�b�g�Ƃق�̂�����Ƃ̉p�ꂪ����E�E�E�E�B
���@���ł̎���
�@���c��`�ő��_�Ƒ҂����킹���]�Ԃ�a����Ǝ��]�Ԃ̃^�C���̋�C���Ƃ���������ꂽ�B�V���K�|�[�����s�ł͉��������Ȃ��������E�E�E�E�B
�@���b�V���\�\�\�I�I�Ƃ����ˑR�̑吺�Ŗڂ��o�܂����B�G�A�t�����X�@���ŁA���̑O�Ȃ̘V�l�����S���Ȃ�ɂȂ��Ă����̂ł���B
�@�p���ɒ����ƁA�@���ɗ��ߒu����Čx�@�ɂ�鎖��悪�҂��Ă����B���p�����Ԃ��C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��������A�V�l�̗אȂ̓��{�l�j�����I�݂ȃt�����X��ŏڍׂ���������̂ŁA�������͂����ɂ������߂�ƂȂ����B���Ԃ��Ȃ������ɒ��悵�Ă���Ȃ����H�ƌ����Ȃ��Đ����������B���݂ɂ��̎��̌Y������͍����|���V���c�𒅂Ă��ăc�[���h�t�����X�̃p���^�[�j�I��ɂ������肾�����B
�@���N�Z���u���O��`�ɓ��������B��X������͂܂����邢�B�߂��̗\���z�e���܂Ń^�N�V�[�𗊂����Ƃ����B�^�N�V�[�̉^�]��Ƀz�e������`����ƁA����Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ă��z�e���ɓd�b����Ό}���ɗ���Ƃ����A�e�ɂ��d�b���Ă��ꂽ�B���炭����ƃz�e������}���ɗ��Ă��ꂽ�B��Ԉ����ꔑ2000�~�̃z�e��formula�i���[���b�p�̃`�F�[���X�j�̃X�^�b�t�ł���B����͈ӊO���B
�����e�̂��钬��
�@�X�^�[�g���Ă����̏����Ȓ��̐^�ɁA���e�����j�������g�Ƃ��ď����Ă������B���Ȃ�ł����B��햖���ɘA���R�����Ƃ����s���e�ŁA�M�ǂ��āi�������j�A�����i�`�X����J�����Ă��ꂽ�L�O�i�Ƃ��ď����Ă���B

�@�J��ニ�N�Z���u���O�͂����܂��i�`�X�ɐ�̂���āA�t�����X���̖��O�̐l�̓h�C�c���̖��O
�ɋ����I�ɕς��������Ă��܂����B���n�����ق̓W���ŏ��߂Ēm�����B
�@�����̐l���C�M���X�ɖS�������B���N�Z���u���O�̍Г�͂���ɗ��܂炸�A�푈�����ɂ̓\�A�R
�������Ă��āA�i�`�X�ɋ��͂����ҁA����l��ߗ��Ƃ��ē����̕ƒn�J��ɑ���A���̌��ʁA
��������̐l���h�{�����ȂǂŎ��Ƃ������Ƃ��B�ɓ��̂ǂ����ł��������悤�Șb���B
���S���O���Ղ�������
�@���炭���Ď��]�ԓ��������āA��������s�����Ƃɂ����B�悭����ƃ~�V�������̒n�}�ɂ��ڂ���
����B����͂܂��f���炵�����ŁA�L��Ȕ�����q��A�����n��A�X�̒�������Ɛi���
�������B�����̓����͓K���B���{�̎��]�Ԑ�p���H���Q�l�ɂ��ď����L���ė~�����B���s��
�Ƃ̋������}���A���]�ԂɂƂ��Ċ댯�ȎԎ~�߂��Ȃ��B
�@�r���u�w�̃J�t�F�v�Ƃ����w�ɂ����������������Ƃ���ǂ��날��̂ŁA���̎��]�ԓ����S���O���Ղ��Ƃ������ƂɋC���t�����B�P�X���I�ɍ��ꂽ�A���e�B�b�N�ȃg���l������Ƃ����͖������Ȃт��H���Ȍk�J�������B
�@�����̒��G�e���i�n�ɒ����Ē��т��Ƃ����B�{�[�_�[�R���g���[���͉����Ȃ��A�����̋����z���h�C�c�̂ɓ�����������Ă݂�Ƃ����ł����ʂ��Ȃ����̃t�����X�ꂪ�S���ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�ꂵ����ɖڂ̑O�̃X�[����o�b�n�i�h�C�c��ŏ���j�ƌ�������A��������ď�ꂽ�B���Ԃ�ᰂ��璆��ᰂɂȂ����B
�@�����Ƀ��N�Z���u���O�̂ɖ߂肻�̓��̓G�e���u�����b�N�̂x�g�ɔ������B
���K�X����̐���
�@���[���b�p�ł͐��̕⋋����_�ł���B�X�[�p�[�A�R���r�j�A�p�����Ȃǂł��܂߂ɍw�����đΏ������B�����������������{�l�ɂ͐ΊD�≖�f�������Ƃ��������ŋɂ߂ĕs�q���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�����Ƃ��ɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂̓{�g���̐��ŒY�_�K�X����Ƃ����̂����ʂɔ����Ă��邱�Ƃ��B
�������Ȕ����ف�
�@�_�Ƃ̔[���ɑ�펞�̕�����l�ߍ��悤�Ȕ����فB�ČR��Ԃɂ�BLOOD&GUTS�Ƃ������������������B����̓p�b�g�����R�������Ō��������t�u�z��̂͂�킽����������o���Đ�Ԃ��O���[�X�ɂ��Ă��̂��I�v���痈�Ă���̂��H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���E�[�t�@���[�[��
�@�x���M�[�֓���A�o�X�g�[�j���ցB�ČR��101����t�c�̖h�q��Ƃ�����~�o�����p�b�g�����R�ŗL�����B�P�O�P����t�c�͍ŋ������Ƃ�����������ɓ��ꂽ���A�x�g�i���ł͒ʏ̃n���o�[�K�[�q���ő呹�Q��ւ邱�ƂɂȂ�B
�@�h���������E�[�t�@���[�[�ɂ́A�����̃h�C�c�R�̐�ԁu�p���e���v�������Ă���B�����̕ČR��ԂƔ�ׂĂ��Ȃ��䂻���ő傫���B��Έ�̏����ł͖Ŗ@���������炵���B
�C���^�[�l�b�g�ŗ\���u�I�e���E�h�E�R�}�[�X�v�ɔ������B���̃z�e���̐l�͍ŋߌ��ւ������ۂɋC�Â����������B�u�푈�ȊO�Ō�������ꂽ�̂̓z�e���J�ƈȗ����߂Ă��I�v�ƁB�����͕����푈�A��1���A2�������o�����Ă���B

�@�`�F�b�N�C���B���̖��O�A�P�C�X�P�E�J�S�V�}�̓t�����X��ł̓P�X�N�E�J�W���V�[���Ɠǂ݁A
�u�J�W���V�[���͉��ł����H�v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��č��f����B
�����ɓ���ƃ_�u���x�b�g�������B�����Ɋ����Ă���������A�Ƃ��ɂ͒j�̓�l���͌������������
������?�@
�@�[�H�̓n�[�t�v���[�g�Ƃ������ƂŁA���͈Ӗ����킩��Ȃ��ŗ\�����A�z�e���ŕ����Ă݂�ƁA
���C���f�B�b�V�������̒l�i���������B�D���ȃ��C���f�B�b�V���𒍕�����R�[�X�̗[�H����������B
���t�H�A�̌����_��
�@�A���f���k���ے�����C�m�V�V�̃����[�t�Ǝ��҂𓉂ޔ肪�O�ǂɏ����Ă��鋳��������B
����ɉ���Ă݂�ƁA��������S������ŏ����Ă������B�����͂܂��Ƀo���W���(1944)�̏œ_�A
�t�H�A�̌����_�������B
�@�u�o���h�@�I�u�@�u���U�[�X�v�Ƃ����f��ɂ��o�Ă���ꏊ���B
��햖���ɋt�]�����q�b�g���[�����痧�Ă������Ńo�X�g�[�j���̒��́u�d���I�v�ɂ��ꂽ
�̂��B���̃t�H�A�̌����_�̔�́u�Ǔ��B���m�A�����A�����ċ]���ɂȂ����s���ցv�Ə�����Ă���B
�푈�Ŗ��𗎂Ƃ����l�͂R�̈قȂ�^�C�v������Ƃ����F���������Ă���B���̒��ł͐펀�������m
�Ə����̂Q�O���ɑ������鐔�̎s�����S���Ȃ����B���̔䗦�͂Q�O���I���ɂ͂X�O�����炢�ɂȂ���
����Ƃ������Ă���B
�t�����X�𗷍s����Ɛ펀�����l���̂�����A���肷��Δ��L�O���������Ƃ���Ō���B
���̑����́A�u�t�����X�̂��߂Ɏ��q�������ցv�Ə�����Ă���B��g�Ŕ������Ă���悤�Ɏv
���Ď��͍D���ł͂Ȃ��B���B���c�Ƃ������Ō������������Ȕ�̉p��̌��t�ł́u�ǂ����ނ��
�]�������������̂ł͂���܂���悤�ɁB�A�����J���R���с~�~�A����ьR�������A�v�Ǝ����ɏ�����Ă��ĂƂĂ��S��ł��ꂽ�B
�@���������m�푈�ŌR��Ƃ��Ď��c���ɂ��̌��t����������Ǝv�����B
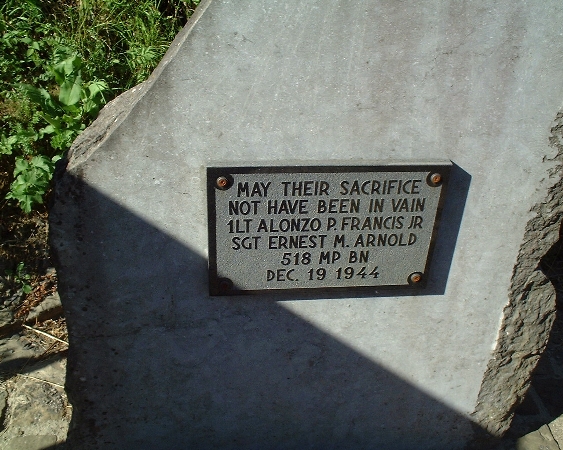
���k�t�V���g�[�ƃu�C������
�@�u�Q�d���A�����͒����˔j�ł́I�v�Ƒ��_�ɐi������ƁA�u����I��U���I�v�Ƃ����͋����B�����̗\��ʂ�S�O�N�d����̐�ԑ��̃��[�g�����ǂ��Ĕ��a��Q�O�����̉~��`���ăk�t�V���g�[�̒����I��Ƃ����̂ł���B
�@�C�������Ă���Ȃ��Ǝv���Ȃ���A�q��̐^�����X�Ɛi�ށB�������̋���̐듃�������Ȃ��B���ׂ͍��Ȃ�т̒����A�b�v�_�E�����Ȃ��肭�˂��Ă��邤���ɁA�S�ׂ��Ȃ��Ă����B�h�C�c�R�����������v���������ɈႢ�Ȃ��I
�@�Ԃ����Ă���l�������̂œ������B�p��ŕ����Ă݂�ƂȂ�ƒʂ����̂Łu�u�b�_�C���U�w���i�n���ɕ��j�v�I�Ƃ��v�����B�����ɍ������Ă��炭�s���Ɣ�J�Ńy�[�X�������Ă����B���̂Ƃ����͒ɍ��̃~�X�R�[�X�����Ă��܂��A�S�O�����قǗ]�v�ɑ��邱�ƂɂȂ����B�K�\�����X�^���h�œ����m�F���āA�����Ԃ������܂��܂��y�[�X�͗����Ă�������B
�@�n���K�[�m�b�N���O�B���łɂV��������Ă���B���S�A������菭�����̒x�����_�̂��Ƃ�{���Ă������A���炭���ƁA���܂ł��������Ȃ����ߐ����̏����Ŏ��̕����܂����Ă����B���x�͑��_�̕������炢�炵�Ă������B�d����͑̂Ɉ����I
�@���ǂ�����ړI�n�̃u�C�����̒��͍ג����J�Ƀw�A�s����̐��܂肽���݁A���̊Ԃɑ��������ƃu�C�����Ï������ł���B
�@���[�X�z�X�e���͂���������낷�R�̏�̐Ԃ������A�E�E�E�E�A��������̌��t�ɐ�債���B��J�Ƌ̖��ɕW�����P�T�O���ȏ�̋}�o���B
�@���[�X�ɒ������Ƃ��ɗ[�H�͂��ł��×~�ȃx���M�[�̂l�s�a�N���u�̑�R�c�ɂ���ĐH���s�����ꂽ���Ƃ������B�J�����[�Ƃ��Ď��̓r�[�����R�{���݁A���_�͓��{���玝���Ă������E�J����H�ׂ��B�ߌ�P�O�����A����Ƒ��z�����݉�X�̓x�b�h�Ɍ����B
<�u�C��������t�����X�ց�
�@���N����MTB�N���u�̐l�ɕ����ƁA�����o�[�͂P�O�O���قǂŃx���M�[�̂Ȃ�Ƃ��Ƃ��������獇�h�ɗ��Ă���Ƃ����B���t���悭�킩��Ȃ��������A�G�L�X�p�[�g�A���ʂ̐l�y�юq���`�[���̂R�ɕ�����ăc�[�����O������炵���B
�@�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂̓u�C������̏��S�b�g�t���[�g����͑�1��\���R�̑��叫�ł������B���Ă���͒����̘b�B�������܂��R�[���ꏊ�ł����������ɐ_�鐫���������ꂽ�l�I��������������Ȃ��B
�@�u�����v�Ə����ꂽ�ׂ��ܑ����H�������ēo���Ă����B�ň��̑̒������A���t�߂̐��т̒��ɃX�_���i�h�C�c��ł̓Z�_���j�ւ̕���͊ȒP�Ɍ�����A�ڂ������͍������z�����D�u�Ɖ������������B�p���c�@�[���[�g���S���Ȃ���I�B1940�N�A�h�C�c�̐�ԕ��������̉̂��S���Ȃ���A�������삯���肽�Ƃ��Ƀt�����X�̖��^�͐s�����̂��I�ނ�̓K�\�����X�^���h�����D���Ȃ��琼�ւƃX�s�[�h���グ�Đi�����A�A���R�f�����E�E�E�E�E�B�@�@
���X�_���遄
�@���ٌ�s�̐��^��s��i�����������̌���͂����ɂ��������������A�i�|���I���R�����v���C�Z���̋@���헪�ɉ������߂��č~�������ꏊ�ł�����B1870�N�����푈�̘b���B
�@��Ǔ��̃c�[���X�g�C���t�H���[�V������T���āA�֍s�E�d�Ԏ����A���Ȃǂ̍Ċm�F���s�����B�p�ꂪ�ʂ����B
�@�t�����X�́u���s�ē����v�͂ǂ��֍s���Ă��D�G���B���E��̗��s�卑�Ȃ̂ł���B�S���҂͒n��ɐ��ʂ��A���ׂ�킩�邱�Ƃ̓l�b�g�ł������ׂĂ����B���{�͂܂��܂��ł���B�܂��킩��Ȃ����Ƃ͂킩��Ȃ��Ɛ����Ɍ�����̂��v���ł���B
�������X�̃V�����p����
�@�X�_���߂��̃V�������r�����W�G�[���i�F���l�����{�E�̌̋��j�����Ԃɏ�����B���]�Ԏ������݉\�Ȏԗ����P������B���]�Ԑ�p�R���p�[�g�����g�ɗa���āA�ƂȂ�̃R���p�[�g�����g�łP���Ԃ��낮�ƃ����X���BReims�Ə����ă����X�ƓǂށB�����낱���̓V�����p�[�j���n��������ƁA�[�H�Ŗ����̃V�����p�����ė��̐������j�����B
�@�x�����ɂ̓J�[�h���g�������A����g�Ɋo���̖��������������B���������̂����߂����ƁA�Ȃ�ǂ�����������̂ł���B
�@�x�g�͓�������킩�炸�ɋ�J�����B�����̐������͂Ȃ��12������ŏ�����Ă���B�x�b�h�ɉ��ɂȂ�ƘL�����������B�`���Ă݂�Ə����������ӂ����ĉ����p�ő������Ă����B���ӂ���C�ɂ��Ȃꂸ�Q���B
���Q�P���I�̓d���큄
�@�V�������h�S�[����`�Ŗ��c�ɂ�����`�݂̂₰���X�����Ă���ƁA�t�����X��ŁA�u�A�����J�A�d����ɁE�E�E�v�Ƃ����V���̑匩�o����ڂɂ����B�@�����t�����X�ł͂܂��A�d����i�F�u���b�c�N���[�N�j�Ƃ����h�C�c�ꂪ�g���E�}�ɂȂ��Ă���̂��ȁH�Ǝv�������A�c�O�Ȃ��ƂɎ��ׂ͗̎G���̏����O���r�A�ɖڂ�D���āA���̐V���L���ƃ^�C�g�����m�F����̂�Y��Ă��܂����B���̂���̓C���N�ł͐��K�퓬���I����������肾�����B
�@���_�́A������߂�炸�A���x�̓}�[�P�b�g�K�[�f�����̃c�[�����O�i�I�����_�j����낤�I�ƌ����Ă����B
���G�s���[�O��
�@�F�l��MTB�̓t���[�����Ȃ����Ă��āA�q���ЂɃN���[�����o�������A�⏞���͏o�Ȃ������B���s�ی�����͂������o���B�Q��Ƃ��G���h�ɂ��܂���u�������_�v���O��Ă��������̎��]�Ԃ͖����������B
���q���Ё�
�@���̈ӌ��Ƃ��ẮA�G�[���t�����X�����������c�\�p���[���N�Z���u���O�E�E�E���]�ԁE�E�E�p���|���{�ł͂Ȃ��A���t�g�n���U�ł̃t�����N�t���g�o�R�̕����悩�����̂ł͂Ȃ����H�Ƃ����B�Ђ���Ƃ���Ƃ�����������Ȃ��B�܂��A�ߔN�̉��B�̃��[�R�X�g�G�A���C���̑䓪�ɂ����͒��ڂ��Ă���B
![]()
�X�W�D�R�D�Q�S�`�Q�U�@�@��{���n�E�˂̓�
��{���n�͓��u�Ƌ��ɁA�E�˂��A���B��ڎw�����B��������͎��߂ł���A�ނ̎o�͂��̎��̂��������Ŏ��E���Ă���B�ŏ���2���łP�W�O��������C�ɋ삯�����ē������ňꔑ���鋭�s�R�ŁA���Ȃ�̗̑͂̎�����ł��������Ƃ��f����B�}�E���e���o�C�N�i700c�j�ł��̗��������Ȃ��A�����̎u�m���C����Ă݂邱�Ƃɂ����B
�Q�R���A����`�����H�ō��m���肵�A�o�X�֍s�ŁA���m�s�X�֓��������B���������A���n���ƕt�߂�T���B�㓡�ۓ�Y�A�_�ޏ����ƐՂ����āA��{���n���ƐՂɁB�����͕\�̓��H�������a�@�ɂȂ��Ă��Đ��Ƃ̔肪����B���̎��ӂ�����Č���ƁA�킸���̋����ɋߓ������Y���ƂƂ����Ŕ������B��͂Ȃ��B�T���В��ň�ԉp��b���o�����j���B�p�ꂪ�o���邪�g�����Ⴂ���߂ɕs�����ȎG�p�������t�����s���������A����グ�����܂����č��O���S����Ď��s�A�ؕ������B���n�͂����ւ�߂��Ƃ����B���̋ߕӂ�T�����邱�ƂŁA�T���В��̐l�Ԗ͗l������������B
�Q�S�����m���o���A�{����o�R���č����������r���A�E�˂̓����Љ��Ŕ�����A���m�����Ԃ̃��[�g�Ƃ��č��쒬���ؓ��Ƃ����\�L���������B����͒ʂ�Ȃ������Z�N�V�������B ���Ö쑺�ɓ���Ɓu�E�˂̓��v�Ŕ��f�����ܑ��������M�˃g���l���̏���z���đ����Ă���B��z�g���l���ƕ����g���l���̏���z���Ğ���������܂Œʂ��Ă��鋌���͐疇�c�B�����ɂ͓ߐ{�M��̉Ɠ��̎j�Ղ�����B�Ƃ̗֊s�������a�������c���Ă���B���Ȃ�傫�ȉƂ��������Ƃ��킩�����B
�P�W�U�Q�N�R���Q�S���i�V��S���Q�Q���j�����A���n�͍��m���o�z�B���u�A�ƞ������܂ň�C�ɋ삯��B�R���Q�T���[��鞍���������B�ߐ{�M���Œ��܂ŒɈ�����B
�@�Q�S����A�������̃��C�_�[�Y�C���Ƃ�������ȊO�ς̏h�ɔ��܂�B�A�����J�Ő��������ቿ�i�h�����z���ނƋ��ɗA�������Ƃ̂��ƂŎ��f�Ȃ������������Ă��Ċ��S�����B�R���N���̑ł��������Ƀt���[�����O�A���z���ނ���p�I�Ƀ��C�A�E�g�����g�C���ȂǁB
�@�E�˂̓��͞������̃p���t���b�g�ɏڂ����B��A�r�[�������݂Ȃ��痴�n�ւ̎v����M�ق���Ƒ�����̐l���ڂ����n�}�������Ă��Ă��ꂽ�I
�@���Q�T���A��z���o�čL��Ƃ����W���ɂł�B��������{��X�܂łܑ͕����H���s���Ɛ��S���ŏI��邪�A�����ł͏������Ă��}�Ȕ������z�����M�����B�ۑ����ݔ����A�M���~�X�R�[�X���{��X�ɓ��������B�傢�ɕs���ɂȂ����B���n���n�߂Ƃ��鑽���̖����̎u�m���������z�����̂��B�����̖�Ԃ͂��̌�A�𗐂̂��߂Ƃ��Ė�Ԃ���C���ꂽ�B���ɍs���Ƌg���Ց��Y�E�˂̋�\�㓻�A�܂������s���Ɨ��n�E�˂̔B�����B
�@�����J�̒����ň�x�݁B�����̗��l�����ĂȂ����߂ɍ��ꂽ���������̂������B����͏h�Ԃ܂œx�X����B���ł����Ԑ��ŗ��l���}������Ă��鏊�����邻�����B�������ԉ��ŗ��n�́u���n�܂���Ƃ���v�Ɛ��������Ă������Ƃ������`������B
�@��������̓��͒n�`�}�̓_���Ƃ͂��Ȃ����Ă���B�ˑR�����������B�~�X�R�[�X�B�������̐����������Ă���̂ł킩��ɂ����ӏ������J��������B�O�O�ɓ��W�����ǂ�B���n��s���~�X�R�[�X�ɔY�܂��ꂽ��������Ȃ��B�p���t���b�g�ɂ̓i���R���̒֎R���̂Ə����Ă��邪�����m�������Ƃł͂Ȃ��B�������Ă��܂��I�B
�@�ѓ��𗍂߂ċ������҂���悤�ɂȂ��Ă���ƁA���K��Ƃ����疇�c�̔������W���������Ă����B�~�n���啽���̂悤�Ɍ������B�B�����܂ʼn����グ��Ɣ��������ɑ�K�͗ѓ�������A�R���ɂ�������炸�������H�ɂ���悤�ȋ���d���f��������ɂ������Ă����B
�@���̂悤�ȓm��ȃR�X�g���o�̎�����́������c���B���̂悤�ȓ���@�l���Q�𐬂��Č����J���Č��I������҂��Ă������A���{�̍����j�]�͖Ƃ�Ȃ����낤�B���������D��苰������B
�@��������͕ӑ��ɓ��蓹�W�A��������ς���B�R���N���̋}�ȍ₪�����ł�����Ɖ���ƔB�����ԏ��ՁB���n�͂ǂ�����Ă�����ʂ����̂��B���Ȑ����Ŕ��D�܂����B�悭�������ꂽ���������ɉ���B���q�����o�ĂقǂȂ��������ցB
�����͂ǂ��ł����B
�V�l���F�[���Ƃ����B�n�j���B
�E�P�W�U�Q�N�R���Q�U�������A���n�͓ߐ{�e�q�ē��ɎR���������B�B�����œߐ{�M��͈����Ԃ��A�r�����h�Ԃ܂Ő����B�L�쁨�{��X���֖偨�Z���������J���������ԉ����֎R���B�������������i�쑺���j����v�ہ��|�����_�[�������������O�t�J���������������i�͕ӑ��j�����t�߂ňꔑ
��v�ۂ���|���ւ̋}�s�ȃg���o�[�X�̓��͕���s�ʁB�n�͓_���s�ځB�������ƒ��߂āA�ܑ����H�ŋ������������B�|�����ɂ͒E�˂̏h�Ƃ������h����������B����ƍ��Ƃ����W���A�̉Ԃ����ɍ炫����Ă����̂Ŏ��]�Ԃ������ʼn������B�Y�{�������F���ԕ��Ő��܂��Ă����B���̋�Ԃ��Q�D�T���}�̓_�����[�g���s�����œ��W�����肾�B
�쉈���̓��������Ɛ_�[�̐_�Ћ����ɏo���B�_��I�Ȍ`�̋�������B�����͂����܂ŁB���łɂT��������Ă���B��{�́u�ӂ邳�Ƃ̏h�v�ɓ��h�B�����ʼn͕ӑ����s�̃p���t���b�g�����炢�A�����̃��[�g����������B�������Ƃ����̂��n�`�}�ɂ͂Ȃ������������ʼn𖾂ł����B
���N�H�ɂȂ�ƁA���n�E�˂̓��������͕ӑ���Âōs���Ă��邻�����B�ߑ����݂��Ă���邵�A�ܑ��p�[�g�̓}�C�N���o�X�ŗA�����Ă����炵���B�u���n����S�����낢�܂����B�o�����܂��v�ȂǂƑ�����̉^�]�肳�������肵�Ă���̂��낤���B���̍Î��̂��߂ɓ��W���������Ă���̂������B�ܑ����H�̕����͂�⓹�W�����Ȃ��B�n�}�����肾�B
�P�W�U�Q�N�R���Q�U�������A���n�͐Ώ㓻�܂Ŕ��������̓����s���A�h�ԁi�T�̔��A���݂̒n�`�}�̏h�ԂƂ͏��������j�܂ʼn���B��������r���ƕʂ��D�Œ��l�܂ʼn���B
��������͌\�蒬�����Ă����W�ɂȂ�B���f�Ȃ���S���������Ă���B
����̗ѓ��������B�Ώ㓻����V���O���g���b�N�ƂȂ荂�x��������B�C�͓��q���̐�̎R�ɎՂ��Č����Ȃ������B�u��������͂���A���܂�ł������v�Ɨ��n���Ɍ������̂͊C�̌����铻�ł������c�A�Ƃ����l�̂����炦���u�������v�����݁v�͂��낭�����ꂽ�B���������菬�c��ɓ��������Ƃ���ŒE�˂̓��͏I������B���Ԃ�����ΊC�̌�����Ƃ���܂ōs�������������A���ʂɓ��q���܂Ŏ������ď��R��`����A�����B
���a�U�R�N�A����P�v���ɂ�藳�n�E�˂̓����𖾂���A�����Q�N�A���ɔF�߂�ꂽ�B���̌�A���l���̐l��������K�ꂽ�B�j�t�e�B�̃t�H�[�����Řb��ɂ��Ȃ��Ă������Ƃ��玩�]�Ԃő������l�����ɂ��邾�낤�B�V�O�O�b�~�R�T�̃^�C���ł������ԗ��͂P�O�O���߂��B���̓����l�Ɉ�����Đ�������Ă���Ƃ������Ƃ��B�E�˂̓��͂��ꂩ������i���l�Ɉ�����铹�ł��葱���邾�낤�B
�u���n�̓��A������͊F���n�̊�v�i�F����P�v�u��{���n�E�˂̓��v���j
�Q�l�����F
�i�n�ɑ��Y�A�X�����s���Q�V�i���n�E�˃��[�g����\�㓻�Ƃ��Ă���̂͌Â����j
���n���䂭�R�i�E�ˎ��̋L�q�͂��܂�Ȃ����l�������ڂ����j
�������쐬�p���t���b�g�i03-5411-1656�A0889-65-1111�j�A�n�`�}�t���B
�͕ӑ��쐬�p���t���b�g�i0889-65-1111�j,��܂��Ȓn�}����
�}���[�������s�L�@�V���K�|�[���`�}���b�J�i�}���[�V�A�j�@2000.9.26�`10.3�@
�@�}���[�V�A�ɂS�N�ԕ�炵���F�l���}���[�����͂������I�Ǝ��������̂������B���������C���^�[�l�b�g�ʼnp�ꌟ���B��펞�̎�������������o�Ă����B��Q�����E���œ��{�R���d���I�Ƀ}���[������쉺���ăV���K�|�[�����̂����Ƃ��̈ړ���i�͎��]�Ԃ���̂������炵���B�g�h�r�ɑ��k���āA��V���K�|�[�������A�N�A�������v�[���V���K�|�[���ԍ��ݖ�6���~�̃`�P�b�g�����B
�Q�j�V���K�|�[���̈��h
�@��ŗ��e�ƕʂꂽ�B���e�̓t�����X�A���̓V���K�|�[���ցB�V���K�|�[���`����猩�Đ����K�͂Ɋ��Q�����B��`�̎s�������d�b�ŁA�h�ɂ̗\����Ƃ����B���������h�̕����̓x�j���Ŏd���Ă��ăx�b�h�Ǝ��]�Ԃ�u����X�y�[�X�̂�����������B�������߂�ƁA�I�[�i�[�͑�j�̃o�E���T�[�ɍd�݂�n���悤�ɂƑ������B
�@�����A�~�[�S�����i�₫���j��H�ׂĕ@�����r���A�ӋC�g�X�Əo�������B�r���l�X�̒����s�ڂɕt�����̂ŁA�������Ă���̂������Ă݂����p�ꂪ�ʂ��Ȃ��B�}�[�N�V�[�g�̂悤�Ȃ��̂�������ꂽ���A���̂悤�Ȃ��̂炵���B
�@���R�����ɗ�������Ė쒹�ώ@���y���B�e�[���[�o�[�h�Ƃ����ڔ��̂悤�ȏ����͕��̍L���t���ς�w偂̎��ŖD�����킹�đ������Ƃ����B�ڂ�����Ă��ĂƂĂ��ʔ����\������Ă���B�傫�ȃg�J�Q�������̂悤�ɂ̂��̂������Ă���B
�@�}���[�n�ƒ����n�̏��N�������l�����Ă��āA�G�r���ċ��Ȃ̂��H�Ƃ��A���ǂ��ǂ����p��̂��������Ă���B���������Ƃ͂����ւȂ��Ǝv���A�ʔ��������Ƃ��v�����B
�@�[���A�����W���z�[���o���̒��������킽�����B���A��Ń}���[�V�A�l�̓V���K�|�[���܂ŏo�҂��ɗ���B���^�o�C�N�̑�Q�Ɏ��]�Ԃ����荞�܂��Ė҃_�b�V�������B�V���K�|�[�����̏o���͎��]�Ԃ������ĕ��s�҃��[����ʉ߂������A���̓}���[�V�A���̎��]�Ԑ�p���[���̓��ǂ������B�u���[�@�j�[�h�@�|���v�B�u���H�|�����āH�v�B��R�O����������ĔY�B�C���h�n�̐l�͂��̔��������ł��ɂȂ�X��������̂��B�|�����Ȃ킿�t�H�[���A�O���l��p�̐\�����̂��ƁB���]�Ԃœ��{�l������Ƃ������Ƃ���ǐE�����z�肵�Ă��Ȃ������悤���B
�@�����A���H�Ƀ����^����H�ׁA�X�^�[�o�b�N�X�ŃR�[�q�[�����݁A�ό��ǂŌ�ʎ�������B�����������ł͂Ȃ��������A���͂Ȃ��������Ƃ������f�i�ޗ��ɂ͂Ȃ�B����o�����Ƃ���A�S���I�Ɣr���a�̊W�̃X���b�g�ɑO�ւ��������B�}���[�V�A���L�H�̔r���a���B�ׂ��ď��a�̃z�C�[�����������������B
�@�n�����̂����u�n�C�E�G�[�v�A�����𑖂��Ĕ����̐�[�������f�B�r���̓��t�߂ł͂T�������鋐��ȃ~�Y�g�J�Q�A�Z���U���R�E�A�J�j�N�C�U���A�L���O�R�u���Ȃǂ�瀎��̂����낲��]�����Ă����B�����w�ł����R���h�[�i��L�j�Ƃ�������B�@
�R�j�N�N�v
�@���[���V�A�嗤�œ�[�̖��Ƃ����ŔɎ䂩�ꂽ���������č`���N�N�v�֓쉺�B�N�N�v�̏W���͓D�̏�ɒ��𗧂āA�n��T�����炢�ɉƂ�������W���̂��B�t�F���[��АE�����z�e���i���h�j���o�c���Ă���Ƃ������Ƃł���������ɂȂ邱�Ƃɂ����B�h�̐e���͒����n�}���[�V�A�l���������͓ǂ߂Ȃ��B�C�X�������k�ł͂Ȃ��̂Ńr�[�������ށB
�@�ނ̌����ɂ́A�Ί݂̃X�}�g�����̓z��͌��܂��肵�Ă���B�������A�}���[�V�A�ł̓C�X�����ƒ����l�ƕ����k�i�^�C�n�j���A�u���肪�Ƃ��A���݂��l�v�ƌ����Ȃ��畽�a�ɕ�炵�Ă���B�X�S�C�I�Ɖ��x�������ČJ��Ԃ����B�}���[�V�A�ł͏Ă������P�O�O�~�����Ȃ̂ɑ��ăr�[����r�͂R�O�O�~�i�����j���炢�ŁA���o�I�ɂƂĂ��������B�����ɂ͎���o���ɂ������߂��A���r�̔������炢�́u�����r�v�����ʂ��Ă���B�e���͂��̒����r�����Ԉ��݂��Ă������A��r���ŏ�������ق����o�ϓI�ł͂Ȃ����H
�@�{�������ׂč��͊C�Ƀ|�C�B�r�j�[�����낤���A�r�����낤���|�C�B���ݏ������̈ӎ��͊F���ł���B���݂Ŕ��������ʂߗ��Ă�����������B���Ƃ�����Ȃ��̂��I
�@�}���[�V�A�͉p�ꋳ��ɔM�S�����A�O���l�ƌ���Ǝq������������Ă��ĉp���b��������B������ What�fs your name?�@��������Ȃ��B���͋߂��̃��X�N���w�����āA����͉��H�Ƃ����˂�ƁA�q���B�͂��ɓ��h���A�E�C�����l�̏��N�������Ȑ��Ń��X�N�A�Ɠ������B�u�I�[�A���X�N�I�v�Ǝ��̓`���������̃����f�B�ő傰���ɗ�q���铮������Č������B����͂��������ւ�q�������ɃE�P�����@�����l�^�ɂ���͎̂~�߂��ق����������낤�B
�S�j�o�c�[�p�n
�@���l�A���q�������؍݂������B���Ă͎��̍z�R�ʼnh�����炵���B���q���I�s���ŏ������u�̘b�͋������ߕt������悤�ɔ����������B�쉈���̉���ŃC���h�n�̐l���Ă��Ă��邨�������N���[�v�̂悤�ȃp�C�����͋I�s���̂܂܂������B
�@���X�g�n�E�X�Ƃ������̃z�e���ɔ��܂����B�����͂�������̎�ނ̒�����ɌQ��Ă���̂����Ȃ��璩�H�̃g�[�X�g��H�ׂďo�������B
�@�r���̓c�ɒ��ɂ́u�V�c�����v�Ƃ����Ŕ̃r�����[�h�ꂪ����A���a�V�c���r�����[�h�����Ă���C���X�g�̌Â��Ŕ��������B
�H���Ń`�L���J���[��H�ׂ��B���]�Ԃ������ɗ������N���Q�l�B��[�Z�u���X�s�[�h�i�V���j���A�Ƌ����Ă����B���Z���Ƃ��Ȃ�Ɖp�ꂪ�B�҂Ȃ̂�����̂œ���q�˂āA���Ă̌���n�o�N���Ɋ�蓹���邱�Ƃɂ����B�S���̖��ʂĂ��Ȃ������Ă���B��Q�����E���ł͂��̂�����ŗE���ȃC�M���X�����S���̖̃v�����e�[�V�����ɐ���Ŕ����������A���{�R��Ԃ͓�炩���S���̖���瀂��E���Ă��܂����Ƃ����B���ł��S���̃v�����e�[�V�����͐���ŁA�����̋C��ɑ傫�ȉe����^���Ă���B
�@�ዾ���ɉH���̂悤�Ȃ��̂��������B�ዾ��@���Ă����Ȃ��B�ǂ����M�Ŗڋʂɕ��S�������肷���āu���ǁv�ɂȂ����悤���B����A�A����Ɋ�Ȉ�Ɋ�ꌟ�������Ă��������A���S�ɒ����Ă���ƌ���ꂽ�B
�T�j�}���b�J�@
�@�L���v�e���h���C�N��������������Ẵ}���b�J�����̎�s�B�X�}�g�������͂��爳�����ꂽ�}���[�������͂͒�����C�X�����ƌ��т����ƂŔɉh�����B�����Ɣ�����������j���ꂪ�����ɂ��������B�C�M���XVS�t�����X�A���{VS���N�����Ɠ����悤�ɁE�E�E�E�B
�@�h�̓o�b�N�p�b�J�[��p�B�̏h�A�J���`�����B���S�̂��߂̏����W�Ɨ҂����\�h�����˂āA�H���Ńr�[�������݂Ȃ���������̋@���_�����B�C�O�ł͂Ƃ�ł��Ȃ����{��ɋQ�����҂������{�l���s�҂ɉ���Ƃ����邪�A�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ��p��b�͏d�v���B
�@�C���h�lIT�Z�p�҂ƃ}���[�n�X��ƂR�l�Řb������ł���ƁA�Ⴂ���������荞��ł����B���m�n�Ƃ��A�W�A�n�Ƃ����f�ł��Ȃ��_��I�Ȕ����̓o��Ŏ��̌㓪�����X�p�[�N�����B�t�����X�l���Ƃ����B�����Ƃ������̏o�g�ŁA���ɂƂ��ēy�n��������ꏊ�������̂Ńt�����X�b�ɔ��W���������������A�C���h�l��ɉ������ă}���[�V�A�ł͂ǂ�ȏ��Ɍ��������q�˂��Ƃ���A�X�}�g�����k���Ɠ������B�����͊댯�炵����A�ƌ����ƁA�ޏ��́A�댯�͊����Ȃ��������A���̃}�}�̓J���{�W�A�l�����玄�̓A�W�A�l�Ɏ��Ă���̂ŐS�z�͗v��Ȃ��̂��ƌ������̂ł܂��܂��������B����ɂ͍`�Œm�荇�����l�̉Ƃ�1�����z�[���X�e�C���Ă����Ƃ����B
�@�܂��`���͂����ɂ��Ă��˂Ǝv���A�X�}�g���C����l�g�����̉\���Ȃɂ��A���낢��������Ă��邤���ɁA��債�Ă����C���h�l���ˑR�{��o���āA�}�h���A�[���͖ڂɗ܂𗭂߂čs���Ă��܂����B���͑P�����Ƃ������悤�ȁA�������Ƃ������悤�ȋC�������B
�@���͂Q�d�Ƀ`�F�b�N���邱�Ƃ�����B���{��Ɖp��A���{����̏��ƌ��n���Ƃ����悤�ɏd�ˍ��킹��Ǝv���������Ȃ����Ƃ������Ă��邱�Ƃ�����B
�@�����A�X�}�g�����������邩�Ǝv���ĊC�݂ɍs�����B�ֈӂ��Â��āA���A�Łu���邱�Ɓv�����Ă���ƃJ���X���W�܂��Ă����B���́u�������v��_���Ă���̂��B���S�H�͂������낤�B�K�Ȃǂ������̂ł͂Ƌ��낵�������B
�@���ɖ߂�ƒ����l���������Ɍ������Ă����B���Ɍ��̐���i�g�ݎ�j�����߂Č����B���o�̓˂����Ƃ��̂悤�Ȑg�����킷�Z�͐����������ςŁA������ꂽ��������͂Q���قǂ�̂߂��Ă������ċ�����B
�@���𗬂���̊ό��D�ɏ�����B�K�C�h�̘b�ɂ��Ƒ�Q�����E���̓��{�R�̓R�^�o�����玩�]�ԂŃ}���b�J�܂ŗ������ƂɂȂ��Ă���悤�����A�R�^�o���㗤�͊m���P�A�������Ȃ̂ŁA�命���̕����ɂ��Ă͊ԈႢ���B
�@�����u�}���b�J�͂R������܂����B���D�̃|���g�K���l�A���C�D�̃C�M���X�l�A�����Ď��]�Ԃ̓��{�l�E�E�E�v�Ƃ����K�C�h���̐����ɂ��������悤�ɓ����̒鍑���R�̎��]�ԕ����͋���Ȉ�ۂ��}���[�V�A�l�ɂ����炵�����Ƃ͊m�����낤�B
�@�����قɂ͋q�ϓI�ɂ͈Ⴄ�Ǝv��������������B��Q�����O��A�}���[�V�A�ɂ����鋤�Y�}�Q�����Ɋւ���L�q�͏��Ȃ��A���{�ɂ�����V�c�ᔻ�Ɠ������A���낢��ȈӖ�����Touchy�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�Ō�̓��͉J�ɂȂ����B�J���`���̓X��ɑ��k���āA�o�X�ŃN�A�������v�[����`�܂ŏ�荞�ނ��Ƃɂ����B�r���o�X��ŁA�����ȉp�������ׂ�Ⴂ�����ɉp��b�̃e�[�v�����ꂻ���ɂȂ����B����Ȃ���ׂ��l���A����ȃr�W�l�X�����Ă���Ȃ�āB��`�Ŏ��]�Ԃ�a���ĐE���H����T���Ĉ����Ă��������H���������B
�@�V���K�|�[���Ŕ�s�@����芷���ė�����ɋA�����B���̗]�C�͂��炭�̊ԁA�����Đ^�g�⎇�Ƀs�J�s�J���钹���]���ɂ�����Ė��̒��̂悤�ł������B
�������̐킢(1560) �@�@
�@�����Ԃ̐킢(1560�N�U���P�Q��)�́A�Ȃ�ƌ����Ă��퍑������\����r�b�N�C�x���g�ł���B
�@���̓��A�D�c�M���́A���F��𖢖��ɏo�w�A�M�c�_�{�Ő����Ԃ��߂�������A�ߑO�P�O���`���߂ɍőO���ɓ����B�ߌ�ɓ����đS�R�ˌ��B���叫�̎��������B���̖�P�Q���Ԃɉ����������̂��낤�B�����ɉ����Ď��]�Ԃňړ����Ă݂��B����łȂ��Ɗ������Ȃ������������邩������Ȃ��B
�@2009�N6��7�������V���A���F�������o���B���̂����͗��������A�ނ���������ɂȂ�͂��ł���B��̌������ɂ́u�Č��v���ꂽ�j�Z���F������邪�A�����̏�̈ʒu�͐��m�ɂ͂킩��Ȃ��Ƃ���Ă���B�����U�V���ƍ����Q�R�����o�R���āA�T�O����ɂ͔M�c�_�{�ɓ��������B���m����HP����_�E�����[�h�ł���p���t���b�g�ɁA���ۂ̍s�R���[�g�Ƃ������̂��A�����Ă��邱�ƂɌォ��C�Â����B
�@�M�c�_�{�͐M���R�̏W���n�_�B�M������[�����Ƃ����S�O�O�N���z���Ă��т���y���ɐG�����B�����ތ��S�I�@���������߂��H�ׂāA�����Ԃɂ����o���B
�@�M���́A�����ɑ�}���Ő��F���o�������ɂ�������炸�A�����M�c�ł͂Q�`�S���Ԃ��߂����Ă���B�㑱��҂����̂��낤���H�B����Ƃ������܂����̂��낤���H���������M�c�ɗ���܂łɞw���R�_�ЁA���u�_�ЁA�@�����ɗ�������Đ폟���F�肵�Ď��Ԃ����������Ƃ�����������(��L�p���t���b�g�j�B
�@�M�c�t�߂̍����r������́A�����ɂ���}���̑傫�ȃK�C�V�t�H�[�������悭�����āA���������߂�������B
�@�M���̕��A�M�G�̎���A�C��̎R���ꑰ�͍�����ɐQ�Ԃ��āA�Q�������̊}���ӂ�܂ōԂ��\���Ă����B�M�G�����ʑO���痠���āA�R���I�s�����N�����Ă����Ƃ����������邪�A�Ƃɂ����}���̍Ԃ͔M�c���ʁA�������ʂɈ��͂������Ă����B���̍Ԃ͂P�T�T�Q�N���A�M���ɂ���Ĕr������Ă���B�O�j�̐M���i�����P�X���j�����͂ŕ��e�̌��͌p���ɏ��o���Ă������킢�ł���B�Ǖ��ő�R��ł��j�錩���ȏ����ł������B���̌�A�M���́A�d�b�E�e���E�Z�킽�������X�ɂȂ��|���A���ɍ�����̖C��y�ё卂��̂Q��̍U���ɏ��o�����̂ł���B���̐M��������`�����r�����悤�Ƃ��āA�N�����̂��A���̂P�T�U�O�N�̐���ł���B
�@���Ǝ��]�Ԃ͍����P���𓌂ɐi��ł����܂��R�����z�����B�M���̗L�͂ȕ����A���v�Ԉꑰ�͎R��E��폊�i�F�������j��̒n�ɂ��Ă����Ƃ����B�R���̏����P�O�����قǏ㗬�ɂ́A���̖����Ɩ��É��O�����p�X�Œm���Ă��鐐��^�������Ȃǂ�����B
�@����������̖��É��w��M�c���猩�āA�������A�}���̏�����O�ł���A���v�Ԉꑰ�͂��̂���A���쐨�͂̏d�������Ȃ�Ă����n���W�c�Ɛ��肳���B�Ƃ���ƁA���̐���ō��v�ԑ�w��A�ꑰ���瑽���̐펀�҂��o���ė͐킵�����Ƃ��������₷���B
�@���͂���ɓV������z�������P�����E�ܓ쉺���č�����̏d�v���_�A�卂���ڎw�����B�����͊C�ɖʂ��Ă������̏�ɂ́A������x������I�]�i�M�c�̐��Ɉʒu���Ă���j�̍�������̉��R�������Ă���A�C�̖��Ƃ̊W�����ɂ���āA���C�������l�̎x�������҂ł����B����`���ɂƂ��Ĉ�Γ̂���������ł������̂ł���B2.5���}�ƂP���}�ŁA�ꏊ�ׂȂ���A�ׂ��H�n��������ɑ卂��Ղ̌������������BJR�卂�w�ӂ肩�猩�Ă��̕ӂ��Ƃ����̂͒��������������A�����H�n�������āA�����Ԃł͂��ǂ蒅���̂ɂ͂����ւ낤�B�卂�w��������ƂQ�O�����炢���낤���H
�卂��F�卂�Βn�̖k���ɐՒn������B�����Ɛ_�ЂɂȂ��Ă��邪�A�x�Ȃǂ��Ȃ�Ƃ��c���Ă���B����̐����ɓ����������B
�@�M���ɂƂ��Č��݂̖��É��s�`��E�M�c�������œ����Ɉʒu����I�]�Ƒ卂�ɓG�����邱�Ƃ͑�ςȋ��Ђł������B�D�c�Ƃ̎������͐��^�ƎҁE���l�ɑ傫���ˑ����Ă�������ł���B
�@���̑卂����U�����邽�߂ɐD�c�����������t���邪�A�ۍ��ԂƘh�ÍԂł���B���łɂ��̓������̍U���ŁA������ɑ��U�D�悳��Ă����B������Ȃ��A���̂Q�̈�\���m�F�����̂ł������B�t����͂�������U���Ώۂ̏邩��T�O�O���`�V�O�O���ʗ��ꂽ�ʒu�ɂ������B���Ƃ̔����Ȃǂ��Ւf���A���͂���������ʂ�����̂��낤�B
�@�ۍ��ԁF�肪����B�卂���ۍ��B�W�����Q�O�����炢���̓��������낵�Ă���B���̓��͌B�|��|�卂��Ƃ̘A�������������ƌ����Ă���B�h�ÍԂ���s���ɂ͒n���̐l����������ɏ]���Ƃ����ꏊ���킩��B
�@�h�ÍԁF�ۍ��̋߂��̕��ʂ̌����B�ۍ��ԂƘA�g���Ėh���ɓ�����i��肾�����̂��A�ۍ���茘�łȗv�ǂł��������A���Ԃ����f���ꂽ���ƂŁA�������藎���Ă��܂����B
�@���͊ۍ��Ԃ�����JR�卂�w���ʂɍ���~��Ă���A�̂̑卂��|�B�|��̘A��������������k�����ɉz�����B���̓��̌�ʗʂ͑����A����ꂽ�m�H�X������B�ƍN�́A���̓����z���ĕ��Ƃ��^�̂��낤�B
�@�M�����M�c�ɒ��������������̂́A���̊ۍ��E�h�ÍԂɓ����āA�卂����ʂŌ��������v�f������������ł́A�Ƃ�����������B�@�ߓ��̍��l���삯�����ēV����͌���n�͂���ɂ͑����̊�������_�������Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̑卂��U���̂��߂̊ۍ��ԂƘh�ÍԂ͂��̓��̕��ō��ŗ��Ƃ���Ă��܂����B���쑤�̎����ł́A���쐨��������ɒ��ʂ��C�ɂ��Ă���A�M�c����卂����ʂɐD�c�����P�����邱�Ƃ�S�z���Ă���i�o�T�s�ځF���Ӂj�B�����炱���A�M��������O�ɂQ�Ԃ𖢖��ɋ��P�D�悵���Ɛ��肳���B
�@�Q�Ԋח��̒m�点�����M���͍��̗��蒼���𔗂�ꂽ�B���쐨�͎��ɑ卂���ʌR�ƖC���ʌR�i�O�q�̑O�q�����j���������A�C����͂���M�����̂R�Ԃ�_���ň��̎��Ԃ��\�z���ꂽ�B
�@�ߑO�W�`�P�O���A�M�c�Ŗ��R�Ǝ��Ԃ��߂������M���́A�ˑR�A�R���̊X����C���ʂɌ��������B�M�����L�ɂ́u�삯�ɋ삯�āE�E�E�v�ƕ\�L����Ă���B
�@���쐨�͂����C����͂���M�����͂̍Ԃ͈ȉ��̂R�ł���B
�@�O���ԁ@�F�������̗��R�A�C��̖k�T�O�O��������B�s���Ă݂����悭�킩��Ȃ������B��\�͂͂Ȃ��悤���B
�@�P�Ǝ��ԁF�����C�������̐��̖k�T�O�O���B�C��̓��T�O�O���B�Ԍ����Ə����Ă������B�s���N�F�̓�����̂݁B�R���قǂ̌�����H������A����ɓo��ƒ����ԕ��ʂ��悭������B
�@�����ԁ@�F�C�w���瓌�ւT�O�O�����ɂ����ĕ������얔�ɂ��������A��\�͂Ȃ��B�C��̓쓌�T�O�O���B
�s���Ă݂�ƁA�����̐�͈ӊO�Ɛ��ʂ��������B�����͕����ēn��͍̂��������������Ȃ��B
�@��������猩��ƁA�卂���ʌR�ƖC����ʌR����������v��͂������̂��H�Ȃ��������x�ꂽ�̂��H����Ŕ�J���Ă����̂��H�B�|���w�ɐ키������͕��R���̐S�z�͂��܂�Ȃ����A�폟�҂̃{�[�i�X����A�G�n�ɂ����闪�D�s�ׂɎG�������������Ă��܂����Ƃ�����������A���������L�^�Ɏc���Ă��Ȃ������b�ȂƂ���ɈӊO�ȗ��R������̂�������Ȃ��B
�@���́A�ۍ��Ԃ���P�T���قǂŖC��Ւn�ɓ����B���S�C�w����k�ɓk���T���̏�Ռ����ɂ���B���H�����V�_�Ђ͓��ȗւ������Ƃ����B�퍑�}�j�A�Ǝv����l��������Ɏʐ^���B���Ă����B
�@�M���͒O���Ԃ��瓌�ɐi��ŁA�P�Ǝ��Ԃɓ���A����ɓ쉺���Ē����Ԃɓ������Ƃ����ŋ߂̐��͒��ڂ��ׂ����B��n�ł��钆���ԂɈڂ��Ă���o�������Ƃ����̂́A��P�ł͂Ȃ��Ƃ��������̏؋������炾�B���o�Ƒ����ŁA�������ɖ�2000���邢��3000�ƌ�����M�����̑��݂́A�����������ی������������낤�B
�@�M�����P�Ǝ��Ԃɓ��������_�ŁA�A���~�X�̂��߂��A�����Ԃ̂R�O�O�l�̕��͂�����̑O�q�����ɐ摖���čU���������Ă��܂��A���s����B���͂̒��������Ƃ����A����Ă͂����Ȃ��~�X�ł���B���邢�͗z����킾�����̂��H�@���̒���A�M���͒����ԂɈړ����A�S�R�ˌ��ɑł��ďo���B���̎��_�ł́A�M�������S�ɔ��f�~�X�����Ă��āA�C���ʌR���A�卂����ʂŌ����W�J���Ĕ����������Ǝv���Ă����悤���i�M�����L�j�B
�@���Ɏ������������̂́A�L���s�̖��S�������n��w�߂��ɂ���A�����Ԍ���(MAP111.pdf �ւ̃����N)�ł���B�����ɖ߂�A���ɐi�ށB�C���狗���ɂ��ĂS�����悾�B�����Ԃ܂�Ƃ����̂��s���Ă����B�L���s�̃C�x���g�ł���B���ҍs����U�肩�����ăG�C�G�C�I�[�Ƃ���Ă���̂����āA�C��������オ�����B�������������15�����炢�̂Ƃ���ɂ́A�L���������ԁi���É��s�j�Ƃ����̂�����A���������u�{���̉����ԁv�Ȃ̂ł́H�Ƃ�����������B�́A�L���Ȑ���A��������Ă������牱���ԂƌĂ�Ă����Ƃ����A������ɂ͎��ۂɏ����Ȑ������B�߂��ɂ́A�펀�҂����Ƃ����`���̂��鎛������B
�@
�@�Ȃ��A����Ɂu�I�P�n�U�}�v�ƌ����Ă��A
�@�`�����{�w��u���������ԎR�A
�A�O�q�i�C���ʌR�j�ƐD�c��͕������퓬���A�`���������ꂽ�ꏊ�A
�@���̂Q�_�͈قȂ��Ă���͂������A��������A���m�ɂ͂킩��Ȃ��Ƃ����B
�@����`���͑O�q�����̐퓬�����āA�����H�A��H���悤�Ɖ����ԎR�����肽�Ƃ���A�M���R�͑O�q��˔j���Ă����B�`���͌�ނ��ČB�|��ɓ��邱�Ƃɂ����B�卂��ɓ����������Ƃ����H�Ƃ�����������炵���B���邢�́A�M���ƑO�q�����̐퓬���n�܂����̂�m���āA����������ނ��悤�Ƃ����Ƃ��낾�����̂��H���������A�����ԎR�Ƃ͂ǂ��Ȃ̂��H�����悤�ȋu�˂͂�������B�u�M�����L�v�ɂ́A���̎��A�ˑR�̍��J�����������Ƃ������A�ނ�̔��f�ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ����̂��H
�@������u�����ԌÐ��v�́A�M�l�炵���悪���邩��A�����������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ����ꏊ�ł���B�`���������ꂽ�ꏊ���Ƃ����m���ȏ؋��͂Ȃ��B�����A��������B�|��܂ł͖�Skm�B�C�邩��͖�S��������Ă���B�����܂ŗ����獡��`���͂Ȃ�Ƃ��������߂�Ǝv�����̂ł͂Ȃ����낤���A�Ƃ������Ɍ��n�����������������v�����B
�@�����V���A�w�D�c�M������S�^�x�ɂ��ƁA���쐨�̖C���ʌR���O�q�����͔�퓬�����܂߂Ă��T��B���̕��͂͑卂����ʂȂǂɕ��U���Ă����B�M�����́A��퓬�����܂܂Ȃ��A�I�肷����̐��s�Q��ł���A�Q�{�ȏ�̕��͍��˕Ԃ��ď��������Ƃ������ł���B
�@���X���鐳�ʍU���������A�Ƃ����͓̂��{���s���̐��ł���B�ӊO�ƍ��쐨�͏��Ȃ��āA�S�R�ł��P�����x�������Ƃ��������o�Ă��Ă���A�C���ʌR�����Ȃ�T�炭�炢�Ƃ����̂��[���ł��鐔�����B�������M���͊�q����ׂ�Ĕ����S����蒆�Ɏ��߂���A�������������B������ǂ�ŁA���n��T�����Ă��邤���ɁA��P�ł��A���R�ł��Ȃ��A���ׂ����Ƃ�������R���w���҂����ׂ����ď������Ƃ����C�����Ă����̂ł���B
�@���̔]���ɂ͏����ɂ���A�u�G�ǂ��̂܂�Ȃ���˂������Ă�낤���I�v�Ƃ����A�C���g�l�[�V�����s���̐M���̍b�����Y���т���݂��������̂ł������B
�@�ȉ��́A�����A�z���ɂ��A�܂Ƃ߂̂悤�Ȃ��́F
���쐨���猩�����ƌo��
���ړI���ɐ��p�̐��C���D��A�̒n�h�q
���헪���卂�邨��іC��̋~���B�t����̔j�p�B
����p���B�|��i�n�Ƃ��A�R���ɕ����A�P�R�͑��U���|�Ƃ��āA�卂����ʂ̘h�ÍԁA�ۍ��ԒD��Ɍ������A�Q�R�͖C����ʂ̒O���ԁA�P�Ǝ��ԁA�����Ԃ��U������B�{�w�i���i�ߕ��j������(�����ԎR�j�ɒu�����B�M���{�����P�����Ă����ꍇ�́A�{�w����w�����o���B
���o�܁���P�R�̑卂���ʌR���t������P�ŒD��A�Ǘ����Ă����卂��ɕ��Ƃ���ꂽ�B��Q�R�̖C����ʌR�́A�����Ԃ̏镺��ł��j�������A�D�c��͕����ɂ��˔j����A�{�w���P�����ꂽ�B
�D�c�����猩�����ƌo��
���ړI���ɐ��p�̐��C���ێ��A�̒n�D��A�ł������`���̓������
���헪���t����i�ԁj�̎���A�P���������쐨�̌���
����p���M���Ɗ��{���擪�ɗ��B�V���십�s�n�͂ɂ��A�t����U�����̍��쐨�̋}�P�i�����j�B����`���������ꍇ�A�����ɖڕW��ύX���邱�Ƃ�O��B
���o�܁�
�@�������F����o�w�A�M�c�_�{�őS�R�W���B�������̑卂���ʐi�o��_�������A�ꑫ��ɘh�ÍԂƊۍ��Ԃ�D��ꂽ�B�d���Ȃ����ύX���A�C����ʂɋ}�s�A�C����ʌR���}�P�����Ƃ���A���R�A���叫�̏P���ɐ��������B
��k�푈�̌Ð���è��ް��(1863)��������ōs���܂����B
�@�푈�͑�̂���s���Ă���l�Ԗ{���̍s��������d�����Ȃ��Ƃ����l�����邪�A�̂̐푈�͎��ʂ̂͐퓬�����قƂ�ǂ������B�Y�Ɗv��������̑�ʐ��Y���\�ɂ��A�i�V���i���Y���Ɩ����`�����Ƒ������̐����\�ɂ����B�l�͑��u�̈ꕔ�ƂȂ�A�����ݖ����E�l���퓬���ȊO�ɂ��L�����Ă������̂��B�����Ď��͍l�����B�p�Y������ʎE�l�Ƃ��Ă̐푈�̖閾���́A�P�X���I�̃A�����J��k�푈�ɂ���̂ł͂Ȃ����ƁB��k�푈�́u�ւ����v���Q�e�B�X�o�[�N�̐킢�ł���B
�l�b�g�Ń����^�J�[��\�ADC���j�I���w�̃J�E���^�[�Ō_����ς܂��A���ԏ�ŎԂɏ�荞�B
�Ԏ�̓J���[���N���X�Ə�����Ă������A�y�����Ԃ݂����Ȃe�h�`�s�T�O�O�������B���̎Ԏ�ɒj�Q�l�Ə�1�l���āA���p���O���݂����B
�@�Ԃ��Ƃ��̃��[�g�𑋂���ƒn�}�Ŋm�F���ďo���B�I�v�V�����Ŏ肽�i�r�Q�[�V�����V�X�e���͓��{��ɂ��Ή��Ŗ��ɗ������B����ł��c�b�̎s����k��ʉ߂Ɏ��Ԃ����������B���B�Ԃ͏������Ă��������H�ł͒��i���萫���ǂ��B�}�C�R������Ń_�u���A�N�Z���܂ł��Ă����̂Ɋ��S�����B�I�[�g�o�C�ɏ���Ă����Ƃ����ӎ��Ɏ�ł���Ă������Ƃ������I�ɂ���Ă����̂��B�Ȃ�ă��u���[�I�I���������{�̃I�[�g�}�͂����������i�K�ϑ��@�\���D�G�Ȃ̂ŕK�v�Ȃ��B
�@�������~��ēc�ɓ��𑖂��Ă���ƁA�w�̍������j�������g���������B�������킢�̏œ_�E�Z���^���[�q�����B������������Ă��āA�_�n��[���͂��̂܂c��A�e���ɓ����������Ă����B
�@���������ɂ����Ă�������邢�͍|�S�̑�C�A�����A�����ŁB���ꂪ���~�u���g�����E���h�g�b�v���I
�@�Z���^���[�q�����Ă���ȂɒႩ�����Ƌ������B�قƂ�Ǖ��n���B�@
�@���ɂ̓q���R���h���Q�H�������Ă����B������̐�c�͐펀�҂�H�ׂ��ɈႢ�Ȃ��B

���퓬�Q���ځA���~�u��������k�R�`�F���o�����卲�̊���ADVD����̕`�ʁ�
�@�Y�����т��グ���藈��G�̓ˌ�����Ďˌ��Ō��ށB���ɓG�͉I��U�����d�|���Ă������A�V�������������Ă����j�~�B�Â��ɕ����ɖ��߁BDo you
understand me�H Go!!�@
�@����͔������������ɍL����q���������B�G�̍U���Ŗ����̑���̓X�J�X�J�ɂȂ����B���낽���ēP�ނ�i�����������ɑ��Ắu��X�͂킫�����B�P�ނ��Ȃ��B�����I�v�B�����҂̂��߂����̒��A���̓ˌ�������B�e���̑������w���u�o�C���l�b�g�I�v�B�e���ˌ��B�{�l�����𗬂��Ă������A�ˌ��̐擪�ɗ��B�T�[�x�������邭��Čy�₩�ɑ����Ă����B��R���̔������炢�͐�ӑr�����Ă����������グ�����A�Ő키��R�͂���Ȋ����������̂�������Ȃ��B�G����˔j���Ă��̂܂܍��ɉ�]�^���B�����ēG�̉I��U���������B
�@���̑呛���̒��ŁA��ÂɎ�����S�̂�K�ɔ��f���A��������m�������߂邽�߂̎w��������̂��������B�{�E�͉p��̑�w�����B�퓬�o���͑f�l�������Ƃ����B
���k�R��͂̏��e�X�v�����O�t�B�[���hM1861�ɂ��ā�
�@�����قɂ͗l�X�ȏe���W������Ă��邪�A��͂͂���B���C�t�����O���点���̍a�A�����邱�ƂŔ���I�ɔ������サ���B�炪�����Ȃ��Ă��l�E�����ł���悤�ɂȂ����B��䰂͂܂������Œe�ۂ͂ǂ�^�ŐK���傫���ւ���ł���B�܂��O�����ł���A���̃��f�����㑕���ɂȂ�̂�M1865����ł���B1865�N�ȍ~�A�㑕�����}���ɕ��y���đO��������������B������1868�N�̕�C�푈�ł͒��Õi���f������ʂɎg��ꂽ�̂ł���B
�@�����������̃G���[�g�̋R�����ɂ͌㑕���i�ꕔ�͘A�����̃X�y���T�[�e�j���o����Ă���A�k�R�R������Buford���R�͑��߂ɉ��n���ėD�ʐ��������x�ؐ�p�����悤�Ɏw�����Ă���B�܂��A�J�X�^�[���R�̐��������k�R��w�����e�̗D�ʐ����ߐM����]��A�z���ɓ�R�����O�X�g���[�g�̖{�w�P���𖽂��đ呹�Q���o���肵�Ă���i�p��wiki�j



���i�|���I���P�Q�|���h�C��
�@�i�|���I���R�����K�i���������߂ɕt�������́B���a���P�Q��������������P�Q�Ƃ������Ƃ����A�Ȃ��|���h�Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B�C�e�̏d���ł����Ȃ�A�����Ɛ������������͂����B
�����̑z�������A���������������r�߂��邩�炱�������̂ł͂Ȃ����낤���H�Ƃ�����A���̋K�i�͑ϋv���ƌy�ʂ����˔���������I�ȋK�i�ŁA���R�Ƃ��g�p���Ă����B���ł͎g�p���@�̓V���v���Ȃق��������B
�@�����ƓS���̂����̎���ɓ����K�i�ŋ������Ă�̂��s�v�c���B��R���[���R���b�l�����Â��C�S���ɑ����āA���ׂ��Ă��̃i�|���I��12�|���h�C�ɒ�������悤�ɗ���ł���B
���R����
�@�悭������̂��A�k�R���u���[�œ�R���O���[�A�Ƃ������Ƃ����A��R�͕n�R����������A�����̃C���f�B�S���P�`�����̂��H�B��������R���Z�̌R���̃f�U�C���̓J�b�R�����Ƃ������Ă���B
���z�ꐧ�ƃQ�e�B�X�o�[�O��̂��̌い
�@1862�N�A�k�R�̏B�ɂ͓z��̏��L��ٔF���Ă���ɂ��ւ�炸�A�����J�[���͈���I�ɓz�����錾���s�����B��R�����B�̓z�ꂪ���S���Ă��邱�Ƃ����サ�A�푈��L���ɐi�߂邽�߂ł���B�����ăQ�e�B�X�o�[�O�폟��ɂ͏�����O��Ɍ��@�����ɋ�������������B�A�����J���O������ɂ���Ƃ������O�̉��A�ނ͌��@��P�R�������ĂւƋ����˂��i��ł������B�ނ͗��O�̎����̂��߂ɂ͓z�ꐧ��F�߁A��ɋ֎~�����B����ɃQ�e�B�X�o�[�O�폟��͈�̑Ë������B
�@���������ꂸ�A�M�O���т��u���\�ȁv�j���̋Ƃ𐬂����ゾ�����B�Q�e�B�X�o�[�O�킩��I��܂ł̂Q�N�Ԃ͐��E�j�I�ȃ^�[�j���O�|�C���g�������B1863-1865��`�ʂ����f��A�u�����J�[���v�ɂ�����`�ʂ͏�I�ȍȂ�c�������A����ɑ����Âȃ����J�[���Ƃ����Δ�ɂ���Đ��藧���Ă���B�ނ͐^���ԂɏĂ����c�_�ɒ��ۓx�̍����_�_��₦���B�̂悤�ɑł�����Ō��ʂ��o���Ă�����
�@
���N����
��k�푈�J��1860�N4��12��
�z�����錾1862�N9��
�Q�e�B�X�o�[�O��1863�N7��
�Q�e�B�X�o�[�O�錾1863�N11��
�哝�̑I��1864�N
���@��13���C���Ă��c��ʉ߁A1865�N1��
��k�푈�I��1865�N
�������ف�
�@�W�I���}��W���Ȃǂ��L�x�œ����̏��悭�킩��B���N�͂P�T�O���N�̐ߖڂȂ̂œ��ʕҏW�̍��q���o�Ă����B�G�s�\�[�h���L�x�B�����̃Z���^���[�q���ɂ͓��S�z��̍��l�������Z��ł����B������A�z�ꏤ�l�����̐l��U�����Ĕ��������Ƃ������A���̏����͌�������R���A�U���҂̐e�w��H���������ē��ꂽ�������B
�@�����ق̑O�ɂ̓����J�[���̒������x���`�ɍ��|���Ă����B�G�߂�9���ōg�t�������������B
�@�g�t�ƌ����Ă����F�����S�̃A�����J�嗤�̍g�t�ŁA����͂���Ŏ��ɔ������B
���Q�e�B�X�o�[�O�錾��
�@�l���̐l���ɂ��l���̂��߂́E�E�E�E�Ƃ��������肪�]��ɂ��L�����B
�@�Q�e�B�X�o�[�O�錾�̂Ƃ������J�[���͓V�R���̏����Ǐ��悵�Ă���A�̒��͍ň��������B�錾�͒Z�������B���ۂɉ��ƌ��������́A���ʂ���̐�������A�v�����g�������̂Ƀ����J�[���̃T�C����������̂��u����v�Ƃ��Ĉ����Ă���B���̐錾������ŕ������c������̎���ɉ�z���ĘN�ǂ����Ƃ������R�[�h���������Ă���A�����قŕ������Ƃ��ł����B�����IYoutube�ł��������Ƃ��ł��邱�ƂɌォ��C���t�������ǁB�A�C���b�V���Ȃ܂���Ăǂ��H
���G�s���[�O��
�@�A�����J�̌R���{�ݓW���͂ǂ������ȋ]�����^���Ă���B�T�O���̂̔ے�͂��Ȃ����A���{�l�Ƃ��Ĉ�a��������B���������ƃA�����J�͎��ۂɍs���Đ������Ȃ��ƁA���ʂ�����������Љ�̒g�����͂킩��Ȃ����낤�B���̔��ʂ̍��ƓI�c�������c�O�Ɏv���B�e�̋K�������Ă������B��X���K�₵��DC�̂��锎���قł́A���̂P�O����ɏe�̗��ˎ������N�����̂ł���B
�U�D�`�o�̉����d����탋�[�g�������i�������ҁj
�������̏������́A���Č��`�o�������P���ɍۂ��ď㗤���s�����n�_�ł���A
�������s�������u�`�o�h���[�����[�h�v�Ȃ�p���t���b�g���쐬���Ă���B�㗤�n�_
���珟�Y��n�͒n�_�܂ł�10km�̏������s���̓`�����Љ�Ă��ċ����[���B
�P�D��ォ��̊C��ړ��B
�@��ȋ��ł͋`�o�͈��V��̒��A120�������U���Ԃňړ��������ƂɂȂ��Ă��邪���Ȃ薳��
���B����͖�P1�m�b�g�ŁA���a����̃f�B�[�[���G���W���̏������t�F���[�ɕC�G����B���I
�푈�̏��C�@�ւ̐�͎O�}�̍ō����x�͂P�W�m�b�g�iwiki)���B
�@�������[���b�p�̐l�͂̃K���[�D�͐퓬���x��7.5�m�b�g�ƌ����Ă���i�p��wiki�j�B
�@�`�o�R�͔n�ƕ�⋕�����D�ɏ悹���Ƃ���ƁA�D���͑����x���Ȃ邾�낤�B���Ȃ݂�
�������E�B���A���̓w�C�X�e�B���O�㗤���̍ۂɁA�u�n�͕��m�T�O�l���̓���������v
�Ƃ��Ĕn�𑽂߂ɗA�������B�R���E�|���E�������ύڂ��A�n�ȊO(������O���I)�̑S��
�����ŘE�𑆂����Ƃ����B
�Q�D�㗤�n�_�̑I��
�@�@�l�͂ɂ��D��������A�D�c����x�ɒ����Ƃ͎v���Ȃ��B�܂��㗤��A���������
�����Ȓn�_�Ƃ������Ƃ��d�v�����H�@�����Ō㑱��҂��Đ����낢�����Ƃ������ƂŁu�����v��
�����n���ɂȂ����Ƃ������A�n���Ƃ��Ă͒������Ƃ����_�͐M�҂傤��������B�ٓV���Ƃ���
��������M���𑗂�A���ɂȂ����D�c��U�����A���̗���̘p�ō��������Ƃ�������
���낤�B�����ɂ�������܂������������m��ٓV���̋߂��̍��l�ɑ��荞��
�ȂǏ㗤�����ł��l���邱�Ƃ͎R�قǂ���B
�R�D������A������
�@�@�S���I�Ƀc���}�L�Ƃ����n���͑����B�c�����Ñ㒩�N��Ŗq��̂��Ƃ��w���B���́u�q�v
�Ŗq��ƍl����ƁA�`�o�ȑO�ɒn�����ł��Ă����\��������Ǝv���B
�S�D���R��
�@�@�@���{�݂͏�W�܂�Ƃ���ł���K������������ł��낤�B�l������P�W�ԎD����
�Ȃ��Ă���B
�T�D���Y��n�͒n�_
�@�@�����̂����Ȃ萅�ʂ����葊���㗬�łȂ��ƕ����ēn��Ȃ����낤�B��M���Ȃ��őD��
��������̂��B���݂ł͂��̂�����ɑ�ʂɐ����Ă���Џ@�|�𑩂˂ĊȈՋ����˂��邱�Ƃ�
�l�������A�Џ@�|�͂P�W���I�ɓ��{�ɓn�������A���݂ł͊��Ȏw��̊O���킾�B���������퍑
����ɂ͎g���Ă��Ȃ��B
�@�Ⴋ���̐퍑�̌������A�Џ@�|���Ԃ������āA����Ől����邺�Ƃ������͖̂����Șb���B
�@�@�`�o�ɉ����������ߓ��Z�e�Ƃ̋���͂��̋߂��ɂ���A���̐l�͉��炩�̃A�C�f�A������
�Ă����ɈႢ�Ȃ��B�͔Ȃ̒����q�Ƃ����ꏊ���A�u�`�o���[�h�v�P�O�����̏I���n�_���B
�@
�U�D�������ʂւ̃��[�g
�@�@���Y�삩����Ԃւ̃��[�g�́A���Â�z���i�W���P�P�T���j�Ƃ��������z���Ă���ƌ���
�`��������A������̓n�͂ɍۂ��Đ��ʂ����Ȃ��n�͒n�_�����߂ē����Ɍ��������̂�
������Ȃ��B
�@�@���]�Ԃő���ƎR�����Ⴍ�Ȃ��Ă��ĉz�������Ȃ�悤�ȃ|�C���g�ł��������A���Â�z��
�͎R�[�����͋C�̂������ł������B���͍��̐�������������̐�n�́A���炳���c�n
������ŎR�z�������Ĉ���쉈���͔̉ȗт�k�サ���ƍl����B
�@�@�^�~�̓n�͂͐퓬�\�͂�D�������łȂ��A�n�͓_�͌����Ă��đ҂���������₷���B
�@�@�R���𐅂ɓ���n���č��G������B�����̋C�z���@�m����\�͂͐l���n�̕����D��
�Ă���B���ꂩ�������n������B���̍ێ߂ɏ㗬�Ɍ������ĕ�������B�㗤��͂�
���邾���������ӂ���邱�Ƃ�O�ꂷ��B
�@��ȋ��ɂ͂Q���P�W�������ɏ������ɏ㗤���A�P�X���ɉ����P���Ə����Ă���炵�����A
���Ȃ薳�����ۂ��B
�@����̃��[�g�����ł͏������̐�������g��쉈���̍��ԉ��~�܂łQ�T�������x�B����
���牮���܂ŁA��㓻�z���]��X���ʼn����܂ŁA��U�O�����قǂł��邪�A�����̏ł�
�R�{�ȏォ�������ł��낤�B
�@�i�|���I���R�͂P�T�O�������Ȃ�����s�R���Ă��đ��퓬�Ƃ������Ƃ����Ă����炵�����A�R��
�ł��������̂͂͂邩�ɓ���B�ݕ��ŕ��������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ���⋂���
����B�@�������r���A�g���E�݂̍��ԂƂ����Ƃ���ŕ��Ɛ��͂̍����̊ق��P�����Ă���B
�@
�V�D���Ԃ̍����̉��~
�@���ԉ��~�́A�����炭���́u���ԁv�Ƃ����n���̂�����ɂ������̂��낤�B���̐̂͑傫��
�O�������������炵���B���t�W�ɏ����Ă��������̒r�͍����L��̂��H�A�Ə��R�ɕ���
�ꂽ�I�{������ݒu�����Ƃ������i�]�ˎ���j���c���Ă���B
�W�D�g���n��
�@�����̂��g���͂�������͂��B�������]�ˎ���ɑ�\�������݂���đ啝�ɗ��ꂪ�ς�
���Ă���B�����̒n�`�͂ǂ��Ȃ��Ă���A�ǂ���n�͂������͑z�������Ȃ��B���ԉ��~��
�ߗ�����̏��Ő�M���W�߁A�s�X�g���A�������̂��H���͐�Ɏ}�����ꂵ�Ă����̂œn��
�ł���|�C���g���������̂��H�g��삩�牮���܂ł́A�ʂ̋@��Ƀ��|�[�g�������B
�V�D�`�o�̉����d����탋�[�g�i��㓻�ҁj
�Q���̑����͎�w�������邪�A�C���͂���オ���Ă����B�����̎�������]�Ԃŏo�āA�g����n�邱��ɂ͎�w�̒ɂ݂������Ȃ��Ȃ����B�`�o�̉����N�U���̌㔼��̎�n�߂͋g���B�ǂ���n�����̂��B�P���������ԉ��~�̂�����̐앝�͌��݂ł́A���T�O�O��������B
�n�͂͂T�l���̐�M�P�z�Ȃ�A150�R�{350�l�̉Ɨ���A������̂�220�����A110���Ԃ�����B�P�O�z�ł�11���Ԃ�����B�����̋��g�� ��͕��Ă��ĕ����ēn�����L�����\���͂��Ȃ肠��̂���������T���Ă��Ȃ��̂ŕs���ł���B
�@���ƕ��̍��ԉ��~���������炵�����Ԑ_�Ђ�K�ꂽ�Ƃ���A���a�T���قǂ̏����Ȓr������A�̂͋���ȎO�������������c���Ƃ����B �g���ƂȂ����Ă��āA��M�������W������Ă����\���������Ɛ��������B�Ƃ���ƍ��ԉ��~�P���͂����D�悷��̂��ړI�������\��������B���Ƃ́A��������z���āA�����Ƃ����Ƃ��ɂ͂������Ă����߂邱�Ƃ�O�ꂷ��K�v���������̂ł���B
�g�����z����Ǝ��͎]��R���ł���B�i���]�R���Ƃ����ʖ������邪�ǂ����ł���������j�B��㓻�͕W�����Ⴂ�̂ŁA�`���I�������I�ɂ�����ʂ����\���������B��㓻�́A�Ⴂ���ǂ����̂Ȃ��炩�ȓ��ł������B�悪
�ǂ݂ɂ������͎��]�Ԃł͈ӊO�Ɣ���B���֑I��̃g���[�j���O���悭����Ƃ��낾�B���˓��C���́A�Ȃ��肭�˂��Ă��āA���j�������������B�Ԃ�ʂ����߂ɍ]�ˎ���͂���ȌX�̂��₩�Ȑv�ł������̂�������Ȃ��B���]�Ԃł̓u���[�L���g�킸�ɉ��ꂻ���Ȋ�
���������B��ʂ̗v�Ղł��������߁A�]�ˎ���͑傫�Ȕԏ����u����Ă����B
�@�`�o�͑�㓻�ȊO��ʂ����Ƃ������_������B�����ɔ����鑊�I�����Ȃ�Ƃ����Ă���₾���A�Q���̎����͓ˑR�̍~��ŃX�^�b�N���� �\��������B�V���\���ł���n���������I����擱�����Ƃ�����h���}�ɂ͂Ȃ邩������Ȃ��B��C�ɋ삯�����ĉ�������P����Ƃ�
���͈̂ӊO��������A�`�o�t�@�����D�݂����ȃX�g�[���[���B��㓻���[�g���Ə��������n�͂���̂ɐ_�o���g���Ă̗��ɂȂ�B
�@���I���́A�_�Ɋ��ɓ����������獁�쌧���ɖ�����A��čs���A�H�ɂ͕Ă�w�ɏ悹�ē������ɋA�����Ƃ����r�W�l�X�̎��̂��铻�ł� ��B���̍ۂɉ������܂��̂Łu�]��j�Ɉ��g���v�Ƃ������t�����܂ꂽ�Ƃ�����������B����͎��ɉ��[�����t�ŁA�������̕��͂���A
�v�w�̑����_�Ɏ���B�����̑������m���Ă���̂ɗl�X�ȉ��߂����Ă���B�{��������������I�������̎��s�v�c�����A�Εׂł��邱�Ƃ� �v�w�~���̏d�v�ȗv�f�ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł���B
�@���͂��̗����l�b�g���ɗ��������A�`�o�R�̏�Ƃ��Ăٌ͕c�͋I�B�̊C���̏o�ł���A�C����Վ҂ɂ���������̂ł͂Ƃ� �����������ĂĂ݂��B��⋂��C�l�ɗ������\��������̂ł́B
�@������C�����̍����ɓ��艮���܂ł͕��R�ȓ��𑖂���L�����̂Ȃ����]�ԗ��ɂȂ�B�Ƃ肠�����A���ǂ��������B���]�Ԃɂ̓J�� ���[�̍���������Ƃ����]�ǂ����B���ǂ�̂��߂Ɏ��]�Ԃɏ��̂��A���]�Ԃɏ�邽�߂ɂ��ǂ�����ׂ�̂��B���������쌧�͓��A�a�̔䗦���������ł���A�g�b�s���O�̂Ă�Ղ�͗ǂ��Ȃ����I
�@�܌��R�ƌĂ��j�b�v����듪�̔����������Ă����B��C���T�{�̌����[�����ƌ����锪�I��������B�������l�ł��u�₭�肳�� �v�Q�q���y���݂ɂ��Ă���l������l�C�̎��ł���B���Ɍ����Ă���͉̂����̔����ł���B
�@�����͂��Ă͓��ł���A�ׂ��C�����������B�����̎��ɂ͓n��Ȃ��̂ŁA�U�ߎ�͈�H�v���K�v�������B���Ƃɕ����đ�R�Ɍ���������Ƃ����A��l���I���ł���B��P�ɋ����������̕��Ƃ́A�C�ɓ����Ă��܂����B�d�v�l�������Ƃ����헪��D�悵���̂��B
�@�������A��P�ɔ����Ă̖h����ӂ��Ă������Ƃ͌����܂ł������B�З͒�@�����邢�͒���Ɏ��{����̐������Ȃ������̂́A�������C����U�߂Ă���Ǝv������ł����̂ł͂Ȃ����낤���H���邢�͎l���̍��l��M�p�����������B
�@�`�o�R�̐ڋ߂�m�点�ɑ���l�����Ȃ������Ƃ����̂��A���Ƃ̔s���ł͂Ȃ����H���邢�͌����̐��K�R���C����U�߂Ă���Ƃ������ɘf�킳��Ă����̂��H
�@�V�R�������A�Ƃ����ꏊ�����������A�F��Ƃ�������͎��ɉA���ȕ���ł���B������ォ��]�|��������A���ʂ���U���̎ז������邽�߂̓S���̕���Ȃ̂ł���B�푈�̓X�|�[�c�ł͂Ȃ��B���Ă悢�̂��I�������Y�Ɗv���Ȍ�̐��E�ł́A������Ή����قǖړI��B���ł���Ƃ����̂����ɉ����āA�ŋ��̐헪�͊j����A�ŋ��̐�p�̓Q�����ƃe���ƂȂ��Ă��܂����B���͂�푈�����邱�Ǝ��̂����E���̐l�X�̍K���������ăq�[���[�͐��܂ꂻ���ɖ����B�q�[���[�͂��߂Ă��́u������v�Ƃ��ċ@�\���Ă�����d�����B
�@���Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����J�l�Ɍ�������A�u�ӂ�I�����͐l�ނ̖{��������ˁv�ƌ����Ă��܂����B�������g�p�����A�����J���̐l�ɂ͌���ꂽ���Ȃ��I10���P�ʂŎ��l���o���ʎE�l�͗��j�I��19-21���I���L�̂��Ƃł���A�l�ނ̖{���Ƃ͑��e��Ȃ��B�����Ƃ��q�[���[�Ȃ�Ă����x�[�X�{�[���ƃT�b�J�[�ŏ\�����I�告�o���ˁB
�@�ߐ{�^��̌̎��̌���ɂ́A�^�ꂪ�n�̑O����u���ČŒ肵���Ƃ�����������A�T�O���قǗ��ꂽ�ꏊ�ɐ�̊G�������Ă���B���ɂ͐�Ζ����i������O���I�j�Ǝ����B���̏ꏊ�͘p�̉��ɂ���A�^��͉����Ɍ������Ď˂����ƂɂȂ�B�L�X�Ƃ������˓��C�Ɍ������Ď˂��������܂ɂȂ邩������Ȃ����j���I�ɂ͋^��Ƃ������Ƃ炵���B���ƌR�͏����W�̂��߂Ɋ݂ɋ߂Â����Ƃ������ʂ�����̂ł́H
�@����˂���A�^��͖������āA�D��̘V���������˂��Ƃ������A�����Ւf����Ƃ����ӊO�ƃV���v���ȗ��R�Ȃ̂ł͂Ǝv���B
�@�l�b�g�����ł͂����������ꏊ��������ɂ��������̂Ŋό��W�҂ɉ��ǂ�]�݂����B
�@�`�o�̋|���Ƃ��̌̎��̌��������A�C�z��̕��ɂȂ����B
�@�`�o�̏��ƂȂ��Đ펀���������^�̕�͋����قNjX�����B���ȋ]���ԋߑ㍑�Ƃ̐헪�I�ӌ�����������B
�@�����̏�܂ŏ��̂͒f�O�B�W������280���قǂ���B��������X�O�����T�C�N�����O�{�₭�肳��Q�q�Ŕ��āB
�@�`�o�R�͕������ē����̏������ɏ㗤���A�������̐���z���ēO��ŎR�z�����A����150�����ȏ�s�R�����B�������ɓG�n�ł̕�⋂͍�����ɂ߂����낤�B���ꂪ1���ł����Ă�3���ł����Ă��A�����ւ�Ȓ����ł���B������\�ɂ����H���͂ǂ�Ȃ��̂��낤���B���Ȃ݂ɃJ�����[�����g�Y����偛�O���[�v�͓��������˂̊�Ƃł���B
�W�D����푈�̓�������
�@��C�푈/��Ð푈(1868�N)�̎��ɉ�Ô˂�8�����̖h�q����~�����ƌ����Ă���B
�@��Ô˂������d�������͓̂������i�R�����j�A���͌��i�w�������j�A��{�����i���C���j�A��{���邪��������́A�i���H���k�ɂȂ����ƍl������Ô˂͓��ɒ��R����\�z���Ă����B���������R�̎�͂��ʂ����͕̂ꐬ���������B�n�͒n�_�����Ȃ�����Ƃ������R�B
�E�ꐬ���͉�Ôˑ�����������\�F����2�����炢�̐����c���Ă����B�����z����Ƃ��ɑ_���ł��邩�������ɂ͓s���������炵���B�L�O�肪����B
�@��Ô˂͂�����z�肵�Ă��Ȃ���������{���ɏo�Ă����咹�\������C�t���ĉ���B�o�������ꂽ��Ô˂͏\�Z���y�ь˃m���őj�~���悤�Ƃ������A�Ԃɍ���Ȃ������B
�@�����ɉ������Â͔��Ց��̔ߌ��ށB

�E���R���ܑ͕�����Ă��邪�g���l�����ł��Ĕp���B��\�Ȃ��B���]�ԂŒʂ�Ȃ����Ƃ͂Ȃ����A�ꕔ�����i2021�H�j�B
�E���C���ܑ͕��ׂ̍����œ�����̒��߂������B���퓬���������炵���B��\�͑��ɖ�����Ă���(2021��)�B�_�ޏ����������̂͂������̓��������B

�E�w�������͗z���������܂߂āA����ʂ�Ȃ������B�ܑ�����Ă��邪�g���l�����ł������߂Ɏ��Ĕp��������B��\�Ȃ��B�����t��2km���������Ď��]�Ԃœ��܂ōs�����i2021�H�j�B���c��͉�����������ċC�����ǂ��B�C�ƎR�̗ǂ��Ƃ���肾�B��Ô֒�R���D�����J�^�`��`�����Ă���B��������̕��ł�������̎��҂��o�����R�Ƃ͎v���Ȃ��B���������֒猩��Ƃ��Ȃ�r�X�����p�����Ă��Ă����B�։z�����F�o���G�c�T�C�Z�����ĂȂ������������B

�E�������ʂ̎R�����͂�������˔j����āA�������O�Ō��킪�������B24���̕悪�c���Ă���B�R������20�N�ʑO�Ƀg���l�����ł��Ĕp���������]�ԕs�i2022�j�B�p�������͖�3km�B

�E������O��̋������Qkm�قǎc���Ă��Đ�������Ă���B�ƂĂ��������͋C��(2022��)�B�������݂����������Ă����B�@���������̃C�U�x���o�[�h�͑�����̑���ɗ��X���̎s�쓻��I�����ĉ�Ó��肵���B���R�͂킩��Ȃ��B
�@����h�͏h�꒬�͊X���݂��Č�����Ċό��n������Ă���B�Q�Ό��̂��ߐ�������Ă����B

�E�߃����1.5km����Ă��鏬�c�R����̖C���ő呹�Q�i�ʐ^�j���o�����B�Ȃ����̂悤�ȏd�v�|�C���g���ȒP�ɒD�悳�ꂽ�̂��H4�ҎR�C�͎˒�����2.6km�B�C���o�Ƀ��C�t�����O������c���̖C�e�������B
�@
�E���Ց��͂Ȃ����E�����̂��H��@�����ł���ǂ�ς���\�������邵�A�_���Ŏw���������\�������������낤�B�ƌ���l�Ƃ��Ă͍l����B��ǂ��S���D�悵�Ă����̂ł́B
�X�D�������ް�ނ̖��(�H�c)
�@2022�N�A�������]�Ԃő��������Ƃ̂Ȃ��s���{���͐X�����c���݂̂ƂȂ����B�ǂ����Ȃ疼�̂��铻���z�������B���͐V�X�o�R�Œ����Ìy���̑�w�ɓ����B�ԗ��͕��ʂɕs�ʂ������B
�@1878�N�ɖk���{�𗷂������E�I�������l�C�U�x���o�[�h�͖�����u���{�ō��܂Ō����ǂ̓������A���͂��̓���J�ߏ̂������v�Ə����c���Ă���B�J�V�Ȃ̂ɖJ�߂Ă���B���J���l�X�Ȕ������͗l��`���Ȃ�������̂䂫�͂������т���ߏグ�Ă����̂��낤���B�H�c�����܂������ɓV�������т��Ă��Ĕ������Ƃ̂��ƁB�H�c���͐̂��疼�Y�i�Ȃ̂ł���B�����V���͑O�N�ɂł�������œ��������Ԃ�ǂ������B
�@���ċg�c���A���킴�킴�����ɗ������Ƃ����芿�����c���Ă���B���R�Ƃ͗�R�������Ă��āA�Ղɓ�����Ƃ����̂́A���̓��ɗR������ÎE�����������Úg���Ă���̂��ȁB
�@�����z���Đ̂̍��S�̐��H�Ղ������ƁA�O�A�d�̔肪�������B���C�@�֎Ԃ��R�A���œ���o��Ƃ����̂͏��߂Ēm�����B�S���t�@���ɂ͏펯�炵���B�N�}�^�J�������ڂ̑O���B
�@�É�������͗\�Ƃꂸ�A���������̖�n�C�c�ɏh���B������܂��i�ʂȓ��������B
�@�����̖ڕW�͓��{�S�����̈�A���ד�(631��)�B���̎�O�̍◜����460m�ł��Ȃ艺���Ă���̍��q�n�_��840m������B����Ȃ���W�I�̓����z���銴�����B
�@���ד��̖��̗R���́A�R��i�������j�Ƃ������ƁA���{�A���n�b�J���������Ă����������邪�A
�A�C�k��ł̓n�b�J�̓��}�u�h�E���Ӗ�����̂ł�������������Ȃ��B���ד��W�]�䂩��̃J���f���̒��]�͐�i�ł���B���T�ɂ͍g�t�̃s�[�N�Ŕr�C�K�X���Ђǂ��ł��낤�B�g�t�͎��]�ԃm���ɂƂ��Ă͗L����f�H�B

�@�\�a�c�ΌΔȂɓ������ė��ق̂ӂƂ�ɑ̂𓊂��o�����B�����͂��������I�ȃX�o�炵�����E���قł������B�I�[�i�[�̓e�����[�N�Ə̂��ė��قɗ����A�H�����R�̂悤�ɐςݏグ�Ă����ď���ɐH�ׂď���ɋ���u���Ă������ƂɂȂ��Ă���B�L���ɂ͐����܂肪���菰�͕����Ċזv���Ă���B�䏊�̔r���ǂ͋l�܂��Ă����B���C�͂Ȃ��ăV�����[�̂݁B
�@�������z�c�ƃV�[�c�͐����ŗ���2000�~�Ƃ����ᗿ���̂���10���ȏ�̐l�����܂��Ă����B�݂�ȃ��s�[�^�[�B�{�݂̗��p���@�ɂ��ċq���������킴��Ȃ��̂Ŏ��R�ɉ�b�ɂȂ�B
�@�̂̃��[�X�z�X�e���h�͐��E���ǂ��ł��ٖM�l�Ƃ̉�b���͂��ފy���������B���͐��E���݂�ȃX�}�z�ł���B
�@���̓������V�B���Ԃ蓻���z���ē��{�s���~�b�h���̐��n�F��ΐ_�R��K��B�Ñ�l�͓��{�e�n�̃p���[�X�|�b�g�Ƀs���~�b�h��A��I�p���[�̃l�b�g���[�N����}�����Ƃ��Ȃ�Ƃ��B���̃p���[�����傷���ď\�a�c�ΎR�������Ă��܂��A�Ñ�l�͂��̃e�N�m���W�[���Ƃ��Ȃ�Ƃ�����Ƃ��E�E�E�E�B�����Č˗����̃L���X�g�̕�I�L���X�g�����ꂱ���ł��S���Ȃ�ɂȂ����Ƃ��B���[�̐��E�̓��[���I
�@

�@���˂�ڎw���ē��։���B�c�O�Ȃ���s���~�b�h�p���[�̉��b�͖����đ����d���B�N����đ̗͂��̂��̂����̗͂̉͂������������������B�u���[�L�V���[���ى����A�X�v���P�b�g������B���N�����Ȃ葖�����ˁB
�@�c�����i���삯�����Ĕ��ˉw����V�����ŋA�����B2022�N�H�E�E�E�l�������Ă����B