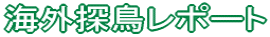
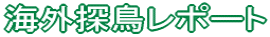
個人旅行による海外探鳥をお考えの方の参考に成れば幸いです。情報はアップデートしておりませんのでご注意ください。ボタンをクリック。
![]() 40.インドで確認した鳥名リスト(2024年) Jul. 2024up
40.インドで確認した鳥名リスト(2024年) Jul. 2024up
![]() 39.インドで野鳥修行の旅はきつかった(紀行文)。April 2024up
39.インドで野鳥修行の旅はきつかった(紀行文)。April 2024up
![]() 38.バンクーバーの冬は3年ぶりの海外旅行
38.バンクーバーの冬は3年ぶりの海外旅行
![]() 37.佐渡にトキを見に行ってもいいかな(English)
37.佐渡にトキを見に行ってもいいかな(English)
![]() 36.奥尻島にアビ類を求めて(2022.04)
36.奥尻島にアビ類を求めて(2022.04)
![]() 35.ハワイ島でハリモモチュウシャクシギとハワイ固有種の観察(後編)Apr.2020
35.ハワイ島でハリモモチュウシャクシギとハワイ固有種の観察(後編)Apr.2020
![]() 34.ハワイ島でハリモモチュウシャクシギとハワイ固有種の観察(前編)Feb.2020
34.ハワイ島でハリモモチュウシャクシギとハワイ固有種の観察(前編)Feb.2020
![]() 33.宮古-室蘭航路で海鳥をみる!Aug.2019
33.宮古-室蘭航路で海鳥をみる!Aug.2019
![]() 32.厳寒期のソウルでヤマヒバリを見たい作戦 Jan.2019
32.厳寒期のソウルでヤマヒバリを見たい作戦 Jan.2019
![]() 31.峨眉山、山麓の報国寺と伏虎寺の7月 Jan.2018
31.峨眉山、山麓の報国寺と伏虎寺の7月 Jan.2018
![]() 30.四川省で録音したムシクイの声メモ Dec.2017
30.四川省で録音したムシクイの声メモ Dec.2017
![]() 29.ムシクイ仙人を目指して峨眉山で修行(2017.7) Oct.2017
29.ムシクイ仙人を目指して峨眉山で修行(2017.7) Oct.2017
![]() 28.中国四川省峨眉山を目指して Aug.2017
28.中国四川省峨眉山を目指して Aug.2017
![]() 27.シンガポール(12月)の鳥名リスト Aug.2016
27.シンガポール(12月)の鳥名リスト Aug.2016
![]() 26.シンガポールのウビン島・植物園・スンゲイブロJan.2016
26.シンガポールのウビン島・植物園・スンゲイブロJan.2016
![]() 25.冬の香港でムシクイ三昧 Feb.2015
25.冬の香港でムシクイ三昧 Feb.2015
![]() 24.台湾の野柳で「黄眉不是(キマユじゃない)」と叫ぶ
24.台湾の野柳で「黄眉不是(キマユじゃない)」と叫ぶ
![]() 23.NYマンハッタンのセントラルパーク探鳥会に参加した(’13)
23.NYマンハッタンのセントラルパーク探鳥会に参加した(’13)
![]() 1.香港の中心部にある公園に行ったら意外と面白かった話(02)
1.香港の中心部にある公園に行ったら意外と面白かった話(02)
![]() 2.香港マイポでシギチの大群を見たけど、ヘラシギはいなかった話(02)。
2.香港マイポでシギチの大群を見たけど、ヘラシギはいなかった話(02)。
![]() 3.香港タイポカウでエゾムシクイの分類を考えた(02)。
3.香港タイポカウでエゾムシクイの分類を考えた(02)。
![]() 4.香港バードストリートでたくさんの飼い鳥を観察した話(02)。
4.香港バードストリートでたくさんの飼い鳥を観察した話(02)。
![]() 5.シンガポールからマレーシアにかけての記録(99)。
5.シンガポールからマレーシアにかけての記録(99)。
![]() 6.フランスのロアール地方、ブレンネでイギリス人を見つけた話(02)。
6.フランスのロアール地方、ブレンネでイギリス人を見つけた話(02)。
![]() 7.フランス、フォンテンブローの森でチフチャフを見飽きた話(02)。
7.フランス、フォンテンブローの森でチフチャフを見飽きた話(02)。
![]() 8.ドーバー海峡を渡る小鳥たちを堪能した話(04)
8.ドーバー海峡を渡る小鳥たちを堪能した話(04)
![]() 9.バルセロナからエブロ河デルタに行って鴨を食べた話(長文、05夏)
9.バルセロナからエブロ河デルタに行って鴨を食べた話(長文、05夏)
![]() 10.韓国洛東江(ナクドンガン)でゴビズキンカモメを探した。
10.韓国洛東江(ナクドンガン)でゴビズキンカモメを探した。
![]() 11.山口県見島(国内です!)は雨だったが鳥見人は熱かったぜ(06春)。
11.山口県見島(国内です!)は雨だったが鳥見人は熱かったぜ(06春)。
![]() 12.ニュージーランドのアホウドリ類は荒海を越えて(長文、06秋)。
12.ニュージーランドのアホウドリ類は荒海を越えて(長文、06秋)。
![]() 13.フランス、フォンテンブローの森にまた行った話(07年春)
13.フランス、フォンテンブローの森にまた行った話(07年春)
![]() 14.苫小牧航路で、ハジロミズナギドリを見たという話(08年秋)
14.苫小牧航路で、ハジロミズナギドリを見たという話(08年秋)
![]() 15.GWの苫小牧-名古屋航路でウミオウムを見た話(09年春)
15.GWの苫小牧-名古屋航路でウミオウムを見た話(09年春)![]()
![]() 16.歯舞・色丹沖クルーズ(y社ツアー、07年夏)
16.歯舞・色丹沖クルーズ(y社ツアー、07年夏)
![]() 17.これが、モントレー、アメリカ西海岸の海鳥だあ!(10年)
17.これが、モントレー、アメリカ西海岸の海鳥だあ!(10年)
![]() 18.台湾の温泉地でカワビタキ鉛色水鶫を「賞鳥」した話
18.台湾の温泉地でカワビタキ鉛色水鶫を「賞鳥」した話
![]() 19.North of Hokkaido Island is Rubythroat's haven!
19.North of Hokkaido Island is Rubythroat's haven!
20.多良間島のGWは結構楽しめた。サンコウチョウが50羽以上。
21.沖縄県伊平屋島は渡り鳥の密度が高かった。
![]() 22.粟国島3月30-31日、セスジコヨシキリを見た話。
22.粟国島3月30-31日、セスジコヨシキリを見た話。
1.香港中心部の公園に行ったら意外と面白かった話(02)
香港観鳥会のhp(英語と広東語)とニフティ情報を参考にした。9月はヘラシギが期待できた。
香港に着いてホテルにチェックインしすぐ裏手の九龍公園(カオルーンパーク)に直行。当地の普通種を堪能した。カラムクドリが見られたのはラッキーか?。オニカッコウ、カオグロガビチョウ、サイホウチョウ、クビワムクドリ、コシジロキンパラなど18種類。
日没後、本屋に行って地図を買い、前述のhpと地名を1時間程照合すると、香港観鳥会HPにある野鳥スポットはどこでも行ける自信がついた。地名に見られる広東語は日本の漢字の発音に近いのも助かる。
宿は香港の中心地の安宿に取った。汚いながらも個室で泊3000円台。6000円台以上のちゃんとしたホテルが良ければ前もってHISなどに相談するとよいだろう。
為替レートはシティバンクのATMが良かった。少額ずつ日本の普通預金口座(charging
account:この単語を知らないと下ろせない)からおろした。
一般論として野鳥観察地に行くには、行きは的士(タクシー)で、帰りは「願呼的士」と書いて地元の人に頼むか、バス(巴士)を拾った。バスは香港鳥見で有効である。
幹線なら本数も多い。ミニバスと冷房バスと普通のバスがあり料金が違う。ミニバスは後払い。小銭はたくさん集めて乗るとよい。運転中に話しかけることは法律で禁止されており、着いたら教えてくれるよう頼むのは難しい。親切な運転手さんであることを期待。地図を見つめて目的地前でボタンを押して停めてもらう。ミニバスは狭い路地にバス停があることがあって位置がわからなくなることがある。
2.香港マイポでシギチの大群を見たけど、ヘラシギは居なかった話(02)。
マイポ(米埔)は野鳥観察の定番。許可証(パーミット)が必要でマイポのパンダショップで入手できるが、係が出払うことがあるので、予約をすると良い(英語可、852-2526-4415)。
潮汐による観察に適した時間は満潮時に基園(gei wai:マングローブの人工的浅瀬、エビを捕るために造られている)を歩きまくるのがよいと感じた。干潮時には広大な干潟に散ってしまう。青、赤、鶴、サルハマの順に多い。残念ながらヘラシギは居なかったが、シベリアオオハシシギ幼鳥、ソリハシセイタカシギ等をゲットした。
香港中心部から地下鉄1時間、バス30分、歩き30分で入り口まで行ける。以下は
マイポで見た鳥のリスト。2002年9月19日と21日、おおむね晴れ。数字と「多」は見た回数。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シロハラウミワシ 1
トビ 多 日本のとは別種説がある。あるいは2亜種?
ツミ? 1 鳴き声が日本のツミに似ていたが、ちょっと違う? ナンバンツミかも??
ミサゴ
ササゴイ
ゴイサギ
ダイサギ
コサギ
アマサギ
ムラサキサギ 1
アカガシラサギ 多 とても多い。
アオサギ 多
カノコバト 多
ベニバト 1
カワウ 1 香港でも増えているというが1回しか。
シロハラクイナ 中国名は「白腹苦悪鳥」??
カイツブリ
シマアジ
ハシビロガモ
マガモ
イソシギ
コアオアシシギ
アオアシシギ 多 大集団で急降下してすごい羽音がした。
アカアシシギ 多
ツルシギ 多
ダイシャクシギ
チュウシャクシギ
オグロシギ
オオソリハシシギ
シベリアオオハシシギ 1 幼鳥
ソリハシシギ
サルハマシギ
キリアイ
トウネン
タカブシギ
ウズラシギ
ジシギsp 2 中国南部で「田」と「中」と「針」がcommonだそうだが。
エリマキシギ
ソリハシセイタカシギ うつくしかあー!!20羽くらいいた。
セイタカシギ 多
コチドリ
シロチドリ
メダイチドリ
オオメダイチドリ
カワセミ
アオショウビン 1
ヤマショウビン 3
ヒメヤマセミ 1
ハクセキレイ 亜種ホオジロ
ツメナガセキレイ(キガシラの可能性もあり)
ツバメ 多
タカサゴモズ 多
コウラウン 多
シロガシラ 多 いろいろな鳴き方でまぎわらしい。頭に来る。
メジロ 多 日本のより腹が白い。
カオグロガビチョウ
シキチョウ
サメビタキ 2
メボソ(?)ムシクイ 雨覆の白線がなかった。すり切れ?
マミハウチワドリ
アオハウチワドリ 1
オナガサイホウチョウ
シジュウカラ
オニカッコウ 多
パプアバンケン 1 キジのような走り方をする。(和名はオオバンケン?)
クビワムクドリ ハトのように太い胴体
オオハッカ
カササギ
アミハラ 草の穂をしごいて食べていた。
スズメ
オウチュウ 1
3.香港タイポカウでエゾムシクイの分類を考えた(02)。
美しいジャングルによく整備された山道が巡らされている。4月〜7月の繁殖期が最適とされているが9月はどうだろう。小鳥の渡りを期待した。
タクシーに乗り「太埔墟自然護理区、事務所」と書いて渡すと15分ほどで入口に着いた。5分ほど登ると案内板があって本日の作戦が決まった。一番短いレッド30分から一番長いブラウン4時間まで4本のルートが詳細に書かれている。道標も完璧に整備されていた。
残念ながらこの季節は鳥は少ないうえに樹冠が高く、識別できない鳥もいたがゴジュウカラの一種などがでた。帰ろうかと思った午後3時頃、カワリサンコウチョウの雌と遭遇した。これを観察しているとチメドリの一種?とムシクイ等からなる小鳥の混群に遭遇した。頭の茶色っぽいムシクイが印象的だった。
道を降りていくと、望遠レンズをもったバーダーがいたので、早速情報交換した。ムシクイは金属的なTin!という地鳴きからエゾムシクイらしいという結論。
ただし、日本の野鳥590(平凡社)によるとエゾムシクイは従来P.tenellipesと表記されていたが、別種説が強いとして、この学名を新称:ウスリームシクイにあて、日本のエゾムシクイの学名にP.borealoides、英名Sakhalin
Leaf Warblerを当てている。私がタイポカウで見た個体はこの説ではウスリームシクイかな?(ごめんなさい。これ以上のことは???)。
下記の2文献では英名Pale-legged leaf warbler(P.tenellipes)は中国では標高1800m以上で繁殖している漂鳥で、虫の鳴くような細い声でさえずるとしている。日本のエゾムシクイとは多少違うようだ。
10月になるともっとワブラーが来るよ、との香港バーダーの話。ARCTICとか、EASTERNとかね。という話だったので、その2種(メボソ、センダイ)は日本にはたくさんいるのであると答えた。しかし意外と10月のタイポカウはムシクイ類の穴場かもしれない。分布からして他のムシクイも出そうだ。
帰りは幹線道路に出てバスを拾ったが、駅のバス停を通り越してしまった。隣の駅に運良く停まったので幸いだった。バスの種類(大きさ)によってバス停が違うことがあるようだ。
<リスト>
トビ
オオタカ 成鳥
ヒメアマツバメ
ツバメ
シキチョウ
オナガサイホウチョウ
カワリサンコウチョウ
エゾムシクイ(ウスリームシクイ?)
ヤブサメ
センダイムシクイ? これもかなり羽色がすり切れていた。
アカハシゴジュウカラ
シジュウカラ 思ったほど腹は黒くなかった。
コウラウン 林縁部に多い
シロガシラ 林縁部に多い
カノコバト
スズメ 民家近くに多い。
チメドリの1種??:白い頬、灰色の背、黒い肩と翼、長めの尾、スズメ大
参考文献1、A FIELD GUIDE TO THE BIRDS OF CHINA, OXFORD, 2000, および
2, A FIELD GUIDE TO THE SOUTH-EAST ASIA, NEW HOLLAND,2000
4.香港バードストリートでたくさんの飼い鳥を観察した話(02)
雨なので、バードガーデンに行った。太子駅から東へ10分ほど歩いたところにある。 「地球の歩き方」に載っているようにかつてのバードストリートが移転したものだ。移転前と比べるとはるかに小規模だというが150mはある。
飼い鳥が多数売られている他、自慢の鳥を見せびらかしに来る人も多い。 シキチョウ、メジロそして石燕というキアオジに似た鳥が多かった(この鳥は何?)。その他オレンジツグミ、コノハドリLeafbird(これは全身緑色で美しい)、キンパラ、コルリ、ノゴマ、オオルリ、インコ類など。目もくらむばかりだ。
英語の図鑑を見ていると人だかりがしてしまった。香港人がシキチョウを指さして、これはファイティングバードだから生きたバッタを食べないと死んでしまうのだという。確かにここには多量のバッタが網袋に入れて売られている。
ファイティングと言えばガビチョウはどうだというと、ワーメイ(英名と中国語名が同じ)もバッタをやらないと死ぬという。じゃあオウチュウは?、と聞くと、そんなやかましい鳥を飼ったら夜寝られないよ!、と言われた。
興味深かったのはメジロ。チョウセンメジロは居なかったが、頭頂が赤褐色のがいた。どこかの亜種か?。総じて日本のより小さく感じた。腹部の色は白から葡萄色までのバリエーションがあった。別種のハイバラメジロOriental White Eyeと思われる腹が黄色いのも少数いた。
飼い鳥の声に誘われて野鳥も来るが双眼鏡をしまっていたのでスズメ、コシジロキンパラ以外の識別はできなかった。
<その他のエピソード1>
尖沙咀のPCショップで野鳥CD(英語)を購入。世界の野鳥を1000種網羅という。CD
3枚組。本屋では「空中恐竜」なる妖しい絵本。アカゲラの模様をした始祖鳥もどきが空に向かって吠えている。想像もしてなかった世界だ。野鳥の写真図鑑を見ると、日本の写真図鑑の転用が多かった。
<その他のエピソード2>
マイポの帰りに落馬洲、ラクマーチュウの「眺望所」でワシを期待してビールを飲みながら深釧方面を見ていた。この辺りの自然環境は数年後には地下鉄の駅が出来て跡形も無くなる予定である。日本人のオバサン集団が来て、ガイドの香港人におバカな質問を次々と浴びせたので吹き出してしまったら、あの人日本語わかるのかしら?と指さされてしまった。
<詐欺師?>
九龍公園でマレーシア人と1時間ほど英語で会話した。最後に食事に行こうと言われたが、怪しいのでマレーシアのことを褒め称えて振り切った。気をつけた方がいい。
5.シンガポールからマレーシアにかけての記録(99)
【場 所】 シンガポールスンゲイブロウ自然公園・ククプ干潟・マラッカの丘
【年月日】 1999年9月下旬
【天 候】 晴れ曇り雨
【観察者】 籠島恵介
【環 境】 ジャングル・廃墟・市街地、田園地帯
【観察種/備考】:自転車で約400km走った。
リュウキュウヨシゴイ:飛行中のと人家の玄関に置物の様にたたずんでいた。
ダイサギ
コサギ
ササゴイ
アマサギ
カザノワシ:黒いの一言,マラッカ上空
シロハラウミワシ:ククプの養魚場
シロハラクイナ:水田に多い
ムナグロ:ククプ干潟
ソリハシシギ
イソシギ
アカアシシギ
ダイシャクシギ
コアオアシシギ
カノコバト
コアオバト:とてもきれい、
オニカッコウ:多い。雄と雌が違う。
ヒメアマツバメ
オオアナツバメ:マラッカの橋の下に巣を作っている。
ナンヨウショウビン:多い
アオショウビン:多い。ヤマショウビンを見なかったのはなぜ?
ブッポウソウ:マラッカ市街で
ムネアカゴシキドリ:郊外の高い木の上でさえずっていたこと数回
ツバメ:多い。胸が赤い。
リュウキュウツバメ:ツバメと並んで電線に停まっていることも。
メグロヒヨドリ:多い。開発で増えていく典型的な鳥だ。
チゴモズ:電信柱から落鳥した幼鳥を拾った。
アカモズ:1回見た。
アカガオサイホウチョウ:シンガポールのスンゲイブローにて
オナガサイホウチョウ:マラッカ市街にて。
シキチョウ:多い。
シベリアムクドリ:シンガポールで群をみた。
オオハッカ:どこでみたのか覚えてない。
ジャワハッカ:多い
カバイロハッカ:多い
ミドリカラスモドキ:多い。雄雌が全く違う色
コウライウグイス:多い
イエガラス:多い。
ハシブトガラス:ジャングルに多かったような
チャノドコバシタイヨウチョウ:マラッカの丘にて。
キゴシタイヨウチョウ:シンガポールにて。見たことのない赤色!クリムゾンレッド!
キバラタイヨウチョウ:バツゥバハの街路樹にて。
49種
6.フランスのロアール地方、ブレンネでイギリス人を見つけた話(03)
フランス中央低地ロアール県のブレンネ地方は、「1000の沼のある地方」と呼ばれている。旅行者にはあまり知られていないが、野鳥とイギリス人バーダーにはよく知られている。垣根・低木・森・野原・約600の湖沼があり、自然保護区は野鳥観察のブラインド(:hide)が用意されている。1日2時間ながらガイドもいる沼もある(行ったらいなかった)。
5月下旬、パリから車で4時間。約700円の高速料金で到着。まず、旅行案内所に突進するも12から15時までお休みなので手近な沼に突撃。イギリス人ツアー(数組)に遭遇。情報交換する。トビ(イギリスでは絶滅)を見たか、大きいねえと聞いてきた。ヒメノガンを見たかと聞くと、見るのはむずかしいとのこと、2年前に見た人がいるという場所を教えてくれた。イギリス人バーダーにもムシクイは全部ワブラーで片づける人がいたり、日がまだ高いの(とは言っても7時頃だが)にワインで談笑しているグループもいるのに変な意味でちょっとホッとしたりもした。翌日はヨーロッパハチクイを狙ってLa
Loche Posayに行ったが空振り。都合により一泊だけで高速道路に乗ってパリに戻った。
参考にしたhpはオランダ人の手による。もちろん英語でとても詳しい。地図はミシュラン238(1cm=2km)とインターネットで得たものを使用。
<宿>英語の通じる宿をインターネットで知ったが予約できなかった。民宿は多い。地元のツーリストインフォメーションを探して、そこで紹介予約してもらって行った。フランスのインフォは優れている。予約してもらう際に重要なのはまず予算を言うこと。私の泊まったのは乗馬クラブと書いてある旧貴族の館で、19世紀の鳥の博物画のコレクションには興奮した。3人で泊まって6000円程度だった(夕食無し)。フランスの民宿(シャンブルドート)は安い。
<注目すべき鳥>多かった鳥はコブハクチョウ(もちろん野生の)。クロハラアジサシとハシグロクロハラアジサシは多数繁殖している。これら2種はそもそも内陸性のアジサシである。残念ながらヨーロッパチュウヒは確実なのに会わなかった。イギリス人は見たと言っていたが。
ムシクイは白眉が薄い3種がよくわからない。メロディアスワブラーがいたとのことだが。それよりも日本でも記録のある白眉の3種、モリ、キタヤナギ、チフチャフ。モリムシクイはなるほど、特徴的な体型と行動をしている。羽ばたきながら枝先をスキャンして降りていく。まるで太りすぎでホバリングのへたなハチドリという感じ。これって日本のセンダイムシクイもときどきやる動作だ。ノスリは日本のとは色が違い、頭が混乱した。イワツバメ、ヒバリ、トビは日本の亜種と別種説がある。
<交通>
レンタカーで行くしかない。ミシュランの238番の地図を確認する。シャトーローで高速道路を降りて入っていく。英語ができるならイギリスの鳥見ツアー会社にインターネットで申し込んで連れていってもらうのもいいかもしれない。
<注意事項>
フランスの田舎はまず英語が通じない。日本人を見るのは初めてという人もいた。緯度が高いため太陽がいつまでも低く、逆光で鳥を見ることが多かった。道のどちら側で鳥に遭遇するチャンスが多いかは地図ではわからない。ツーリストインフォメーションでもらったパンフには、適した観察時間帯が推奨されている。確率的にこれにしたがった方がよさそうだ。また沼の状況、特に水位は年によっても変化する。最初にビジターセンターに行って情報を集めるとよいだろう。
フランスの6月は日の出は6時頃、日没は午後10時頃。サマータイムの1時間のずれに注意。秋冬の狩猟期はハンターとバーダーの仲は険悪だそうだ。誤射が怖い。
全日空便は夜20時パリ発なので最終日を有効に利用できてよい。エコノミー症候群は怖いので、水ボトルは1リットル用意して無理矢理飲んだら帰国翌日の体調がよかった。
<見た鳥>
カンムリカイツブリ、カワウ、コサギ、ゴイサギ、アオサギ、ムラサキサギ、コブハクチョウ、
マガモ、キンクロハジロ、ホシハジロ、トビ、ノスリ、チョウゲンボウ、コウライキジ、バン、
オオバン、ユリカモメ、クロハラアジサシ、ハシグロクロハラアジサシ、シラコバト、モリバト、
カッコウ、ヨーロッパアマツバメ、(ニシ)ヒバリ、ショウドウツバメ、ツバメ、(ニシ)イワツバメ、
ハクセキレイ、ミソサザイ、クロウタドリ、クロジョウビタキ、ノビタキ、ヨーロッパムシクイ、
スゲヨシキリ、ズグロムシクイ、ノドジロムシクイ、キタヤナギムシクイ、モリムシクイ、
コノドジロムシクイ、マダラヒタキ、シジュウカラ、アオガラ、エナガ、キバシリsp、
ノドグロホオジロ、ズアオアトリ、ゴシキヒワ、アオカワラヒワ、イエスズメ、ホシムクドリ、
ニシコウライウグイス、カササギ、ニシコクマルガラス、ミヤマガラス、ハシボソガラス
7.フランス、フォンテンブローの森でチフチャフを見飽きた話(02)。
フォンテンブローの森:
パリ周辺のブーローニュの森でも探鳥は楽しめるだろうが、少しパリから離れたほうが安心して鳥を見れるというものだ。パリのリオン駅から1時間ちょっと。森は極めて広く迷いやすいので歩くなら健脚向きだ。地図が駅の売店で入手できる。AVON駅に貸し自転車屋があってバルビゾンまでのサイクリングは観光の定番。自転車で散策するのもいいだろう。大木も多く、部分的な伐採もされ樹木の多様性が保たれているが樹木が高すぎて観察を逃すこともあるかも。
AVON駅近くにETAPというチェーン店ホテルがあって朝食付2500円程度。誠実でないスタッフもいるが安くて快適。
駅の裏から森に入っていく道沿いにチフチャフが多かった。4月〜7月にかけて見たが7月下旬にはほとんど見かけなかったことがある。1割くらいキタヤナギムシクイが混じる。両種の識別は慣れると簡単だ。体型、声、行動が違う。チフチャフのさえずりはチンチャッチャという金属的な感じがした。英語耳に切り替えて聞くとチフチャフと聞こえる。尾を振る動きは独特のものがある。
ハイタカがヨーロッパアマツバメの集団に突っ込んでいくのも何度か見たことがある。
宿泊したアパート5階から見たキバシリは近縁種があり識別に注意が必要でちょっと自信がない。クマゲラは声だけ聞いた。マミジロキクイタダキ、コアカゲラ、セリン、カンムリガラなどをみた年もある。なお歴史好きにはフォンテンブロー宮殿はベルサイユ宮殿より面白いかも。2002年6月の数日間の記録を下に記載します。
<フォンテンブローの森、セーヌ川、ムランにかけて>
コブハクチョウ:セーヌ川
マガモ
ハイタカ:日本のよりものどが赤い。
モリバト:たくさんいる。ヒメのほうを見たいのだが。
コアカゲラ
カオジロアカゲラ
クマゲラ??:市街地で声を聞くとは思わなかった。たぶんそう。
ヨーロッパコマドリ
クロウタドリ:あまりにもたくさんいるので日本では見たくなくなった。
クロジョウビタキ:写真で見たモンゴルの亜種とはだいぶ感じが違う。
チフチャフ:いっぱいいた。
キタヤナギムシクイ:少しいる。
マミジロキクイタダキ:初めてキクイタダキをみた子供のころの感動がよみがえった。
ハシブトガラ
シジュウカラ:巣箱あり
アオガラ:巣箱あり
ゴジュウカラ
アオカワラヒワ
ズアオアトリ:年齢差、性差が大きいのはアトリと同じか
ゴシキヒワ
イエスズメ
ホシムクドリ
カササギ
ハシボソガラス
8.ドーバー海峡を渡る小鳥たちを堪能した話(04)。
2004年4月27日カレー(Pas de Calais)周辺。
前もってインターネットで英語探鳥レポートを検索したらいくつかあった。イギリスの探鳥ツアー会社のホームページも役に立った。海鳥を見るにしてもドーバー海峡(フランス語ではパドカレ)をフェリーで渡るよりレンタカーで岬巡りをした方がよさそうという結論で、パリ北駅からTGVでカレーまで1.5時間で行き宿泊。翌朝レンタカーでブーローニュ・スル・メールまで南下することにした。ここは一通りヨーロッパのカモメが見られる?
La Porteというよい場所があるそうだ。結果的には30km走ったところのグリネ岬まで行って時間切れになったのだが。 1日しか探鳥日を取れなかったのが残念。実は新婚旅行だったのである。
<砂丘>
カレー駅(市内の方)に事務所があり9時に営業開始というエイビスの話であったが、実際はなく、エイビスに乗りたければ駅員に呼び出してもらえというフランス語のポスターがあったのみ。
駅の窓口に30分並んでエイビスの事務所につないでもらう。すぐにエイビスの迎えが来た。レンタカーでスタートしたのはすでに10時を回っていた。
カレーのフェリーポートで軽くカモメ類をスキャンした後はD940を西へ向かった。港にはヨーロッパ産セグロカモメ、オオカモメ、幼鳥のキアシセグロカモメ?(よくわからない)がいた。西に砂丘が広がっていて、防砂林と海浜植物の中ではウタツグミ、ハシグロヒタキ、チフチャフなどがいた。メロディアスワブラーも多いと情報にはあったが、わからなかった。
<岬巡り>
グリ・ネ岬(灰色の鼻の岬)はドーバー海峡をフェリーで渡るよりも海鳥が見られると言われている。カレーから車で1時間半で着く。絶壁の上のカフェからでも小鳥や海鳥が楽しめる。
小鳥たちは海峡を渡ろうとして強風に押し戻され、岬の個体数の密度が高まっていく。
ベニヒワが多かったので、コベニヒワを探したが、この地でも珍鳥のようだ。ムネアカヒワや、黄金色のツメナガセキレイ英国亜種などを堪能した。
タヒバリ類の緑色が強い個体を見て、これはマキバタヒバリだと思った。海峡をひっきりなしにアジサシが通過して行く。この中にキョクアジサシが混じっていることは間違いないだろうが、遠すぎて確かめるすべはない。シロカツオドリの巨大さにもおどろいたが、アホウドリ類、ミズナギドリ類は見られなかった。パワーのある望遠鏡をもって行くべきだったか、あるいはもっと気合いが必要か。観光地としてはすこしカレー寄りのブラン・ネ岬(白い鼻の岬)の方が美しい。
<レンタカーとTGV>
TGVはパリの北駅から出る。北駅とその周辺の地下鉄は犯罪が多い。ソフトクリミナル
の博物館だ。ニセ警官がパスポートや財布を見せろと言ってきたりする。Calais-Frethunまでは1時間ほどだ。そこからバスで、港町まで行くといくつかホテルがある。
日本のエイビス(フランス語でアビス)で予約。日本と大きく違うのは3点。マニュアル車しかなかったこと、バックギアの入れ方が違うこと、ガソリンスタンドでの給油をフランス語でこなすことであり、これらは事前にガイドブック等で学習することができる。
とまどったのは、車の返し方で、所定の場所に車を停めて無人の事務所のポストにキーを投函するというものだ。こんないい加減なやりかたでよいのかと思った。
カレーではイギリス人がよくレンタカーを借りるので、レンタカー屋さんは英語がうまかった。
借りる(check out)事務所と返す(check in)事務所を違うところにしたので、返す場所がわからなくてとても困った。
<英語>
フランスとしては英語がかなり通じる方であるけど、 ホテルのバーでビールを注文したら、アンヌックしかないと言われた。出てきたのはハイネッケンだった。
<ホテルの予約>Hotel Metropol
インターネットで知った電話番号に国際電話。たどたどしいフランス語で話しかけたが
、英語とスペイン語のどちらにしますか?と言われて、ばればれ。英語で予約した。
直接ホテルが予約を受けずにホテルと契約した電話サービスが取り持つことがあるようだ。
<リスト>
シロカツオドリ、ウミウ、アオサギ、ホンケワタガモ、チョウゲンボウ、シギsp、セグロカモメ、オオカモメ、アジサシ、モリバト、(ニシ)ヒバリ、ツバメ、マキバタヒバリ、タヒバリ、ミソサザイ、ウタツグミ、クロツグミ、ハシグロヒタキ、チフチャフ、ノドジロムシクイ、ワタリガラス、ハシボソガラス、ニシコクマルガラス、ムネアカヒワ、ベニヒワ、ツメナガセキレイ、イエスズメ、ホシムクドリ
<所感>
チフチャフ:モズのように尾を動かす。これはキタヤナギムシクイとの識別点である。
ハシグロヒタキ:一回砂丘で見た。
マキバタヒバリ:タヒバリとの識別はむずかしい。100%の自信はない。
クロジョウビタキ:どこでみたか忘れた。シロビタイの方を見たいのだが。
ワタリガラス:カレーでは珍しいかも。
ズアオアトリ:いろいろな声でなく。年齢差による形態がいろいろ。
ツメナガセキレイ:Brithish亜種で黄色みが強くとてもきれいだった。
クロウタドリ:多いので見飽きた。
ニシコクマルガラス:これも見飽きた。
オオカモメ:ごつい。セグロカモメより2回り大きい。幼鳥は肩羽のイカリ模様が太く、全体的に黒っぽい模様となる。
キアシセグロカモメ?:成鳥はいなかった。幼鳥はそれらしいのがいたが擦り切れていてよく分からない。
9.バルセロナからエブロ河デルタに行って鴨を食べた話(長文)
<スペインの探鳥は魅力的>
私はフランスに4回探鳥旅行して、ある程度、フランス中央部の鳥のイメージがつかめてきた。
しかしスペインはピレネー山脈に環境が隔離され、地中海の固有種もあるため、フランスとは違う探鳥が楽しめるのである。
今回はバルセロナとエブロ河河口を基点に適当に歩き回ることにした。内陸部のヒバリ類を見て回ったり、ピレネー山脈をドライブして山岳の固有種を見たり、という選択肢もあるだろう。
エブロ河河口(デルタエブロ)の8月下旬はベストシーズンではない。仕事の都合でこうなった。
むしろワーストシーズンと言っていい。しかし今回55種の鳥を見て、15種のライファーを出したことはまあまあ成功といってよいと思う。
ここで書くことは防犯と鳥の話に偏るが、この国の歴史、芸術、伝統などについても、
リオハのワイン、パエリア料理、映画エルシド、ヘミングウェーの小説、芸術家ダリなど、私の血を騒がせたものは多い。鳥だけを見るために行くにはもったいないとも言えるだろう。
<言語>
英語はホテル以外通じない。バルセロナを含むカタルーニャ地方はカタラン語でスペイン語とは少し違う。例えば1時20分といえば、1時20分前を意味する。おはようは、ブエノスディアスと言わずにポルトガル語のようにボンジア!という(正確にはポ語はボンディア)。
ロードサインもカタラン語で書かれているものがあってスペイン語に精通した人も戸惑うかも。
<イージージェット>
今回私用によりフランスに立ち寄り、パリーバルセロナ間はエコノミー航空の雄、easyjet.comを使用。
座席指定はない。アテンダントはTシャツ。予約方法はインターネットのみ。遅れても待ちませんと強調
してあり15分前にチェックインしなければ空席待ちの人にバンバン回していく。
<個人旅行>
旅行計画を立てるということほど楽しいものはない。
今回利用した情報もイギリスのヤフー検索とsurfbirds.comから検索した英語の紀行文が重要な情報源であった。
surfbirds.comは世界各地の探鳥レポートを募集していて、かなりの確率で行きたい場所の紀行文を得ることができる。ぼくも投稿しようかな。10年前には考えられなかった時代になっている。
<スペインの犯罪事情>
スペインは誘拐・殺人は比較的少ない。例えばブラジルなどよりもはるかに安全だ。何をやっても死ぬことはないであろう。責任は持てませんが。
都市部においてはソフトクリミナルは極めて多いため情報を集めて対処することが肝心である。
金持ちの旅行者と見抜かれないようにするのが基本だ。スペイン人は帽子を被らない人が多いので被らない方がよい。
お金や光学機材だけでなくパスポートは犯罪者にとって垂涎の的である。
情報を集めているうちに分かったのは、各民族ごとに犯罪の傾向が違うということだ。そしてそれぞれに対策がある。
<バルセロナ観光船>
コロンブスの塔のあたりから港内一周の観光船が出ている。カモメ好きにはたまらない。市内にも関わらず
引ったくりを気にせずカメラを振り回せるし、キアシセグロカモメmichahellisの幼鳥と成鳥がそろっていた。
桟橋から観光客に餌をねだる卑しいやつはユリカモメだが、湾内にはニシズグロカモメも多い。
バルセロナのキアシセグロカモメはよくドバトを食べているという話だ。
<モンジュイック地区>
妻の希望でミロ美術館に行った。ピカソは年齢を経て芸風が変化していくが、ミロは若いときから一貫して「変」である。妻は大喜びだった。私は、どちらかというと美術館の前でみたハシナガムシクイの方がうれしかった。この地区は樹木が多く、探鳥には良いのだが、この付近は貧しい移民が茂みの中に多数占拠しているので意外と危ない地域だ。西アフリカ系は体が大きく力もあるからやっかいだ。
歩かずにバスで軍事博物館に移動。この岡の頂上はシロハラアマツバメが多い。何気なくイベリア半島固有種だ。
<エブロ川への出発>
カタルーニャ広場近くのeasycar.comを探すが、これはなくpepecar.comというのがあったので聞いてみると
ここだと言われた。イギリスの会社がスペインの会社に丸投げしているらしい。
バルセロナ市内を抜ける。英語でROUND-ABOUT、フランス語でロンポンと呼ばれる丸い交差点は
すぐ慣れて好感を持てた。この「丸い交差点」というやつは信号機が要らなくなり、渋滞も事故も減るというので
フランスなどでは信号機が減ってきている。日本でも導入すればよいのだ。
ただ、五叉路などで信号機と組合わせてあると怖い。都市部にはあるので注意だ。
北上する高速道路A-2と7ルートは一見遠回りのようだが道がまっすぐだから時間が早い。
聖地モンセラットの素晴らしい山々、妙義山のようだ、を見ながら120kmで走行。サービスエリアは40kmおきにある。
泥棒が金目のものを持つ旅行者を物色する場所でもあるのでカメラなどは見せない方がいい。アラブ系のグループが携帯電話で連絡を取りあっている。
高速道路で走行中、「おまえの車から煙が出ているぞ!」と大声で指摘して止めさせて、
強盗を働くのだ。助けを呼べないように車のキーを強奪することはいうまでもない。
深夜のドライブインで襲われることもある。アラブ系は情報力、連係プレーが得意だ。
<デルタエブロ>
高速道路2時間半走行後、デルタエブロの出口40番で降りて、N340を4km西へ行き、運河沿いに下流に向かった。まずは
観光案内所(インフォルマシオン)が目的地だ。スーパーマーケット「シャンピオン」の近くにある。
うまいレストランとアカハシカモメのポイントを聞くためだ。ただでいろいろな地図をくれた。
このカモメを見に来るバーダーは多い。はっきり言って右岸の塩田がポイント。この種の70%はここで繁殖する。
ノガンはなんとかという場所で見られるが遠いという。左岸のハイドのある場所に近い場所にはニシツバメチドリ
がいる。ハシボソカモメはそこら中にいる。地図上のハイドのマークのあるところはみなおすすめだ。チュウヒは冬がいい。
とまあこれくらいだろうか。スペイン語なまりの英語で聞き取りにくかった。
Where the birds are in Northeast Spain,という本を買った。この本は、鳥ごとにどこにいくと見られる可能性が高いかを簡潔に記述してある。
鳥の識別や説明はほとんど書いていない。スペイン以外から来た人がスペイン東北部で効率よく珍鳥を稼いでいくことために特化してある凄い本だ。うれしいことに英語だ。(Where
birds are in North West Spain, Steve West,Arts Grafiques Dalmau,)
ヒメチョウゲンボウ、ヒメノガン、ヒメコウテンシなど「姫」狙いのバーダーにもお勧めだ。
コシギ、コバシチドリ、コヒバリなど「コ」、あるいは「ヒゲ」情報もある。amazonでも手に入るかな?そのうちコシギなど見に行きたいものだ。
<左岸Riumar近くの灯台>
とりあえず、トルトサの宿で昼寝をして、観光船に乗ろうとriumarの町をめざした。川rioと海marをくっつけた分かりやすいこの町名。
分岐点を右に行き、船着場についたが、最終便は出てしまっていた。がっかりして川を見ているとヨーロッパチュウヒ
とカンムリゴイがとんだ。
次に灯台近くのハイドを目指した。夕暮れの草原は、絵の様に美しく、空にはクロハラアジサシ、ハシグロクロハラアジサシ、ヨーロッパアマツバメがどんどん通り過ぎていく。干潟にはムラサキサギ、オオフラミンゴ、ハシボソカモメ、オグロシギ、など。
鳥を見るのに支障がない程度で蚊は追い払われるという最適の風が吹いていた。1週間前に来た人はぼこぼこになったそうだ。
欧州では珍しい水田にはダイサギがいた。欧州では比較的珍しい種だがエブロでは増えているそうだ。河川の富栄養化のためだろう。
<トルトサのお城>
エブロから40分ほど北上してトルトサのお城に泊った。かつてのアラゴン王国の居城の一つだ。
王様は定期的に領内の城を渡り歩いて暮らしたということだが、それでは参勤交代の逆ではないか!
城は巨大で素泊まり1万円程度。レストランあり。広大な城壁を見てスペインの壁と言えばカベバシリ!っと、ずいぶん探したが、いなかった。もっと標高が高くないとだめのようだ。代わりにヨーロッパハチクイをゲットした。
この鳥の飛び方はシャープな機動というか、かっこいい。
<エブロ2日目>
朝、城の周りをめぐるとミサゴのようなタカが飛んだ。ボネリ?ミサゴ?わからなかった。朝焼けの山々がきりきりと美しい。
イソヒヨドリ、アオカワラヒワ、ムジホシムクドリ。早朝のパン屋ではスペイン語で「ウノ、パン、ポルファボール(パン一つください)」。それくらいしか言えない私。
デルタエブロ町に戻り、渡し舟に車を載せエブロ河を渡河した。前後に運転席がある平べったい長方形の渡し船だ。 かつての第2次ポエニ戦争はハンニバルがこの大河を渡ることで始まった。その壮大な歴史と違ってあまりにものどかな風景だ。
<沼のハイド>
あのカモメひらひらしている、妻の指摘で空を見上げると、オニアジサシだった。おお、でかしたぞ妻!。
ムシクイ?が葦に止まって、風に上下している。白眉がはっきりしていて嘴が太い。灰白色の背部と白い脇、ゴマのないするっとした外見。想定外の鳥。Booted
Warbler,ヒメウタイムシクイと思ったが違うようだ。写真はあるけど不明種。
ハシブトアジサシとか、アジサシとかも飛んでいる。カモはマガモとアカハシハジロ。ほかにもいるかもしれないけれど熱心には見なかった。砂洲に入り、硬くしまった砂浜を8km行って車を止めた。
ここから先の塩田が珍鳥アカハシカモメの繁殖地だ。英語とスペイン語で注意事項が書いてある。
早速数十羽の群れがいた。反対側の砂浜を見るとすっぽんぽん男性ヌーディストが数名、肌を焼いていた。望遠レンズを持った私は肩身がせまい。無視して前進。抗議されたら自分も脱ぐか?。
ものすごい羽音がして50羽くらいのドバトが通り過ぎた。たぶんこれが野生のカワラバトなのだろう。
<ヒバリ類>
ヒバリ類ではヒメコウテンシを見た。
エブロでも場所を選べばコヒバリCalandrellarefescens、ヒメコウテンシ、クロエリコウテンシ、ニシヒバリがいると思われる。(注:ニシヒバリAlauda
arvensisは、ヒバリをA.arbensisとA.japonicaの2種類に分けるという説をとった。
日本でも記録のあるコヒバリは学名C. cheleensis、英名はAsian Short-toed Larkとされることが増えてきた。
その場合はコヒバリとは別種となる。)
その外、スペインにはテクラヒバリ、デュポンヒバリ、モリヒバリなんかもいて、スペインはヒバリ天国という話もあった(surfbirds.comにあった北欧人の探鳥記録)。
<スペインのパエリア事情>
パエリアはスペイン各地で全く違うものがあり、個性的である。ウサギの肉が入ってないのはパエリアではないね、とまでいう人もいる。エブロ名物は魚醤をつかった鴨肉のパエリアだ。これは旨かった!。
この鴨肉はこの地域に多いアカハシハジロかもしれない。ここでは鳥打猟師の組合ががんばっていて流域の開発を阻止している。フランスではバーダーとハンターは深刻に反目しているが、スペインではそうでもないようだ。
<バルセロナへの帰還>
高速道路を経てバルセロナ市内にレンタカーを飛ばした。高速道路は120kmで流れていて、分岐点を正しく選んでバルセロナに車を導くのは難しい。現地を知っているナビがいなければ時間に余裕を十分持たせるべきだろう。
間違った出口を出たときでもあわてないことだ。
レンタカーを返して出口を出るときに、そこに犯罪者が潜んでいる可能性があると思った。大きな荷物を持って暗い人通りの少ない路地に出るからだ。
先頭に僕がであると暗がりに怪しい男が3人いた。手ぶらの妹が離れて警戒。男の一人が私を追い越そうとした。
挟み撃ちにするつもり?「かなり危ないかも!」と妹が日本語で叫んだ。私は妻を車道に押し出した。
私は左手を胸ポケットに入れて(武器を持っているふり)威嚇した。男は小さく手を振り行ってしまった。
用心に越したことはない。人ごみに入ったときには長いスカートをはいた東欧人のすりに注意する。
子供や赤ん坊を楯にしてすりを働くのもいるらしい。
いろいろ書いたがくれぐれも人種的偏見を持たないようにお願いしたい。それぞれの民族や国家に良い人と悪い人がいるのは当たり前の話なのだから。これはあくまでも2005年時点での情報でもある。
<ワイン等>
エブロ河上流を産地とするリオハのワインは素晴らしい。ブルゴーニュの高級ワインか?と思わせるものがある。
それに対して黒ワインと呼ばれる濃厚なのは日本人にはタンニンがきつい。下痢するかも。現地の生ハムによく合うが。
バルセロナにはセネガル料理店がある。クスクスは美味しくて栄養バランスもよい。多くの黒人スポーツ選手を輩出する地域の食べ物だけはある??。
<鳥のリスト>
アオサギ、コサギ、ダイサギ、アマサギ、ムラサキサギ、カンムリサギ、ゴイサギ、オオフラミンゴ、マガモ、アカハシハジロ、ノスリ、ワシタカsp、ヨーロッパチュウヒ、チョウゲンボウ、オオバン、セイタカシギ、シロチドリ、ミユビシギ、アオアシシギ、アカアシシギ、イソシギ、オグロシギ、チュウシャクシギ、キアシセグロカモメ、ニシズグロカモメ、ユリカモメ、ハシボソカモメ、アカハシカモメ、ハシブトアジサシ、アジサシ、クロハラアジサシ、ハシグロクロハラアジサシ、オニアジサシ、サンドイッチアジサシ、シラコバト、モリバト、ヨーロッパアマツバメ、シロハラアマツバメ、カワラバト、カワセミ、ヤツガシラ、ヒメコウテンシ、ヨーロッパハチクイ、ツバメ、イワツバメ(ニシイワツバメ)、イソヒヨドリ、クロウタドリ、ムナフヒタキ、ハシナガムシクイ、シジュウカラ、ハシボソガラス、ムジホシムクドリ、イエスズメ、カササギ、アオカワラヒワ
番外:ドバト、オキナインコ(バルセロナにて)
<おおまかな一人分、1週間のお値段>
仕事の都合で8月中旬というハイシーズンとなってしまい、高くついた。ぐー。
19万円:福岡ー成田ーパリ間、全日空
5万円:パリーバルセロナ、イージージェット
10万円:宿泊費、食費(お土産代含まず)
10.韓国ナクドンガン探鳥記(04’)
ゴビズキンカモメは韓国釜山に近い洛東江(ナクドンガン)ではかつては毎年の記録があったらしいが、最近河口
堰ができてその数が激減したという。しかしいないこともないという情報(http://www.birdskorea.org/birds_latest.asp)
を得た。福岡から4時間でいける場所なのでちょっと1泊で行ってみることにした。
乙淑島(ウルスクド)の野鳥観察公園がナクドンガンでは地元によく知られている。
<交通>
博多港から高速船に乗り約3時間で釜山。往復2.4万円。ビザ不要。港から地下鉄まで歩いて10分。
地下鉄中央洞駅(チュアンドン)から下端駅(ハダン)まで30分。そこからタクシーで洛東江(ナクドンガン)のウルス
クドまで5分(300円)。ただし朝は渋滞するので歩いた方がまだ早い。徒歩でも40分程度。
ハングル文字を覚えたので駅や港で戸惑うことはなかった。ハングル文字は簡単で40分で覚えられる。
タクシーは便利で安いが、白タクにつかまらないように「模範タクシー」を選ぶと無難だ。
<環境と観察種>
河畔林と草原、工事現場、干潟、池などから成る。河口堰のすぐ上流側はカモメ類が水浴びをするポイントとなっている。
公園管理人が鳥の説明をしてくれた(韓国語!)。「野鳥公園」を作っていてカモ類、カワウ、小鳥類が多い。
<旅行記>
8時45分の高速船ビートルに乗り、海上の鳥を観察。カツオドリ、カモメ類3種、オオミズナギドリ、カンムリカイツブリ、
ウミウが見られた。時速60km?くらいの猛スピードなので鳥見は難しい。幸いに福岡とそれほど変わらない寒さだ。
降りたらまず、換金して、食堂(シクタン)に入りチゲを食って、地下鉄駅へ。
30分でハダン駅に到着し、タクシーに乗ってウルスクドというが通じない。この地名は発音が日本人には難しい。
ハングル文字を書いて理解してもらった。観光案内所でもらった地図から書き写したものだ。
カモメ類の群れが河口堰の上流に集結して水浴びをしている。200羽以上いるが、ゴビはいなかった。
下流方向に歩くと事務所があり、鳥の写真が多数飾ってある。説明する人が話しかけてくるが全然わからない。
とりあえず、韓国語で、「私は日本人です。鳥とカモメが好きです」と答えた。「イゴヌン、イッスムニカ?」(これはいます
か?)と図鑑を出して情報収集をした。ゴビズキンはいないという。がっかりしたが、ダルマエナガはいるという。
そのほかにもいろいろ見られそうだ。
下流沿いの道を1時間ほど歩いて石油施設?の門があった。トラブルになることを恐れて入らなかった。この施設の先
にもポイントがあると先ほどの人が言っていたようだがどうなのだろう・・・・。
帰り途中、草むらではネズミのようなものが多数チーチー鳴いて暴れていた。ダルマエナガの群れだった。
西側にはヨシ原と小さな川と工事現場と池が織りなす広大な環境が広がっている。次の日に行くこととして帰った。
名物のふぐ鍋(ポグックク)を食べた。トラフグが1匹入っていて辛くなくておいしかった(500円)。ケチャップを
つけて食べることを薦められたのは驚いた。
ハダンは大きな町で旅館(ヨグァン)やホテルがかなりある。日本語が通じるホテルサファイアが無難だが、
素泊まり8千円は高い。片言ハングルで川のほとりのヨグァンを狙うのも手だろう。イッパンチュセヨ(一泊お願いします)。
翌日は、ホテルを出て、途中のコンビニで食料を買い、ウルスクドまで40分歩いた。渋滞が凄い。西側の池を中心に見て回った。
ウグイスが地鳴きしている。別種説がある亜種チョウセンウグイスかもしれないがよくわからなかった。
可動堰のすぐ上流で再びカモメ類を見た。セグロカモメが多く、オオセグロカモメは少数の幼鳥がいた。その中に、亜種mongolicusらしき個体が1羽いた。体型とゴマの少なさからの推定だが、第3回もしくは第4回冬羽で、嘴の先端が黒い。断定は困難。前述のサイトでニール・モーズ氏は、ナクドンガンにmongolicusは2−10羽いると書いている。
撤退の時間となった。ゴビズキンは現れなかった。砂地の干潟が好きだという。今回歩いた場所には砂地干潟はない。
まだ情報不足だ・・・・。可動堰脇の橋を渡ると、大きな魚の群れが行く手を阻まれてうごめいているのが見えた。
長良川でも見られる大いなる水産資源と税金の無駄遣いだ。
帰りはチャガルチ市場でキムチとマッコリ酒(安くて旨い、お勧め)を買った。ターミナルの土産物屋は高い。
私はプサンのこの雰囲気がとても好きだ。漁協事務所というのが地図にあったので行ってみた。カモメ類の群を期待したが、単なる事務所だった。チャガルチ辺りにはカモメ類が集結している場所はないのかもしれない。
釜山港の午後の出国手続きはとても混んでいる。博多港に帰る人は大阪行きの乗客の群れに巻きまれないように早めに並んだ方がいい。相変わらず高速船からの鳥見は至難で、シギ類が飛んでいたが種類はわからなかった。
真っ赤な夕焼けの中、博多港に入港した。次に韓国上陸するときは、昌原の注南貯水池のクロハゲワシを見に行こうと思う。
<リスト>
カツオドリ、ウミウ、オオミズナギドリ、カワウ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、オオバン、コサギ、アオサギ、チュウサギ、
ダイサギ、オオハクチョウ、マガモ、コガモ、カルガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、ホシハジロ、ホオジロガモ、
キンクロハジロ、ミコアイサ、トビ、チョウゲンボウ(亜種?)、ハマシギ、イソシギ、アオアシシギ、セグロカモメ、
オオセグロカモメ(幼のみ)、カモメ、ユリカモメ、ウミネコ、キジバト、ハクセキレイ、タヒバリ、モズ、ダルマエナガ、
ウグイス(亜種?)、ジョウビタキ、ミヤマホオジロ、スズメ、カササギ、カラスsp
11.山口県見島は雨だったが、鳥見人は熱かったぜ(06’)
サイトのタイトルに「海外」とあるのに国内のことを書いてしまいます。山口県萩から1時間半ほど船で渡る見島。
「おにようず」号は比較的揺れず欠航もけっこう少ない。船体が細いせいなのだろうか。
見島には民宿もたくさんある(テント泊の人もいた)。おすすめの離島である。日本海にある離島であり渡り時期が充実している。基本的にレンタカーはないが、どこからか調達する人も?。島にはコンビニは無いが、宿でおにぎりを作ってもらった。
岡山から新山口まで新幹線で2時間弱、バスで萩まで1時間。前泊。タクシーかバスで船着き場まで10分。
鳥屋は船着き場の駐車場まで車で来る人が多い。私は8時20分発の「おにようず」に乗る。船のスケジュールは季節的に変更される!。
まず本村の船着き場対岸を見て回った。ここでシマゴマが出たことがあるからだ。クロサギ1羽。
本村から宇津の民宿、北国屋までゆっくり歩いて2時間だ。
本村近くの八町八反の田圃と北の岬が私のお気に入りなので重点的に歩く。
いきなり英語でオオメダイチドリがいるよ、と言われたが見たところ・・・・メダイチドリのような気がした。よくわからない
としておこう。私は微妙な足の色の差とか初列突出とかはわからない。有明海で、見飽きてしまいカニを食べるのはオオメダイという識別法をしていた。足と嘴が短いのでたぶんメダイと思う。
この島のGW中は一日で、ムシクイ3種の地鳴きによる識別ができるようになるだろう。センダイはフィフィフィ、メボソはジッジッジッ、エゾはチンチンチン(センダイのを金属的にしたtin)。今回はセンダイが圧倒的に多い。
成せばなるかな?ムシクイ識別・・・・。小さい、褐色そして眉がカラフトムジセッカではないから・・・ムジセッカ。
あの鳴き声は・・・・キマユムシクイ!口笛で寄ってくる。
島の中を車で探索するグループ、徒歩組、バイク組などがあちこちに見られた。連休前半は晴れすぎて
いまいちだったと贅沢なことを言っている人もいたそうだが、連休後半の雨の中を歩き回りながら今晴れたら大当たりと思っている人もいた。雨の中をとぼとぼ歩いていると、マミジロキビタキがでた。
翌日は、曇りで、カラアカハラのポイントに直行。さえずりに導かれてエンカウンター!カラスバトも飛んだ。しばらく見ていると福岡組が来て、さっきミゾゴイがでたという。その場所に行ってみるがいなかった。調子が上向きになってきたところで時間切れ。
大峠を越えて八町八反を覗いて本村からおにようずに乗った。船は横波を受けながら宇津港へ。宇津で粘った人はイナダヨシキリを見た人もいた。船からはアジサシ類が1羽飛んだほかはオオミズナギドリ多数。
服装:
一般バーダーは白っぽいベージュ色の「ポケットたくさんのチョッキ」を着ている人が多いが、私はやはり黒っぽい服装をおすすめする。野鳥観察には黒っぽい服の方が経験上よいように思える。有明海の干潟で実験したことがあるが、ハマシギの群れで5〜10mくらい接近できる距離が違った。目のよいワシタカにも黒っぽいのは有効だという人もいる。
今回私は迷彩服を着用したが、身体が大きいこともあり、鳥はともかく人間には威圧感を与えているような気がする。
福岡の若い人で旧西ドイツ軍のコートを着ている人がいたが、それほど威圧感を与えないようなデザインとなってよかった。
ジャックウルフスキンというメーカー製の紺色のチョッキは比較的安価で高品質だ。背中がメッシュでザックで蒸れないし
生地が軽い。個人的には肩章が丈夫なボタン留めだともっとよいが(肩からカメラ等をぶら下げるため)。
今回雨が降っている中を歩き回ったが、こういうときには新素材の下着が乾きやすくて快適だ。
ゴアテックス製の雨具はやはりよいが、私の自転車用のものは歩くと音がしやすいので鳥見には生地の柔らかいものがよい。
見た鳥
アマサギ、アオサギ、コサギ、チュウサギ、ダイサギ、クロサギ、ウミウ、オオミズナギドリ、マガモ、カルガモ、
オナガガモ、トビ、ハチクマ、ハイタカ、ミサゴ、チョウゲンボウ、メダイチドリ、トウネン、アオアシシギ、サルハマシギ、
ムナグロ、オグロシギ、タカブシギ、イソシギ、チュウシャクシギ、ウミネコ、キジバト、カラスバト、ホトトギス、アマツバメ、
ツバメ、ショウドウツバメ、コシアカツバメ、ツメナガセキレイ(3亜種)、キセキレイ、ハクセキレイ、タヒバリ、
マミジロタヒバリ、アカモズ(シマアカモズ)、カラアカハラ、ウグイス、セッカ、コヨシキリ、オオヨシキリ、ムジセッカ、
キマユムシクイ、メボソムシクイ、センダイムシクイ、エゾムシクイ、キビタキ、マミジロキビタキ、オオルリ、サメビタキ、
コサメビタキ、エゾビタキ、ツリスガラ、メジロ、アオジ、ホオジロ、カワラヒワ、シメ、スズメ、コムクドリ、ハシブトガラス、
ハシボソガラス・・・・65種
見れなかった鳥(GW中の耳情報):
ヤマショウビン、ミゾゴイ、ブッポウソウ、イナダヨシキリ、サンコウチョウ・・・・。
怪しい情報はこの1.5倍ほどかな・・・・。
参考HP:
見島で鳥見:http://www.eonet.ne.jp/~occhan/
12.ニュージーランドのアホウドリ類は荒海を越えて(06年秋)
<プロローグ>
アホウドリ類を見るなら、ニュージーランドのカイコウラだ!。世界一の海鳥のスポット!という賞賛の言葉を何度か海外野鳥雑誌でみたことがあった。カイコウラはいつかは行こうと思っていた場所である。海鳥ウオッチングボートを経営する会社のHPはここである。http://www.oceanwings.co.nz/albatross/ocean_wings/

南半球の海鳥を見るのにシドニーとカイコウラを比較してみると、シドニーは船でポイントに行くのに3時間かかるがカイコウラは30分である。ポイントが陸に近いのである。船酔いのリスクを考えるとカイコウラの方が断然良い。
日本近海で記録のある種類を数種多く見られる可能性ではわずかにシドニーの方がよいかも。ロイヤルアホウドリのコロニーとペンギン2種を押さえたいならNZ南島のダニーデンDunedin(デンマーク人の村なので読み方が違う)も候補だ。
船酔い対策に自信があればNZ北島オークランドから北のケルマディック方面に出ている3日間ツアーもあり、マニアックな人にはおもしろそうだ。カワリシロハラミズナギドリKermadec
Petrelなどが見られそうだ(上記HPのリンクのページからアクセス可能)。
日本の夏はカイコウラの冬である。順当に言えば、7〜9月より1月の方が海鳥の種類は多い。特に7月はかなり寒い。1月では見られるが9月では見られない海鳥はミナミオナガミズナギドリ、アカアシミズナギドリの2種を含めていろいろある。NZ冬の方が見やすい鳥はプリオン(クジラドリ)など。アホウドリ類は7−9月の方が見られるステージが多いかもしれない。なお、私の行った9月は天候が荒れることがある。10日くらいボートが出なかった事例がある。夏と冬2回行くというのもいいだろうが、どちらか1回しか行かないならば、年末年始に行くことをおすすめする。
<参考文献その1>
さて例によってsurfbirds.comの紀行文、http://www.surfbirds.com/index.phpを検索してグラハム・ゴードンさんの軽妙洒脱な紀行文を読んだ。
(以下引用・・・鳥たちが現れる前に、私はかすかに鳴き声を聞いた。さえずりとか地鳴って知ってる?その静寂はイスラエルの猛禽が獲物をねらう時のようだ。私はそれ以外の言葉を知らない。船の周りを旋回するたくさんの鳥たちはまだ、かすかに見えるだけだ。その時ゲーリーが魚のはらわたを海面に投げた。わあっ!地獄の釜蓋が開いたあ!!・・・。)
この著者は抱き合わせ販売の安売り世界1周チケットを買ってヒッチハイク・バックパッカーの長期旅行をしてアホウドリ類をたくさん見てイギリスに帰ると、深夜に友人から電話がかかってきた。
(以下引用・・・・
著者「こんな時間に電話してくるなんてノゴマかトラツグミでも出たというのかね・・・・」
友人「もっといいものが出たんだ」
著者「ノゴマとトラツグミよりも良いものがこの世にあるのかね?」
友人「あるんだよ。ワタリアホウドリだあ!」)
<NZはこんな国>
NZは福祉と男女同権の先進国である。異文化の原住民のマオリ族の人口が大きかったこと、農業国のため女性の地位が相対的に強かったこと等が背景にある。
人口は約200万人、治安はいいとはいっても犯罪は人口10万人当たりの殺人が日本の2倍で、強姦は30倍。やっぱり注意はしなければならない。車上荒らしも多いそうだ。
日本人でリタイヤ後の新天地を求める人も多く、何人かの人がHPを持っているので土地を知るのに参考にした。
<手続き・旅の概略>
宿・ボートの予約などインターネットからすべてやった。クライストチャーチからカイコウラまではバスも列車もあるが、私たちはレンタカーを借りた。ホテルはボート会社の事務所の隣。よいレストランがあった。
入国審査で、農家・家畜施設に入ったことがあるか?という問いがあり、正直にイエスと書いたところ、管理官からいろいろ質問された。その時の衣類靴は持ってきていないと答えてパスした。食べ物は持ち込むといろいろ質問される。
畜産物、植物、原則として持ち込み不可である。野外で使用した靴を持ち込んだか?というチェックもある。そういう点は「地球の歩き方」でチェックしておいた。
英語はイギリス英語でちょっととまどうこともあるがあまり問題を感じなかった。道ばたにはTAKEAWAY(:もってけえー!)という看板の店を何度も見たが、ピザやサンドイッチやランチボックス持ち帰りの料理の店らしい。米語のテイクアウトのようだ。旅の途中でサマータイムが始まってしまい間違わないように気をつけた。クライストチャーチでの最後の夜は日本人経営のB&B「木蓮」に泊まったがとても良かった。
<レンタカー>
空港のAVISレンタカー、保険はフルに加入し(Full-Insurrance、約2万円)、Buy
Petrolを選択しなかった。
車はほぼ新車のFordのフォーカス2000CC。右ハンドルなのにスイッチ回りは左ハンドル仕様でウィンカーが出しづらい。しかし高速カーブが続くNZの道を走るにはFFよりFR車の方が快適だ。バリバリ伝説の走り屋がFFを馬鹿にする理由が分かった。
イギリス英語なのでガソリンスタンドはPetrol stopという。間違って1回ハイオクを給油してしまったのは無駄遣いだった。
<アホウドリ観察ツアー>
上記のHPから予約可能。事前に何度かメールのやりとりをしていた。スタッフは親切で外国人向けの英語表現を心がけているように感じられた。前日のリコンファームは事務所に行って行った。悪天候で中止になるかもという説明があった。
当日起きると小雨が降っていた。
今日の海は膨らんでいる(swelling)と、ゲーリーさんは言った。うねりがあるという意味だ。風とうねりのある日はより多くの種類の海鳥が出ると前向きに考えた。遠くの方も見ることにしよう。クルーはゲーリーさん一人。客はタイ人、スウェーデン人、オーストラリア人、私たち日本人の6名だ。もしツアー参加者の合意があれば2時間を4時間に延長するのもOKという話だったが、船酔いが心配なのでその説得作業はやめておくことにした。
ぼくの船酔い対策はまず酔い止めを飲むこと。船が上に持ち上げるときに息を吸い、下がるときに吐くが吐ききらないこと。身体をゆったりとさせかつ背筋を伸ばして頭を垂直に立てて遠くを見ること。どうしてもだめで可能なら思い切って横になって寝てしまうのもよいかも。
ワゴンで5分ほど移動、クリッパー(船)で沖へと向かう。うねりは恐ろしいほど大きいがゲーリーさんの巧みな操船で、船はあまり揺れなかった。 ニュージーランドミズナギドリの大群が見えた。この鳥は春夏の高山帯で繁殖し、毎日海に出て餌を取るタフな通勤者だ。白っぽいアホウドリ類も遠くにいる。
ゲーリーさんが船を止めるとマダラフルカモメがたくさん寄ってきた。魚のあらを大きな正方形に凍らせたものを海に放り込むと争って食べ始めた。ワタリアホウドリは船の上空を通り過ぎ離れて着水してからゆっくりと泳いできて突然叫び声を上げ「お毒味役」を追い払ってあらを食べ始めた。初列風切が短く、次列風切りをもつ上腕骨が長い。カモメ類とは違う翼を持っている。凄い大きさと力強さだ。翼長は3mを超え、水かきは人間の掌より大きい。同種同士の喧嘩も始まった。とにかく船は揺れ、波しぶきを浴びながらも時間を忘れて見入った。

3か所で餌付けを行い、ワタリアホウドリ6(Gibson's)、ロイヤルアホウドリ2(Northern
1,Southern 1)、マユグロアホウドリ、ハイガオアホウドリの5種類のアホウドリを見た。
ミズナギドリは3種類(ニュージーランド、ハシボソ、ウエストランドクロ)。やはりこの時期のミズナギドリ類は種類数的には貧しい。 ペンギン類も見なかった。
最近の研究ではワタリアホウドリは4種に、ロイヤルアホウドリは2種に分かれるとされる。この研究をしたのはシリハイという人だが、どこの人?まあ誰がやってもトリは面白いのである。
しばらくするとハラジロカマイルカがはねている。近くで泳いでいる黒い生物はウェットスーツを着た人間だった。雨なのにしかも寒いのに3mのうねりの中で大喜びで泳いでいる。ドルフィンエンカウンターツアーというのは年中無休だそうだ。
ミナミオットセイの繁殖している岩に近づくとうねりは複雑さと激しさを増した。タイ人と私の妻が相次いで吐いた。げー。港に入っても妻を気遣っているうちに私はいつの間にか船が陸上を移動していることに気が付いた。台車に乗り上げてトラクターに引かれていたのである。こうして私たちのアルバトロスエンカウンターは終わった。
<マグロ漁の犠牲になるアホウドリ類>
マグロ消費量の多い日本に住む人間として耳が痛い話であるが、マグロ等の延縄漁で多くのアホウドリ類が犠牲になっている。餌付きのロングライン(延縄)を投入するときにアホウドリ類が餌を食べて引き込まれてしまい、溺死するのである。
特にワタリアホウドリは調査が始まってから30数年で64%減少しているという。しかしロイヤルアホウドリはあまり減少していない。ロイヤルアホウドリの方は、保護政策(外来種ネズミの駆除。毒餌の入った青い筒を何度か見た)などが当たって増加しているのと相殺されているような気がする。いずれにしてもアホウドリ類が次々に危惧種、絶滅危惧種に指定されていく現状は危機的である。日本近海でもクロアシアホウドリやコアホウドリのランクが悪化している。
対策としての研究も進んでいる。5隻の日本漁船の協力で調査を行ったところ、アホウドリのじゃまをする吹き流し設置と延縄ラインを重くして沈降速度を速めることにより、犠牲になる数が4万羽からたった25羽に減ったという!!餌をカプセルに入れて食べられないように投入する方法も開発中である。放水でアホウドリを追い払う、夜間に投入作業を行う、餌が見にくいようブルーに染めて投入するという研究もある。
これらの方法は普及段階に問題がある。勧告だけでは緩いし、公海上の規制が緩いこと、アホウドリ類は世界の洋上を回遊するのでNZだけ保護しても効果が薄いことなどによるのである。
一般人として何かしたいという人にはNZの保護団体が作っているTシャツを買うことをおすすめしたい。ワタリアホウドリのデザインがとてもよい。生地も良い。気に入ったので私も買った。上記のHPにある通信販売で購入可能だ。
<ホエールウオッチングボート>
この50人乗りぐらいの船は95%の確率でクジラを見ることができるといい、浮上中のクジラをソナーで見つけて急行する。船内ではビデオをやっていて、海底が深いため、深海イカを食べるマッコウクジラが岸近くまで来るという説明、浮上したクジラをシャチが狙うシーン、そしてシャチとアオザメが戦う貴重なシーンがあった。他のお客さんはインド人が多かった。クジラを見て、イルイル!と叫んでいて日本語みたいだった。さて、ホエールウオッチングボートでもアホウドリは見られるが、アルバトロスボート船の方が近くで見られ種類数も見られるだろう。識別ではゲーリーさんの助けも得られるし。

<KOWHAI川河口付近>
カイコウラから車で10分ほど南下し近くの川に行った。NZと言う国は徹底的に国土の自然を破壊して農地にしているが、川沿いには治水のため自然林を残していることが多い。先ず河口に出て、ツアーでもらしたlittle
shagを見た。2時間ほど川沿いの道を散策して種類数を増やした。
<オットセイコロニー>
潮だまりにミヤコドリ2種とカオジロサギがいた。ミナミオットセイもたくさん見た。
<自然林>
NZのシダ植物(:Fern)はラグビーチームのトレードマークになるほど有名であるが、かなりの山間部に行かないと見ることはない。Fyffee
Palmer Nature Walkはカイコウラから車で10分ほどにある散策路である。保護活動開始から10年ほどしか経っていないが、とりあえず自然林だ。1時間の行程を3時間かけて歩いた。
山の固有種が期待できたがBellbirdばかりであった。 ライフルマン、モアポーク、ユニークな名前の鳥たちにも会いたかったのだが・・・。、猛禽の声がしたので崖を上ると固有種ニュージーランドハヤブサが居た。これはラッキーだった。
<ヨーロッパカヤクグリ>
これもイギリスからの移入種だ。ブレナムの某有名ワイナリーの生け垣でイワヒバリに似たこの鳥が2羽ディスプレーをしていた。交互に後ろ向きになり総排泄口を見せるのである。もう1羽はそれをのぞき込む動作をしているのがケツを嗅いでいるようで面白い。私はよく知らないが、日本のイワヒバリもこういう動作をするらしい。
<カモメ類総論>
NZにはミナミオオセグロカモメ、アカアシギンカモメ、クロアシギンカモメの3種がいる。ミナミオオセグロカモメはこちらの図鑑ではBlack
backed Gullと書かれている。他国ではKelp Gullという英名で呼ばれることが多い。最近の遺伝学的な研究ではニシセグロカモメの祖先が赤道を越えて迷行したのに起源をもつという。第一印象的にはオオカモメっぽい。この鳥についてはいずれ「カモメ資料室」の方で議論したい。
アカハシギンカモメは形態も生態もユリカモメに似ているが翼端にミラーがあるのがセグロカモメ的で面白い。ゲーリーさんの話ではクロハシカモメは淡水性が強いそうで、ブレナムとカイコウラの中間地点のKentという村近くのため池で見た。


上左:アカハシギンカモメ、上右:ミナミオオセグロカモメ
<ワイナリー>
NZではソービニオンブランとピノノワールが増えている。良いワインはその存在がインターネットですぐに世界に広まるのである。ブティックワイナリーと称して「世界的に最上級とされるもの」を目指すのが流行りの経営のようだった。でも本当に作りたいのはこういうワインだと言って、食中酒向きの独特のリースリングを推薦してくれたワイナリーがあった。
<今回の旅のエピローグ>
英語の国であるため、言語的な不自由を感じなかったし、食べ物もワインも安くて旨かった。体感的な治安状態は良かった。
<種類>
ワタリアホウドリ(spp. gibsonii)
ロイヤルアホウドリ(Northern)
ロイヤルアホウドリ(Southern)
ハイガオアホウドリ(Salvin's A)
マユグロアホウドリ(White-cap A)
オオフルマカモメ
マダラフルマカモメ
ニュージーランドミズナギドリ
ハシボソミズナギドリ
ウエストランドクロミズナギドリ
カワウ
マミジロウ
ゴマダラウ
シロハラコビトウ
カオジロサギ
コクチョウ
カナダガン
マガモ
マミジロカルガモ
ミカヅキハシビロガモ
ハシビロガモ
ハイイロコガモ
ニュージーランドスズガモ
クロアカツクシガモ
ミナミチュウヒ
ニュージーランドハヤブサ
カンムリウズラ
セイケイ
オオバン
ミヤコドリ
ニュージーランドミヤコドリ
ズグロトサカゲリ
チャオビチドリ
ミナミオオセグロカモメ
ハシグロカモメ
アカハシギンカモメ
シロビタイアジサシ
ニュージーランドバト
ドバト
オーストラリアツバメ
ハイムネメジロ
ニュージーランドセンニョムシクイ
ハイイロオウギビタキ
クロウタドリ
ウタツグミ
ニシヒバリ
ニュージーランドミツスイ
ヨーロッパカヤクグリ
ズアオアトリ
ベニヒワ
ゴシキヒワ
アオカワラヒワ
キアオジ
ホシムクドリ
カササギフエガラス
イエスズメ 全56種、うち移入種17種(赤字)
13.フランスのフォンテンブロー紀行(2007年5月):


<フランス観光旅行について一言>
フォンテンブローはパリから60kmほど南南東にある町で、歴史的な宮殿がある。町が広大な森林に囲まれており、野鳥が多い。石畳の町並、旧貴族の館、セーヌ川沿いの風景などは、これでもかというぐらい美しい。19世紀に多くの画家が育った場所、バルビゾンやグレーにも近い。ミレーの「落ち穂拾い」の背景になった場所も、ほぼ当時のまま残っている。
フランスへ行った日本人観光客の多くが、バスの中で長い移動時間を過ごして、あわただしい割には記憶に残らない観光しかしていな
い。その点、ここはパリからもシャルルドゴール空港からも車で2時間くらいで楽しめる「フランスの田舎」である。
私は初めてフランス旅行をする人にモンサンミッシェルはお勧めしない。短い日程で長旅と疲労する人が多いからだ。パリ近郊の「普通のフランス」こそ、面白いと私は思う。
また野鳥観察で海外に行く場合には、野鳥の多いスポットを一日中歩き回って疲れてしまい、文化とか食事とかを楽しめないこともある。ほどよく鳥が出てくれて、ゆっくりのんびりと贅沢な海外野鳥ツアーが楽しめる場所の一例として、ここを紹介したい。私も若いときほど体力がないということを自覚し始めた。夕食後バタンキューで寝てしまって、せっかくの家族・友人との会話のチャンスを逃してしまうのも残念だ。季節としては、5〜6月がお勧めであり、7月は暑いので避けた方が無難だ。
<パリからフォンテンブロー、大統領選挙に巻き込まれた>
パリには長距離列車の出る駅が4つある。そのうちの一つLyonリヨン駅から南下する列車に乗ろうとしたら、列車が来ない。周りの人に聞いてみると隣の駅から出るというのでびっくり。
別の人に英語で聞いてみてもそのとおり。ポスターの存在に気づいて読むと「集会:Convention」のために、一部の列車が隣のBercy駅から発着するという。国を挙げての大統領選挙なのだ。選挙当日には一部の列車は運休するらしい。
地下鉄を乗り継いでBercy駅に行くと、ジャンダルメリ(憲兵隊=警察・軍隊を取り締まることのできる組織)がうじゃうじゃいた(4/29Bercy)。群衆に紛れて行ってみると、サルコジ支持者の集会で、大画面スクリーンの周りに数千人規模の人が集まっていた。ロワイヤル候補のことを少しでも評価する人に対してはブーイングが起きていた。メモを取りながら聞く人や、支持者同士で議論している人もいた。熱いぜ、アンガージュマン! アフリカ系、ベトナム系の方も多かった。
サルコジ陣営は、ベルギーやロンドンなど隣国のフランス人を訪れて、支持を訴えた。今までのフランスは労働者保護政策のしすぎで、IT関連企業とその労働者が逃げ出しているからだ。残業禁止ではIT企業はやりにくかろう。
海外を遊説して回る選挙運動というのは斬新な印象だ。サルコジ候補のポスターは、「いっしょにやろう。できるさ!」というスローガンだった。極右的なイメージを払拭したいという意図が見えるが、逆に全体主義的な感じもする。ふしぎなスローガンだ。
サルコジ候補は日本ではこわもてのイメージで報道されているが、雇用問題やHIV感染者保護や女性問題などソフトな政策も打ち出した結果、候補者のバイル氏が中立に回り、右派のルペン氏は支持者に棄権を呼びかけている。前回の選挙ではルペンは過激な意見で国民の人気を高めたが、フランス大統領になるためには、50%以上の支持を得なくてはならないため、どうしても決選投票になり、過激な主張では乗り切れないことがはっきりした。
フランス大統領になるためのサルコジの戦略とはすなわち、閣僚として実務実績を上げ、右翼的言動(:外国人失業者をクズと罵ったりした)で注目を集め、選挙前にリベラルに転じることである。バッターの直前で鋭く左に曲がる球を投げるという点で松坂大輔投手とサルコジとの共通点を感じる。ぼくは2ヶ月前は絶対、次の大統領は女性だと思っていたのである。左から右に曲がる球は投げづらいの・・・かな?
ロワイヤル候補はブログやセカンドライフなどでサルコジを批判するほか、HPを充実させて政策をアピールしている。
HPを見ると、「サルコジ、危険な多数派」というページがあり、ヒットラーとの共通点を指摘している(:経済的な困窮をネタにして支持を得やがって・・・・等)。
ロワイヤルのポスターはラ・フランス大統領、という感じで大統領を女性名詞にしているシンプルなものだった。
いずれにしても、インターネット時代の選挙戦という点で、日本はフランスの選挙をよく研究する必要があるだろう。また海外で生活する日本人は選挙投票がしづらいので、インターネット・電話投票などを認めて欲しい。今はいちいち大使館に行かないとだめみたいだ。
さて、Bercy駅を出たフォンテンブローへの列車はムランMelun駅で前後に分かれて、前半車両がアボンAVON駅方面に向かう。こういう事の確認はやっぱり少しフランス語ができないと見落としがちである。まあなんとかなるだろう。
フォンテンブローのETAPホテルではまたもや予約ミスがあった。私は交渉時にフランス語と英語、両方で2重チェックした!
<競馬場跡の灌木林までのサイクリング>
フォンテンブローの森は何度か行っているので、ちょっと違った植生のある場所を地図(駅の売店で入手)で探した。直線距離
で10kmくらい北に競馬場があり、その隣に広い灌木林が広がっていることに目を付けた。自転車を借りて森林の中を20km程走った。林床で落ち葉がカサカサと音がするのは、小さなネズミだ。今の季節には多く見かける。チフチャフも多い。日本で記録のあるシベリア亜種とは地鳴きが違うと言われている。道標はしっかりとしているが地図を読めない人は道を外れて森に分け入るのはやめた方がいい。
この森には、コガラとハシブトガラが両方いる。どう棲み分けているのかが興味深い。針葉樹と広葉樹で棲み分けているとも言われている。国道を注意して横切り、急な山道を下ると競馬場の脇の松林に出た。
尾が長い小鳥を見た。セキレイ類かと思ったらノドグロホオジロだった。目的の灌木林には数種類の鳥が鳴いていたけれど、私がわかるのはチフチャフだけだ。茂みに隠れて出てこないうるさい声のを待ち伏せしてやっと見たその鳥は、頭が丸くてホオジロ類の様であったが、べたっとカーキ色。ニワムシクイGarden Warblerだ!こんなムシクイ類がいるというのは衝撃的だった。実際に見てみないとわからないものだ。
もう1種類、腰のあたりが微妙に黄色いムシクイ類を見たが、おそらく渡り途中のBoneli's
Warblerだと思う。茶器で言うなら「織部焼きの渋さ」に頭がスパークした。
この日は、こうして4時間ほどの探鳥を行った。夕方になると、森の中にコフキコガネに似た甲虫が吹雪のように大量に舞い始めた。数年前にはこんな現象は無かった。フランス革命(1789)時のパリ市民は、今年の夏は25℃もあって暑い、と日記に書いていたが、2006年のパリの7月は35℃を越えた。何かがおかしい。
夕食後の深夜、ほろ酔いで歩いていると、駅の近くでメンフクロウが目の前を横切った。
<宮殿の庭園>
翌朝、フォンテンブロー宮殿の裏門から広大な庭園内に入って、うっそうとした森林、開けた野原を散策した。庭園内だけなら入場料無料。チフチャフ、ズグロムシクイ、カラ類が多い。樹木は胴回り1mを越えるのがほとんど。シロビタイジョウビタキがオオルリに似た声でさえずっているのを見た。カッコウは日本のと同じ声だった。
クロウタドリは極めて多い。中国南部のとはかなり違うカタチをしているという欧州人のコメントを聞いたことがある。
パートリッジ(アカアシイワシャコ)を探して庭園内の草原を探し回ったが、見ることはできなかった。大運河のほとりには古ぼけたスフィンクス像が佇んでいた。いつの時代のものだろうか? この宮殿を創設したのは、フランソワ1世であり、歴代の王が手を加えている。
ミソサザイが自分ほど大きな蛾と格闘していた。それはもうプロレスのようであった。こいつらは日本のものと全く違う。くっきりと白い眉、2割くらい大きな体、乾いた白樺林にも棲む適応性など。ちなみに、ミソサザイはベルサイユ宮殿の庭園(プティトリアノン〜田舎家周辺)にもいた。しかし地鳴きとさえずりは日本のと同じであった。
町中にはヨーロッパアマツバメが多い。春夏は使われていない暖炉の煙突内部に営巣するのだ。写真を撮ろうと頑張ったが、未熟なために識別点を表現した良い写真が撮れない。興味があるんだけどなあ。中国までは来ているので日本にも来るかもしれない。鳴き声は日本のアマツバメによく似ているが、腰は白くない。7,8月頃になるとその年生まれの幼鳥も加わり、町の上空に鳥柱が立つことがある。それを狙って、美しい赤味のかかったハイタカが突っ込んで捕食することがある。
<諸事情>
フランスには狩猟雑誌が数誌あり、ヤマシギの見つけ方など、いろいろなことが書いてあり、立ち読みするだけで面白い。ただ、フランスの野鳥愛好団体と狩猟団体は非常に仲が悪く、沼でカモ類を見てたら足下に弾を撃ち込まれたとか、「野鳥の会」の事務所が焼き討ちにあったりという話がある。
ユーロが高騰しているのでフランスには行きづらくなっているのは残念である。そこでお金の節約の仕方であるが、お土産は空港ではなくて町中のスーパーや朝市で買うのが良いようである。意外性を楽しむ余裕があれば、いろいろなものを発見することができるだろう。
<リスト>
チョウゲンボウ
ハイタカ
コウライキジ
セグロカモメ
ユリカモメ
マガモ
モリバト・・・・・・・・ヒメモリバトはいないのが残念
シラコバト
カッコウ
ヨーロッパアマツバメ
ツバメ
アカゲラ
ミソサザイ
クロウタドリ
チフチャフ
キタヤナギムシクイ
ズグロムシクイ
ニワムシクイ
ボネリムシクイ
シロビタイジョウビタキ
マダラヒタキ
ヨーロッパコマドリ
エナガ
シジュウカラ 日本のとはさえずりが違い、腹が黄色い
アオガラ
コガラ
ハシブトガラ
ゴジュウカラ
ハシボソガラス
カササギ
カケス
ノドグロホオジロ
ズアオアトリ
アオカワラヒワ
イエスズメ
14.苫小牧航路でハジロミズナギドリを見た話(08年秋)。
9月上中旬、三陸沖では、Providence Petrel、ハジロミズナギドリが数十〜数百の単位で見られることがわかってきた、という話を小耳に挟んだ私は、名古屋ー苫小牧航路(太平洋フェリー)に乗った。合計21羽!期待通りのトリが、期待通りの状況で出たのである。

初日は房総半島付近で夜が明けて夕方仙台港、2日目は青森県付近で夜が明けて、昼前に苫小牧入港、夜に折り返しの出港。3日目は、宮城県沖で夜が明けて、0920仙台入港。4日目に名古屋に戻る。
大洗−苫小牧航路と比較して、三陸沖を通過するゴールデンタイムがかなり短いが、西日本に住む人にとっては、選択肢の一つだ。名古屋/北海道往復2.5万円(B寝台)は安い。B寝台はテレビが無く、静かでよかった。A寝台はBにテレビが付いているだけだ。夕食はバイキング形式で2000円。
今回、私が工夫したのは、プロミナー用の三脚の足に装着する振動吸収装置である。プチプチを3重底にしてセロテープで留めただけだが、船のエンジンの振動を遮断する効果は実に大きかった。しかし完璧ではないので、改良の余地があると思う。
船の振動は舳先側の方が少ないほか、左舷の方が少ないような気がしたが、確かではない。エンジンの負荷状況?でずいぶん振動量が変わるような気もする。

0日目:30分遅れて20時半出航。
1日目:コアホウドリ1、オオミズナギドリ多数、アカエリヒレアシシギ300+の群れを1つ。オットセイ10±の群れを1つ。魚の群れがビチビチと水面下にうごめいている所には、付属品のようにトリやマリンマーマルが付いていることがあるので要注意だ。トビウオも出た。仙台1900入港、2000出航。
2日目:6時10分、最初のハジロミズナギドリが飛んだ。インターセプト(迎撃)成功!。断続的に2時間半にわたり次々と1〜4羽ずつ出た。これだけ出るとじっくり観察できる。原則的には上面の翼には白い線は出ないところが、ケルマディック(カワリシロハラ)との違いと思うが、ハジロも初列内弁の根本がちらりと見えて細い白線になって見えることがよくあった。羽軸が白いケルマディックとの違いは微妙ではあるが、左右で大きさが違ったり、最外側には欠如していたりするところがハジロだろうか。オオミズナギドリと比較してみると、焦げ茶の色調、上下動が大きな飛び方が印象に残った。苫小牧1045着。
せっかく北海道まで来たので、ラーメンを食べて北大演習林に行ってハシブトガラを見た。最近、コガラとの識別についての詳しいレポートが英語のHPに載っていて興味をもったのである。1900苫小牧出航。
3日目:三陸沖で夜明けを迎えた。沿岸が近い。ううむ、期待していたヒメクロがいない。アカエリとオオミズナギドリはたくさん出て、仙台港に入港0920。出航1220。
4日目:御前崎付近で夜明け。雨だった。デッキ部分の大きな「いしかり」だが、雨よけは「きたかみ」の方がやや大きいようだ。船内から海をみていると、伊良湖岬付近で、オオタカが飛んだ。雨が小降りになってきたので甲板に出ると、海上にオオミズとアカエリがたくさんいた。1羽ハイイロヒレアシシギが混じっているのが見えた。ポートアイランドを過ぎると、ぱったりと無くなってウミネコとウミウばかりになった。ナゴヤにちなんで長さ758mに造られたという名古屋大橋トリトンをくぐり抜けて0910に入港。充実した船旅が終わった。
15.GWの苫小牧-名古屋航路でウミオウムを見た話

太平洋フェリー、5月GWの名古屋−苫小牧航路の往復の旅。近くに来た一部の海鳥しか識別できない私でも、ライファーが楽しめて嬉しい。名古屋フェリー乗り場は、名古屋駅からあおなみ線20分、バス10分である。
15倍の双眼鏡(C社の手ぶれ防止)と、例の震動対策でプチプチ巻きを装着した30倍のプロミナーを使用した。
<往路>
2日目の日の出は遠州灘。ミズナギドリ類が結構いた。
アホウドリ幼鳥は、妖怪のようにゆっくり飛んでいた。もっと感動的な出会いを期待していたのだが遠かった。しかし推定生息数2390羽(2009年現在)の中の1羽であり、貴重な出会いである。
ハイイロとハシボソの違いは、簡単であると同時に難しい。先達たちの話を聞くと、私がまだ会得していない技がありそうだ。 沖合で、陸鳥に出会うことがあるのは何度経験しても不思議な気持ちになる。いずれも船の回りをぐるぐる回りながら留まろうとはしなかった。メジロが20羽くらい。キジバト、ハクセキレイ、ホオジロ類の1種など。
たくさんのアビ類が、ばたばたと海面をはたきながら飛ばずに船から遠ざかっていく。もう少し早い時期だともっとたくさん見られるらしい。真後ろからで識別できないことが多いが、意外なものも混じっていたりするかも知れない。
3日目の三陸沖は一番寒かった。イシイルカの群れがシュパュ!と白い水しぶきを上げている。セーター、カーディガン、レインを着込んでもまだ寒い。
<復路>
出航翌朝は意外と温かったので、苫小牧のユニクロで買ったアンダーウエアは使わなかった。ウミガラス、ウミスズメ、それとウトウはたくさん見た。
ウミオウムが1羽、海上の空高く飛ぶ。人間から「変な顔」と言われても、見えない目標に向かってまっすぐ飛行を続ける姿には、高潔な意志のようなものを感じさせた。少ないながらも、冬から春にかけて遭遇率は決して低くはないのでは?と思う。
<リスト>
アホウドリ:茨城県沖、幼鳥1、黒っぽくて、真後ろから見るとクロアシとよく似ている。
コアホウドリ:かなり多
クロアシアホウドリ:多
ハイイロミズナギドリ:かなりの数がいたと思う。
ハシボソミズナギドリ:多い。魚の群れの上に集団で着水するのが見られた。
オオミズナギドリ :多い。
オナガミズナギドリ:少数がいたという情報あり。自分は自信をもって言える個体は見ていない。
アカアシミズナギドリ:数回見た。ハシボソと比較して大きくて、ゆったりしていて、嘴が肉色だった。
オーストン:3羽。銚子沖。アナドリかな?と思ったがオーストンに落ち着いた。
ヒメウ :夏羽で顔が赤かった。夏羽は初めて見た。1羽
ウミウ :
オオハム :多い。ほとんど夏羽、
シロエリ :多い。ほとんど夏羽、
アビ :多い。夏羽
アカエリヒレアシシギ:極めて多数
オオトウゾクカモメ:1羽、銚子ー茨城沖
トウゾクカモメsp:??
オオセグロカモメ:
セグロカモメ:
ウミネコ:
ウミオウム:ウトウと思ったが、嘴が短く鮮やかなオレンジ色だった。高い場所を飛んでいた。宮城県沖にて1羽。
ウトウ :茨城県沖くらいまで、かなりの数がいた。
ウミガラス:三陸沖くらいまで。夏羽
ウミスズメ:三陸沖以北。
その他の生物:
イシイルカは数頭から20頭くらいの群れを何回か見た。英語で、「雄鶏の尻尾」と表現される波切りスプラッシュは独特。そのうちの何頭かは、リクゼン型という、白い部分が前方に広がっているタイプであることが確認できた。
ネズミイルカの数頭の群れを金華山周辺で見た。
トビウオ・トビイカは見なかった。キタオットセイは何回か見た。
追記:太平洋フェリーは、新しい船を建造するらしい?。現在この航路に就航している3隻は、川の名前だから、新船の名前は、「ながら」か「いび」か?と愚考する。
<旅程>
5/1金:地下鉄築港駅からタクシー、1830いしかり乗船、1900出港、
5/2土:1640仙台着、1940発
5/3日:1100入港、トヨタレンタカー(0144-35-0100)、2階案内所、1050円配車料。
鵡川、コンフォートホテル苫小牧泊0144-31-3211、「黒船亭」でタラバガニなどを賞味。量が多く、旨い!。
5/4月:鵡川、レンタカー1700西港に返す。1830乗船、1900出港
5/5火: 1000仙台着、1250発
5/6水: 1030名古屋到着、
16.歯舞色丹沖クルーズ(y社ツアー参加、2007夏)
写真(左上から順に):ハマナス、エトピリカ、灯台、トウゾクカモメ、オットセイのジャンプ、
ハシボソミズナギドリの大群、ツノメドリ若鳥、船首波に乗るイシイルカ








17.これがモントレー、アメリカ西海岸の海鳥だあ!
「モントレー(カルフォルニア)の海鳥観察8時間コースに参加した話」


ミナミオナガミズナギドリBuller's Shearwater、シロハラアカアシミズナギドリPink-footed
Shearwater
カルフォルニアのモントレーは、バーダー人口の多いアメリカ大都市圏を控えて、産業として洗練された海鳥観察船(8-12時間)が年数回プロデュースされている。毎日出港するクジラ観察ボート(1〜4時間)も、機材は同じなので、かなりの鳥を期待できるが、沖合に行くほど、遠洋性の海鳥を見るチャンスが多いため、より長時間の海鳥ツアー企画の方がよいと思われる。
サンフランシスコ空港からモントレーは150km南、空港からバス,Montereyairbus.comが日毎11便ある。「地球の歩き方」などにも書かれている情報だ。
海鳥&クジラボート会社のHP上の9月の記録によると、クビワカモメとシロナガスクジラが期待でき、天候も穏やかなようだ。シロハラアカアシミズナギドリ、ヒメシロハラも期待できそう。港ではカルフォルニアカモメとアメリカオオセグロカモメを撮りたい。 http://www.montereyseabirds.com/
海鳥ツアーは9月は5日,19日の2回催行。約8時間。12時間、24時間のスペシャルツアーはもっと良いらしい。 沖縄発なので台北経由を考えた。成田経由の全日空と比べると半額だが、チャイナエアはマイルが貯まらないし、サンフランシスコで宿泊が必要。アシアナは、ソウル空港経由で帰りに一泊必要。結局成田経由ユナイテッドにした。 空港からのバスも念のためネットで予約。なぜか郵便番号の入力が必須。
ジャズフェスティバル開催中の為か、気に入った宿が取れなかったので、安いユースホステルにした。これは正解だった。レストランも、コインランドリーもスーパーも近い。自炊も可能だ。カリフォルニアロールの寿司パックとカルフォルニアワインの相性にはかなりよいものがあった。
<初日17日>
エンジントラブルで、沖縄発が2時間遅れた。ぎりぎりで成田空港での乗り継ぎに成功。サンフランシスコ空港から、携帯で妻にメールしようとしたら、FOMA圏外だった。2時間15分でモントレー到着。ユースホステルにはカギが掛かっていて入れなかった。11時から17時まで、マネージャーがいないのだ。後で気づいたのだが、YHの駐車場にはコインロッカーがある。
ジョンスタインベックに出てくる「キャナリーロー(缶詰横町)」まで歩いて10分。作中の店をモデルとしたカフェでコーヒーを買った。海にはケルプの森が広がっていて、ラッコやアザラシがたくさんいる。ウミバトが20分置きに飛んでいく。海岸にはアメリカオオセグロカモメがたくさんいる。ポテトチップを少量撒いて、おびき寄せて、写真を撮りまくった。結構満足感があった。
<翌日18日>
YHから早朝フィッシャーマンズワーフまで30分歩いた。霧が掛かっていて暗いが、オオアオサギの写真を撮れた。このアメリカ大陸固有種は、イギリスでの記録も幾つかあるが、その過半が「偶然船に留まった個体が運ばれてしまった」ケースである。そのため、発見される度に人為的要素が疑われている。こういうケースで日本でも見つかるかもしれないのである。
クジラ観察船4時間コースは、9時出港。ピニョ岬を回り込んで、カーメル市沖に出たら、からっと晴れた。俳優のクリントイーストウッド氏が、世界一気候がいい場所だと気に入って、市長まで務めた場所だ。ゴルフコースで有名なペブルビーチもある。
ハイイロミズナギドリやクロアシアホウドリ、ウトウ、ウミガラス、ヒレアシシギ2種、など。
シロナガスクジラ=ブルーホエールは、あっさり見ることができた。英語でブルーと言えば、憂鬱という意味もあるが、ここでは、ブルー!!と言って大喜びする人々を見ることができる。尾ひれ=プルークを見せずに沈降していくのが意外だった。多くの文献で、プルークを見せてから沈降するのが特徴と書かれている。また高速で逃げていくという記述も読んだことがあるが、私の見た個体は、人間に慣れているのか、時速10kmくらいでゆっくり泳いでいる。5回目に浮上した個体が沈降するとき、端正な形のプルークが見えた。かなり珍しいことです!とリーダーから解説があった。ザトウ・シロナガス・シャチの三種類。
日没まで時間があるので、海岸沿いを歩いてみた。枯木に穴がたくさん開いていて、ドングリが詰まっていた。たぶんドングリキツツキの蓄えだろう。松林ではヤブガラとアメリカコガラ。観光案内所のある池では、アメリカオオバンや、フタオビカイツブリなど。
<3日目19日>
出発1時間前の0630にチェックインして、昼飯のマフィンを買ったり、海鳥の本を見たりして時間を過ごした。乗客乗員は合わせて30名くらい。私の500mmケンコーレフレックスレンズは注目の的で、いろいろ質問された。スモールでパワフルでチープだが、扱いづらい、と言ったお答えだろうか。
ツアーリーダーの娘さんが、オリーブの大枝を軍旗のように掲げてやってきた。渡りの小鳥がやってきて休むことが期待できるという理由で船のマストに掲げるそうだ。
海鳥初心者なのに、こんなマニアックな船に乗ってしまった。周りはみな達人に見える。オオミズナギドリなら任せてくれとか言おうかな?
不安でいっぱいだ。英語が聞き取れるのか?持病が出たらどうしよう。勉強してきたことが通じるだろうか? 出発前のブリーフィング・・・・。救命具の使い方!、鳥が現れたら、リーダーが方向と種類をマイクで伝える。なんか珍しいもんを見たらリーダーに伝えること。リーダーは5名。質問は気軽に。背の高い人は海に落ちないように注意。船酔いになったら、海に吐いて、鳥の餌にすること。
親子ラッコやウやアシカを見ながら微速前進で港を出たところで、突然船がUターン。遅刻した人が到着したのでピックアップするのだとのこと。大笑い。
魚油をまぶしたポップコーンを撒きながら、意欲満々で船は奔る。港のカモメ類をサクラとして30km沖まで連れて行くのだ。また魚油の臭いは何種類かのミズナギドリ類に対して誘因性がある。周りのミズナギドリはハイイロが大半を占める。次に多いのは、シロハラアカアシミズナギドリだった。思ったより明るい褐色味の色をしている。魚油に惹かれているのだろうか。距離はかなり近い。ミナミオナガもいる。船長が船内放送で、鳥の名前と方向を言う。聞き逃さないように集中した。ハイイロとウミガラスはそこら中にいるので放送無し。あの黒いフライングテニスボールはなんですか?と尋ねたら、アメリカウミスズメCassin's
Aukletとのこと。放送で聞き取れなかった。悔しいが、他にも聞き逃しがあるかもしれない。
みんな疲れてきた昼頃、船尾にいたリーダーが、サバインズ・グールと叫んだ。遂に出た!クビワカモメだ!いつの間にか、ポップコーンに群がるカモメ類に混ざっていたのだ。思ったより小さい。しかし船から直ぐに海面に降りていなくなってしまった。
後半から、トウゾクカモメ類が次々に出始めた。「じゃえーがー」と書いて、イエーガーと発音するのは、ドイツ語(:狩人という意味)由来だからだ。ポーマリン(トウゾクカモメ)、パラスィティク(クロ)、ロングテール(シロハラ)の3種。
クジラ類はザトウクジラ、シロナガス、カマイルカ、セミイルカ、イシイルカ、シャチ。
若いシャチ3頭がブローをあげていた。近くにアシカがいる!シャチが狙っているのかも?という放送があった。
「Oh!get it! get it!」と隣の男がつぶやいた。アシカは身をくねらせてジャンプした。それは食えるモンなら食ってみやがれ!という生存をかけた強い意思表示のようにも思えた。
巨大なマンボウも見ることができた。午後3時港に戻り、大満足の海鳥ツアーが終わった。
<4日目:20日>
モントレー水族館に行った。環境教育の展示が充実していたほか、ジャイアントケルプの丸ごと展示が素晴らしい。生きた野鳥の展示もあった。タヒバリアメリカ亜種夏羽、ヒレアシトウネン冬羽成鳥の写真が間近で取れた。識別オタクが喜びそう。タヒバリは冬羽を撮りたかった。
ババガンプシュリンプで昼食。映画「フォーレストガンプ」に出てくる会社をリメイクしたレストランだ。それだけではない。主人公のそっくりさんが店の前に出てきて、映画の台詞を言ったりする。
「ママは言った。人生はチョコレートの箱。開けてみるまでは何が入っているか分からない」とか言うのだ。
海岸の遊歩道を散策していると、黄色い花の写真を撮っている人がいて、ブーンという羽音がした。アンナハチドリの雌だ。喉が夕日を反射してルビー色にきらりと一瞬輝いた。しばらく観察し、様々なシャッタースピードで撮影した。丁寧にお礼を言ってその場を離れた。

最後に取り残したウミバトの写真を撮って早めに宿に帰った。こうして鳥見が終わった。予想していた鳥がなんとか見られて、予想外の鳥が予想外に出てくれて、美味しいものも食べられた。
モントレーは、来てみるまではわからない良いトコロなのであった。
観察種:
ハシグロアビ、フタオビカイツブリ、フルマカモメ、ハイイロミズナギドリ、ハシボソミズナギドリ、
シロハラアカアシミズナギドリ、ミナミオナガミズナギドリ、カッショクペリカン、アオノドヒメウ、ヒメウ、
ダイサギ、ゴイサギ、オオアオサギ、シジュウカラガン、アカオノスリ、アメリカチョウゲンボウ、
アメリカオオバン、クロキョウジョシギ、アメリカオオセグロカモメ、カルフォルニアカモメ、
クビワカモメ、オグロカモメ、キョクアジサシ、ユウガアジサシ、トウゾクカモメ、クロトウゾクカモメ、
シロハラトウゾクカモメ、ハイイロヒレアシシギ、アカアシヒレアシシギ、アメリカウミスズメ、
ウトウ、ウミガラス、ナゲキバト、アメリカヤマセミ、(ドングリキツツキ食痕)、ツバメ、
クロツキヒメハエトリ、マネシツグミ、タイランチョウsp、サンショクハゴロモガラス、テリムクドリモドキ、
ヤブガラ、アメリカコガラ、イエスズメ、ホシムクドリ、アメリカカケス、ワタリガラス、アメリカガラス、
アンナハチドリ 番外ドバト 合計52種
18.台湾の温泉地でカワビタキ鉛色水鶫を「賞鳥」した話


台湾の野鳥写真図鑑(中華民国野鳥学会)、「台湾の野鳥300図鑑」がでた。日本語で書かれている。かなり質が高いと思う。そんな中、私は台北から1時間半で行ける温泉地、烏来(wulai:ウーライ)温泉に注目した。山裾の景勝地で、冬期には漂鳥が降りてくる。日本での珍鳥カワビタキがたくさんいるという。私は台北のホテルから日帰りで行くことにした。
台北市のホテルを出て、地下鉄淡水線で新店(シンティエン)駅まで30分。そこからバスで烏来を目指した。紙に行き先を書いて見せた。小銭をたくさん用意して、おつりに備えた。一人40NTで40分かかった。
烏来バスターミナルに到着。降水確率30%なのに沛然と雨が降っていた。がっかりしたが、さっそくカワビタキの雄が2羽、川岸でディスプレイ対決をしていた。やっぱり色のはっきりした個体の方が強いみたいだった。ディスプレイは、深紅の尾を上下に振り地面に叩きつけながら、びら−りびら−りと閉じたり開いたりする。万札紙幣を数える銀行員の様だ。
全身地味な鉛色で赤い尾がアクセントとなっている。中国名は鉛色水鶫と書く。雌は、尾の基部が白く、飛び立つとき、尾を振るときにフラッシュする。1羽の雌成鳥は警戒心が薄く、足下まで近寄ってきた。2009年には日本初記録?があった鳥なので、じっくり観察した。雌は成鳥でもPC先端に白点がある。鳴き声は、ルリビタキのような、イソヒヨドリのような感じだ。けっこう攻撃的で、キセキレイを追い払うこともあった。キセキレイの好みそうな岩石の多い渓谷には必ずいた。
繁華街の橋を渡って烏来大飯店のT字路を曲がり、支流の上流に向かった。川沿いの車道からもう一つのターゲット、シロクロビタキを探したが居ない。再び戻って、ガイドブックにあるとおり、賞鳥路線と書かれた看板のある急な階段を上ってお墓の方向に行く。「あの辺は、ヤマムスメがいつも居る」、との地元人の情報だったが居なかった。和名はイケてないが、英名は、フォルモサ・マグパイと言って、台湾を象徴する美しい鳥である。
屋台には、テッケイ(竹鶏)という鳥が焼鳥となって売られていた。別名タイワンコジュケイとも言われている鳥だ。コジュケイの亜種という説もある。
翌日も烏来温泉に行った。山道を歩いていくと、美しい朱色とレモン色のベニサンショウクイの群れが通っていった。色鉛筆が飛んでいるようだ。ヒメオウチュウがこの群れにつきまとって、ちょっかいを出していたのは珍妙で笑えた。上記文献のとおりだった。
沖縄もそうだが、亜熱帯は、冬でも葉が茂っており、近くで鳴いていても、鳥が見えにくい。時間をかけたら、もっと鳥が出たであろう。メジロ亜種ヒメメジロspp.simplexは、濁った声で鳴くことが多い。セグロセキレイかと思ったほどだ。喉の黄色いエリアが広く、目先の黄色が顕著だ。光彩の赤味が強く、背中黄色味が強いなど形態的にリュウキュウメジロとかなり違う。また、目の回りの白色部が、大きくてぎざぎざのものや、嘴が異様に長く大きい個体もいた。個体差が大きいように思えた。
帰りのバスを待つ長い行列に辟易し、タクシーの運転手に声をかけた。運賃は相場の倍の600NTだと言われたため、まけてくれ!と中国語で言った。当然、反論は中国語でわからなかったが、渋滞で遠回りするからだと言っていたようだ。その場に居合わせた他の日本人と相乗りをして帰ることにした。渋滞を避け、美しい田園風景をぬってタクシーは新店を目指した。
最終日になった。台北市内にある植物園は、小南門という地下鉄駅から歩いて10分。我々は時間節約のため、タクシーを使った。運転手に南海学園植物園と紙に書いて見せたらすぐに理解してくれた。
植物園は南海学園と博物館に隣接した公園で、市民の憩いの場である。2時間もあれば、一通り歩くことができるだろう。短い冠羽のあるタイワンオオタカも2回ほど見た。サシバより尾が長く、あまり汎翔しない。シロハラを追って音もなく林間を飛ぶのを見た。春には、ズグロミゾゴイも繁殖しているらしい。キツツキ目の原始的な鳥とされるゴシキドリのため、営巣用の柔らかい丸太を木に縛り付けたりする事業なども、当所の名物となっている。
台湾政府は、野鳥を観光資源と考えて宣伝、保護、教育をしている。海外の野鳥雑誌での特集記事(Birdingworld
2008)もその成果だろう。烏来ではヤマムスメのいる場所を教えてくれた一般人もいた。政権交代後のこの国では、中国大陸からの観光客が100万人を越え、台湾経済は中国寄りにシフトしている。その反動として、台湾固有種の美しい野鳥たちが台湾アイデンティティのアイテムとして、クローズアップされているという側面に気づかされた。まあ、それはともかく台湾固有種15種というのは、とても素晴らしいことである。
<烏来温泉>
コサギ、アオサギ、サシバ、カンムリワシ、タイワンオオタカ、イソシギ、ヒメアマツバメ、アマツバメ、カワセミ、ゴシキドリ、リュウキュウツバメ、タイワンショウドウツバメ、イワツバメ、キセキレイ、ベニサンショウクイ、シロガシラ、クロヒヨドリ、カワガラス、ミソサザイ、ヒタキsp、カワビタキ、シロハラ、ズアカチメドリ、ヒメマルハシ、ヤマガラ、メジロ、スズメ、ヒメオウチュウ、ハシブトガラス、30種・・・・番外:ドバト、バリケン、テッケイ(焼鳥をみた。養殖ものか?)
<植物園>
コサギ、ゴイサギ、タイワンオオタカ、バン、シロハラクイナ、カノコバト、ゴシキドリ、キセキレイ、シロガシラ、アカモズ、ルリビタキ、シロハラ、ヒメマルハシ、メボソムシクイ、メジロ、スズメ、カササギ、タイワンオナガ、ハシブトガラス、19種(その他:中正紀年堂にて、クビワムクドリ)
<参考文献>
地球の歩き方、台北
台湾の野鳥300図鑑、中華民国野鳥学会・・・・・・日本語
台湾野鳥地図、勝星出版(台湾)・・中国語
Birdwatching in Taiwan, Wild Bird society of Taipei ・・・・英語
19.Northern Hokkaido Island is Rubythroat's haven!


Early July 2009, I and my wife visited at Hokkaido. I enjoyed myself to watch Rubythroat, Lanceolated warbler,
diisplaying Latham's snipe, screaming Wryneck, noumerous flowers and beutiful sunset. My wife isn't interested in birding so much, but was pleased with comfortable hotel, hot spa, golden sunset and nice seafood.
I concluded that the best Ruby's heaven in Japan is this Okhotsk area in Hollaido, especially around Saroma lake, Sinobutsunai lake, and Komuke lake. To get there, the nearest airport is Abashiri. The second best is Asahikawa airport. They are connecting to Tokyo airport(Haneda airport).
July 2nd,
We flew to Asahikawa airport and got a rent-a-car there. I stayed night
at Asahikawa city.
July 3rd,
I started to Monbetsu city beside Sea of Okhotsk.
I tried to see Hazel grouse and Grey-headed woodpecker on the way, but couldn't get them. I stayed at Monbetsu-prince Hotel(81-158-23-5411) . It was pretty good.
July 4th, Sinobutsunai lake and Komuke lake
I got up early at 4AM before dawn. And I drove from Monbetsu to Komuke lake for 20km.
Rubies were appealing themselves every 50m. Lanceolated warblers were singing 'sisisisisisisis' in low heath. I managed to get a glance at this bird. An early birder catch 'The Lance'. After eating breakfast at 8AM, I couldn't already listen to them at all there. But I heard strange screaming voice. It was a wryneck!
Going back to Monbetsu fishing port, I saw a young White-tailed eagle and many Slaty-backed gulls. We enjoyed hours of fishing some soles. We got 20 soles from the bottom of the sea.
July 5th, mountain area
I tried some grouses in the mountain area again, but I couldn't. We terrified at Brown bears. We stayed at Turuga Resort
Hotel(81-152-54-3305) besides Saroma lake. It was very comfortable. Dinner
was the best in this tour. Especially scallops are famous for its taste
in all over Asian countries. Wine of indigenous grape in Hokkaido was nice
suprised.
July 6th Saroma lake
15 minutes walk from the hotel, I got to the Wetland park and the 'visitor
center'. It was in the middle of summer. Flowers were in full bloom around
the heath. Several Latham's snipes were displaying in flight. Rubies and
3 spesies of warblers including Lanceolated were singing in the heath.
Wryneck, Stonechat....etc were there.
July 7th Sounkyo
I tried grouse at Sounkyo, a famous landscape site. I get on a cable car to see it. But I couldn't get some grouses again. When a Bullfinch was singing badly, my wife whistled well. He shocked very much and flew away. She was sorry to him.
July 8th.
We went back from Asahikawa airport to Nagoya.
20.多良間島GWはサンコウチョウがたくさんいた。

多良間島は宮古島から船で片道2時間、石垣島から40km、宮古島から60km離れており、渡り鳥の中継地点として、思わぬ珍鳥が入ることがあるそうだ。GWの3日間をこの島にかけてみた。
水田・湿地がないのが残念だが、防風林は200年以上の歴史があり、巨大なものがそだっている。樹木が豊かだと、海も豊かなのであろう。シュノーケル系の魚愛好家からも評価が高いようだ。
多良間島フェリー(0980-72-9209)で上陸すると、サンコウチョウとキマユムシクイがうるさいくらい鳴いていた。旧飛行場では、ツバメチドリがたくさんいた。多数繁殖しているようだ。なんとエゾセンニュウが1
羽さえずっていた。アダンの影からヤマシギが飛び出した。貯水池のコンクリート斜面にはアオアシシギが多数。
夕方、物見の塔がある丘に登ってみた。ガジュマルの実が成っているところでは、メボソムシクイ系の地鳴きが聞こえた。録音して検討の結果、コムシクイという結論となった。
民宿は丸宮(0980-79-2881)に泊まった。地図には丸藤と書かれている。オーナーは漁師さんの宿である。客層がいい。魚中心の食事もよく、設備も離島にしては、こんなもんだろうというレベル。鳥見に疲れて闘牛ならぬ闘山羊(地元ではピンダアースという)を見に行った。GWに1日だけやっている。後ろ足で立ち上がってゴーンと角をぶつけるダイマツという大技は迫力がある。
体力消耗を避けて後半戦にラッシュをかけるもの、ボディー攻撃を狙うもの、金的を狙うもの、戦う前に戦意喪失するものなど、山羊もたいへんなのだ。
サンコウチョウはトータルで50羽以上、7割くらいが長い尾を持っていた。サンコウチョウが長い尾を持って渡りをするという話は本当らしい。
最終日の帰り際に、聞きなれない騒がしい声がした。10羽くらいで鳴き交わしている。アカショウビンの群れだった。多良間島は人口1300人、人口増加率日本一の村である。
ササゴイ、アカガシラサギ、アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、クロサギ、アオサギ、ズグロミゾゴイ、シマアジ、
ミサゴ、ハヤブサ、ミフウズラ、オオクイナ、シロハラクイナ、ムナグロ、シロチドリ、メダイチドリ、キョウジョシギ、キアシシギ、アオアシシギ、クサシギ、タカブシギ、トウネン
イソシギ、ヤマシギ、セイタカシギ、クロハラアジサシ、アジサシsp、ツバメチドリ、キジバト、ズアカアオバト、キンバト、アオバズク、
アマツバメ、アカショウビン、ショウドウツバメ、ツバメ(アカハラツバメを含む)、リュウキュウツバメ、ヤツガシラ、
ツメナガセキレイ(キマユ・マミジロ)、ビンズイ、ヒヨドリ、アカモズ、イソヒヨドリ、セッカ、キマユムシクイ、センダイムシクイ、エゾセンニュウ、
コムシクイ、サンコウチョウ、エゾビタキ、サメビタキ、メジロ、スズメ、コムクドリ、
21.伊平屋島(沖縄県)
珍鳥狙いの一発屋にお勧めしたい隠れ家的な離島だ。那覇在住者にとっては、自家用車で
行けるというのはちょっとありがたい離島である。
沖縄本島の北西30kmに位置している。他の島から離れているから、悪天候の時に渡り鳥
が入ってくる確率が高いかもしれない。南北8km位で、総面積は効率よく可能
性の高い場所をチェックするのにちょうどいい大きさと思えた。南北に細長いために、南北
の岬に鳥が集中しそうな気がするが、どうだろうか。北端の岬や、南端の野甫島もねらい目だろう。
環境の多様性も高く、田名湿地周辺の広大な水田地帯は素晴らしい。山間の林道はカラ
スバトもいるという(未確認)。野甫島と伊平屋島は橋でつながっている。
浜に打ち上げられた珊瑚の欠片がきれいだ。島の人は人柄が素朴。地酒がある。イヘイヤ
トカゲモドキという珍しいは虫類がいるらしい。残念ながらハブは多い。晴れているときは、
海の青色が遠浅の白い砂に映えて美しい。
キャンプ場も完備しているし、民宿もいくつかある。
(1)H23年10月9-10日
那覇から運天港までは高速経由で2時間弱。運天港までの道がややわ
かりにくい。「まるみや」という沖縄そば屋を右折するのが目印かもしれない。
1100運天港発、1220伊平屋着。
島のレンタカー(46−2090)は借りず、乗用車をフェリー(0980-46-2177)で輸送した。
往復15000円(運転者込み)。運天港での駐車代500円。乗客一人往復だと5000円。
伊平屋観光ホテル(46-2123)。飯はまあまあ。工事業者がたくさん泊まっていた。キャンプ場完備
シベリアムクドリを早朝に野甫島で見た。宿に戻って朝飯を食べた後、しばらくタシギ
などを水田地帯で見たり、林道の展望台からサシバの汎翔を見ていると、土砂降りになっ
た。視界ゼロ。公園の駐車場で雨が止むのを待った。2時間ほど待つと止んだので再び水
田巡りをしていると、タシギとツメナガセキレイの数が増えていた。見えるところに出て、
羽繕いに忙しい。何か出るという予感の中、遂にセジロタヒバリが出た。見た瞬間に顔の
形だけでも確信できた。
港に行くと、船が故障で来ないという。代わりの船が伊江島から来てくれるそうだ。い
つ来るか分からないので港で2時間、漫然と時間を過ごした。離島はこういうことがあるのだ。
帰りの船は、追い風・追い波だったので、余り揺れなかった。海鳥は一回だけ出た。腹
が白いのでオオミズナギドリかと思ったら、飛び方が違う。初列の白斑がないトウゾク類。
シロハラトウゾクカモメ成鳥2羽だった。
(2)H24年春
ヤツガシラは50羽以上居た。すごい。
(3)H24秋
オオムシクイ(後日、音紋判定で確認)。カッコウ幼鳥、ヒバリではないヒバリ類、
マミジロタヒバリ、上空を通過していくアトリ類、サシバなど。
22.粟国島3月30-31日、セスジコヨシキリを見た話。
島の概況:
沖縄県粟国島は周囲20kmしかなく、徒歩でもなんとかなるかな。島の大きさが小さく、
周りに他の島が無いことから、いろいろな珍鳥が出ている穴場だ。
一日にフェリー1往復、飛行機3往復。民宿多いが観光客は少ない。
飛行機:
イギリス製のアイランダーという離島用の飛行機。低い高度を250kmhで飛ぶ
250馬力×2の10人乗り(パイロット1名を含む2×5列の座席)。乗る前に体重を計り、
体重で席を決める。機内に通路は無く左右のドアから乗る。パイロットの隣の席は絶景。後
ろの席も窓が大きく、下の方が見えるのでクジラとか海鳥とかも見えそうだ。さすがにこれ
らは見なかったが、コバルトブルーの環礁の上空を経由し、25分という短い時間に海の美しさを満喫した。
ブリキのような愛らしい飛行機で、最高に楽しかった。片道約7500円でこれは安い!
鳥の概況
キマユムシクイが多く、沖縄本島とは渡りのコースが違うように思えた。
本島の西側に位置する久米島・渡名喜島・粟国島のラインはかなりの珍鳥が記録されている。
島の西側は標高が高く、東側はサトウキビ畑と、フラットな牧草地になっている。高い山は無い。中央に自然林
に囲まれた池があり、御嶽(うたき)の森林がベルト状に連なっている箇所がある。大きな貯水池には意外な水鳥が入るかもしれない。今回はセスジコヨシキリの他は特記すべき鳥はなかった。
セスジコヨシキリ:
Speckled Reed Warbler または Streaked Reed Warbler (Acrocephalus sorghophilus)
目の前に止った鳥は背中の筋が明瞭でセッカによく似ていた。しかし嘴が大きく、セッカではないと感じた。
全体の構造的印象もセッカではないと思い、尾を見ると帯がない。足の色が明るいオレンジ色
ではない。目が黒い。すぐに藪の中に消えた。声は無かった。写真も録音もなし。
東ヤマトゥガーという場所。
宿のおばあのお話
昔、竜巻で馬が渡名喜島まで飛ばされたことがあるとかで、カゼが強い日は竜巻が怖いそうだ。
朝になると正装したおばあが集まってきた。「拝み」のため、本土から来た島出身のユタの皆様だそうだ。
島には拝所が多いが、そこに三本足の猫がいたら、手を突いてお辞儀をしなければならないそうだ。しないと怖い目にあうそうだ。
23.NYマンハッタンのセントラルパーク探鳥会に参加した。


マンハッタンのセントラルパークは東西800m、南北4km。マンハッタンの地図はこの
公園の大きさが物差しになる。ここではボブさんの探鳥会が定期的に催行されている
(http://www.birdingbob.com/)。
記録リストの「良い鳥」にビビっと来た私は予定を変更して飛び入り参加した。
セントラルパークの北東にあるコンサバトリーパークの「鉄の装飾つきゲート」に9時集合。
地図を見て行ったらすぐにわかった。時間前にぶらついていたらアカオノスリが出た。西海岸
で見た個体とはかなり違っている。
主催者ボブさんがアジアに行っているため、代わりのデボラさんがリーダー。望遠ストロボ付
きの400ミリを抱えていた。参加者は私も含めて17名。時間通りに9時スタート。概ね3−4時
間かかるが、途中で帰るのもOK。
東の5番街側をスタートして西に向かうのはなるべく太陽を背にするためである。効率よくスポ
ットを回ることで次々に鳥を発見できた。ヒタキ類が4種も出たが、梢先の識別は逆光で難しい。
デボラさんのデバイスは逆光でも特徴を捉えた写真を提供して細かい識別点を指摘してくれた。
野鳥誘致のための造園デザインが凝っている。ベリー、ナッツ、草の実、ひまわりなど、鳥の
餌になる植物が要所要所に生えている。それらは10m四方位でフェンスで囲われている。サ
クランボが生っているところでバルチモアオリオール(大リーグの球団名と同じ)、オーチャード
グラスが密集しているセクションでイエスズメの群れの中に地味なVesperSparrow(タヒバリシト
ド)を見つけられた。また小川の周辺は下草及び下層木を自然のままにしてある。上空から見る
と、いかにも水が得られそうに見えるので、渡り途中の小鳥が降りてくるのである。日本にもこん
な公園ができないものだろうか?
タナジャーとかオリオール(両方ともムクドリの1種)とか未知の鳥の識別は中々難しかったが、ベ
テランの参加者が親切に教えてくれた。
人と情報が集まるところに鳥を見に行くのは、未開の地に乗り込んで行くのとは全く別の喜びがあ
る。
ところで、アメリカの都会は公衆便所が少ない。地下鉄では警備員を見つけて鍵を開けてもらわ
ないとトイレにありつけない。NY地下鉄ではほぼ無理。地下鉄外のカフェを使用すべき。前出の
HPには野鳥情報のみならず、公園内のトイレの位置や現地への交通手段も詳しく書かれていて
参考になった。
<Bird List>:私が見た鳥のみを記載。
Red-taied Hawk アカオノスリ
Northern shavelerハシビロガモ
Wood Duck アメリカオシ
Mallard マガモ
Morning Dove ナゲキバト
Northern Flicker ハシボソキツツキ
American Robin コマツグミ
Eastern Kingbird オオサマタイランチョウ
Eastern Wood- Pewee モリタイランチョウ
Yellow-bellied Flycatcher キバラメジロハエトリ
(下嘴の先端が黄色いことで識別、デボラさんのカメラが効果的だった。)
Red-eyed Vireo アカメモズモドキ
American redstart ハゴロモムシクイ
Northern Cardinal ショウジョウコウカンチョウ
Baltimore Oriole バルチモアムクドリモドキ
Rusty Blackbird クロムクドリモドキ
Summer Tanager ナツフウキンチョウ
Starling ホシムクドリ
Vesper sparrow タヒバリシトド
House Sparrow イエスズメ
Rose-breasted Grosbeak ムネアカヒワ
Gray Catbird ネコマネドリ
Blue Jay アオカケス
24.台湾の野柳で「黄眉不是(キマユじゃない)」と叫ぶ。
台湾で渡り鳥の記録が多い「野柳」はイエリョウと発音する。
日本からのアクセスは意外と良い。台北桃園空港から台北駅まで1時間、さらにバスで1時間。
台湾本で見た野柳のサバクムシクイの写真にジーンと来た。完全に油の落ちた羽毛で恨めしそうな三白眼で、呪われた珍鳥は俺だけじゃねえ!とでも言っているようだった。
今回は基隆(キールン)のビジネスホテルをベースにした。台北から基隆までバスで1時間、野柳まで30分。小雨が続いている。前線が停滞すれば、渡り鳥も滞留する。よし!。野柳は1.7km、幅200mの細長い半島だ。
まな板を斜めに太平洋に突っこんだような半島で、北側が絶壁で南側はなだらかなスロープになっている。この地質学的なクリティカルポイントは、奇岩怪石が連なる観光地でもある。入場料は80元。入場は7時半から17時まで。18時くらいまでが開園時間だ。
半島の奥の方は人は比較的少ない。トイレ周辺の森に鳥が多いと台湾ガイドブックには書かれている。渡り鳥は水が欲しいので、水気のありそうな黒っぽい植生がライン状に連なっているのを見て上空から見て降りてくる。台湾人バーダー数人と出会った。
この近くにお住まいのR先生は野鳥の写真は撮らないけど、撮りに来た人を指南していい写真を撮らせるのが趣味である。こういう面倒見の良い人をフランスでは「麗しきクロウタドリのようだ」という。私もご指導を賜ったが中国語なので99%わからなかった。3月より4月の方が鳥が多いとのこと。コグンカンドリはよく漁港に入るということだったが、今天有没(今日はいない)。基隆の近くの宜蘭というところでオジロビタキが出たそうだ(写真を見る限りニシではない)。
メジロが多い。渡り期のムシクイ類はメジロの後をこっそり追っていることがよくある。そのようなときムシクイは鳴かないことが多い。案の定、探してみるとキマユムシクイがいた。
次の日もキマユらしきものがいて、メジロがいなくなると、チュイーという声を出した。しかしトーンが低く、さえずり出したのは全く違う声だった。R先生との会話で覚えた中国語が自然に口に出た。
「黄眉不是:ホヮンメイプーシー!」
黄みがなくキマユではない二本翼帯のムシクイって何!。隣の台湾人カメラマンに撮影を任せて録音を優先し、後から撮影に参加。ガジュマルの葉に隠れるのでなかなか写真が撮れない。下嘴半分が黄色、腹部と下尾筒が白色なのでバフイロムシクイでもない。
たぶんフタオビヤナギムシクイだ。ヤナギムシクイの可能性も否定できないが、分布から言ってフタオビだろう。 R先生いわく、フタオビヤナギはここでは4回めだとのこと。なお、この個体は夕方4時まで4回出てきたがやはりほとんど撮影できなかった。台湾人も失敗。後日録音も失敗していたことが判明!

カラフトムジセッカのようなのも出た。目先の眉斑がバフ色だが、嘴が細くて(カラフトの中国名は巨嘴柳鶯)、下面の色が汚白色系、過眼線と眉の形からも、たぶんムジセッカだ。愛想の良いルリビタキも何羽かいた。

野柳のバス停にたむろしているタクシーの運将(ウンチャン:日本語が台湾語化した単語)いわく、6時以降はバスが減るからタクシーにしたほうがいいと私の耳には聞こえた(信じないでね)。「我要公車」(我はバスを要す)と言い続けると、この人は300元って言ってるよ、ほらこっちの人は250元って言ってるよ!と2人の運将が掛け合い漫才のように値下げを始めた。結局、タクシーで基隆まで帰った。ちなみにバスは30元。台北駅行きは70分で便数も多かった。 とにかくLCCの就航で関西以西から行きやすくなった台湾に私は注目している。
参考文献
Birdwatching in Taiwan, Wild Bird Society of Taiwan
台湾野鳥地図 周大慶、謝宗宇 晨星出版
25.冬の香港でムシクイ三昧


香港はホテルの相場は高い。インターネットで日本のビジネスホテル程度のものは取れた。部屋狭い。
新界のMTR駅の近くに宿を取り、地下鉄で探鳥地をめぐった。両替1HK=16.3円。
ターゲットはムシクイ。5種類(キマユ・カラフト・オジロ?・シセン?・ウスゴシ)を見ることができたが、小さく
てすばしこいので識別には望遠レンズと録音機が必要だ。後3種は日本に来ることがあるかもしれない。
イルカ観察は尖沙租のホテル集合で、バスで移動。4時間のオペレーション。30フィートくらいのボート。
イルカは見られなかった。香港の湾は海洋汚染が深刻で、イルカの第一仔は汚染された母乳ですべて
死んでしまうそうだ。海上でのコシジロアジサシのピークは8月下旬とも言われているが台風シーズンでもある。
12年ぶりのマイポ。川向こうの深センは、高層マンションだらけだ。九龍公園はインドネシア人で超満
員。中国の大都市は食事とマッサージが楽しみだ。インスタントコーヒーとホットミルクティをまぜた鴛鴦
(おしどり)という飲み物があった。四川料理の辛味のニュアンスは日本では味わえないアジだ。年甲斐も
なく歩いたからマッサージでは、すごい疲れてますね、ソルジャーですか?と聞かれた。マッサージは痛い
けど効いた。今日はよく眠れますよと言われた。まさにそのとおりだった。
香港では公衆便所が少ない。というわけで、「チャジョーナーリー(北京語だ)!、トイレどこですか!!、
もれそうです!」と叫んで人家に押し入った強盗が逮捕されたそうだ。
I visited Hong-kong in winter, Dec.26-30 2014.
Some good web site makes this hot spot better than the other Asian places for birding.
The first day, I bought map of Hongkong to point the destination to taxi driver .
2nd day,Tai-po-market大埔墟 Nature Reseave is mountanious field. I took a taxi and pointedentrance
of the Area on the map at MTRstation.
I took BROWN route of 7km. Actually It took 6hours to walk out because
of too much good birdthere.
3species of leaf-warbler were seen. But some birds is hard for me. Specurated
to be 'Chinese'
シセンムシクイ or 'Lemon-rumped'ウスゴシムシクイ.
Leaf warblers are one of the frontier for me in this area. High performance
gadgets will be needed.
After then I added the target to Sha Lo Tung沙螺洞, But new building was cutting
the road and couln't
reach there.
3rd day, I was picked up in front of Kawloon Hotel 九龍酒店 at 尖沙租 to join the tour of dolphin
watching. Pink dolphin is speciality of 3rd day. It is threatned in poluted sea in Hongkong.
We couldn't see it. 4hours operation. If it's late August, Alutien tern
will be expected.
4th day, I visited Maipo Nature Reserve. We need to make a reservation.
But OK!?. White-taied
オジロムシクイ and Blyth's warblerヒマラヤムシクイ were difficult to told from. Should
atention to their behavior.
26.シンガポールのウビン島・植物園・スンゲイブロ
17年ぶりのシンガポール。この国は一人当たりGNPは日本より上になった。関空発
のシンガポール航空のエアバス380に乗りたかったが人気が高く、2ヶ月前なのに予
約が取れなかった。直行便/ビジネス客の需要が多いのだろう。
シンガポールの野鳥観察のアドバンテージは、英語を使用するハイレベルのバーダ
ーが情報を発信していること。目的の鳥が生息していれば、その目的を達成しやすい。
私の目的は、サンバード(タイヨウチョウ)、マダラチュウヒ、フルーツダブ(ハト)、
それとメボソムシクイ上種である。
そのために、植物園、チャンギ埋立地、ウビン島、スンゲイブロを選んだ。
個人的に案内してくれる経験豊かなガイドもいる(ネットで検索してね)が、今回は頼ま
なかった。
<植物園>
美しいコアオバトを撮影しながら、赤いヘリコニアのセクションへ。しかしサンバードは
来なかった。遠くの梢に出たのみ。帰り道にサンバードが近くに寄ってきた。キゴシタイ
ヨウチョウ=クリムゾンサンバードだ。
雄の上半身は赤を強調した仮面ライダーV3の様にかっこいい。深紅の中に瑠璃色
と朱色のストライプが入って精悍さを強調している。ヘビのように長い舌をベロベロ出
している。これがあるから嘴を花弁構造に深く差し込まないのだ。なるほど。
赤い花に来る黄色いサンバードを期待していたが、黄色い花に来る赤いのが撮れた。
現地バーダーと情報交換した。この人は汗をかくのが嫌なので歩かずに一日中座っ
ているそうだ。私は「良き兵士とはよく歩く兵士である」というナポレオン陛下のお言葉を
信じていたが。こういうスタイルは熱帯ではいいかもしれない。しかし、この人の行動力
は旺盛で、アジア各地の有名場所を歴訪している。
チャンギ埋立地は空港の向こう側にあり、イーストパークからの貸し自転車でのアプ
ローチを考えたが、今期はダラチュウは出ていない。それどころか工事が始まって不可
逆的に環境が悪化しているとの情報で結局、諦めた。
<ウビン島>
ウビン島へは、定員12人の木造船、運賃3ドルの船が不定期に出る。人が集まれば
逐次出港。到着してすぐ、カササギサイチョウが出た。幸先がよい。
レンタサイクル8ドルなり。アオサギの中に変なのがいた。Great-billed Heronスマトラ
サギ。アオサギよりも淡色だったのは意外。
サメビタキのようなのは、違和感がびんびんでBrown-streaked frycatcherと思われる。
スプリットスピーシーズだ。和名は、ミナミコサメビタキ(センスがない和名でしょ)。
野生のセキショクヤケイは、やっぱりコケコッコーと鳴いていた。ドラミングも。
気温が急に下がるとスコールの前触れだ。ドバーっと来た。
見せてもらおうか!シンガポールの折り畳み傘とやらの性能を!
<スンゲイブロ>
地下鉄クランジ駅(ブギスから40分)からバス20分。近くのクランジ湿地では、近年、
体重400kgのイリエワニの死体が見つかったことがある。こえー! スンゲイブロで実際
に、4mオーバーのワニを2匹も見た。
ワニに注意との看板も見た。ワニは獲物を水に引き込みツイスト回転して関節をはず
して無力化を計る。対策はワニに抱きついて回転に耐え、口の奥に手を突っ込むことだ
そうだ。水を飲み込んでしまうため、ワニは驚いて離してしまうことがあるとのこと。万が
一の時にはぜひお試しあれ。
しかし怖いのは蚊だ。デング熱・マラリヤ等を持っている。虫除けは必須。汗で流れる
ので、少し刺された。
2mサイズのミズトカゲはたくさんいる。こんな奴が越冬地にいるから日本のクイナ類も
警戒心が強くなるの だろう。
5種類の小鳥の混群が突然現れた。メボソムシクイ上種が含まれていた。撮影と録音
に成功!3種のうちどれか後で調べよう。こんな地味な種が、赤道でこんなカラフルなお
友達に囲まれてにぎやかに鳴き交わして生活しているというのは想像もしていなかった。
サンバード、サイホウチョウ、そしてコノハドリ類。こんな派手なバードシャワーは一日2回だけ。
ところでインドトキコウとシロトキコウがタイの動物展示施設で交雑種を作り、逃げ出したも
のがスンゲイブロウに多数棲みついている。純粋種はここではどちらも稀。そしてシロト
キコウは絶滅危惧種である。シンガポールは移入種についていろいろ考えさせられる。
<シンガポールの生活>
現地の新聞テレビでは天気予報が全く無かった。もしもあったら雨季になると、
「今日の降水確率は100%、くもり時々晴れて時々雨でしょう」と同じのが毎日続くだろ
う。チキンライス(ハイナンチーファン、海南鶏飯)はシンプルで奥が深い味わい。ラクサ
は、トムヤムクンに沖縄そばを入れたようなもの。庶民料理は安いが、酒類と洋食は日
本より高い。
言論の自由が保証されてないため「南の北朝鮮」と揶揄されているが、英字新聞を読
むと政府の意向をそのまま流す感じは、日本の大新聞と大差ないと感じた。
27 シンガポール旅行(12月)の鳥類リスト
シロハラクイナ シロハラアオサギ アオサギ ササゴイ ダイサギ チュウサギ コサギ
ヨシゴイ ムラサキサギ リュウキュウガモ セキショクヤケイ ハヤブサ ツミもしくはミナミツミ シロハラウミワシ
シロガシラトビ ミサゴ ハチクマ シロハラクイナ チュウシャクシギ コアオアシシギ アカアシシギ、
イソシギ ムナグロ ベニバト チョウショウバト キンバト コアオバト ブッポウソウ
サンショウクイ カササギサイチョウ コムシクイ サメビタキ ミナミコサメビタキ オニカッコウ キマユムシクイ
セアカハナドリ ジャワハッカ カバイロハッカ ミドリムクドリモドキ イエガラス ハシブトガラス ハチクイ
アオオハチクイ キゴシタイヨウチョウ アオガシラタイヨウチョウ ノドアカタイヨウチョウ ハシナガチビタイヨウチョウ シロビタイムジオウム ダルマインコ
マミハウチワドリ ブッポウソウ アカガオサイホウチョウ メボソムシクイ コムシクイ ルリコノハドリ マングローブセンニョムシクイ
ナンヨウショウビン カワセミ シキチョウ アミハラ、マレーアナツバメ、スズメ、オオギビタキ、シロボウシゴシキドリ
ムネアカゴシキドリ シマベニアオゲラ アオハウチワドリ コウライウグイス インドトキコウ交雑種 ドバト
<印象に残った鳥>
(1)Pink necked Green D コアオバト 雄雌幼鳥でかなりのバリエーションがあり、どれも実に美しい。
台湾では記録アリ!与那国島で期待したい!
(2)Germain's swiftlet マレーアナツバメ 唾液で巣を作る。巣は一応食えるらしい。
高級なのはジャワアナツバメで数倍の値が付くらしい。
(4) Ioraヒメコノハドリ およびGerygoneセンニョムシクイ
世界的に見ても腹部が黄色い鳥は多い。下痢して死にそうと思われることで捕食者を
避けるとか?毒鳥への擬態? かつてブラジルに行ったときに、ブラジル人は腹の黄色い鳥を
すべてベンテビーと呼んでいた。
(5)メボソムシクイ上種:かなり普通に越冬個体が見られた。文献ではスプリットした
3種の区別はされてないが、録音できた3個体を声紋分析すると、すべてがコムシクイだった。
<今回見られなかった鳥で興味深い鳥>
(1)シロアゴヨタカ チュウイーと鳴くそうだ。最近シンガポールで増えてきている。昔はいなかったそうだ。
台湾でも増えており、夜うるさいから駆除しろと苦情があるとか。そのうち先島諸
島でも記録されるだろう。
(2)コウライヒクイナ SGのバーダーがレベルアップして普通にいることがわかったらしい。オオクイナ
に似ているが、最新情報からオオクイナとは鳴き声も生態もかなり違うような印象を持った。
オオクイナとヒクイナの中間のような存在なのかもしれない。
(3)タカサゴクロサギ 稀だけどコンスタントに記録が出ている。
(4)ヒメクロウミツバメ:9-11月にシンガポール海峡(南の方)でかなり見られるという。
今後の情報収集に注目したい。ビンタン島とかのフェリーはどうか?
(5)コシジロキンパラ:沖縄では、これが外来種なのか議論しているうちに激減してしまった。
SGでも激減している。ウビン島に少数がいるらしい。
(6)コシジロアジサシ:9-10月と春に少数がコンスタントに見られている。香港でも記録がある。
(7)毒々しい緑のサトウチョウを見たかったが、見られなかった。椰子の木についているそうで、惜しい。
28.四川省峨眉山を目指して 2017年7月
 写真はカオジロガビチョウ。
写真はカオジロガビチョウ。
中国の英語情報がここ数年で急に向上し「良い鳥」の情報が得られるようになった。今や中国人の質×量
の英語力は日本人を上回るだろう。中国人大卒者に聞くと大学の勉強はかなり厳しいらしい。そして大学
進学率は40%を越えて、上昇中だ。
関空から南京経由で成都(チェンドゥー)。飛行機は同じだが、南京で降りてパスポートチェックを全員受け
なくてはならない。これを知らず、しかも放送を聞き逃し最後に降りたため、案内係の航空会社職員が居な
くなっていた。言葉がわからないのに深夜の南京空港を独りでさまよった。幸い英語をしゃべれる親切な人
がゲートに連れて行ってくれた。危なかった。成都空港では大阪(ターパン)から来たひとはこちら!という
中国語を聞き取れず、違う列に行きそうになった。成都のターミナルからホテルまではリンタクに付きまと
われた。うっかり乗ったらヘンなところに連れて行かれていたかも。
成都の午前中は三国志の博物館に行った。桃の木の下に義兄弟×3の石像(カッコイー)、諸葛孔明は
300年前からイメージが形成。炎天下には劇辛の坦々麺!やっぱり本場はいいですねえ。屋台のサンマは
秋刀魚と書かれていて大人気。日本近海(公海)で取れたものだろう。
成都からバスで峨眉山市まで。バスの時刻表はガイドブックのと違って困惑。列車に変更すべきだったか。
7時間後の時刻表にないバス。途中で降ろされて白タク?に詰め込まれて良心的な追加料金10元を取ら
れた。状況不明白。とにかく峨眉山市には着いた。ホテルの場所を聞くと三路向う、というので行ってみたら
簡単に見つかった。商店で冷えたビールはありますか? ヨー!(有!)という元気な返事に救われた気がした。
明日はムシクイの聖地、峨眉山だ。がんばろう。
29.ムシクイ仙人を目指して中国峨眉山で修行 7月
前日夜、成都から峨眉山市に到着して峨眉山市に宿泊。
本日は早朝からバスに乗って標高2400の雷洞坪(レイドンピン)まで。途中停車の休憩中、トイレに行き
たくなったが、バスに置き去りにされたら大変だ。隣の人に「我去洗手場ウォーチョーシーショウジェン」と声を
かけていった。「地球の歩き方」の語学指南ページを丸暗記したのが通じた!カンタンな中国語の成否でひど
い目にあう可能性はある。ゲートで下ろされて、185元(3500円)もの入山料を支払った。中国人も払っている。
恐ろしいことにバスに戻るときにバスの車両ナンバーを覚えてないとバスに戻れずに迷子になることがある。
ナンバーを中国語で言えるかな。
雷洞坪(レイドンピン)午前9時半。早くも腰の白い丸い体型のムシクイ!長年私があこがれていた鳥らしきもの
がうようよいる。しかし天気が良すぎて?たくさんの観光客が登山道に殺到し大声で鳥を飛ばすのだ。(加油!
→がんばれ!)。まるで満漢全席のご馳走が並べられては、次々に水洗便所に流されていくような気がした。
録音しても大声の中国語に邪魔された。しかし、後から映像と録音を振り返ると、ウスゴシムシクイ、シセンムシクイ、エメ
イムシクイ(仮称)、およびヒマラヤムシクイが!!バフマユ・キバラもいた。異常に人馴れした個体を近接撮影。黄金色
のマユグロモリムシクイは美しかった。午後4時に接引殿(雷洞坪から1km上)まで下ってきてヤナギムシクイ?らしきもの
を近接撮影。なんとムシクイ類だけで8種類。その他11種。不明種多数。売店は数多く、食料を持っていく必要は
ない。
人のめがねを奪い取る猿がいるという悪い噂もあったが、私の眼鏡は大丈夫だった。ただ1000mはあろうか
という大絶壁を悠然と移動する猿を見た。ニホンザルより大きい。「珍愛生命、柵乗り越えること無かれ。」という
中国語の看板が読めなかったのであろう。
ウスゴシムシクイ Lemon-rumped W 録音
シセンムシクイ chinese leaf-W 撮影 録音
エメイムシクイ(仮称)Emei leaf-warbler 録音
ヒマラヤムシクイ Blyth's leaf-W、おそらく分布からclaudiae、撮影、接引殿より下。
マユグロモリムシクイ Goledn spectacle warbler視認、撮影
バフマユムシクイ Hume's leaf warbler 録音
いったん下がって上がるチュイという地鳴き。キマユとは違うチュイ。
キバラムシクイ Tickell's Leaf-warbler P.affinis → 最近ではスプリットしてalpine leaf-warbler
といわれることが多い。 録音ハクセキレイのさえずりのような声、視認
ヤナギムシクイ Greenish warbler 撮影
<ムシクイ以外>
ハシブトガラス
アマツバメ
ヒガラ
ハイイロカンムリガラ
シロエリカンムリチメドリ
ホトトギス
メジロ
キバラウグイス
カキハガビチョウ
ミヤマウグイス 眉斑が白い。喉が白い。
キバラウグイス
30.四川省峨眉山で録音したムシクイ類について
今回確認した8種のムシクイのうち6種の録音データのメモ。
song・callはhandbookの記述抜粋、感想は実際の録音データとxeno-cantoを聞き比べたもの。
ウスゴシムシクイ、エメイムシクイ、バフマユムシクイ、キバラムシクイについては撮影できなかったので、参考程度とする。
ウスゴシムシクイ Lemon-rumped W 録音
song:単調なラトルの後に低くて長いピッチ。tsirrrrrrrrrrrrsisisisisisisisisi
別タイプ:非常に長く続くシャッター音tsetse tsirrp tsitsitsi
call:ハイピッチのpist・psit
感想:尻上がりの短いチュイ、キマユとは違う感じ
シセンムシクイ chinese leaf-W 撮影 録音
Song:特徴的な金属的な機械的な音、tsiridi tsiridi tsiridi(切迫した感じの尻上がり)
call:様々なタイプの tsuee tsuee tsuee
感想: フィフィフィ(地鳴き)
エメイムシクイ(仮称)Emei leaf-warbler 録音
Song:オジロ・ヒマラヤと大きく異なる。trill 4-6KHz
Call:tu-du-du
感想:スズメのような声、シシシシシシ。
ヒマラヤムシクイ Blyth's leaf-W、おそらく分布からclaudiae、撮影、接引殿より下。
Song:callを引き伸ばしたようなpi-che-ee
Call:音節不明瞭なpi-cha
感想:エゾムシクイのような声。
バフマユムシクイ Hume's leaf warbler 録音
song:地鳴きに似たweesoo または長いフェイドしながら下がるeeeeezzzzzzzzzzzz
call:tooee tsui chwee,キマユより乾いた声、スズメのようなchirp
scewp (mandelliiはtiss-yipと鳴く)、seest sweest 短フラットな声
感想:いったん下がって上がるチュイという地鳴き。キマユとは違うチュイ。
キバラムシクイ 2度視認、撮影できず。半信半疑だったが録音でさえずりが入っていた。四川省、甘粛省などのは
スプリットしてAlpine Leaf-warblerとされるようになってきている。
song: chip-whi-whi-chi-chiという速い連続ノート
call:スズメのようなchep,chi,sit,など。
感想:ハクセキレイのさえずりの様な連続ノート。
31.峨眉山の山麓、報国寺と伏虎寺、7月
峨眉山ろくの観光基地、峨眉山市。朝から昼過ぎまで、標高400-700m程度の低山。ムシクイは少ない
が日本にはいない鳥が楽しめた。前日の亜高山帯の鳥とは全く違う亜熱帯の鳥である。沢沿い
のエンビシキチョウ類が2種、カワビタキも。
中国絵画でよくモチーフになるサンジャクは三尺の尾を優雅にゆらして五言絶句のリズムを刻んで
いた。あの杜甫先生は四川省成都にも居たことがある。
今回の旅を総括して、英語をしゃべれる中国人は日本並みに少ないが、英語堪能の中国人からは、
日本人って、なんでそんなに英語がへたなの?と聞かれた。中国の大学進学率は4割を超えて増加中。
私の丸暗記中国語は意外と役に立ち、同じ漢字文明圏なので筆談も「可以」。だが台湾で通じた
言葉が通じないことも多かった。支払いで値段を聞き間違えて、しこたま叱られた。四スーと十シーが
むずかしいんだよな。
中国人はみんなスマホを持っており、すぐに中国語を変換して英語で示す。また峨眉山の
標高約3000m地点で日本からの電話が携帯に入った。すげー
成都ではシェアバイク=モバイクが普及し、オサイフ携帯のみで現金を持たない人が急増。
中国のIT化は日本より進んでいる。もともと中国は儒教の国で礼節の国だったが、文化大革命で
人が人を信用しなくなった。「信用の希薄」を背景にITが創造する信用システムは瞬く間に広がった
のだそうだ。民泊にも注目だがちょっと怖い。
さて今回は雷洞坪から報国寺までのエリアを探索しなかったし、キツツキ類など見落とした鳥も
多い。言葉のストレスが多かったが、四川省!また来たい。
チャイロサンショウクイ
サンジャク
シロクロヒタキ 私に気を取られてヘビに襲われそうになった。
セアカエンビシキチョウ
クロヒヨドリ (白頭型で台湾のとは違って面白かった)
カヤノボリ
カッコウ
ホトトギス
スズメ
コシジロキンパラ
ハクセキレイ
シキチョウ
カワセミ
オニカッコウ
コサギ
ズアカチメドリ
シロガシラ
カオジロガビチョウ
カンムリオオタカ
コシアカツバメ
イワツバメ
カノコバト
ギンムクドリ
オオルリチョウ 沢にいた。
不明ヒタキ 幼鳥?
チョウセンウグイス callのみ。
エンビタイヨウチョウ
ズアカエナガ
カワビタキ
カノコバト
ウンナンゴジュウカラ 独特の声。
ドバト
コジュケイ
32. 厳寒期のソウルでヤマヒバリを見たい作戦。
韓国ではヤマヒバリは普通の冬鳥だそうだ。これを見たくて週末の電撃作戦を試みた。
とりあえず有名なハイキングコース北漢山ブクハンサンに行くことにした。エアソウル航空券は
往復2万円台前半だった。
12/7(金) 高松1135ソウル1320着。
仁川空港からソウルまでは高速バス。車内トイレはないが快適。この区間の高速鉄道はバスの
利便性に負けて廃業したそうだ。高速鉄道 の運営は難しい。台湾の高速鉄道も赤字らしい。日
本の長崎新幹線、四国新幹線は大丈夫か?
広大な黄海の干潟をバスから眺めるとモンゴルカモメらしきものもいた。
ホテルは東横イン、外国にきた感じがしない。
12/8(土) 北漢山と三枚肉
朝の気温は当然マイナス10℃以下。筋肉が引き締まって坐骨神経痛が消滅して体調はすこ
ぶる快調。地下鉄3号線 市内から旧把撥クパバル駅まで30分。山城入口までバスのバスは
20分くらい。バス704番線はすぐ判ったが、上下2つあってどちらかわからなかった。ハングル
は覚えたが、不勉強で意味まではわからないのである。タクシーは近すぎるせいか乗車拒否。
韓国人も拒否されてた。
バス待ちの登山ルックの人に聞くと親切に付いて来いとのことで、問題解決。以下のホーム
ページにも登山者についていけば間違いなし と書かれている。
http://english.knps.or.kr/Knp/Bukhansan/Intro/Introduction.aspx?MenuNum=1&Submenu=Npp
山頂まで5km強で、山頂までの標高差は900mくらいと急勾配。カササギ、ダルマエナガなど
楽しみながらゆっくり登山。標高700m付近 でヤマヒバリ5羽の散開した群れに遭遇。しかし近く
に寄らせてもらえなかった。カラ類はハシブトガラ、シジュウカラが多く、ヤマガラ・ エナガもいた。
キツツキ類はアカゲラ・オオアカゲラ・コゲラが多く、ヤマゲラもいた。ハイガシラコゲラは見なかっ
たが、念頭に入れるべきか。
夕方市内に戻って疲労がどっと出た。焼肉店は外国人のあしらいに慣れていて問題なし。豚
三枚肉サムギョプサルはキムチと野菜がどっ さり付いて来た。美味。汗蒸幕チムジルバンは
韓国式スーパー銭湯で、地元民のまねをしていれば問題なし。900円。ドーム状の低温サウナ
は、麻袋の床にこだわりがありそうだ。岩盤浴に似ている。安眠用の穴ぼこは閉所恐怖症の人
には厳しいか。
12/9(日)
朝鮮戦争を描写した韓国映画ブラザーソウルを見て感銘を受けたので、三角地の戦争博物館
に行った。ソ連・北朝鮮から鹵獲した兵器が 充実していた。熱心に見ていたら、アンニョンハシ
ムニカ、と丁寧語で声を掛けられた。遺族と思われたのかも?
<蛇足>
かつて韓国大統領の金大中氏は、半島統一後は朝鮮と韓国の国名を廃してそれより一つ前の
王朝名「高麗:コリョ」にしたらどうかと提案した。「高麗連邦」は実現するだろうか。
北漢山の寺の伝説。退屈した若い王が高僧に「今日は無礼講だ。冗談を楽しもう。お前は豚に
似ている」「貴方は仏陀に似ている」「それのどこが面白い冗談なのか?」「豚は他の豚しか見な
い。仏陀は自分しか見ない。貴方も自分しか見ていない。」意味の深い印象的な皮肉である。
・・・私は自分をしっかり観察しているのだろうか?
お土産のお菓子ハニーバターアーモンドはウイスキーにとても良く合う。
小さいもち、トッポギはいろいろ使えて、鍋のシメに入れても美味。汎用性が高くて煮崩れしない。
○○ヌン、オディエヨ?(○○はどこですか?)と聞くとネイティブ韓国語で返答されて、僕のレベル
ではわからないことが多かった。
○○ヌン、チョチョギムニカ?(○○はあちらですか?)と指差すととりあえず方向だけはわかった。
33.宮古-室蘭フェリーに乗ったっつもな


苫小牧八戸航路は洋上に約7時間いるのに対して宮古室蘭航路は約10時間と長い。ウミツバメ類
を見る可能性もありか? 2018年に開設された新しい航路で海鳥観察の選択肢の一つである。
宮古のホヤのサシミは夏が旬でうまかった。生臭くて食べられない人は酢で洗って食べるとよい。
宮古ゲストハウス3710は簡素で快適。
盛岡前泊で6時ごろ発のバスだと宮古駅8時着。宮古駅発の連絡バス8時に乗れる可能性がある。
乗れなくてもタクシーが何台かいたので出港までは楽勝だろう。2kmを人力移動も可能。
朝0925出港!
海鳥の繁殖地として知られる島を掠めて太平洋上に躍り出る。期待したが、だめだった。
夜行動する鳥だから難しい。
速度は20ノットで太平洋フェリーの26ノットより遅い。屋根付きの甲板は海面に近く、
クロアシアホウドリはとても近くで見れた。
海上でオットセイを見るときは、絶滅種のニホンアシカではないかとだめもとで
チェックをしているが、それらしいものを見たことはない。耳介が大きい。色が黒っぽい(写真)。
船内の「24時間営業オートレストラン」とはレトルト食品の自動販売機があるという意味である。
カップのコーヒーはないのはゆれるから仕方ない。
14時25分、青森県沖でエトピリカ若鳥が1羽浮いていた(写真)。噴火湾の入口で、カマイルカの
大群に遭遇した。
室蘭上陸。室蘭に着いたらその日の夜発に乗って宮古港に翌朝戻るか、苫小牧のフェリーに
移動するか?地球岬で渡り鳥を見るか?探鳥をするか、いくつかの選択肢がある。
この地ではヤキトリはいわゆる豚串のことを意味するのがおもしろかった。床屋が多い。
翌日は室蘭のイルカウオッチングボートにのるつもりだったが、悪天候を勘考して休養に当て
苫小牧に移動。太平洋フェリーで、仙台へと向かった。
日の出からAM10時着岸まで特筆する鳥は無かったが、やっぱり快適な船旅だった。
34.ハワイ島でハリモモチュウシャクシギと固有種の観察(前編)
 Iiwi
Iiwi
ハワイ島における複数の英語レポートにハリモモチュウシャクシギの記録があり、しかし調べてみるとハワイ
諸島では普通種だがハワイ島では少ないと書かれていた。渡りのコースから当然だろう。だがどう考え
ても最近の自分は運が無く、その分今回は運が巡って見られるような気がした。→見れた!
またハワイ島のスペシャルな鳥はハワイミツスイ類。特にイイウィ(ベニハワイミツスイ)は見て
みたい。→見れた!
固有種ハワイミツスイ類と日本のメジロとを比較してみたら何かが発見できるかもしれないと思った。
ヒロ(東部の町)は小説家の片岡義男さんがとても誉めていた記憶がある。スコールが多いので虹
が多いとか。気候は気持ち良いらしい。コナのKONAコーヒーは甘味があって旨い。
<準備段階・ロジ>
ESTAはメルアドの入力が大文字しか出てこないが大丈夫。米国政府サイトだと14ドルで申請可能。
業者の日本語サイトだと手数料がかかる。retrieveという単語には探し出す=検索するという意味もあ
る。承認に2日くらいかかった。それまでおとなしく待つ。
成田を夜出て日付変更線を越えて、その日の朝にホノルル。乗り継ぎでハワイ島西岸のコナに着く。
乗り継ぎ時間は2時間しかない。ホノルルーコナは便数が多いから、乗り継ぎ失敗時には何とかなる
か?直行便は便利だがかなり高い。
<カノコ・ホノコハウ歴史公園>
空港で外来種の出迎えを受けてからレンタカーを借りた。まず向かったのはここ。空港に近く行きや
すい。
ビジターセンターで地図入りパンフレットがもらえた。伝統的養魚池には水鳥が多い。半日くらいで回
れる。コスズガモ、クビワキンクロ、ワライカモメ、メリケンキアシシギなど「日本人好み」のがいた。
ビジターセンターの日系人ガイドは、ハリモモは見たことがないとのこと。やっぱり少ない。一般的な
ことを聞くと日本語。難しいことを聞くと英語になる。逆だったらいいのに?
<Trail tour>
1月2日に1日ガイドツアーに参加した。参加者は私以外はアメリカ人とカナダ人。説明はもちろん
英語のみ。産業・郷土史・言語・植物・地質学など多岐にわたる解説があり、理解できた部分は
すべて興味深かった。冗談はわかりにくかった。朝食・ランチボックス付きでコーヒーもおいしかった。
参加者の数名は生物の高校教師で、やっぱり適応放散について授業で教えるから興味があるの
だろう。ハワイミツスイ類は適応放散の実例とされ、多様な形態・生態にも係わらずアトリ科である。
ガイド氏によるとハワイミツスイ類は11月から2月がよいという。花が少ないので鳥が集中して発見
しやすいからだという。4月は満開だから1日1羽しか見られない時もあるとのこと。ところがネットに
よると、プロカメラマンのジャック氏は、4月は花があちこちに咲いていて下の方にも鳥が下りてくるから
いい写真が撮れるベストシーズンだという。写真はイイウィ(ベニハワイミツスイ)。こんな顔してアトリ科
です。時折オープンスペースをひらひらと飛ぶことがあり、日本のハイタカ・ツミがいたらイチコロだと
思った。
ツアーの前日にジャングルの入り口だけアクセスしたが、道もポイントもわかりにくく、やっぱりツアー
参加は効果的であると思った。
<ハワイミツスイ類>
Jack Jefferyさんのサイトでハワイミツスイ類の基本の予習ができる。また惜しげもなく撮影方法を
公開している。日本の鳥を撮影するにも役に立つかもしれない。
<PALILLA>
ママネという植物を守るためのヤギ駆除ハンターがいるからとのことで蛍光色ベストを着て
生息地を歩いた!! パリーラはウソを大きく丸く黄色くしたような鳥だった。他の鳥が食べない
ママネの種子を食べる。ママネの種は高濃度のフェノール化合物を含む。300万年だけでこのような
耐性を得たのはすごいことだ、と言えるかどうかは、もっと調べてみないといけないけど、鳥の
生化学的研究はこの5年で発展したフロンティアなので成果を期待したい。ちなみにメジロは少なくとも
600万年以上の進化史を持つが、この成分への耐性が他の鳥よりかなり弱い。
<ハワイの生物史>
500万年にハワイ諸島が出現した。鳥類が入り始めてからは300万年しかないが、アトリ科から
数十種類もの多様性が生まれた。それは適応放散という現象と説明されている。現在では人為的
影響で多数が絶滅しているがそれでもその一部を見ることが可能である。
35.ハワイ島でハリモモチュウシャクシギと固有種の観察(後編)


<ハリモモチュウシャクシギ>
ゴルフ場で1羽見つけたら、グリーンの向こう側に去ってしまった。追いかけたら別個体が横に
いた。うーむナイスバーディー。満足して先に進み、行き止まりを確認して戻る途中に警戒心が無い
のが7羽現れた。
ハワイ島では数が少なく場所も限られているが、きっかけはたまたま帰国前日に現地の人と会話
して得た情報だった。
「〇〇リゾートになんとか車を停めて、ゴルフコースを南方向に回り込むんだ。今年はラッキーで7羽
いる。」 うーん、茶柱が立ちそう。 観察ポイントはホテル、貸別荘、ゴルフ場、フェンスおよびガード
マンで一般人がアクセスすることが制限されていた。あちこちに、「個人資産を尊重せよ」!ともったい
ぶって書かれた看板がある。しかし、その不愉快な制限のおかげで貴重な鳥が保全されているのも
事実である。越冬地では風切羽がぬけて飛べなくなる。写真の個体は初列に新羽と旧羽がある。
岩場とゴルフ場を歩いて往復しているようだ。越冬地には捕食者がいないことを前提に進化したの
だろう。
I thought Natural right is defined in the American constitution. Nations
have a right to freely
access to the ocean!
<ハワイガン>
先祖はカナダガンの系統。
人類史以前にハワイ島に定着し、水かきが退化して半分くらいになった「陸生の鳥」であったが、
19世紀以降に人的影響、外来種のマングース・野豚・猫・ネズミの侵入により減少。放鳥された一部
は先祖がえりしてゴルフ場の池で繁殖するようになった。
<メジロ>
見た個体はすべて腹はブドウ色を帯びていた。亜種メジロ?ヘリコニアあるいは在来種kea等へ
の吸蜜をみたが、盗蜜行動は確認できなかった。ハイビスカスへの盗蜜痕も無かった(n=100)。
山間部の雨林においては、蜜利用をするハワイミツスイはメジロより大きいためか、メジロの方
から避ける感じだった。声と行動に種間の軋轢は感じられなかった。
カメハメハ大王(1世)
ハワイ諸島を統一した英雄。博物館で長さ6.6mの遺品の長槍を見た。肖像画では僧帽筋上部
が異様に盛り上がっていて、あの筋肉であの長さの槍を自在に振り回したと考えると、なんとも恐ろ
しい。
コミミズク
ポリネシア人といっしょにネズミがこの島に侵入してから、この鳥も定着できるようになったと
言われている。またアメリカ人入植者が作った牧草地帯で増えたのであろう。天敵がいないので
日中にもよく出てくる。
<Hiro>
ヒロは東部の町で、西部の町コナと比べて雨が多い。元旦のためかダウンタウンはひっそりと
していた。日系人が多いためか、招き猫がさりげなくある店が多い。サーフィンでは有名な町らしい。
大きな池というか川が広くなった場所はカモ類が多く、放鳥されたハワイガンの一部も住み着いて
いる。ミカヅキシマアジが定着し繁殖しているらしい。
総括
ハワイ島は居心地がよかった。観光地のプライドによってよそ者に対して気持ち良く接しようとする
人が多く、観光客もそんな風に染まってしまうからではないだろうか。それに対して自分は英会話に
集中するあまり、会話の最後に感謝の言葉を忘れてしまったことが2回あったのが残念だった。
IPAというビールがおいしかった。オージービーフによく合う。治安が良く、レストランはどこもよかった。
コーヒーはちょっと高いがおいしい。気候も最高だった。ヒッピーという存在がここでは再生産され
続けていることにも考えさせられた。
36.奥尻島にアビ類を求めて(2022.4)


ただでさえアビ類がいそうな場所に北に帰るアビ類が加わる、そんな場所を夢見て北海道奥尻島に行ってきた。
4月中旬はちょっと早かったか。換羽中のアビ類が入りそうな浅瀬や港があって、環境的にはいい感じだった。
昼頃着いて翌朝帰るスケジュールでも、島内探索でオオハム2、船上ではシロエリオオハム1を観察した。
船上からみた個体は飛べずにばたばたともがいていて、離陸できずに1kmほどしぶきを上げていた。
換羽中と思ったら風切りの欠損はなかった。
島内情報ではアビも最近居たらしい。ポイントが分かればもっと出そう。
私は大人の休日倶楽部パスと青函フェリーを使用した。青函フェリーは片道4時間。行きはアビ類2個体。
帰りは曇っていて撮影しづらかったが20個体見た。片道なんと1500円なので、1アビ75円である。
函館港から移動しようとしたら乗る予定の1本前の列車が人をはねて運休してしまった。
新函館北斗駅から江差港までのバスは80分くらい。本数は少ない。
奥尻島には民宿ある。ゲストハウスのマスターが鳥にも理解と興味がある人で実にいい人であった。
素泊まり。近くにいい温泉がある。フェリーの港近くにコンビニがあって食料を買える。
季節の変わり目で気温が25°から8℃まで変動し寒かった。
航路は2時間ちょっと。ハシボソミズナギドリ、ウトウやケイマフリが飛んでいた。海にはオットセイとイシイルカが多かった。
オットセイは足鰭と前足を海面に出して輪を作っている個体が多かったが、これは風を受けてヨットのように進んでいるのだろうか。
植生はブナ林。周囲65kmほどで、丹念に回るのは1日では無理だが、港だけならOK。
公園で変わった行動をしているカラスを撮影したらワタリガラスだった。
ヒバリは大きい感じがした。亜種オオヒバリだろうか。
5月になると小鳥類も期待できそうだが、天売島と比べると情報の少なさがネック。
ヤツガシラとマミジロキビタキは毎年見られるそうだ。天売島よりバス行程の短いのはちょっと利点かな。
また天売と違い水田がある。何か入りそうな予感がする。渡り鳥なら南端と北端の周辺がよいかな。
奥尻島にはワイナリーがある。ぶどう生育のギリギリ限界。寒冷だからリースリングもいけるかもしれない。
クマとシカとサルがいないのは大きな利点だと思う。
ウニなんかも旨いらしい(4月は漁期外)。フェリーは江差11時発で東京や仙台からその日のうちに江差に着くのは難しい。
珍鳥目当てで離島を訪れるバーダーは奥尻島も選択肢の一つである。
37.佐渡にトキを見に行ってもいいかなあ?


Can we visit Sado island to see the Crested Ibis (Toki)
Toki is a symbol of indigenous creature in
Japan.
Color of plumage remind of Cherry blossom
that Japanese like.
They live in only Sado island in Japan
under strict supervision now.
Can we watch them as a curious ordinary
birder?
500+ population may not be enough to
maintain the number for long.
We should be careful not to disturb them.
1.See from your car.
2.Not walk in crop field.
3.Do not use flash.
We should avoid to watch during breeding
season of spring and summer.
If I can just add a point, plumage of
summer is not beautiful.
I visited Sado in the middle of October
2022. It seems to be the best season.
Rice harvests is done from September to
October. It's done mostly when I visited.
It starts to snow from late November. When the snow hides foods, Toki goes
to creeks and hard to see.
2 ferry boats go around 4 every day.
I drove my car to Niigata port and tucked it
in the ferry. It is a little bit exciting like a Star Wars or a fighter in the
aircraft carrier.
Do you know AC of Japan Imperial Navy? It
is amazing form.
Anyway, Sado is vast to seek them. Breeding
facility may be a first place to go.
Facility staffs do 'Soft Release' that
means just open the door. Toki can return to the facility,
when they starve. So, some birds may be
stuck in the field near there.
After 20 minutes got off the ferry, I
noticed 3 birds were pecking something in the rice field by chance.
Next, where I visited was 'Toki No
Terrace'. It accompanied with cage and we may see it.
From the high roof top, I looked for the birds by telescope. I managed
to find out 3birds far from there.
I approached slowly by car and I got photo.
Sado island is nice for sightseeing、Goldmine、Tarai-boat、Old
big-ship, and foods.
江戸幕府:福島と酒田の余った米を大阪と江戸に運べ。金も人も時間もやらんが、千石船を作ることは許可する。よいな!
Tokugawa shogunate:
Bring rice to Edo and Osaka. We don't supply money, labor and long period. But
we allow you to build the bigger ships(72t).
河村瑞賢:ははぁー!かしこまりました。
Mr. Kawamura (:great merchant): OK!! My pleasure!

Igoneri is strange local food. It isn't bad
taste but almost no taste. Who did invent it? What for?
Goldmine is just a cave, but historically
very important.
38.バンクーバーの冬は約3年ぶりの海外



バンクーバーは日本では「珍鳥」の鳥が見放題、しかも交通の便の良いところに探鳥地があり、情報もたくさんある。
カジュアルな海外探鳥地と言えるだろう。ホテルを一か所固定してそこからレンタカーで日帰り探鳥。オフシーズンで旅費も安い。
航空運賃は6万円なのに燃料サーチャージ12万円で、ぼったくりバーのようだった。シアトル乗り換えだと安いが
ESTA申請が必要になる。中国での感染拡大を受け2022年11月からArriveCANの申請が突然再び必要になった。
北米大陸の西海岸は冬は比較的雨雪が多い。最悪ホテルで缶詰めになることも想定される。しかしオフシーズンで
航空運賃が一番安くてお得なのが2月である。降水確率の平均は20%。気温は仙台と同じくらいかな。
写真をツイッターに乗せている。
手続きの多くはスマホ。
eTa,VisitJapanWeb,ArriveCAN,ワクチン証明、エアカナダのチェックイン。全部スマホ。
とてもストレスと時間がかかる。便利な世の中とは高血圧の頭の固い老人には厳しい。
ArriveCANは承認メールが来たがUQコードは得られなくて不安なまま飛行機に乗った。成田空港に着くとエアカナダから突然スマホ
でのチェックインを求めるメールが来て慌てた。
帰りの便も同様でなぜかワクチン証明をアップロードできなかったが、空港でペーパーを見せたら大丈夫だった。pdfを添付すれば
よかったのに思いつかなかったのだ。
帰国時に必要な厚労省のシステムはクッキーの設定を変えないと固まってしまうことがある。
日本の税関はQRコードの事前申請をしておかないと商業レーンに並ばされるので時間がかかる。不安だらけだったが空港では行き
も帰りも拍子抜けするほど簡単だった。
成田からバンクーバーの乗客は8割くらいインド人だった。その3日ほど前にインドでヒンズー教徒のお祭り
マハーシヴァラトリがあった。帰省後日本経由でカナダに戻る人のようだ。こうやって航空運賃はアップダウンするのだ。
なぜかシーク教徒もいたけど・・・・。
ベジタリアンフードはありませんか? それは事前に予約してないとだめです。という会話があちこちで聞こえた。
旧正月の前後には中国人ベトナム人が増えるのだろう。
<レンタカー・ホテル>
空港で借りたレンタカーはワーゲンの北米大陸限定車種ジェッタ。車幅が広い。予約段階ではホンダのフィットだったが変更する
かも、とは書かれていた。ナビは付いていなくて高い車種に変更しますかと聞かれて断った。
保険等の説明では1割くらいゆっくり話してくれたけど、こういう気遣いは純ジャパ(帰国子女ピープルは日本国外で幼少期を過ご
していない人をこう呼ぶらしい)
にはうれしい。心を落ち着けてマニュアルを読んで30分かけて操作を確認してスタート。
ナビは自分のスマホでやればいいのだが、信号待ちでもスマホを手にしていると捕まることがあるらしい。
カナダでは日中でもライトを付けるのが普通。停車しているスクールバスに注意。シグナルが出ていたら絶対に追い越さないこと。
ホテルはスタンレーパークまで歩いて15分の中国系の安いホテル。
wifiがあるので夜部屋に戻ったら音声をダウンロードして予習と復習。
レンタカー返却時には専用のレーンがあって誘導する標識があるのでわかりやすかった。空港で借りてよかった。ベトナム系の
店員が現れて、駐車場で手続き終了。
<スタンレーパーク>
繁華街から歩いて行ける探鳥地。海鳥も山の鳥も充実している。計画の中に入れておくと便利だ。
駐車場でドアを開けたら太った猫が温かい車内に強引に入ってきた。追い出すのに手間取っていたら、ごめんなさいねと金髪の
女性が引き取ってくれた。
海沿いに歩き始めてすぐキタホオジロガモがいた。日本では珍鳥、略してニッチン。
30分ほどでアラナミキンクロ20羽くらいの群れを発見。帰国後に写真をチェックしたらアメリカビロードキンクロの雌と幼鳥も写っていた。
カナダガンが芝生を食べていた。この地で見られたのはカナダガン亜種チュウカナダガンParvipes。宮城県で見るシジュウカラガンとは
どう違うのか?首輪状の白斑の有無がよく言われている。左右の頬の白斑が顎でつながっているかどうか注意してみたが、
つながっているものも確実かつ少数いるようだ。宮城県のシジュウカラガンはつながっていないのが確実かつ少数いる。
シジュウカラガン亜種アラスカシジュウカラガンtaverneriを探したがよくわからない。たぶんいなかった。オレゴン・シアトルとかもう少し
南下するらしい。
詳しい記述が2019年バーダー誌11月号にある。胸が暗色とは書かれていたが、これで確実に見分けられるものでもないようだ。
宮城県で見るシジュウカラガンでも首輪が消えかかっていたり、頬の白が顎でつながっていたりすることもある。
犬の糞は飼い主が片付けろと看板があるが、ガンの糞は犬のと大きさがそっくりである。
3日目にはエボシクマゲラが幹を掘っているのを見た。犬が近づいても逃げなかった。半島なのでクマはいないがコヨーテはいるらしい。
犬のリーシュは外さないようにとのこと。
半島の真ん中にあるビーバーレイク周辺は鳥が多いと言われている。見たかったルビーキクイタダキが最終日に目の前に現れた。
近すぎて撮れない。幸い5m先の枝に移動してくれたが、甘ピン。濁った弱い地鳴きも確認した。
興奮してほくほくしての帰り道、乗馬した婦人警官がトレイルに突然現れた。
<ライフェル渡り鳥サンクチュアリ>
次回来るときはネット予約するようにと言われた。入場料8ドル。フクロウ類も多いと言われているが見つけられなかった。
パンフレットには見つけ方が書いてあって、うーむその手があったか!と・・・。
あちこちに、鳥インフルエンザまん延防止のためエサやり禁止の表示がある。
しかし老人たちは動物にエサをやると元気になる。彼らはこれをがまんできない。大量の餌が売られていてエサをやっていい場所が限定されている。
何人かの老人たちが変な質問をしてくるので困惑したが「赤毛のアン」みたいにやればよかったのだ。
カナダの自然って素敵ですね。私は気に入りました、とかなんとか。常に人に気に入られるように努力をしなくては。
アメリカハイイロチュウヒが飛んでいた。日本でも記録がある。
北米産のオオアオサギはイギリスでは何回か出ている。迷行の多くは大西洋を横断する船に止ってしまって
連れて行かれたから。というわけで北米からアジアへの船舶のルートを調べることで日本での初記録の
可能性が高い場所を知ることができるかもしれない。北米からプサン・上海に向かう貨物船の多くは津軽海峡を通過する。
津軽海峡に向かう船は歯舞色丹沖、根室半島沖そして襟裳岬の近くを通る。オオアオサギが最初に見る「日本」はたぶん色丹である。
北日本で腿が茶色い大きなアオサギがいたら要注意である。識別点の褐色の腿は直立姿勢の通常の個体では見えないこと
が多かったが見えることもある。飛んだ個体を下から見ると明らかにわかる。最初のあれ?変だなという気づきが重要だろう。
ナキハクチョウは遠かった。近くのウエストアム干拓地にもいるらしい。
<ホワイトロック桟橋>
傾斜度20度の急坂を車で下って、沿岸道に出た。車をでると汗ばむ陽気だったが、桟橋を歩くと風が強くて寒さで悶絶した。
ここは海ガモ、アビ類が近寄ってくる素晴らしいところ。満潮だったらもっと良かったかも。
荒波親方、アメビロキン、ヒメなど。沖合にもコオリガモやアビやカイツブリ類がいた。アビより明らかに大きくて首が太いアビ類が
いて、ハシジロアビかもしれないと思った。近くに来るとよいなと思いつつ岸にもどって暖を取って戻ると近くにいた。ハシグロアビだった。
赤毛の女性とすれ違ったのが「赤毛のアン」を想起させてうれしかった。
<バウンダリーベイ>
バンクーバー市街地から車で2時間くらい、アメリカ国境に近く、雪に覆われたレイニヤー山がまじかに見える。
北米のシロフクロウは2013/2014、2017/2018が当たり年であった。しかし2021/2022はDCにも来たが全体的にいまいち。
一年ズレて2022/2023も当たり年かもしれないという予測がネットにあった。現地で直接情報を収集してみると全員今シーズンは
見ていないとのことだった。4年後に来るからまた来てねという人もいた。農家の庭の樹にハクトウワシの巣があった。
ゴルフ場にはアメリカヒドリの大群がいて芝刈り・肥料散布に励んでいた。
コミミズクやアメリカハイイロチュウヒがバンバン飛んでいた。インド人4人がやってきてカモを撃ち始めた。
ここでは狩猟は許可されているのか?ここは有名探鳥地だろ?
とバーダーに聞いてみると、詳しいことは知らないとしどろもどろ。もしかして日本人旅行者かも?
カナダは憲法に多民族主義を明記しているのが興味深い。アメリカもオーストラリアもこれを明記していない。
勇気をもって軋轢を乗り越えて良い社会を創ろうとしているのだが。
<アイオナ自然公園>
ハクガンの名所だが今回見ることはできなかった。厳寒期には南下するらしい。
処理施設からの下水管が4km沖合まで延長されていてその上が遊歩道になっている。海鳥とユキホオジロのスポットである。
よくわからない新世界ホオジロがいたが、ゴマフスズメの北方の亜種ではないかと判断。かなり赤かった。
<海洋博物館>
26日は天気予報が良い方向に外れて快晴で喜んだが風が強くトレイルは前夜の大雪で覆われているので博物館に行った。
展示されているセントロック号は北回り航路通過に初めて成功した船で2回の越冬を経て1941-1943にこれを達成。
バンクーバーで建造され、300馬力のディーゼルエンジン、舳先部分の装甲、そして大量の食糧を搭載していた。
拙著に書いたジョンフランクリン卿は1847年にこの航路にチャレンジして遭難死している。
透視術を行うイギリスの有名貴族がこの人はまだ生きていると1850年に断言したが、1847年に死亡
していることがその後確認された。
帰ろうとして車のキーを回したら警報が鳴りエンジンがストップ。ワイパーに「違反切符」があった。黒い服を着た人がきたので、警官か?と
聞くと、笑って犬を散歩させに来ただけとのこと。どうすればいいか聞いたら、あのマシンで金を払えば良いとのこと。有料駐車場なのに
金を払わなかったということらしい。盗難防止のための費用だとか。クレジットカードオンリーである。延滞金があればネットで支払えとのこと。
スマホもカードも無いなら車も動かせないし、永遠に延滞金が積みあがる。ひどい!
<Pacific Wren>
ミソサザイから最近スプリットした種で、和名を付けるとしたらタイヘイヨウミソサザイとかだろうか。
<その他>
油断してウはよく識別しなかったのは大失敗。撮った写真は後日見ると全部ヒメウだった。見慣れているはずなのにね。
ペルシャ料理は肉と野菜とライスがセットになっていて美味。
トーテムポールなど先住民の独特の文化がよく言われているが、欧米との出会いによる急速な社会構造の変化を反映した
結果というものも多い。ポトラッチなんかもそうらしい。
カナダとアメリカの英語は違うの?
(炭酸飲料をPOPSというのはアメリカ英語。他国では射精という意味にとられてしまうことがある。)
アメリカ人:よかったら、POPS飲む?
カナダ人 :え?
<確認した鳥>
ナキハクチョウ、カナダガン、マガモ、オカヨシガモ、ハシビロガモ、アメリカヒドリ、コガモ、アメリカオシドリ、カワアイサ、ウミアイサ、
コスズガモ、スズガモ、クビワキンクロ、キタホオジロガモ、ホオジロガモ、アラナミキンクロ、アメリカビロードキンクロ、ヒメハジロ、
ヒメウ、オビハシカイツブリ、ハジロカイツブリ、ミミカイツブリ。クビナガカイツブリ、アンナハチドリ、ヒレアシトウネン、ワシカモメ、
カモメ、クロワカモメ、アメリカセグロカモメ、アビ、シロエリオオハム、ハシグロアビ、ヒメウ、オオアオサギ、ゴイサギ、ハクトウワシ、
アメリカハイイロチュウヒ、コミミズク、ハシボソキツツキ、エボシクマゲラ、アメリカガラス、ワタリガラス、ステラーカケス、
アメリカコガラ、クリイロコガラ、アメリカキバシリ、pacific wren,ビーキクイタダキ、コマツグミ、ムナオビツグミ、ホシムクドリ、
テリムクドリモドキ、ワキホシトウヒチョウ、ユキヒメドリ、オウゴンヒワ、コマフスズメ、キガシラシトド、
ミヤマシトド、サバンナシトド、イエスズメ、ハゴロモガラス
Summary:
I visited Canada. Though prosedure was not confortable but I enjoyed my trip.
39.インドで野鳥修行の旅!
19世紀インドの鳥類学者ヒュームのことを知って感動したので、インドに行くことにした。犯罪も狂犬病も毒蛇も怖いけど
行くと決めたら絶対に行くのが絶対に正しい。デリーとアーグラに宿を取り、史跡と探鳥地を回った。
<予防接種>
予防接種は狂犬病、A型肝炎そしてB型肝炎を受けた。肝炎は2回受けなくてはならないが出発まで時間がないので、
気休めで1回受けた。破傷風は10年前に打ってるから今回はパス。デング熱は怖いがワクチンはあまり効かないみたい。
ちなみに今まで受けた予防接種で一番痛かったのはブラジルに行くときに受けた黄熱病だがインドにはほとんど発生は
ないから今回はパス。
<eVISA>
ネットでやる。ルールはころころ変わるらしい。e-tourist-visaは25ドルで、顔写真、パスポートpdf、クレジットカードが必要。
私的な会社が日本語で代行申請をするサイトもある。入国日当日に発行されるArrival visaもあるが出たとこ勝負みたいな
感じだ。
審査に72時間かかるから待てとのこと。実際には15時間くらいで承認された。
<ホテルと列車の予約について>
ニューデリー駅周辺はトラブルが多い。一つ手前のスタジアム駅に近いホテルなら歩いて行ける。予約したホテルは
前払いの必要なしと書いてあるのに、ホテルから今すぐ払えというメールが毎日来た。しかも支払いのためのページ
にアクセスできない。メールを出したが返信がなく、このホテルはキャンセルした。
ホテル送迎、列車、両替、SIMを予約した。インド人だけど日本語はメールの文章も完璧。自分のスマホはSIMフリー
であることを確認。SIMは1400円。長距離バスはトイレがないから列車にした。
列車のチケットも現地のシゲタトラベルに依頼。列車の予約はネットでもできるが特殊な用語が多くて面倒。
<デリー>
空港到着後、予約したタクシーでホテルまで。ホテルはニューデリー駅近くでトラブルの名所だが難なくチェックイン。
翌朝興奮して早く起きて払暁にホテルを出たら牛がたくさんいた。セブ種系で結構大きい。栄養状態がいいようだ。
飲食店が夜のうちに路上に出した残飯を食べに集まって来たのだ。ドブネズミ、犬、イエガラス、ニシトビそして人間も。
残飯を与えるのはバクシーシ(喜捨)だから止むことはない。牛の群れで渋滞しようとも、伝染病がまん延しようとも。
ニシトビの群れ。トビとはけっこうすみ分けている感じでデリー市内ではニシトビ。翼下のパッチが不明瞭、翼が細長い、
顔つきが違う、旋回する時の尾羽のひねりがない。尾羽の食い込みが深いが開いているときは浅く見える。識別は可能だが、
難しいことも多い。
楽しい矢継ぎ早の英語のやりとりをしているうちに口車に乗ってしまった。以後、なるべく現地人と接触しないようタクシーで
移動することにした。
<Okhla BS オクラ野鳥保護区>
インドのデリー中心地からタクシー約30分。ヤムナー川左岸の約3kmの堰堤を徒歩で往復。午後は逆光。早朝は
スモッグがひどいので遠くが見えない。ゲートが開く時間は不明。入場料を取るため、物乞いなどが入れず、ゲートの中は
比較的安全だが、周辺にはホームレステント村がある。タクシーで入口まで行って長時間待っていてもらった。ニシトビが
アジアレンカクをつかんで飛んでいた。カシミールムシクイ、バフマユムシクイなどがいた。
タクシーの車内にサイババグッズがあったので、あなたはサイババ(麻原の師匠)を信じますか?
と聞いたところ、イエスとの答えに思わず笑ってしまったが、ひどく失礼だったと反省。
<鉄道デリー/アーグラ間200km>
夜明け前のデリー駅は牛、物乞い、寝に来る人、そして物売りで大混雑。視界十メートルの濃厚なスモッグ。寝ている人を
踏んづけて乗客がホームに突進する。列車の乗り方もよくわからない。予め手配したタクシードライバーに列車に乗るまで
エスコートしてもらったのでなんとかなった。指定席の座席は快適で飲み物とベジ軽食がでることもある。英国夫人がトイレに
狂喜していた。便器の上に靴で上がるから泥だらけ! スモッグで列車は遅れがち。突然スモッグが晴れて1時間遅れる予定
が定刻に着くこともある。線路の幅がとても広い。植民地時代の無計画性の名残り。
<ソアサロバ Soor Sarovar BS 1月19日>
アーグラからタクシーで1時間くらい。ヤムナー川の大きな三日月湖で、インドガンなど水鳥も多かった。治安的に不安なので
念のためにドライバーさんにいっしょに来てもらった。つまらなそうだったので気の毒に思って車の中で待っていてもらった。
その直後に若者集団に囲まれて双眼鏡を貸せ!としつこくせまられた。貸したら戻ってこないだろう。インドガラスが集団で
喚き散らしているので藪をかき分けると巨大なフクロウがいた。羽角が跳ねた。なんとワシミミズク! 森の中には
チフチャフtristisが多かった。インドにはヨロビン(PPなし)とビンズイ(PPあり)は両方いるらしい。自分が見たのは後者のみ。
すみわけているのか? ナマケグマの収容施設があり飼育員が解説してくれた。
スプリットして別種になった。200万年前から急に分化したらしい。街中にはいなかった。
<ケオラディオ Keoladio国立自然公園>1/20
記事がバーダー誌2007年にある。アーグラから56km。バスは表示の文字がアルファベットじゃないのでよくわからない。
入口はバーラトプルという町の近く。インド人的にはここはBharatpur National Parkとして認識されている。アーグラから2時間。
タクシードライバーは英語ができず、ヒンディー語をスマホに音声入力してアルファベット化して示すがヒンディー語で意味不明。
彼はアルファベットを読めない。俺がガイドを選んでやるというらしいがリベートを取りたいだけ。旅行計画を台無しにしかねない
ことだからひどい。NOと言っても土産物屋に連れて行くのもリベートを取っているのだろう。こんなのをサービスと称して高額の
チップを要求する。こういう人はインドには普通にいる。鉄道駅のあるバルトプルに宿泊して歩いて入口に来るべきだった。
入場すると中で食料水を得る場所はない。いったん出る人もいるみたいだ。
靴底に刺さった。帰国後にペンチで抜いたものも5本くらいあった。靴底の薄い所に当たったら怪我するから破傷風のワクチン
は必要。またここにはヒョウが多いからあまり道を外れて奥に行かない方がいい。
ケオラディオは世界的に有名な探鳥地で、英語可の有能な電動リキシャ野鳥ガイドが複数いる。自分で選ぶべき。当日行って
雇用も可能。リキシャは電動で静か。有名なサイクルリキシャはもういなかった。ガイドはヨタカとかカンムリワシとかを次々に
見つけてくれた。
クロノビタキ雄は冬羽も黒い。オガワコマドリは多かったが、地面にいることが多く、ホコリっぽい風景でキレイに撮れない。
ヒヨドリ類は、シロミミヒヨドリ、コウウラン、シリアカヒヨドリ(声はピンポロスッポンピョーンと聞こえる)
アーグラのホテルの上空でエジプトハゲワシ。インドではハゲワシ類が激減していて、牛の治療のための薬が原因という話だ。
外傷によるフレグモーネが多いから病気の牛にはとりあえず安価なステロイドの大量投与。牛の死体を食べたハゲワシ類が
腎臓障害で死ぬというストーリー。殺鼠剤で死んだネズミを食べて死ぬという話もある。
<下痢でダウン>
ケオラディオからホテルに戻ったらひどい悪寒がして足の筋肉が吊りまくった。脱水症状に続いて激しい下痢。翌日は予約
したタクシーが来たけど昨日の不良運転手なので追い返した。タージマハール観光をパス。ひどい下痢でもアーグラ城は見たい。
16世紀に造られた城なのに大砲を装備した19世紀の反乱軍を撃退。城門には日本の城と同じような枡形構造があって防御力
がありそう。ヒュームは大反乱の時に120km徒歩で移動してここに逃げ込んだ。
<スルタンプールSurtanpur NP 1/22>
デリーに戻って翌日、ここに行った。空港の南にある工業都市グルグラム(旧グルガオン)の近く。デリーから南西に車で2時間
くらい。さすがにデリーには英語ができるドライバーがいる。NP内は治安が良い。周回約5kmの広大な湿地帯があり、予約すれ
ば電動カート付きのバードガイドを雇うことができる。入場料が安い。隣にレストランがあるのも助かった。かなり高いやぐらがあり、
とびものの撮影やムシクイ類の撮影に適している。大都市が近いから大気汚染で灰色っぽい写真になりがち。午前中は反時計回
り、午後は時計回りがよい。アカケヅメシャコも見ることができた。
るのか。、他国から飛んでくる渡り鳥は普通に警戒心が強い。
<ブッダ・ジャヤンティ・パークBuddha Jayanti Park 1月18・23日
デリーの中心部にあり大統領官邸近くだからホームレスが排除されていて治安は良さそうだが、公園の奥にはいるらしい。
野犬は多い。子犬に近づくと母犬が攻撃してくるそうだ。レストラン(いつも開いてるのか?)のそばのイチジクの大木にはアオバト
類が来ることがあるらしい。ヒメコガネゲラ、インドコサイチョウもいた。都心でもなかなか侮れない。パンくずでバフマユムシクイを
撮れた。2時間ぐらい歩き回っても飽きない感じの広さ。駐車場は28.620224724424784, 77.17786429485422 ホテルからリキシャ
で行って、帰りは電話でピックアップしてもらうのがよいか。雨期にはコブラも出るとのこと。ヒメコガネゲラ、バフマユムシクイ、
シキチョウ、オナガサイホウチョウなど。
<エピローグ>
生もの厳禁、食べ物にはネズミが触っているはずだ。食べなかったけどインド風にアレンジしたやきそばが辛くておいしいらしい。
食べたカレーは全部美味だった。ダルカレーはレンズ豆の使い方がフランス料理とは全く発想が違っていて甘みが出るまで煮込
んでいた。
商店で売られているクッキーはまずかった。レストランでプレインナンを頼んで取っておくとか。朝食のときにサンドイッチを頼むと
かで対処。
SIMで自分のスマホをインド仕様にしたら、変な電話がたくさんかかってきたがヒンディー語だから全く分からなかった。
性犯罪が多いから女性はインドには行かない方がよい。盗難、詐欺が多いので路上で話しかけてきた人は信用しない。交通
事故が多いからレンタカー・レンタバイクの運転は止めた方がいい。交通倫理は無く、逆走、割り込み、なんでもあり。流しのリキ
シャ―は短距離に限っては比較的安全。日本語ができる旅行代理店は看板があるから信頼できるだろう。
下痢が悪化して帰国時には「だだもれ」状態。帰国後病院で点滴を受けた。食中毒のカンピロバクター感染症。腸粘膜は復活
するのには5日かかる。体重が5kg減った。大気汚染がひどいため、乾いたセキが1か月続いた。スモッグがあるから遠い距離
の撮影ではかすんでしまうし、光線がキレイじゃないから美しい写真が撮れない。渋い鳥を近くで撮るのが良い。
インドって鳥は最高、そして鳥以外は最低! 話のネタに一度は行くべきだ!?
<補記>ヒュームはイギリス出身。19世紀のインド鳥類学の父と言われる鳥類学者でしかもトップの長官まで出世したインドの国家
公務員。二足の草鞋を履く人だった。文官なのにインド大反乱で戦闘部隊を率いて大活躍、退職後は国民会議派という政党を作った。
40.インドで確認した鳥名リスト(2024年)
:地名のBSはバードサンクチュアリ、NPはナショナルパーク、種名の順番が少し乱れています。)
<ブッダジャヤンティパーク、オクラBS>1月18日、PM
ハイイロガン、ハシビロガモ、アカボシカルガモ、コガモ、ホシハジロ、ニシトビ、オジロゲリ、オオホンセイインコ、ワカケホンセイインコ、
インドコサイチョウ、コウウラン、ユリカモメ、ヒメコガネゲラ、ツバメ、オナガサイホウチョウ、バフマユムシクイ、ミドリムシクイ、
カシミールムシクイ、ツチイロヤブチメドリ、インドハッカ、シキチョウ、キガシラセキレイ、アジアレンカク、シラコバト
<Soor Salovar BS> 1月19日 10時から13時ごろ。
ワシミミズク、カイツブリ、インドクジャク、インドトキコウ、インドガン、アカツクシガモ、インドカルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、
インドトキコウ、アカアシトキ、ヘラサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、モモイロペリカン、インドヒメウ、カワウ、ニシトビ、インドトサカゲリ、
クサシギ、アオアシシギ、セイタカシギ、ソリハシセイタカシギ、ユリカモメ、チャガシラカモメ、オオズグロカモメ、カワアジサシ、
クロハラアジサシ、ワカケホンセイインコ、アオショウビン、オナガベニサンショウクイ、チフチャフtristis、バフマユムシクイ、ビンズイ、
チャイロオナガ、イエガラス、インドハシブトガラス(仮称)、ツバメ、アジアマミハウチワドリ、シロハラウチワドリ、インドハッカ、
ハイイロハッカ、キツツキSP
<ケオラディオ NP 1月20日> 9〜14時
ハイイロガン、インドガン、アカハシハジロ、コガモ、アカボシカルガモ、オナガガモ、オカヨシガモ、マガモ、カイツブリ、インドトキコウ、
ゴイサギ、シロハシスキコウ、インドアカガシラサギ、クロトキ、ブロンズトキ、ヘラサギ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、アマサギ、
チュウサギ、モモイロペリカン、アジアヘビウ、インドヒメウ、カワウ、アジアコビトウ、ニシトビ、トビ、カラフトワシ、ソウゲンワシ、
カンムリワシcheela、カタグロトビ、タカサゴタカ、シロハラクイナ、バン、オオバン、レンカク、アジアレンカク、セイタカシギ、
ソリハシセイタカシギ、インドトサカゲリ、クサシギ、タカブシギ、アオアシシギ、キジバト、キアシバト、ワカケホンセイインコ、バンケン、
ヨタカ、ニシヒメアマツバメ、アオショウビン、タカサゴモズ、オウチュウ、イエガラス、シリアカヒヨドリ、ウチワドリSP。、ヤブチメドリ、
インドハッカ、ズグロムクドリ、オガワコマドリ、シキチョウ、クロノビタキ、オジロビタキ、キセキレイ、ヤナギムシクイ、バフマユムシクイ、
ノドジロムシクイ、アラビアムシクイ、
<スルタンプール NP 1月22日> 8時から昼食をはさんで14時まで
アカケズメシャコ、インドクジャク、コブガモ、マガモ、コガモ、オカヨシガモ、オナガガモ、メジロガモ、キンクロハジロ、ハシビロガモ、
ホシハジロ、コブガモ、カイツブリ、インドトキコウ、シロハシスキコウ、コハゲコウ、クロトキ、ブロンズトキ、インドアカガシラサギ、アオサギ、
ムラサキサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、アマサギ、アジアヒメウ、インドヒメウ、カワウ、ミサゴ、トビ、ニシトビ、カタグロトビ、
タカサゴタカ、シロハラクイナ、バン、オオバン、セイケイ、レンカク、インドトサカゲリ、オグロシギ、アオアシシギ、クサシギ、チャバラサケイ、
シラコバト、ワカケホンセイインコ、アオショウビン、ヒメヤマセミ、タカサゴモズ、チャイロオナガ、イエガラス、インドハシブトガラス(仮称)、
シロミミヒヨドリ、チフチャフtristis、バフマユムシクイ、コノドジロムシクイ、セジロヤブチメドリ、ツチイロヤブチメドリ、ハイバラメジロ、
インドハッカ、オガワコマドリ、クロジョウビタキ、シキチョウ、インドヒタキ、クロノビタキ、ノビタキ、オジロビタキ、ムラサキタイヨウチョウ、
アラビアウタムシクイ
<ブッダジャヤンティパーク、1月23日>12時から14時まで
オナガサイホウチョウ、シキチョウ、チャイロオナガ、ツチイロヤブチメドリ、ハイバラメジロ、バフマユムシクイ、インドハッカ、ドバト